もし、あなたが嫁ぐ先のお姑(しゅうとめ)さんが大変厳しい方で、初対面の挨拶の時、自分は座布団に座りながら、嫁となるあなたには座布団を与えなかったら、どう感じますか?
また、もしあなたの息子の嫁に迎える女性が大変気位が高く、まだ会ってもいない姑のあなたへの贈り物の宛名に、何の敬称もつけていなかったら、どう感じますか?
どちらも、常識的にはあり得ないことでしょう(そもそも最近は、こうしたシチュエーション自体、少ないと思います)。しかし、幕末の江戸城大奥で、実際に起きたことでした。そして、これらがきっかけの一つとなって、嫁姑の関係が険悪になるのです。
ところで、幕末の江戸城大奥で最も存在感を発揮した女性といえば……?
それは篤君(篤姫、天璋院〈てんしょういん〉)だった、といってよいでしょう。
篤君は薩摩の島津家より、13代将軍徳川家定(いえさだ)の御台所(みだいどころ、将軍正室のこと)として嫁いだ女性です。実は輿入(こしい)れにあたり、養父島津斉彬(なりあきら)より、次期将軍を聡明な一橋慶喜(ひとつばしよしのぶ)にするよう、家定を説得する密命を受けていましたが、失敗。むしろ家定の最大の理解者として、障害を抱えつつ将軍職を務める夫を全力で支える道を選びます。その辺については「密命を帯びて大奥へ…篤君が固めた決意とは? 大河ドラマ『青天を衝け』が楽しくなる予備知識」の記事もご参照ください。
しかし家定の急死により、結婚生活はわずか1年半で終止符が打たれました。篤君は24歳で落飾(らくしょく、仏門に入ること)し、天璋院と称します。その後の篤君は、家定が後継者(14代将軍)と決めた、13歳の家茂(いえもち)の養母として成長を見守りました。そんな家茂が17歳となった文久2年(1862)、御台所を迎えることになります。相手は孝明(こうめい)天皇の妹宮・和宮(かずのみや)。朝廷との強い結びつきを世間にアピールしたい幕府が企てた、政略結婚でした。
しかし、和宮が京都からお付きの者たちを連れて大奥に入ると混乱が生じ、篤君と和宮が対立することになります。今回は対立を経て、共闘に向かう幕末大奥の嫁姑のドラマを紹介します。なお、篤君は落飾後に天璋院、和宮は静寛院宮と称しますが、本記事では篤君、和宮の呼称も併用します。
 大奥碑(千代田区)
大奥碑(千代田区)
「公武合体」がもたらしたもの
篤君の不安
万延元年(1860)、ある日の江戸城内でのこと。
「いま、何と申した? もう一度申してみよ」
篤君(天璋院)の鋭い眼光に、拝謁していた島津家の江戸家老は青くなりながら、同じ内容を再び言上します。
「ははっ。ご公儀より内々の話として当家に申されますには、上様の御台所として帝の妹宮であらせられる和宮様がご降嫁(こうか)されますと、天璋院様は畏(おそ)れ多くも、和宮様の姑(しゅうとめ)となられます。つきましてはしばらく大奥を出て、島津家にお戻りいただければ、宮様への差しさわりのおそれもあるまい、とのことでございまして……」
「無礼であろう! 島津家出身の私が姑では、身分違いと申すのか。私は先代の公方(くぼう)様の御台であり、ご当代の母じゃ。いかに皇妹とて上様に嫁ぐ以上、徳川家の嫁として上様を支え、母親を敬うのは当然のことではないのか。島津家に戻ることは断じてせぬ。私から老中(ろうじゅう)に伝えおくので、そう心得よ」
と、言いつつも、幕府閣僚の朝廷に対する弱腰に、和宮降嫁の不安を篤君は強く感じていました。
将軍家茂の御台所に孝明天皇の妹宮を迎えるという話は、井伊直弼(いいなおすけ)が幕府大老(たいろう)を務めていた頃から持ち上がっていたものです。尊王攘夷(そんのうじょうい、天皇を尊び、外国を打ち払うという考え方)の気運とともに、朝廷の許しを得ずに開国へと舵を切った幕府への批判が高まる中、婚儀は幕府にとって、朝廷との結びつきを世間にアピールする格好の機会でした。こうした朝廷との融和を図る幕府の政策は、「公武合体」と呼ばれます。
しかし安政7年(1860)3月に、大老井伊直弼は桜田門外で水戸浪士らに討たれました。後任の老中安藤信正(あんどうのぶまさ)は、井伊のように強硬な政治ではなく、より穏便に公武合体の象徴としての和宮降嫁(こうか)を進めます。篤君が島津家の江戸家老を叱ったのは、この頃のことです。ところが降嫁を快く思わない尊王攘夷派の浪士らによって、安藤も文久2年(1862)1月に坂下門外で襲われました。襲撃は失敗したものの、負傷した安藤は失脚。和宮降嫁も、幕府が攘夷を実行することを条件に朝廷が許すこととなり、幕府は朝廷に譲歩した結果、政治に口を挟まれることになったのです。篤君の不安は、的中しました。
 江戸城坂下門(千代田区)
江戸城坂下門(千代田区)
和宮の決意
一方、和宮にとっても徳川将軍家への降嫁は、決して望むものではありませんでした。
将軍家茂に輿入れする話があることを、兄の孝明天皇から和宮が聞かされたのは、15歳の時。しかし、すでに和宮には婚約者がいました。有栖川宮熾仁(ありすがわのみやたるひと)親王です。もちろん孝明天皇もそれは承知しており、和宮が降嫁を拒絶したこともあって、結婚には賛成できない旨を幕府に伝えました。
ところが幕府はあきらめず、1ヵ月後に再び申し入れ、しかも「降嫁が実現するのであれば、開国の方針を転じて、朝廷が主張する攘夷を行ってもよい」とにおわせたのです。この幕府の譲歩には朝廷内の公家たちも驚きました。下級公家の岩倉具視(いわくらともみ)は、
「幕府は自らの権威が低下し、人心が離れていることを悟り、朝廷の権威を利用しようとしています。この好機に、政治的決定は朝廷、その執行は幕府があたるという体制を築くべきです。朝廷の力を回復させるためにも、外国との通商条約破棄と攘夷実行を幕府が約束するのであれば、今回の降嫁は許可すべきでしょう」
と意見を述べました。孝明天皇が心を動かされる一方、幕府の買収工作もあって、朝廷内は降嫁の方向へと傾きます。しかし、かたくなに拒み続けたのは、和宮でした。妹宮の切々とした訴えに、孝明天皇も無理強いはできず、代わりに、昨年生まれたばかりの我が子・寿万宮(すまのみや)を、江戸に送ることを考えます。そして幕府が承知しない場合は、退位することまで覚悟しました。
板挟みとなった孝明天皇の苦境を知り、和宮はさんざん泣いた末に、降嫁を承知します。万延元年(1860)8月のことで、有栖川宮との婚約は、もちろん破棄となりました。そんな和宮を孝明天皇は、翌文久元年(1861)4月に内親王(皇女)とします。関東に嫁いでくれる妹を思って、身分を高めたのです。和宮が輿入れのために京都を出立(しゅったつ)したのは、同年10月のことでした。
 和宮像(公益財団法人 日本女性学習財団蔵)
和宮像(公益財団法人 日本女性学習財団蔵)
幕府が演出した和宮の大行列
2万5,000人の行列
ここで、江戸に向かう和宮の桁外れな規模の行列について少し紹介しましょう。文久元年10月20日辰の刻(午前7時~9時頃)。和宮は長い行列とともに、桂御所を出発。136里(約534km)の中山道を25日間かけて、江戸へ向かいます。
皇女の行列が通るということで、各宿場の建物は見苦しくないよう修繕され、中山道に架かる橋も多くが架け替えられました。また通り道には厚さ3寸(約9.1cm)、幅4尺(約121.2cm)の置き砂が切れ目なく敷かれて、それは和宮が江戸で最初に入る清水(しみず)屋敷まで続いていたといいます。
行列の規模も破格で、警備や人足(にんそく)まで含めると、総員およそ2万5,000人にのぼりました。その人員が一度に動くと街道が混乱するので、行列は4日間に分かれて出発し、第一陣は和宮出発の前々日に出発しています。各宿場が請け負う人数も膨大で、近江(現、滋賀県)の草津宿では総勢1万人の人足と、馬500頭が徴用されました。宿場だけでは人数が収まり切らず、周辺の商家や民家も宿や休憩所として割り振られ、それは草津の総戸数の4分の1に及んだといいます。
 中山道妻籠宿(南木曽町)
中山道妻籠宿(南木曽町)
諸大名が投入した人数は70万人
また当時、降嫁に反対する者たちが行列を襲うという噂があったため、警備には細心の注意が払われました。沿道に所領のある各大名は行列の警護を命じられ、25日間に総勢70万人もの人員が投入されています。一行が通過するまで村人は外出を禁じられ、通行を見下ろす山や高所に立ち入ってはならず、物音をたてることも取り締まられました。商売は禁止、寺の鐘をつくのも遠慮、犬や猫の鳴き声さえも聞えぬよう、沿道から遠ざけることを命じられています。
これほど大がかりな下向(げこう)となったのは、幕府が「公武合体」を世間に強くアピールするためだったとされます。とはいえ費用は幕府の負担ではなく、動員された諸藩に割り振られました。一説に総額74万両、現在のおよそ100億円にあたるともいわれます。諸藩にとっては迷惑以外の何ものでもなく、幕府の威光に恐れ入るというより、むしろ反感を強めたことでしょう。
婚礼の行列に「縁起が悪い」とされる、板橋宿の縁切榎(えんきりえのき)を迂回した和宮一行が、江戸城清水門から御三卿(ごさんきょう)・清水家の屋敷に到着したのは、11月15日。約1ヵ月間、旅の疲れを癒した和宮が、いよいよ江戸城本丸大奥に入ったのは12月11日のことでした。
 縁切榎(板橋区)
縁切榎(板橋区)
しきたりの違いが招いた衝突
幕府への不信
和宮は大奥に入るにあたり、女房衆ら約80人のお付きの者を従えていたとされます。その中には、和宮の実母観行院(かんぎょういん)の姿もありました。また和宮の側近で、お付きを束ねる上臈(じょうろう、高級女官)が庭田嗣子(にわたつぐこ)です。庭田は宮中で宰相典侍(さいしょうのすけ)という最高位の女官でした。『和宮御側日記』など、大奥での和宮に関する記録を残しています。
しかし、清水屋敷に滞在中から、和宮をはじめとする京都側には「話が違う」と感じることが多かったようです。京都側が重んじたのは江戸城内においても「御所風」で暮らすことで、それは幕府もすでに了承済みだったはずでした。ところが肝心の大奥側は、御所風のことは一切承知していないと主張し、幕府の役人たちの受け答えも曖昧です。あるいは和宮降嫁を折衝した幕府の役人は、和宮が大奥に入ってしまえばこっちのものと、朝廷と口約束だけをしていたのかもしれません。京都側は幕府への不信感を募らせながら大奥に入りますが、やがて不満が爆発することになります。
天璋院が無礼である
和宮が初めて大奥に入った12月11日。和宮は御殿の上座に座り、大奥の人々と対面。その後、対面所の上段で将軍家茂と初めて対面します。家茂は和宮が贈った小直衣(このうし、公卿の日常服)姿でした。さらに袿(うちき)姿(表衣〈うえのきぬ〉の内に着る衣だけを着た略装)の天璋院(篤君)とも対面し、祝宴となります。家茂と和宮の婚儀が翌年2月に決まったこともあり、華やかな宴となりました。しかし庭田は、御所風の一件もあり、心にもやもやとしたものを抱いていたようです。
そしてほどなく、庭田は次のような手紙を宮中の典侍局(てんじのつぼね)、内侍局(ないしのつぼね)宛てに送りました。いずれも宮中の高級女官であり、実質は孝明天皇への報告だったでしょう。
「天璋院が無礼である。天璋院は和宮に面会しても会釈も礼もせず、普通の姑同様に接しようとした。しかも天璋院は茵(しとね、敷物のこと)の上に座り、和宮には敷物もなかった。(庭田ら)和宮側近に与えられた部屋は暗く、8畳2間のみである。大奥の者たちとの折り合いも悪く、和宮が涙したこともあった……」
天璋院(篤君)が一番の悪者にされていますが、これは12月11日の初対面時ではなく、その後、篤君の部屋で個別に対面した際のことでしょう。いかにも篤君は意地の悪い、皇女を皇女とも思わない不敬の姑のような印象を与えますが、これについては篤君の側にも言い分はありました。
 『千代田の大奥 長刀稽古』(国立国会図書館デジタルコレクション)
『千代田の大奥 長刀稽古』(国立国会図書館デジタルコレクション)
姑を呼び捨てに
「和宮と天璋院とは、初めは大層仲が悪かつた。会ひなさるまではネ。お附(つき)のせゐだよ。初め、和宮が入(い)らした時に、御土産の包み紙に〈天璋院へ〉とあつたさうナ。いくら上様(皇女)でも、徳川氏に入らしては(天璋院は)姑だ。書きすての法は無いといつて、お附が不平をいったさうな。それであつちですれば、こつちでもするといふやうに競つて、それはひどかつたよ」
以上は、篤君や和宮と親しく接した幕臣の勝海舟の談話(『海舟語録』)の一節です。
いかに皇女であっても、将軍家茂に嫁ぐ以上、篤君は姑です。その姑を和宮側が呼び捨てにしたことで、篤君のお付きの者たちが憤慨しました。もちろん、だからといって篤君が、対面の際に意地悪をして和宮に敷物を与えなかったわけではありません。武家の嫁と姑のしきたりを、そのまま踏襲したに過ぎなかったのです。宮様であっても武家に嫁いだ以上は、武家のしきたりに従うのは当然であると、篤君は考えていました。
しかし和宮たちは、御所のしきたりを通すことを前提として大奥に入っています。たとえば公家社会では、嫁の位が高ければ、対面の際に姑であっても嫁の上座には座らず、対等の位置で、それぞれ敷物を用いるのが普通でした。つまりしきたりや考え方の前提が異なるため、さまざまな場面で喰い違いが生じたのです。勝海舟が語るように、当人たちよりもむしろそれぞれのお付きの者たちが感情的にヒートアップしてしまい、不幸にも篤君と和宮の対立の構図がつくられていきました。
武家風と御所風
ではこの時の大奥において、武家風と御所風のしきたりでは、どんな点に違いがあったのでしょうか。わかりやすいところをいくつか紹介してみましょう。
【装束】 武家の女性は、小袖の上に礼服である打掛(うちかけ)を羽織ります。一方、公家の女性は肌着として着た単(ひとえ)の上に、袿(うちき)を羽織って、袴(はかま)をはきました。袖口(そでぐち)も大きく異なり、武家の女性は小袖なので袖口が狭いのに対し、公家の女性の袿は袖口が大きく開いたつくりになっています。
【髪型】 大奥の武家の女性のうち、お目見え以上(将軍や御台所への目通りを許された者)は「片はずし」という髪型でした。後ろでひとつにまとめた髪を輪にし、髪の片端を笄(こうがい)に巻きつけます。笄を抜くと、すぐに下げ髪となりました。御台所は、御着帯(妊娠5ヵ月の儀式)までは「おまたがえし」という髪型で、束ねた下げ髪を輪にし、輪の下で髪の先を笄に千鳥がけしたものでした。一方、公家の女性は髪を肩や背中のあたりでゆるやかに結ぶもので、「おすべらかし」といいます。

【化粧】 武家の女性は式日(儀式を行う日)には眉(まゆ)をおしろいで塗りつぶしますが、公家の女性にはその風習がありません。また武家の女性は化粧の際に顔剃りもしますが、皇族の女性にその風習はなく、和宮の顔の毛が目立ったという記録も残ります。
【言葉】 大奥の女性は、江戸風の言葉を用いました。篤君も、実家の島津家では上級武士は江戸言葉を使うように命じられていたため、やはり江戸風の言葉です。一方、和宮らは御所言葉でした。
このように、武家風と御所風ではさまざまな違いがありました。京都側の若いお付きの者たちの中には、大奥の慣習を「野暮ったい」と嗤(わら)う者が少なくなく、馬鹿にされた大奥の者たちも、目の色を変えて京都側のあら探しを行い、陰で嘲笑するといった中傷合戦が繰り返されたのです。
家茂と和宮
同い年の夫婦
そうした中で文久2年2月11日、将軍家茂と和宮の婚儀が行われました。二人は同い年の17歳。周囲の喧騒をよそに、家茂と和宮の仲はいたって睦まじかったといいます。家茂は真面目で物堅い性格で、若年ながら自分の立場をわきまえて、難しい政局に対処していました。そんな家茂の姿は、やはり政治に翻弄されて将軍に嫁いだ和宮には、共感するところがあったようです。家茂もまた、か弱い身で関東に来なければならなかった御台所に、いたわりの情を示しました。
庭田嗣子の4月9日の日記には、庭で乗馬をする家茂を、和宮は高台に上って眺めたと記されています。やがて和宮の元に戻ってきた家茂の手には、自ら庭で手折った石竹(せきちく)の花があり、「おみやげ」と言って進呈しました。和宮は嬉しそうに受け取ったことでしょう。また家茂は、和宮へ珍しい金魚や、べっ甲のかんざしを贈ったこともありました。
家茂が和宮に示す親愛の情を、大奥の者たちの目に最初のうちは「上様が機嫌を取っておられる」と映ったようです。しかし、二人の仲睦まじさが本物であることがわかると、大奥の者たちと、和宮のお付きの者たちとのいさかいも、次第に鎮静化していきました。
 石竹
石竹
わだかまりの氷解
ただし篤君には、どうにも納得できなかったことがあります。それは家茂が和宮を「御台」と呼ばず、「宮様」と呼ぶことでした。篤君としては和宮に対し、徳川の嫁としての自覚を促したいという思いが強くありました。たとえ皇女であっても、和宮の役割は、将軍である夫家茂を支えることではないのか……。まっすぐな気性の篤君だけに、その後、勅旨によって「和宮が正式名称、呼称は宮様である」とされても、夫に「宮様」と呼ばせる和宮に対し、割り切れない思いを抱いていたようです。
そんな篤君の和宮に対する見方が、あることをきっかけに変わりました。正確な日時は不明ですが、勝海舟が『海舟語録』で次のように語っています。
「或る時、浜御殿(現在の浜離宮)へ天璋院と将軍と和宮と三人で居(い)らしたが、踏石(ふみいし)の上にどういふものか天璋院と和宮の草履をあげて、将軍の分だけ下に置いてあつたよ。天璋院はサキに降りられたがネ、和宮は之(これ)を見て、ポンと飛んで降りて、自分のを除(の)けて、将軍のを上げて辞儀(じぎ)なすつたさうで、それでぴたと静まったよ」
和宮の将軍を敬う行動に、篤君が大いに驚き、見直すことになった出来事でした。
「和宮は身分を鼻にかけて、徳川家をないがしろにしているとばかり思っていたが、それは私の思い違いであったようだ。和宮も私と同様、政略で将軍に嫁いだ身ではあるが、今では家茂殿を慕い、将軍の御台所として立派に務めを果たしている」
篤君がそう思い至った時、篤君と和宮の間にあったわだかまりは、氷解していたといいます。子孫繁栄を願って、仲良く一緒に「亥(い)の子餅」を食べる家茂と和宮、そんな息子夫婦を温かく見つめる篤君……。そんな穏やかな空気が、ようやく江戸城大奥に流れるようになりました。
 浜離宮恩賜庭園。かつての徳川将軍家の別邸・浜御殿(中央区)
浜離宮恩賜庭園。かつての徳川将軍家の別邸・浜御殿(中央区)
大坂城に死す
家茂の上洛
しかし対立の緊張が解けた大奥とは裏腹に、幕府を取り巻く状況は日に日に厳しさを増していきます。和宮との婚儀を行った翌年の文久3年(1863)と、翌々年の文久4年(元治元年)、家茂は2年続けて上洛しました。徳川将軍としては、229年ぶりのことです。京都の朝廷が存在感を増し、政治の中心が江戸から京都に移る中、幕府は朝廷との関係を強化し、幕府政治の正当性を世にアピールする必要がありました。正室和宮の実兄である孝明天皇に初めて拝謁した家茂は、幸い天皇より信頼を寄せられますが、一方で朝廷が実行を迫る攘夷は現実的に難しく、真面目な性格の家茂には、精神的に重い負担となったことでしょう。
家茂が留守の江戸城大奥では、和宮がお百度を踏んでいました。徳川家康が尊崇した芝増上寺安国殿の黒本尊(阿弥陀如来)のお札を部屋の上段に置き、四方の椽(えん)座敷(畳敷きの縁側)を7日間、ぐるぐる廻るものです。家茂への加護を、黒本尊に祈るためでした。一方、上洛前、家茂は和宮に小さな「這い這い人形」を贈っています。絹のぬいぐるみで幼児をかたどっており、凶事を払ってくれる人形とされていました。和宮と家茂が、互いの身を思いやっていたことが伝わってきます。しかし、2人が一緒に過ごす時間は、もうあまり残されていませんでした。
長州征伐の陣頭指揮
慶応元年(1865)閏5月、家茂は3年続けて、3度目の上洛に臨みます。しかも今回は朝廷との折衝だけでなく、幕府に敵対する長州藩毛利家を征討すべく、大坂城で幕府軍の陣頭指揮を執るための出陣でした。第二次長州征伐です。この時、家茂には感じるところがあったのでしょう。自分に万一のことがあった際には、跡目は田安亀之助(たやすかめのすけ、のちの徳川家達〈いえさと〉)にしたいという意向を、内々に和宮と天璋院に伝えるよう側近に命じていました。また和宮には「土産は何がよいか」と尋ね、和宮は西陣織を所望したといいます。家茂が帰還した折に、美しい西陣織の着物をまとった姿を見せたいと願ったのでしょう。が、これが夫婦の永別となりました。
反幕府の姿勢を強める長州藩毛利家は、前年の元治元年、将軍家茂が江戸に戻った後の京都に進軍し、京都御所に攻め込みました。禁門の変です。しかし長州軍は御所を守る幕府方に撃退され、さらに同年、幕府軍による第一次長州征伐が行われて、長州藩は戦う前に謝罪恭順しました。ところが、ほどなく長州藩内に再び反幕府勢力が台頭、一方で幕府が公表した長州処分について、諸藩は非協力的な態度を示し、このままでは幕府の存在が軽んじられかねない事態となったのです。そこで幕府は再び長州征討を行うことで、強大な武力を改めて天下に示そうとしました。
 大坂城跡(大阪市)
大坂城跡(大阪市)
君ありてこそ
この第二次長州征伐に、薩摩藩、広島藩、佐賀藩などは出兵を拒否。薩摩藩に至っては裏で長州と手を結び、支援を行います。幕府軍は慶応2年(1866)6月、ついに長州藩領に攻め込みますが、新式の銃火器を用いる長州軍に、まさかの連戦連敗。
こうした難しい戦局の陣頭指揮を、将軍家茂は大坂城で続けていました。家茂は開戦前の4月頃より胸の痛みを訴え、6月には食欲が衰えて、7月には胸苦しさや呼吸困難の症状が現れます。脚気(かっけ)でした。家茂の体調不良の知らせが江戸に届くと、和宮や篤君は寺社に平癒(へいゆ)の祈禱を命じ、和宮は医者3人を軍艦で大坂に向かわせます。しかしそのかいもなく7月20日、家茂は大坂城内で薨去します。脚気による心不全でした。享年21。脚気は当時、原因不明の病でしたが、困難な長州征伐指揮の重圧と心労が、家茂の死期を早めたことは、容易に想像できます。
家茂の棺が江戸城に帰って来たのは、9月6日のことでした。その時、家茂が生前、和宮への土産に用意していた西陣織も届けられます。和宮は西陣織を抱きしめて、さめざめと泣きました。悲しみの中で和宮が詠んだのが、次の歌といわれます。
空蝉(うつせみ)の 唐織(からおり)ころもなにかせん 綾も錦もきみ(君)ありてこそ
 唐織
唐織
15代将軍徳川慶喜
2人の大御台所
結婚して4年で将軍家茂を失った和宮は、21歳で落飾し、静寛院宮(せいかんいんのみや)と呼ばれることになりました。家茂の急死により、早急に決めなければならなくなったのが、徳川将軍家の継承者です。家茂は、田安家の亀之助に継がせたいという意向でした。しかし幕府老中らは、亀之助はまだ4歳で、困難な政局にあたる将軍職には適さないとし、一橋慶喜を推します。
かつて慶喜と対面し、よい印象を抱いていない篤君は、亡き家茂の意向を守るよう強く主張しますが、和宮の見解は異なりました。「確かに幼年の亀之助では、国事多難な政局の舵取りをすることは難しい」と、篤君に再考を促したのです。篤君はそれでもなお家茂の意向を重んじ、大奥の大半も篤君を支持しますが、結局は和宮や篤君の手の届かないところで、慶喜の継承が決まりました。
慶喜は2年前の元治元年3月より、禁裏御守衛総督(きんりごしゅえいそうとく)として京都にあり、在京幕府勢力の指導的立場です。将軍就任後も引き続き畿内に滞在し、篤君や和宮にすれば、顔も見ぬうちに慶喜が徳川宗家と将軍職を継ぐかたちとなりました。慶喜の正室で一橋屋敷にいる美賀君(みかぎみ)も、従来のように御台所として大奥に入ることは見合わされます。このため江戸城大奥は、篤君と和宮という2人の大(おお)御台所が中心となって運営されることになりました。
和宮が将軍慶喜に命じた3ヵ条
慶喜は長州と休戦協定を結び、長州征伐を終わらせたうえで、12月5日に将軍宣下を受けました。その直後の12月25日、孝明天皇が崩御。一貫した攘夷論者である一方、幕府政治を支持していた天皇の崩御は、幕府方には大きな痛手でした。和宮にすれば、夫家茂に続く実兄の訃報であり、孤独感を深めたことでしょう。この頃から、和宮と篤君の距離が縮まります。夫に先立たれ、その直後に後ろ盾であった養父・島津斉彬を失った篤君には、よく似た境遇の和宮の心細さが誰よりも理解できたのかもしれません。一方、勝海舟は当時の和宮についてこう語っています。
「将軍が大阪でなくなられて、棺の中に色々入れる時にネ、フト、和宮からのお手紙があつタ。それを入れようとして、フイと見て、ビックリしたよ。その精神の凛乎(りんこ)たることといふものは、実に驚いた。『一旦、徳川氏に嫁した以上は、徳川氏の為に生命をすてる。お還(かえ)りの早いことは、一日千秋の思ひでお待ち申すが、国の為に速やかに凱旋があるやうに』といふ意味さ」
すでに、婚家である徳川家のために尽くす覚悟を固めていた和宮でした。それもあってのことでしょうか、和宮は将軍に就任した慶喜に、次の3ヵ条を守るよう文を送っています。
「朝廷によく忠勤を励むこと、天璋院に孝行すること、(火事になった江戸城の)本丸を再建すること」
将軍慶喜と、徳川家の行く末を思っての和宮の言葉でした。しかし、慶喜から返事はありません。和宮はさらに「征夷(攘夷)の職掌を専一に、精勤を励み、(先般送った)3ヵ条の返答を」よこすよう伝えます。和宮には、そもそも自分が徳川家に降嫁したのは攘夷実行が条件であったのに、慶喜が諸外国の外交官らとたびたびパーティーを開いて、なし崩し的に開港を進めているのは納得できない、という思いもありました。が、慶喜からの返事は、やはりありません。
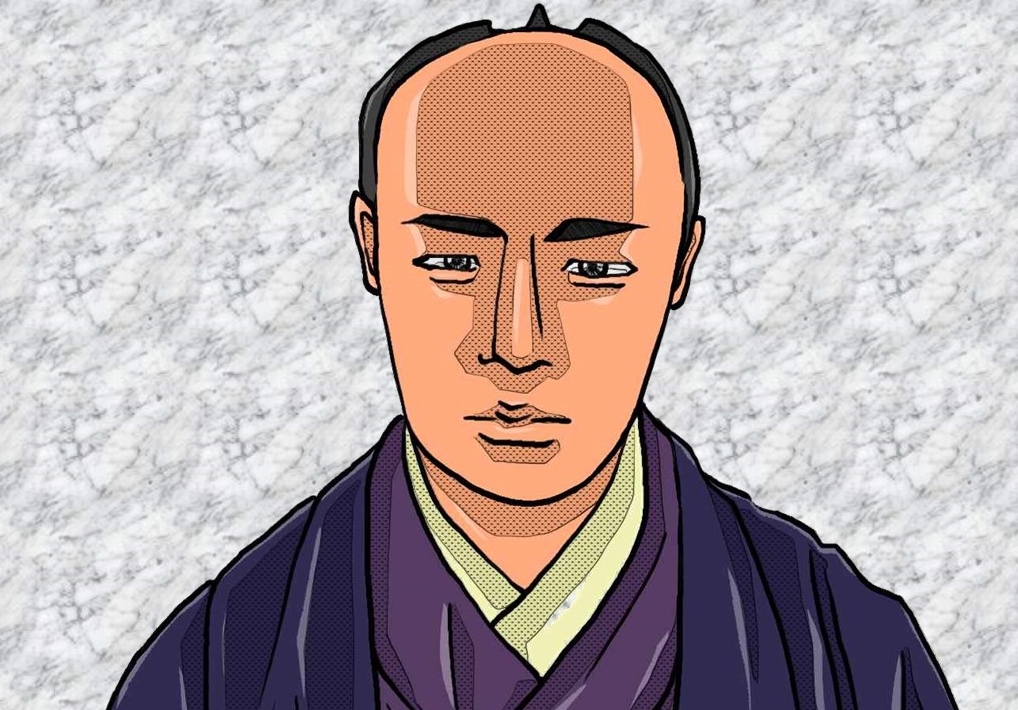 徳川慶喜
徳川慶喜
共に闘う
朝敵徳川慶喜
そして、時代は急速に動きます。慶応3年(1867)、長州藩と同盟を結ぶ薩摩藩が倒幕へと動く中、将軍慶喜は機先を制するかたちで、10月14日に政権を朝廷に返上する大政奉還を断行。ここに260年続いた徳川幕府は、あっけなく幕を閉じました。それでも徳川家は全国最大の大名であり、慶喜は引き続き政権を掌握できると読んでいたといわれます。が、12月9日の王政復古の大号令で発足した、倒幕派主導の新政権から慶喜は除外され、さらに辞官納地(官職の辞任と所領の返納)を命ぜられました。これを不服とする旧幕府側は慶喜を擁して、翌慶応4年(1868)1月に薩摩を中心とする新政府軍と衝突します。鳥羽・伏見の戦いです。しかし、錦の御旗を立てて「官軍」となった新政府軍に敗れ、旧幕府軍は「賊軍」、慶喜は「朝敵」のレッテルを貼られました。
大坂から軍艦で江戸に逃げ帰ってきた慶喜が、篤君に面会を求めたのは、1月12日のことでした。先に和宮に面会を申し込んだものの、断られています。これまで和宮が何度文を送ってもなしのつぶてであったのに、困った時にだけ頼ろうとする慶喜へ、和宮は厳しい態度を示しました。
逃げるわけにはいかない
篤君に経緯を説明した慶喜は、「朝敵の汚名返上の嘆願を朝廷に奏上いたしたく、なにとぞ静寛院宮様(和宮)へのおとりなしをお願い申し上げます」と頭を下げました。大奥にひと言の相談もなく、勝手に徳川幕府を終わらせた慶喜に強い反感はおぼえたものの、篤君は慶喜の嘆願を承知します。その理由は「これは慶喜一人の問題ではなく、徳川家の存続に関わることと」と直感したからでした。そして依然、慶喜との対面を拒む和宮に、篤君はこんな言葉をかけたといわれます。
「賊名は上様(慶喜)のみならず、徳川家に被(こうむ)ったもの。泉下の温恭院様(家定)、昭徳院様(家茂)もさぞお悲しみでございましょう」
それは、亡き夫たちが受けることになった汚名を、生きながらえている私たち正室の手で晴らさなくてどうするのか、という篤君の強い意志表明でした。和宮は、ハッと我に返ります。
「そうであった。私は亡き家茂様に、徳川家の為に命をすてると誓った。徳川家のため、家茂様の名誉を守るためにも、逃げるわけにはいかない」……。
ここから、篤君と和宮の「共闘」が始まります。
篤君と和宮の嘆願
京都の新政府に対し、先帝の皇女・和宮の言葉は少なからぬ影響力がありました。和宮が東海道鎮撫総督橋本実梁(はしもとさねなや)に宛てた書状では「私への御憐愍(ごれんぴん)と思って、汚名を雪(すす)ぎ徳川の家名の立つよう、私の身命に代えてお願いいたします」「徳川家の滅亡を見ながら生きながらえるのは残念ですので、その場合は私にも覚悟があります」と、我が身に代えても徳川家の存続を認めるよう切々と訴えています。和宮の嘆願は新政府の公家たちの心を揺さぶり、寛大な処置をほのめかす者も現れました。
しかし、薩摩藩の者たちは強硬でした。たとえば東征大総督府下参謀の西郷吉之助(さいごうきちのすけ、隆盛)は、和宮の嘆願に対してこう言っています。「慶喜退隠の嘆願など、不届き千万である。静寛院宮(和宮)も、やはり賊の一味となって、退隠ぐらいで済まそうと思っておられるようだ。ここは断固として、徳川を追討すべきと存ずる」。
そんな西郷に嘆願書を送ったのが、篤君でした。「(徳川家存続について)私がこの一命にかけて、ぜひにもお頼みするところでございます」「私が徳川家に嫁したのも、御父上様(島津斉彬)の深い御思慮があってのことです」「(徳川家存続を)取り扱っていただければ、私の一命をお救いくださるよりはるかに重く、ありがたく」「この困難をお救いくださりましたら、島津家ご先祖やお父上様(斉彬)への孝行の道が立つだけでなく、徳川家への義理も立ち、あなた様の武人としての徳と、人間としての仁心もこの上ないものと思います」と、西郷が尊敬してやまない斉彬の名を出した上で、西郷が重んじる道徳心に訴えました。和宮の嘆願は聞く耳持たない西郷でしたが、島津斉彬が見込んだ旧知の篤君の手紙は、さすがに無下には扱えなかったでしょう。一説に落涙した、ともいいます。
 『千代田の大奥 哥合』(国立国会図書館デジタルコレクション)
『千代田の大奥 哥合』(国立国会図書館デジタルコレクション)
一命にかけて
嘆願書で和宮は「私の身命に代えて」、篤君は「私がこの一命にかけて」と、それぞれ徳川家の存続に命をかけることを伝えています。その覚悟が本物であることは、彼女たちが江戸城を動こうとしなかったところにも表れていました。
慶応4年2月15日、東征大総督の有栖川宮熾仁親王率いる軍勢が京都を進発、江戸へ向かいます。その3日前、慶喜は江戸城を退去し、寛永寺で謹慎生活を開始。幕臣たちも櫛の歯が欠けるように、日に日に城内から姿を消していきました。しかし、篤君と和宮はまったく動揺せず、あらゆるつてを用いて嘆願書を送り続けます。思えば有栖川宮熾仁親王は、和宮のかつての婚約者であり、新政府軍の中心は、篤君の実家の薩摩藩でした。篤君も和宮も実家の軍勢から攻められる立場となりましたが、ひるみません。そして危険を冒して嘆願書を運ぶのは、大奥の女性たちでした。かつての武家風、御所風の対立など関係なく、大奥が一丸となって徳川家を守ろうとしたのです。
江戸城総攻撃を目前に控えた3月13日と14日、勝海舟と西郷吉之助による有名な会談が行われます。13日の会談は短時間で終わりますが、この日、勝が西郷に伝えたのは「皇女(和宮)を人質に取り奉るような卑劣な根性は持ちあわせませんので、ご安心ください。その他については、また明日」ということのみでした。しかし、言外には、こんな意味が含まれていたのかもしれません。
「和宮や篤君が命がけで徳川家存続を嘆願していることは、あんたらもよくご存じのはずだ。徳川家としては、和宮や篤君に無事に城からご退去を願いたいところだが、ここであんたらの軍が無理に城を攻めるというのなら、覚悟を固めているお二人がどうなさるか、こちらも責任は負えませんぜ」
よく知られる通り、勝と西郷の会談の結果、江戸城総攻撃は中止となります。篤君と和宮の命がけの闘いが、江戸城無血開城、徳川家存続の切り札の一つになった可能性はあるといえるでしょう。
 「江戸開城 西郷南洲 勝海舟会見の地」碑(港区)
「江戸開城 西郷南洲 勝海舟会見の地」碑(港区)
明治のある日
維新後、和宮は一時、京都に帰りますが、明治7年(1874)には東京に戻り、徳川宗家を継いだ田安亀之助改め徳川家達の養育にあたる篤君と再会しました。以来、2人は互いの屋敷をよく往来したようで、その頃のことと思われるエピソードを勝海舟が語っています。
ある日、勝の家に2人で遊びに来た時のこと。食事を出すことになりますが、下女が青くなって勝のところにやってきます。聞くと、2人が食卓でにらみ合っていると。勝が出て行き「どうなさったのです?」と訊くと、お互いに「私がお給仕するはずのところ、あなたがなさろうとされるから」。勝は笑って「なんだ、そんなことですか。それならばよい方法があります」と言って、お櫃(ひつ)をもう一つ出し、それぞれの側にお櫃を置きました。「さ、天璋院様のは、和宮様がなさいまし。和宮様のは、天璋院様がなさいまし。これで喧嘩にはなりませんでしょう」。すると2人は「安房(あわ、勝のこと)は利口者です」と言って、大笑いになりました。その後、仲良く一つの馬車に乗って帰っていく2人の大御台所を、勝は見送ったといいます。

参考文献:原口泉『篤姫』(グラフ社)、芳即正編『天璋院篤姫のすべて』(新人物往来社)、辻ミチ子『和宮』(ミネルヴァ書房)、家近良樹『徳川慶喜』(吉川弘文館)、勝海舟『海舟語録』(講談社学術文庫)、北上真生『近世期における宮廷記録とその周辺』(神戸大学学位論文) 他
「大奥」についての基礎知識はこちら
女たちの最前線「大奥」ってどんなところ? 3分でわかる記事は以下よりどうぞ!
▼和樂webおすすめ書籍
コミック版 日本の歴史 幕末・維新人物伝 篤姫

大河ドラマ『篤姫』はこちらから












