2019年9月13日から10月20日まで、東京・京橋の京橋の戸田建設本社ビルで美術展「un/real engine–慰霊のエンジニアリング」が開催中だ。
本展は、「2021年以降をマジメに考える」をコンセプトに、アーティストの藤元明が提案した現在進行中のアートイベント「TOKYO 2021」の企画のひとつで、8月3日~24日に実施された建築展「課題「島京2021」」に続いて開催されている。


会場は災害と慰霊をテーマにしたSite A「災害の国」(会場ビルの日本橋方面)と、祝祭と慰霊をテーマにしたSite B「祝祭の国」(会場ビルの銀座方面)の2つで構成され、第一線で活躍している有名作家から新進気鋭の若手作家まで、約50点の作品を展示している。
日本の歴史を「災害と祝祭の反復」という視点で見つめ直し、そのなかで新たな表現、技術を生み出してきた芸術の営みを「慰霊のエンジニアリング」と名付け、現代美術史の再構成というアプローチでその系譜をたどっていく本展。その見どころを紹介していく。
祝祭と災害の反復のなかで「慰霊」に未来を見出す
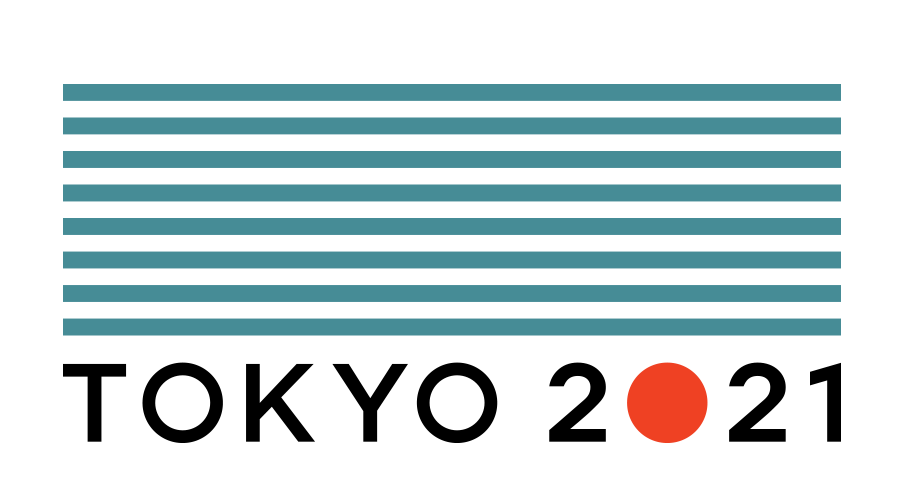
まずは、2019年現在がどういう位置づけで、なぜいま「慰霊」なのかを整理するところから始めたい。
日本は2020年の東京オリンピック・パラリンピック、2025年の大阪万博と大きな「祝祭」を目前に控えている。本展が問うのは「祝祭とはそもそも我々にとってどういう意味をもっているのか」であり、その答えのひとつが「大きな災害を乗り越えたことの証明としての祝祭」だ。
例えば、1964年の東京オリンピックは、敗戦・原爆投下を乗り越えて立ち上がった戦後復興、1970年の大阪万博は、その戦後復興を加速させる高度経済成長の象徴的意味合いが強くあった。現に、2020年の東京オリンピック・パラリンピックは「復興五輪」と声高に叫ばれ、2011年の東日本大震災という「災害」に対する「祝祭」という位置づけである。
日本の歴史を「災害と祝祭の反複」とみてとるならば、災害大国・日本がこれまでどういう風に災害を乗り越えてきたのか、そして、今後どういう風に災害を乗り越えていくのかを考えることは先の未来への備えとして必要不可欠なことでもある。
本展のキュレーションを手がけた美術家の黒瀬陽平は、序文にこうしたためている。
今まさに眼前で繰り広げられようとしている忘却と反復のなかで、「宿命」に抗い、反復の外へ出るための術を模索することこそ、芸術の「使命」であるはずだ。……災害と祝祭は宿命的に繰り返すかもしれないが、それを乗り越えようとする人々の想像力や表現、技術は、決して同じ繰り返しではない。それは孤独な「喪の作業(mourning work)」ではなく、その時代のあらゆる文化、科学と関係しながら更新されてゆく、慰霊のエンジニアリングなのである。
【災害の国】時間のヨコ軸に沿って「災害」を思い返す
高度経済成長が終わり、消費社会、情報化社会へと向かっていく1970年代を起点とした本展。美術の世界では、のちに「メディア・アート」と呼ばれる、最新のテクノロジーを用いた動向が台頭し、アーティストたちは現代美術を一種の「シミュレーター」として機能させながら、災害記憶をヴァーチャル化し、作り変え、投企してきた時代である。Site A「災害の国」の鑑賞ポイントは、記録を記憶として焼き付けるヴァーチャル体験としての「時間のヨコ軸」である。

本展で最もタイムリーな作品、カオス*ラウンジの《東海道五十三童子巡礼図》(2019)は、江戸と京都を結ぶ東海道をベースに、悟りを開くために智慧を求めて旅に出た善財童子の物語を描くことで、7月に発生した「京都アニメーション放火事件」への追悼を表している。本展準備中に事件が発生し、急きょ展示が決まったという本作は、会場の前の道が旧東海道であることともリンクし、東京にいながら被災地を想うシミュレーション的「慰霊」の実践を提起している。

八谷和彦の《見ることは信じること》(1996)は、赤外線LEDによる電光掲示板の文字を読み解く体験型の作品だ。専用スコープを覗いて読み解く特殊な掲示板には、阪神淡路大震災が発生した95~96年にかけて、八谷がインターネット上で集めた当事者の生身の声が映し出され、テレビや新聞が拾いきれなかったリアルな言葉を20年以上の時を経て追体験することができる。

渡邉英徳の《震災犠牲者の行動記録》(2016)は、東日本大震災による被災者の地震発生時から津波襲来時までの避難行動を俯瞰で可視化したデジタルアーカイブ作品だ。作品のもとになっているのは、岩手日報社が地元の遺族からヒアリング、収集した記録で、そのなかから遺族の承諾を得ることができた情報のみを使用している。いかに災害を表象するかという課題に、記録のビジュアライゼーションという形で応えた新時代の慰霊の可能性を示唆している。
【祝祭の国】空間のタテ軸に沿って「祝祭」を問い直す
「祝祭」は非日常的なお祭り騒ぎの側面だけではなく、光と影、生と死という両義性を常にはらんでいる。それを端的に示すSite B「祝祭の国」の鑑賞ポイントは、会場における作品配置で祝祭の両義性を端的にあらわす「空間のタテ軸」である。

Site B「祝祭の国」で観客を最初に待ち受けるのは、第22回TARO賞大賞を受賞し、車イスで活動する檜皮和彦の《hiwadrome type ZERO spec3》(2019)である。岡本太郎へのオマージュであり、1970年の大阪万博を想起させる作品だ。
正面に現在を象徴する「太陽の顔」と背面に過去を象徴する「黒い太陽」の2つの顔をもつ《太陽の塔》(1970)。「人類の進歩と調和」をテーマにした大阪万博に「光と影」の二面性を見出した岡本の意志が見え隠れする《太陽の塔》に複数の車イスを組み合わせ、檜皮自身の姿を投影することで、「祝祭」で置いてきぼりになりがちな現実の社会問題や葛藤を表し、2021年の東京パラリンピックを示唆しているようにもみえる。

檜皮の作品の背後に並ぶのは、弓指寛治の《黒い盆踊り》(2019)だ。祝祭の本来の「死者と生者をつなぐ」機能をもつ盆踊りをモチーフにしたこの作品、実は《太陽の塔》と同じく2つの顔をもっている。正面からみると、踊り手が皆カラフルで躍動感にあふれているのに対し、まぶしい光を放つ《hiwadrome type ZERO spec3》の影にみると、踊り手が皆真っ黒なのである。生者を活気づけるのみならず、死者を想い、慰める側面をあわせもつ祝祭の両義性を感じとることができる。

弓指の作品の隣に並ぶのが、藤本明の《幻爆 着弾 ver.》(2017)である。放射線状に広がる無機質な光線は着弾の瞬間のようにもみえるし、絶望のなかで異彩を放つ美しい光のようにもみえる。

もう一度《黒い盆踊り》に視線を戻そう。今度は真っ黒な踊り手は被爆し、返り血をあびた人たちのようにもみえる。それは祝祭に先行する大きな死でもあり、未だ解決に至っていないこの国が抱えつづける戦後の負債を目の当たりにしているようでもある。

ほかにも多数の刺激的な作品を展示している本展。会場である戸田建設本社ビルの建て替え前という条件を存分に活かし、ビルの解体作業中に出たがれきで作品を造形したり、もともとあった茶室を大胆にペインティングしたりと、自由でライブ感あふれる演出も魅力的だ。
この国で繰り返されてきた災害と祝祭と向き合い、2021年以後の世界に、どんな社会、どんな人間をのぞむのか。会場に足を運び、問い直した瞬間、あなたはすでに「TOKYO 2021」の作品の一部と化している。
美術展情報
un/real engine–慰霊のエンジニアリング
会期:2019年9月14日(土)~10月20日(日)
会場:TODA BUILDHING 1F 東京都中央区京橋1-7-1
入場:無料 ※Site Bは要事前予約https://tokyo-2021.peatix.com/
開館時間:11:00-20:00
定休日:火曜
公式HP












