琳派の代名詞ともいえる国宝「紅白梅図屏風」を描いたのが江戸時代中期の絵師・尾形光琳。中央の水流を隔て、紅白の梅が対峙する、デザイン性や画面構成の工夫に富んだ屏風は観るものを魅了します。京都で活躍した町絵師・俵屋宗達の絵を手本にして研鑽し、新しい表現を追求した光琳は、みずからの画業を締めくくるように本作を残しました。そんな尾形光琳がどんな人物だったのか、3つの視点でご紹介します。
尾形光琳ってどんな人?
1.尾形光琳は、金欠の貴公子!?
光琳は万治元(1658)年、京の呉服商「雁金屋(かりがねや)」の次男として生まれました。生家で美術工芸の粋(すい)に囲まれて育ったものの、親の遺産で放蕩三昧。30代後半には金を使い果たしたため、借金をしながら絵を描き始めました。画業で成功するも束の間、生来の派手好みは収まらず、やはり借金漬けの生活が続いたそう。豪華で華麗な作品から受ける印象とは異なり、実は生計を立てるために絵を書いていたとは意外!
▼尾形光琳の人生について、くわしくはこちら
琳派の琳は光琳の琳!尾形光琳の人生はいつ見ても波瀾万丈
2.尾形光琳は、300年後も評価されるデザイン性の持ち主!
 尾形光琳 「紅白梅図屏風」 国宝 二曲一双 紙本金地着色 江戸時代(18世紀前半) 各156.0cmx172.2cm MOA美術館蔵
尾形光琳 「紅白梅図屏風」 国宝 二曲一双 紙本金地着色 江戸時代(18世紀前半) 各156.0cmx172.2cm MOA美術館蔵
光琳は、あらゆるモチーフをデザイン的に描く天才的なセンスをもっていて、宗達に画面構成をならいながら、独自の画風を確立しました。「紅白梅図屏風」でも、大きな水流を中央に配し、その左右の金地には紅白の花をつけた梅の老木と若木という自然の景観を題材にし、実際の自然界ではありえない、異空間をつくり上げています。その印象的な画面が日本美術のイメージとかけ離れているにもかかわらず、ひとつの絵としてまとまっているのは光琳の圧倒的なデザイン力によるものなのです。

尾形光琳「燕子花図屏風」(右隻) 国宝 六曲一双 紙本金地着色 江戸時代(18世紀前半)各151.2×358.8cm 根津美術館蔵
「燕子花図屏風」は、『伊勢物語』の八橋(やつはし)の段、在原業平(ありわらのなりひら)の東下りを題材にしています。燕子花(かきつばた)のモチーフをくり返し、ジグザグに配した画面をつくったクリエイティブさは群を抜いています。
その卓越したセンスは弟乾山(けんざん)と共作の陶芸や工芸、きものまで、幅広いジャンルに発揮されました。そして梅花紋や流水紋など、後に光琳文様と称されたモチーフの数々は、その後の琳派の絵師が受け継ぎ、現在も様々な用途に使われ、琳派を有名にしたのです。
 雑誌「和樂」 2018年6・7月号の付録二筆箋では「紅白梅図屏風」の流水紋がモチーフに
雑誌「和樂」 2018年6・7月号の付録二筆箋では「紅白梅図屏風」の流水紋がモチーフに
▼「紅白梅図屏風」の見どころについて、もっと知りたい方はこちら!
尾形光琳「紅白梅図屏風」の謎を解く! 中央の川は女性のボディってホント?
3.尾形光琳は、アール・ヌーヴォーの火付け役だった
19世紀末から20世紀初めにフランスを中心にヨーロッパで流行した「アール・ヌーヴォー」は、植物の文様や流れるような曲線を特徴とした国際的な美術運動で、それがやがて「ジャポニスム」へとつながっていきました。
どうしてそのような傾向が生まれたのかというと、要因はなんと、琳派の絵画にあったのです。欧米では当時、シーボルトが持ち帰った酒井抱一の「光琳百図」や、宗達や光琳らを日本の真の印象主義と称したフェノロサによって琳派が紹介されており、光琳文様の自然表現はクリムトやミュシャなどの画家に大きな影響を与え、西洋絵画に新しい風を吹き込みました。光琳の斬新なデザイン性は日本のみならず、世界の芸術家を驚かせるほどのセンスだったのです。
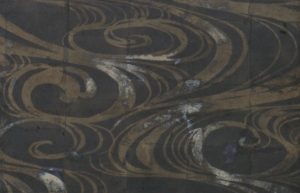 水の流れをデザイン的に描いた『紅白梅図屛風』の流水文は、アール・ヌーヴォーの先駆け!
水の流れをデザイン的に描いた『紅白梅図屛風』の流水文は、アール・ヌーヴォーの先駆け!
<番外編>琳派という表記は後世につけられたものだった
現在、琳派とは一般にも通じる言葉になっていますが、実は後につけられたものなんです。明治時代には、宗達、光琳、尾形乾山、渡辺始興(しこう)、酒井抱一、鈴木其一、池田孤邨(こそん)らが「光琳派」と称され、大正時代に宗達の再評価が進むと「宗達光琳派」と呼ばれるようになり、「光悦派」という呼称も見られました。
それが「琳派」に統一されたのは、昭和47(1972)年の東京国立博物館創立百年記念特別展「琳派」からのこと。平成16(2004)年の東京国立近代美術館の「琳派RIMPA」展では、菱田春草、横山大観などの日本画や、クリムトやウォーホルの作品なども琳派的なものとして紹介されました。光琳の「琳」は美しい玉を意味し、琳派は画派の作品傾向まで表した名称だったのです。












