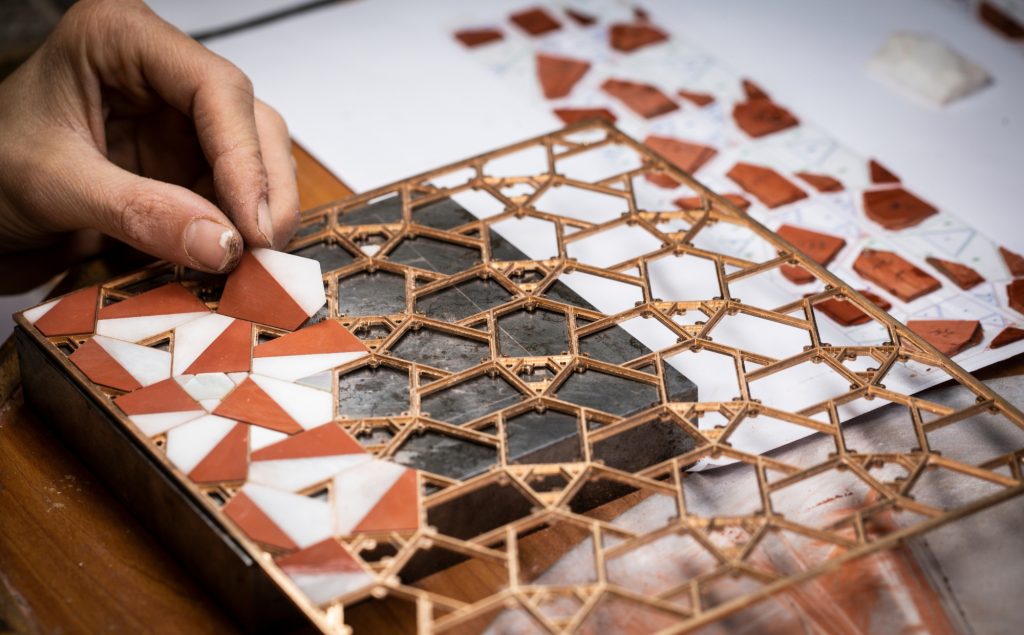七夕
七夕の天の羽衣うちかさね寝(ぬ)る夜涼しき秋風ぞ吹く 藤原高遠
天の河深き契りは頼めどもとだえぞつらきかささぎの橋 宜秋門院丹後
七夕の夕べ祈(ね)ぎごとを書いた短冊や紙飾りを笹竹に結びつけ軒に立て、隣家の飾りと見くらべて子供心に楽しかったことを思い出す。今はほとんどこの風習は個々の家に見ることはなくなり、保育園や図書館の入口で見かけるくらいだが、まだ千年の星伝説は生きているのだと嬉しくなる。
都市部では文字どおり七月七日をその日とし、地方では旧暦の八月七日にするところも多い。笹竹を立てる習俗は江戸時代からで、折ふし天の川が美しい季節でもあり優美な女手での行事となったのだ。本来は中国の古伝説牽牛星と織女星が年に一度接近する夜を嘉(よみ)して、ロマンティックな詩歌が残されている。あるいは乞巧奠(きっこうでん)と呼びならわし、女性の手技の上達を祈って染糸や布を供える祭りでもあった。

したがって万葉集以来、七夕の空を仰いで詠まれた歌はひじょうに多い。掲出歌二首のうち、はじめの歌の作者藤原高遠(ふじわらのたかとお)は平安中期の人、中古三十六歌仙の一人である。歌は二星が会うただの一夜を思いやりつつ、「初秋の風の涼しさの中で、二人はやわらかな天の羽衣を重ね合って寝ているよ」と空想をたのしんでいる。
では女性の歌人たちはどんな歌を詠んでいたのだろう。沢山の恋の歌があるにちがいないと思うのだが、実は意外に醒めていて、勅撰二十一代集中の七夕の歌の多くは男性歌人によって占められている。その中から女性の一首をあげてみよう。
「天の河深き契りは頼めどもとだえぞつらきかささぎの橋」という歌。作者は宜秋門院丹後(ぎしゅうもんいんのたんご)とよばれた中世初頭の人。後鳥羽院の中宮であった女院に仕えた女性である。ここでは二星の恋を自らの恋のように感情移入してうたっている。「天の川を渡って年ごとに必ず来るという契りは頼もしいかぎりだが、一年に一日という途絶えがちな逢瀬(おうせ)とはあまりにつらすぎますよ、かささぎさん」と、川瀬に翼を並べて橋の役をしてくれるという鳥、かささぎに訴えている。

また七夕の宵は、疑似的に、時には本音の恋の歌を交わしあえる楽しい場にもなった。古今集を代表する紀貫之(きのつらゆき)と凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)は男同士でこんな恋の歌を贈答している。
君にあはでひとひふつかになりぬればけさ彦星の心地こそすれ 躬恒
あひ見ずてひと日も君にならはねば七夕よりも我ぞまされる 貫之
躬恒は彦星、貫之は織姫の立場から逢いたさを訴えあって親愛を深めている。「たった一日か二日というのに、あなたと逢っていない私は、まるで彦星が織姫を恋うような思いですよ」というのに応えて「お逢いせず一日でもあなたのそばに居りませんと、彦星のあなたよりずっと私の方が思いはまさるのです」というもの。こんな歌を交わしてのち、笑いながら会ったであろう二人を思うと、七夕の契りにまさる友情の深まりにほのぼのとした思いになる。
馬場あき子
歌人。1928年東京生まれ。学生時代に歌誌『まひる野』同人となり、1978年、歌誌『かりん』を立ち上げる。歌集のほかに、造詣の深い中世文学や能の研究や評論に多くの著作がある。読売文学賞、毎日芸術賞、斎藤茂吉短歌文学賞、朝日賞、日本芸術院賞、紫綬褒章など受賞歴多数。『和樂』にて「和歌で読み解く日本のこころ」連載中。
現在、映画『幾春かけて老いゆかん 歌人 馬場あき子の日々』(公式サイト:ikuharu-movie.com)を上演中。
※本記事は雑誌『和樂(2021年6・7月号)』の転載です。構成/氷川まりこ