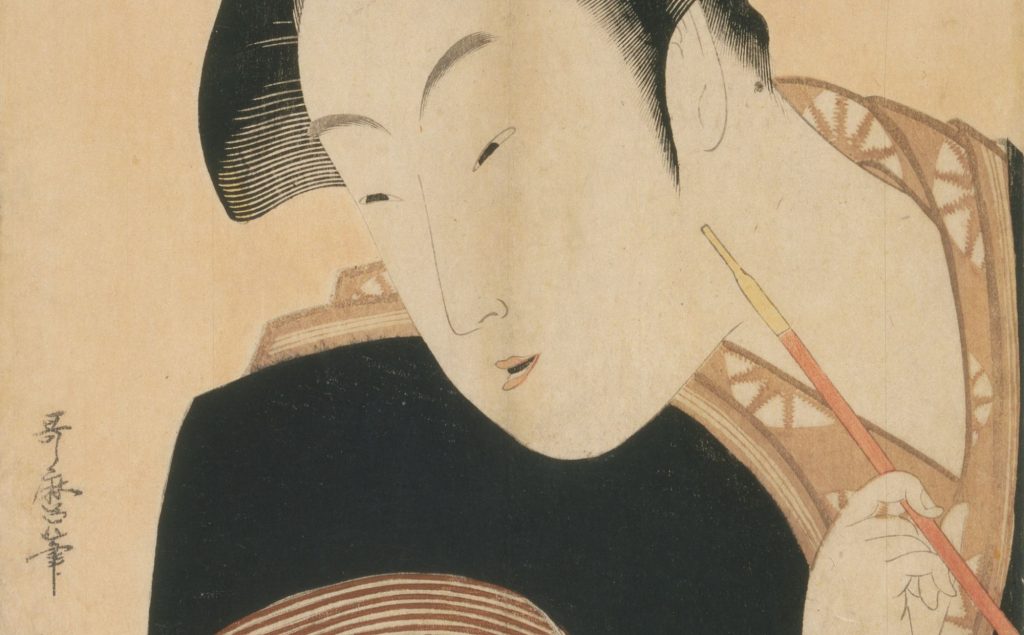平安貴族にとっての刀
本邦で刀と言えば、「武士の魂」というニュアンスで受け止められがちだ。戦争と切っても切れぬ関係にあることもあって、どうしても武家が台頭する平安時代末期以降の刀剣について語られる機会が多い。ただ争いごととはあまり関係がなさそうな平安貴族たちも、実はその生活は刀と共にあった。というのも彼らは朝廷に出勤する際、束帯と呼ばれる服を着用していたが、ある一定以上の身分にある貴族たちは必ず腰に太刀を佩(は)く定めだったためだ。
この太刀は実用というより、容儀を高めるための飾りで、「平緒」と呼ばれる平打ちの組紐で吊るし、結んだ余りを身体の前に垂らすように定められていた。ことに折ごとの節会や行幸の際には、柄を鮫皮で包み、鞘(さや)を玉や金銀、蒔絵や螺鈿で装飾した飾り太刀と呼ばれる太刀を佩くのが定めで、清少納言は『枕草子』の中で「めでたきもの(立派なもの)」として、「唐錦、飾り太刀」と数え上げている。
現在、東京国立博物館所蔵の国宝・梨地螺鈿金荘餝剣(なしじらでんきんそうのかざりたち)は、あの藤原道長も一門に連なる藤原北家の後裔・広橋家に伝えられたもの。山形金物と呼ばれる平緒に連なる金具には、菊を繊細に彫り、鞘には螺鈿で尾長鳥をあしらっている。十二世紀後半の作と推測され、総長約一メートルに及ぶ長さながらも、金具の細工の繊細さやほんのわずかに反った刀身のために、大変優美な印象を受ける名品だ。


秋篠宮殿下も受け継がれた「壷切太刀」
なお刀が身近だったのは貴族に限らず天皇も同様で、草薙剣が八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)・八咫鏡とともに古くより天皇の権威を表す神器として大切に守られてきたことは、今日でもよく知られている。また十世紀初頭以降からは、「壷切太刀」という宝剣を皇位継承のシンボルとして天皇が東宮に伝承する慣例も行われており、刀が平安社会においていかに親しみ深い存在だったかがよく分かる。
この壷切太刀は鎌倉時代の説話集『続古事談』には、平安時代前期の公卿・藤原基経が父親から受け継いだ剣と記されているが、実際のところははっきりしない。いずれにしても最初の壷切太刀は、藤原道長の孫・後三条天皇の時代に火事で焼失しており、その後は新しく作られた二代目・壷切が東宮に伝えられる太刀として用いられた。鎌倉時代、承久の乱の際に一時期行方不明になるも、数十年後に再発見され、五年前、現在の東宮・秋篠宮さまが「立皇嗣の礼」に臨まれた折にも、天皇陛下から親授されている。ゆえに当然、一般人が親しく眺めることができようわけがないが、江戸時代に記された儀式関係の文書の中に、この剣のスケッチが含まれており、それによれば柄は白い鮫皮、瑠璃玉を金飾りとともに随所にあしらい、梨地部分には鳳凰を螺鈿で飾った美しい太刀だと分かる。
坂上宝剣の謎
またこちらは現在に残っていないが、平安時代から鎌倉時代にかけて、天皇家に代々伝えられた剣の一つに、坂上宝剣と呼ばれる剣もある。これは平安京に遷都したことで知られる桓武天皇の時代の名将・坂上田村麻呂の剣だったと伝えられており、雷が鳴ると自ら鞘から抜ける奇瑞を働くと、説話集『古事談』などに記されている。
鎌倉時代の貴族・西園寺公衡の日記『公衡公記』によれば、この刀は両面に天皇への忠誠等を誓う計二十三文字の銘文が刻まれていたという。坂上宝剣という名もその銘文にあるもので、黒地に胡人狩猟図を金蒔絵し、全体は銀装、白銀を随所にあしらった太刀だったそうだ。
『古事談』によれば、醍醐天皇は鷹狩のための行幸の際、この坂上宝剣をたずさえて出かけたところ、太刀の端の石突という飾り金具を落としてしまったという。累代の重宝とあって、天皇は「稀有のことなり。古き物を(大変なことになった。古い品なのに)」と狼狽したが、鷹狩で働く犬がその後、その石突をくわえて運んできたので、事なきを得たという。
実は先に述べた壷切太刀が東宮に伝えられる太刀として用いられるようになったのは、この醍醐天皇が皇太子時代、父である宇多天皇から壷切を賜ったのが初例とも言われている。それが本当ならば、醍醐という帝の周囲には、様々な伝承を持つ古き太刀が複数集まっていたわけだ。それにもかかわらず坂上宝剣の金具をなくしかけたのだから、なるほど天皇の「大変なことになった」との思いは強かったことだろう。
ちなみにこの宝剣の元の持ち主だった坂上田村麻呂は征夷大将軍として、当時東北地方に暮らしていた蝦夷と呼ばれる人々の追討に当たり、阿弖流為(あてるい)・母礼(もれ)という首長を降伏させた人物。十世紀ごろに成立したとされる『田村麻呂伝』というその伝記には、「身長五尺八寸(約一七七センチメートル)、胸厚一尺二寸(約三十六センチメートル)」と、彼が大変大柄だったと記されている。となるとその所用だった坂上宝剣もまたかなり大ぶりな太刀だった可能性があるが、残念ながらその全長に関する記録はない。ただもしかしたら醍醐天皇はいささか大きすぎるその太刀をもてあまし、金具が落ちたのにも気づかなかったのかも――と推測すると、古しえの天皇が急に身近に感じられてくる。