「幽霊画」と聞くとどんな絵を想像するだろうか。
幽霊画といってもさまざまで、幽霊の姿を単独で描いたもの、歌舞伎の舞台などで演じられる芝居絵、物語(文学)に登場する幽霊を描いたものもある。なかには、一見すると風景画のようだが、よく見ると幽霊の姿が描かれているなんてものもあって、興味は尽きない。
そのほとんどが、肌の透けるほど薄い着物を着ていて、悲しくあきらめきったような顔、うつろな眼差し、そして多くは足が描かれない。なぜだろう?
異界をたずねて歩く
幽霊画を鑑賞するということ―それはつまり、得体の知れない仄暗い異界をのぞき見ることだ。
現世で生活する私たち生者は、あの世について、冥界から戻り現れた幽霊たちを通して知ることしかできない。神社の家系に生まれた私は神仏として信仰されていたり、土地の人々に慕われている対象によく会いにいくのだが、幽霊画もそのひとつだ。
例えば、東北地方には異界との交流を重んじる伝統が未だに根付いている。山形には死者と架空の結婚式を絵馬に描く『ムカサリ絵馬』の文化が残っているし、お盆や彼岸の法会(ほうえ)に幽霊画を開帳する寺が増えるのは、家の魔除けに幽霊画を飾ったり、雨乞いの呪具にする習慣があったからだ。
それだけでなく、「あの世」を語ることのできる幽霊画がお寺に飾られるのは、亡くなった人を思い出して懐かしむ盆供養の場としての意味もある。お盆の期間にお寺に訪れる参詣者の人たちのためでもあるのだ。
幽霊画の名品とそこに描かれる多様な世界は、先人たちにとっての幽霊はどんな存在だったのかを考えるヒントを私たちに与えてくれる。
足のない幽霊はどこから来たのだろう?
足のない幽霊についての記述は日本の国文学者、暉峻康隆(てるおかやすたか)が紹介した文政一二年(1829年)の随筆『松の落葉』にでてくる。それによれば、足のない幽霊は江戸中期の絵師、円山応挙からはじまるという。とはいえ、応挙が生まれるよりも60年ほど前、寛文十三年の浄瑠璃本の挿絵にすでに下半身のない幽霊の絵があることを、近世文学者であり芸能史学者でもある諏訪春雄は指摘する。江戸以前の幽霊画は、数は多くないものの足が描かれていたというのだ。諏訪は、幽霊が足を失う理由として、歌舞伎の幽霊が漏斗(じょうご)と呼ばれる足のすぼまった衣装で足を隠したこと、それから応挙の絵が関係していると述べる。
また、美術史家の辻惟雄は、岩佐又兵衛(1578~1650)筆『山中常盤物語絵巻』巻六に描かれている、埋葬の際の白装束を身につけた、しかし足はある、常盤御前の姿が後に応挙が描いた幽霊図の原型になっていることを指摘する。
このように幽霊画発祥のルーツはいくつかあるが、現存する幽霊画のなかで応挙以前に描かれたと思われる作品は今のところないそうなので、やはり幽霊画の創始は応挙と考えてよいだろう。応挙以降、数々の画家が幽霊画を描いているが「幽霊画」を描いたのはいったいどんな絵師たちなのだろうか?
今回紹介するのは、幽霊画を描いた絵師たちの足跡および人柄と当時の背景を鮮やかに伝えてくれる3冊の書物。
幽霊絵師を知る3冊
息づかいまで描きこむ幽霊絵師・円山応挙の人生
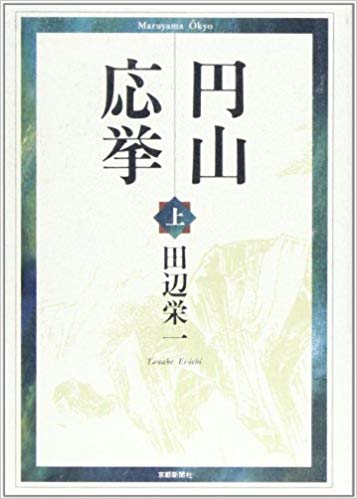
円山応挙(1733~1795)は江戸時代中期の絵師。幼名は岩次郎。通称、主水。京都に農家の次男として生まれ、玩具商へ奉公に出された。そこで出合うのが、勤めていた玩具店で扱っていた西洋伝来の「眼鏡絵」。眼鏡絵の入り口にはレンズが取り付けられていて、のぞくと絵の中に入ったような臨場感が味わえた。応挙は遠近法を駆使した眼鏡絵の制作から多くのことを学んだ。
17歳のときに狩野派の絵師、石田幽汀の門人となった応挙は本格的に絵の修行を始める。狩野派の画法のほか、古典や中国の絵画を習得し、目の前の対象を見て描くという新しい考え方と技法でそれまでにない絵画表現を実現してみせた。
「主水は、このところ、写生、という言葉の意味を考えつづけていた。(略)絵師として世間を渡って行くためには、画教というか、画面全体からうける感じが鑑賞する人の眼を満足させる必要がある、とも思っている。心象主義とでもいうのであろうか?」
そんな彼がどうして幽霊なんてこの世にあるかなきか分からないものを描いたのか?
その答えが、応挙をめぐる人々との活き活きとした会話から浮かび上がってくる。伊藤若冲など、個性的な絵師が登場するのも読んでいて楽しい。
本書は、資料不足のためにフィクションの部分もあるが、応挙の入門期から新たな画境に至る円熟期の生き様、絵師としての苦労を京都の町を背景に鮮やかに描いた一冊だ。
団鬼六と責め絵画家・伊藤春雨の最強タッグ
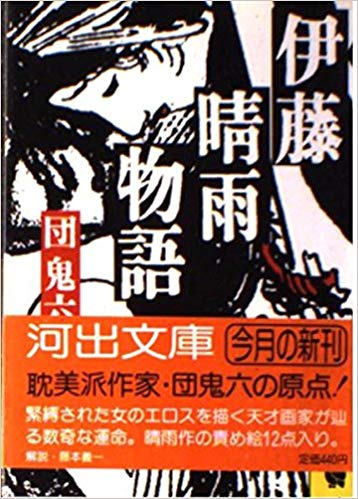
小説家の団鬼六がSMポルノ小説に本腰をいれる契機になった『伊藤春雨物語』は、小説というより評伝にちかい。
女性の官能を巧みに描くことに定評のある団鬼六が風俗画や責め絵で知られる絵師・伊藤春雨(1882~1961)の生涯を小気味よい筆致で描いてゆく。マニアでなくとも、心惹かれる組み合わせだ。
晴雨は、明治から昭和初期の画家。浅草の彫金師の家に生まれ、8歳で江戸琳派の野沢堤雨に師事した。最後の浮世絵師と称されることもある晴雨の幽霊画はどこかモダンな印象を見る者に与える。それは絵描きを目指して職を転々としながら看板絵や劇界、新聞社で小説の挿絵を描いて身につけた技術のためかもしれない。だからか、洒脱な描線や柔らかな陰影、透けるように青い春雨の幽霊画はときに劇的。
女絵にしても、晴雨の異常なモノへの執着心やもって生まれた性向が交じりあいながらも、どこか冷めた研究心のようなところも伺える。明るいうちには新聞雑誌の挿画、舞台の幕画などの仕事にかかり、夜には自室にこもり自身の芸術を追求する描写からは画家としての熱心さが伝わってくる。また、巻末の48の絵は圧巻だ。
エキセントリックかつハイクオリティ・河鍋暁斎
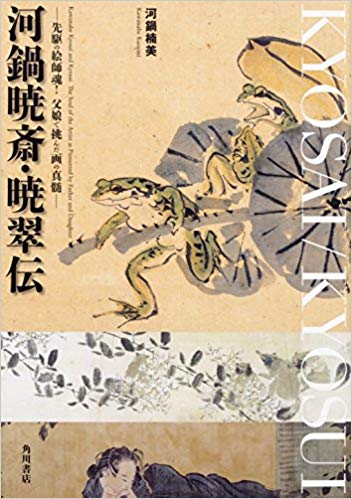
最後に紹介するのは、日本人はもちろん海外の方にもすすめたい一冊。
早くから絵の才能を発揮した河鍋暁斎(1831~1889)は、伝統的な画風を習得した絵師で、浮世絵、戯画、行灯画、巻物、屏風などを描いた。あまりにも幅広い芸域のため、所属するところが定まらない感じを世に与えた作家と言えるだろう。
暁斎の多様な世界観と幅広い画業を支えたのは、当時の画家のみならず日本に住んでいた外国人や能、狂言、歌舞伎役者との交流だった。
そのエッセンスがつまった本書で著者は―「国際人 暁斎」の中で、「暁斎存命時に来日した外国人の中で、暁斎に会った者、文章を残した者、作品を所有した者等、暁斎と直接・間接的に関わった人々を数えると、現在判明しただけで21名にも及ぶ」と述べている。その一人がパリでその一大コレクションを所蔵展示する現・国立ギメ美術館を創設したフランス人実業家、エミール・ギメ(1836~1918)で、帰国後出版された著作のなかで、暁斎との鮮烈なやりとりを伝えたと記している。だからこの一冊には、そうした交流を経て創作された、乙女心をくすぐる美しい紙製品のデザインや絵本など、幽霊絵師以上の暁斎の姿がある。
ところで社交的な印象も与えるこの暁斎、幼少時に川で拾った生首を写生したという逸話も残されている。見る者に強烈なインパクトを与える、幽霊絵師・暁斎の写生に基づく的確な描写もうなずける。
夏はこの世ならざるものたちの季節…
幽霊はどれも、死んだ後になんらかの事情でこの世に姿を現した人間の姿だ。変わり果てた姿が見る者の心に切なく沁みるのは、彼らがかつては私たちと同じように生きていたことを私たちが知っているからかもしれない。と言っても、幽霊画にはじんわりと怖さがこみあげてくるおどろおどろしい作品だけでなく、ユーモラスに風刺を含む作品もある。土着の民間信仰と深い関わりのある作品も多い。
それに、幽霊画の名品を数多く送り出してきた絵師たちだって幽霊ばかり描いていたわけじゃない。いずれも画才にあふれ、絵師として見事にその卓抜なる技量を発揮してきた面々だ。
この3冊を読んでから展覧会に行くもよし。絵を見たあとで絵師たちに思いを馳せるのもよいだろう。今回紹介した絵師たちによる幽霊画は、谷中・全生庵で開催中の「幽霊画展」でもみることができる。
じめっと不快な日本の夏。
日本を代表するユニークな絵師たちによって描かれた幽霊画を見に出かけてみてはどうだろうか。
谷中圓朝まつり 幽霊画展
会期 2019年8月1日~2019年8月31日 ※土日祝祭日も開催
会場 全生庵
住所 東京都台東区谷中5-4-7
開館時間 10:00~17:00(最終入場16:30)
拝観料 500円
https://www.yureiga.com












