この世のキワにいるかもしれない不思議な存在。怪しく、不吉な日常ならざるもの「怪異」。
妖怪や怪異をフィクションとして楽しむ妖怪文化が盛り上がりをみせた江戸時代、怪異は文学の中にも棲みついた。「仮名草子」「浮世草子」「読本」などに収められた怪異譚からは日本独自の妖美で淫虐な世界を覗くことができる。
なかでも江戸時代後期の読本作家、上田秋成の『雨月物語』(1776)は日本でも指折りの怪談・怪異小説だろう。中国や日本の古典に素材を得たこの古典物語集には、人間世界の邪悪な葛藤や報われない想いを抱えた亡霊たちが日常の闇にひっそりと登場する。
■和樂web編集長セバスチャン高木が解説した音声はこちら
上田秋成の『雨月物語』より3つの物語をピックアップ
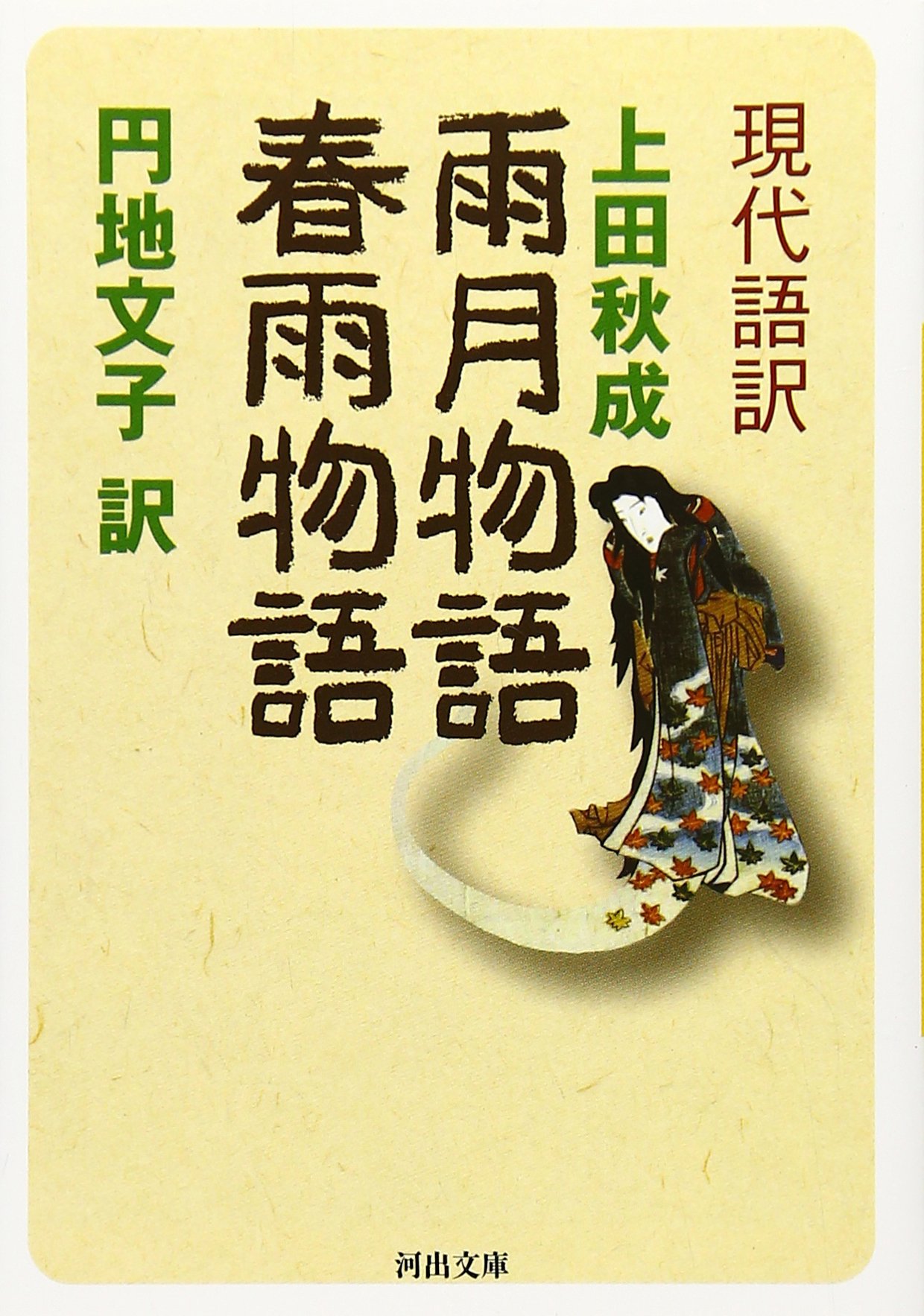
愛する人を待ち続けた女の怨霊が迎える悲しい結末「浅茅が宿」
舞台は現代の千葉県松戸あたり。
京へ商売に出て一儲けをたくらむ勝四郎という男が妻をひとり家に残し出立してしまう。
戦乱のために家に戻れず、7年もの歳月が過ぎた後。
ようやく勝四郎が故郷へ帰ると、家は7年前と同じ場所に建っている。戸の間からこぼれる灯り。家に近づくと、中ではやつれた妻が勝四郎を一途に待っていた。夫を迎え入れた妻はさめざめと泣く。2人は7年間の出来事を語りあい、床を共にする。
夜明け頃、勝四郎は目を覚ます。どうも様子がおかしい。妻の姿がないのだ。屋根は風にめくられ、家は昔の面影もないあばら家になっている。
勝四郎は妻が会いたいと嘆きつつ夫の帰りを待ち、しかしすでに死んでいたことを知るのだった。
夫に裏切られた妻の執拗な復讐
「吉備津の釜」
正太郎という名の女癖の悪い男がいた。
正太郎は磯良(いそら)という娘と結婚するが、袖(そで)という愛人をつくり妻のところには寄りつかなくなる。さらに正太郎は磯良の優しい心につけ入りお金を持ち逃げる始末。騙されたショックから磯良は病に倒れ、死んでしまう。
一方、正太郎は愛人の袖とよその土地に住みついていた。しかし袖もまた物の怪が憑いたかのように発狂し、亡くなってしまうのだった。
悲しみに明け暮れる正太郎。あるとき墓参りで出会った若い娘から「主人を亡くした未亡人に頼まれて墓参りをしている」と聞いた正太郎は、娘の案内で未亡人宅へ向かう。正太郎が未亡人に話しかけると、振り返った女性は磯良だった。「どれほど辛かったか思い知らせてやろう」という磯良の姿に、正太郎は気絶してしまう。
正太郎が陰陽師に助けを求めると陰陽師は今から42日間物忌みをし絶対に外に出てはいけないと告げ、正太郎の体に呪文を書いた。夜になると家の外では護符のために侵入できない怨霊が恐ろしい声で叫んでいる。
さて、やっと夜が明けたと安堵し戸を開けると、夜明けと思ったのは実は怨霊の幻術だった。正太郎は青ざめる。
翌日。軒先には男の髪の毛だけがぶら下がり、大量の血が入り口に流れていた。
美少年を溺愛するあまり鬼になった住職
「青頭巾」
改庵妙慶(かいあんぜんじ)という僧侶が旅の最中に、下野の国(現在の栃木県)の小さな村を訪れた時のこと。僧侶は村人から近くの山に住んでいる寺の住職の話を聞く。
その住職は自分の身の回りの世話をさせていた美少年の稚児を溺愛し、しだいに本職まで怠るようになった。稚児が病で亡くなると、その死をあきらめきれない住職は火葬も土葬もせずに、遺骸を側において抱きしめ、その肉が腐るのを惜しみ、肉を食べ骨をしゃぶり、ついには食べ尽くしてしまったという。そして里に下りてきては墓を暴き、死肉をむさぼり食い、村人を追いかけ回す鬼に成り果ててしまった。改庵妙慶は村人の話を聞き、鬼となった住職を何とか正気に戻さなければと決心する。
その夜、改庵妙慶が山に登り荒れ果てた寺の中で座禅を組んでいると、僧とも俗人とも区別がつかない鬼と化した住職が現れる。改庵妙慶が一喝すると、僧のおぼろげな姿は氷のように消え失せ、改庵妙慶の被せた青頭巾と白骨だけが草葉のなかに残っていた。
秋成が怪異のなかに見出した「哀しみ」と「美しさ」
古い妻の夫への執拗な復讐を描く「吉備津の釜」は身の毛もよだつ恐ろしい物語だ。護符のために侵入できない怨霊が「ああにくい!」と怒り恨む声の凄さ。月明りにすかし見えた男の髪の残骸や壁の生々しい血がそそぎ流れる様子などは思わず背筋が寒くなる。と同時に、ほのかに悲しみが漂っているようにも感じる。
「浅茅が宿」で勝四郎が妻の背中をなでさすり「もう夏の短夜は明けるだろうに」となぐさめる場面。さめざめと泣く妻の異様な美しさ。
妻はもうこの世の人ではないと夢見心地の勝四郎は涙さえ出ない。そんな勝四郎が妻の筆の跡と思われる和歌を発見し、詠み、泣き崩れる場面には格別の哀しみを感じる。
秋成は「青頭巾」の愛しさのあまり稚児を食べてしまった僧を、異常な悪人として描いていない。そこにいるのは、鬼に変じてしまうほどの過剰な愛を抱え、過激な欲望に振り回された人間の成れの果て。人間の内奥に潜む「性(さが)」だ。秋成は怪異のなかに人間のもつ哀しみと美しさを見い出していたのだろう。
人々を魅了する美しくも悲しい亡霊たち
『雨月物語』を読んでいると、妖怪や幽霊などの怪異が本来の棲みかとしているのは人間の心の内部なのではと思えてくる。人の心のなかにある恐怖心、嫉妬、悲しみなどを物語にしたものが怪異文学だとするなら、『雨月物語』で登場人物たちに奇々怪々な災いをもたらす怪異たちは、現代の日本人にも通じるところがある。
月岡芳年が描いた「皿やしき於菊の霊」「保多舞とうろう」などの浮世絵が今もなお人々を魅了するのもまた、幽霊たちの哀しみと美しさに惹かれてのことかもしれない。


見えるものと見えないもの
近代の科学や技術は現実世界から怪異を排除してきた。
現代では日常レベルで化け物を意識することはほとんどないだろう。だからといって、怪異がもはや信憑性を失ったということはない。
病があれば現世の神々に手を合わせて回復を祈り、都市の各所や片隅に神の小社が祀られているのを見つける。強大な自然の威力は私たちを畏怖させるのに充分な力を備えている。
異界冥界は人間と表裏一体の存在だ。そして、怪異は江戸の時代から変わらず私たちの日常の傍らにある。












