「口紅」と聞いて、何色をイメージしますか?
赤? ピンク? それとも――
江戸時代後期、「緑色」の口紅が、女性たちの間で大流行しました。紅花から作られる「紅」を塗り重ねて、下唇を玉虫色に光らせるメイクです。一体なぜ、緑色の口紅が流行したのでしょうか。そこには、日本独自の美意識が深く関わっていました。江戸時代から続く「日本最後の紅屋」、伊勢半本店で、口紅の歴史と「紅」の秘密を取材しました。
「小町紅」の謎めいた輝き
古今東西、代表的な口紅の色と言えば、やはり「赤」です。赤は太陽の色。古くから、生命力やパワーの象徴、魔よけの色として用いられてきました。世界各地で、古代から赤い色を唇や身体に塗る風習があったことが確認されています。日本でも、縄文時代には、既に赤い塗料を顔や体に塗る風習があったようです。

赤い口紅の原料となる紅花が、中近東・エジプトからシルクロードを通って日本に伝わったのは3世紀半ば。奈良時代には、日本でも、身分の高い男女が紅花の色素を化粧に使うようになりました。遣唐使から伝えられた唐の流行にならい、唇をくっきりと赤く塗って、額や口元に花や星の絵を描くこともあったそうです。このころから化粧には、赤・白・黒の3色が使われていました。
平安時代になると、貴族や平家の武士など、高貴な男性もこぞって化粧をするように。この時代の化粧は、女性のお洒落というより、身分や階級を表すもの。女性が口紅をつける場合、唇が小さく見えるように、下唇にほんの少し紅を点すのが流行したようです。
江戸時代の後半になると、庶民の女性も化粧を楽しむようになります。中でも「紅」は、口紅や頬紅、目元や爪の先など、ポイントカラーとして重宝されるようになります。
粋な江戸の女性たちの間で憧れの的になったのが「小町紅」。京都産の高品質な紅ブランドです。紅の原料を買い取って精製し、販売する「紅屋」が続々と誕生しました。文政8年(1825年)、日本橋で創業された伊勢半本店も、そんな紅屋のひとつ。明治に入り、海外から入ってきた安価な化学染料に押されて多くの紅屋が廃業する中、日本に存在する唯一の紅屋として、現在も「小町紅」の伝統を守り続けています。
s.jpg)
写真は、現在も伊勢半本店で購入することのできる小町紅です。「紅猪口」と呼ばれる、紅を塗った磁器の内側が、美しい玉虫色に輝いています。この玉虫色の表面を、水で湿らせた筆で撫でると、一瞬で鮮やかな紅色に変わり、赤い口紅として使うことができます。
紅花から取り出した赤い色素を、どうやって玉虫色の小町紅に加工するのか、その製法は現在も秘伝とされ、歴代の紅匠(紅職人)にのみ受け継がれているとのこと。さらに、紅花の色素がなぜ赤から玉虫色に、また玉虫色から赤に変化するのか、そのメカニズムも、いまだ解明されていません。
江戸のトレンドメイク「笹紅」
そんな謎めいた小町紅を唇に塗り重ねることで起こるある「変化」をいち早くファッションに取り入れたのは、当時大人気だった歌舞伎役者や、太夫や花魁など、身分の高い遊女たちでした。

上の浮世絵をご覧ください。紅を点す女性の口元をよく見ると、下唇が緑色に見えます。純度が高く、精製の密度が細かい小町紅を何度も塗り重ねると、唇が玉虫色に輝くのです。「笹紅」と呼ばれるこの斬新なメイク法は、新しいもの好きの江戸っ子たちの間で、たちまち大流行します。
玉虫色に光るのは、品質の高い小町紅だけ。当時の小町紅は、現在の金額で1つ6~7万円という高級ブランド品です。庶民の女性たちには、とても手が届きません。そこで女性たちは、下唇を墨で塗りつぶした上から、精製の粗い廉価な紅を塗り、流行の「笹紅」を再現したそうです。いつの時代も、流行のお洒落を取り入れたいという女性たちの思いは変わらないのですね。
玉虫色の口紅と『陰影礼賛』

当時の女性たちのメイクをイメージしてみましょう。着物の襟から上は、白粉で真っ白に塗りつぶされています。結婚した女性たちは毎日お歯黒をつけて歯を黒く染め、出産後は眉を剃り落としていました。最後の仕上げは「笹紅」。上唇は赤、下唇が玉虫色です。
――いかがでしょう? 現代の色彩感覚に照らすと、正直、かなり違和感があるのではないでしょうか。ヨーロッパや中国など、同時代のほかの地域で「緑色の口紅」が流行したという記録は残されておらず、どうやら日本だけの現象のようです。
幕末から明治初期にかけて日本を訪れた外国人たちの目にも、日本女性のメイクはかなり奇異なものに映ったようです。「日本人の紅や白粉を皮膚につける熱心さは(中略)醜悪化の技術にほかならない」(R.オールコック)などと酷評されています。
一体なぜ、このようなメイクが流行したのか。その秘密を解くヒントを、谷崎潤一郎『陰影礼賛』の中に見つけることができます。
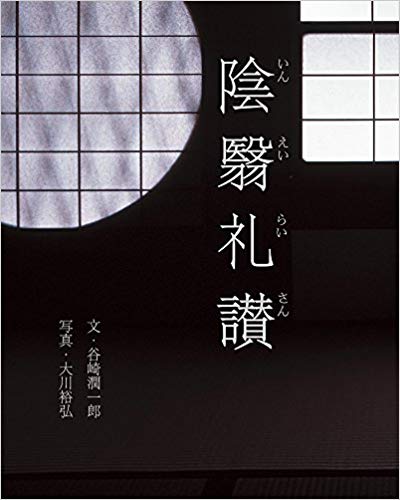
私が何よりも感心するのは、あの玉虫色に光る青い口紅である。(中略)あの紅こそはほのぐらい蝋燭のはためきを想像しなければ、その魅力を解し得ない。古人は女の紅い唇をわざと青黒く塗りつぶして、それに螺鈿(らでん)を鏤(ちりば)めたのだ。豊艶な顔から一切の血の気を奪ったのだ。私は、蘭燈(らんとう)のゆらめく蔭で若い女があの鬼火のような青い唇の間からときどき黒漆黒の歯を光らせてほほ笑んでいるさまを想うと、それ以上の白い顔を考えることが出来ない
江戸時代の日本には、現代のように、部屋の隅々までを照らす蛍光灯はもちろんありませんでした。街灯などもありませんから、日が暮れると街は闇に沈み、家の中も真っ暗です。灯油を使った行灯が一般的でしたが、ほのかに人の顔が認識できる程度。薄暗がりの中で、白粉を塗った女性の顔が、白く浮かび上がって見えたことでしょう。そして玉虫色の唇が、妖しく美しく光ったのではないでしょうか。
緑色の口紅は、光だけでなく影までも「美」の要素として味方につける、日本独自の美意識を反映しているのかもしれません。
関東大震災が日本女性のメイクを変えた
大正時代末期、日本女性のメイクにとって、大きな分岐点となる出来事が起こります。それが、関東大震災。体の動きが制限される和服を着ていたために、多くの人が逃げ遅れて犠牲となったのです。これをきっかけに、動きやすい洋服を身に着ける女性が急激に増えたと言われています。その結果、服装に合わせて、メイクも洋風に変化していきます。西洋から伝わったスティック型の国産口紅が販売されるようになったのも、大正時代からです。
第二次世界大戦中、金属の供給が不足するようになると、木製の容器に入ったリップスティックが販売され、大戦直後には、紙巻きの口紅も作られていました。

戦争も、お化粧をしたいという女性たちの気持ちを奪うことはできませんでした。あるいは、明日をも知れぬ命だからこそ、身だしなみを整えておきたいという思いがあったのではないでしょうか。
戦争が終わると、化粧品や口紅は百花繚乱の時代に。ハリウッド映画を真似たピンクベースのメイクが流行したり、昭和30年代からは、化粧品メーカー各社による「落ちない口紅」戦争が勃発。女性たちが、個性の表現としてお洒落を楽しむ時代が訪れたのです。
現代に生きる「小町紅」の魅力
昭和に入り、西洋風の手軽で安価な口紅が流通するようになると、精製に手間のかかる小町紅の生産は縮小されていきます。日本最後の紅屋となった伊勢半本店では、現在も、主に山形県産の紅花を使って、化粧用のみならず、絵の具用の紅や、和菓子などに使われる食紅の製造・販売を続けています。

伊勢半本店が運営する「紅ミュージアム」では、伝統的な紅の製造方法や化粧の歴史について、詳しく知ることができます。併設のミュージアムショップでは、小町紅の購入や、無料体験もすることができます。

一般的な口紅とは違い、つける人の肌色や筆に含ませる水の量、重ねる回数によって、色が変わるのが紅の特徴。リップだけでなく、チークやアイメイクにも使うことができます。筆者も体験しましたが、さらりとした軽い着け心地で、自然な発色が魅力的です。もちろん、重ね塗りすることで玉虫色の「笹紅」になります。

自分自身で使うためのみならず、贈答用としても人気の小町紅。天然素材100%で、自然な発色で血色が良く見えることから、病気の方のお見舞いに買い求める方もいるそうです。
時代や環境の変化に合わせ、さまざまに形を変えながら、日本の女性たちの唇を彩ってきた口紅。それは身だしなみや装いの意味を超え、女性の気持ちを華やかに盛り上げて非日常へと誘い、時に勇気を与えてくれる「スイッチ」のような存在なのかもしれません。
次に口紅を選ぶときには、古人を魅了した小町紅を、選択肢のひとつに加えてみてはいかがでしょうか?
伊勢半本店「紅ミュージアム」について
住所:東京都港区南青山6-6-20 K’s南青山ビル1F
開館時間:10:00~18:00
休館日:毎週月曜日(祝日または振替休日の場合は翌日休館)・創業記念日(7月7日)・年末年始
公式webサイト:https://www.isehanhonten.co.jp/museum/












