妻がいる身でありながら、単身赴任先で魅力的な女性に出会い、恋に落ちてしまう…
今も昔も、そんな醜聞は尽きません。
1200年以上前の奈良時代にも、遊女との恋におぼれ、上司にも浮気がバレて、こってり叱られてしまったサラリーマンがいました。
「上司」とは、和歌の達人だった大伴家持(やかもち)。家持は、部下にお説教をするときも和歌を使いました。その歌が『万葉集』に収録されたため、後の世まで「単身赴任先で浮気をした男」の名前が語り継がれることになってしまったのです。浮気を知った男の妻がとった、衝撃の行動とは……!? 不倫の恋の顛末を見ていきましょう。
万葉の貴公子、大伴家持の憂うつ
天平勝宝元(749)年、越中(現在の富山県)に国司(行政官)として赴任していた貴公子、大伴家持は悩んでいました。部下である尾張少咋(おわりのおくい)が不倫の恋をしているという噂を耳にしたからです。少咋は、妻と子どもを都に残し、史生という下級の書記官として単身赴任していました。にもかかわらず、遊女の左夫流児(さぶるこ)にうつつを抜かし、官舎に彼女を連れ込むありさま。その姿は地元の人たちの間でも笑い物になっていたのです。

当時は現代と違い、男性が複数の女性とお付き合いすることが珍しくない時代。家持自身も、都ではモテモテのプレイボーイとして名を馳せていました。とはいうものの、やはり現代でいう「正妻」と「妾」のような区別はあったよう。苦楽を共にした正妻は、たとえよそに別の恋人がいようとも、まごころを持って大切にするべきという価値観は存在していました。
これは想像ですが、少咋の浮気が「できごころ」の範囲にとどまっている間は、家持も目をつぶるつもりだったのではないでしょうか。家持のような風流人にとって、恋は人生のスパイス。一人の女性にのめり込みすぎず、秘密の駆け引きを楽しむことは日常だったはずです。でも、きっと少咋は家持と違い、妻以外の女性とあまり恋をしたことがない、真面目な役人だったのでしょう。真面目な人ほど、恋に夢中になると、うっかり落とし穴にはまったように周りが見えなくなってしまうものです。

地元の人にまで後ろ指をさされている部下を放っておけば、上司である家持自身の評判にもかかわります。といって、部下のプライベートにあからさまな口出しをするのも野暮ったい……
「よし、私の和歌で、少咋の目を覚まさせてやろう!」と思ったのかどうか。家持はおもむろに筆を取り上げて、手紙を書きはじめます。
「序文」からスタートして、「長歌」さらに「反歌3首」から成る長い長い手紙です。部下の浮気をとがめるにしては、やけに長いのが引っかかりますが、まずはざっと読んでみましょう。

妻を放っておいて、若い女性にのめり込んでいる君は、なんてどうしようもないんだろう!
序文と長歌は何しろ長いので、本文の引用は省略しますが、意訳するとだいたいこんなことが書かれています。
「法律では、妻を離縁してもいい7つの条件が定められている(子がないこと、淫乱であること、舅・姑に仕えないことなど)。このうち1つでも犯せば妻を離縁できるが、どれにも当たらないのに妻を捨てたものは、1年半の懲役に処する。妻を持ちながら重ねて結婚したものは、1年の懲役。相手の女は杖で百叩きにされる。
良い夫の道とは、妻と別れることなく、同じ家で共に財産を守ることだ。古い妻を忘れて新しい女を愛するなんて、とんでもない! 古い妻を捨てようとする君の心の迷いを断つために、いくつかの歌を作った」
法律を引用した上で、「これからお説教するから、心して読みなさい」という前書きです。
長歌にはどんなことが書いてあるのでしょう?
「神さまの時代から、両親を見れば尊く、妻子を見れば切ないのがこの世の道理。君もかつて貧しかった時代には、愛しい妻と『いつまでこんな貧しい生活が続くのか』と泣いたり笑ったりしたことだろう。苦労の末、ようやく春の花が咲くように暮らしむきが良くなったのに、今度は君の単身赴任で、2人は離れて暮らすことになった。いつになったら君からの使いが来るのかと、待っている妻の心はどんなに寂しいことだろう。よりどころもなく左夫流児という女と結びあって、2人で心の奥底まで惑っている君の心の、なんとどうしようもないことだろう!」
辛苦を共にした妻を放っておいて、若い女性にのめり込んでいる少咋を、上司として情けなく思う家持の気持ちは、ここまででもう十分伝わってきます。けれど、筆がのってきてきたのでしょうか。家持の追求は、まだ続きます。
ああ恥ずかしい! 若い女に溺れている君が出勤してくる後ろ姿
あをによし奈良にある妹(いも)が高々に待つらむ心然(しか)にはあらじか
(奈良にいる愛しい妻が、首を長くして待っているであろう君の心よ。今のままではいけないんじゃないか?)
1首目で家持は、まず「奈良にいる奥さんのこと、考えてみろよ」と反省を促しています。
里人の見る目恥づかし左夫流児にさどはす君が宮出後姿(みやでしりぶり)
(里の人たちのこっちを見る目が恥ずかしいじゃないか。左夫流児という女に溺れている君の、朝出勤してくる後ろ姿は)
「しりぶり」って、何だか情けない響きの言葉ですよね。「君、自分の行動を客観的に振り返ってごらんよ。ああ、恥ずかしい!」と別の視点から少咋を説得しようとしています。
紅は移ろふものぞ橡(つるはみ)のなれにし衣(きぬ)になほ及(し)かめやも
(紅に染めた衣は色あざやかだけど、すぐに褪せてうつろってしまうものだよ。着慣れた橡染めの衣に及ぶことがあるだろうか。いや、及ばないだろう)
「橡」はクヌギの実のどんぐりのかさを使って染める、渋染めです。褐色を重ねることで黒っぽい色を出します。庶民の女性たちがふだん着として身につける、いわば「生活の色」。都に残してきた奥さんの象徴です。一方、「紅」は遊女である左夫流児の象徴。確かに美しく目を奪われるかもしれませんが、すぐに色褪せてしまう。苦楽を共にし、長く寄り添ってくれる奥さんとは比べようもないだろう? とダメ押しの一撃を加えた歌です。
内容は「浮気男へのお説教」ですが、さすが和歌の名人大伴家持、衣にたとえた表現が見事ですね。
夫の浮気を知った妻の、怒りの行動とは!?
さて、上司の家持から長い長いお説教の手紙を受け取った尾張少咋は、さすがに自分の行動を反省したのではないでしょうか。もしかすると、都の妻に「長い間、寂しい思いをさせたね。僕にはやっぱり君しかいないよ。これからは一緒に暮らそう」なんて甘い言葉をしたためた手紙を送ったかもしれません。
ところがその矢先、事件が起こります。万葉集には、その顛末を詠んだ家持の和歌も収められています。
(詞書)先妻の、夫君の喚使(かんし)を待たずして自ら来たりし時に作りし歌一首
左夫流児が斎(いつ)きし殿に鈴掛けぬ駅馬下れり里もとどろに
(本妻が、夫からの迎えの使者を待たず、自分から乗り込んできたときに作った歌
左夫流児が大事に守ってきた家に、鈴もかけない駅馬が乗り込んできたよ。その勢いといったら、里をとどろかすようだった)
都からの公的な使者は、その印として、馬に鈴をつけることになっていました。その鈴もつけず、少咋の妻がすごい勢いで少咋の家に乗り込んできたというのです。現代ならば新幹線か飛行機を使うところでしょうが、裸の馬で奈良から富山まで駆けてきたというのがまた、妻の怒りの激しさをあらわしているようで迫力があります。少咋、絶体絶命のピンチです。
少咋の家で、妻と浮気相手の左夫流児がはち合わせして修羅場が繰り広げられたのかどうか、万葉集には語られていません。「里をとどろかすようだった」というのですから、少咋のスキャンダルは当時の人びとの格好の噂の種になったことでしょう。現代で言えば、週刊誌でスクープされ、SNSで炎上……というところでしょうか。
尾張少咋の浮気事件をめぐる謎
ところで、少咋の浮気をめぐるドラマがミステリーだとすると、まだ解かれていない謎が残っていると思いませんか? そうです、奈良にいる妻に、いったい誰が少咋の浮気を知らせたのか、ということです。
なかなか左夫流児と別れない少咋に業を煮やした家持が都に使いを送ったことも考えられますが、わざわざ都にいる少咋の妻を怒らせて事を荒立てるのは、風流人の家持らしくない気がします。

そもそも、少咋の浮気を上司である家持がたしなめ、浮気を知った妻が乗り込んできて里が大騒ぎになる……というこの筋書き自体、コメディとしてあまりにも出来すぎているような気がします。さらに、一連の歌の作者である大伴家持は、万葉集の編纂者としてもその名を知られています。これらのことを考えあわせると、私には、このストーリーの裏で、にやりと笑っている「プロデューサー・大伴家持」の顔が見えるような気がするのです。
尾張少咋の浮気事件は確かに存在したのでしょうが、どこまでが真実で、どこからが家持の文学的演出なのか。単身赴任先で浮気をし、都に残してきた妻をおろそかにする役人たちが後をたたないため、この物語を通じて「浮気はダメよ!」とお灸をすえる意図もあったのでは……? と妄想はふくらみます。
「誰が、妻に少咋の浮気を知らせたのか」という謎については、『万葉恋づくし』(梓澤要/新潮社)という小説で大胆な仮説が示されています。興味がある方は、ぜひ万葉集と共に、手に取ってみてはいかがでしょうか?
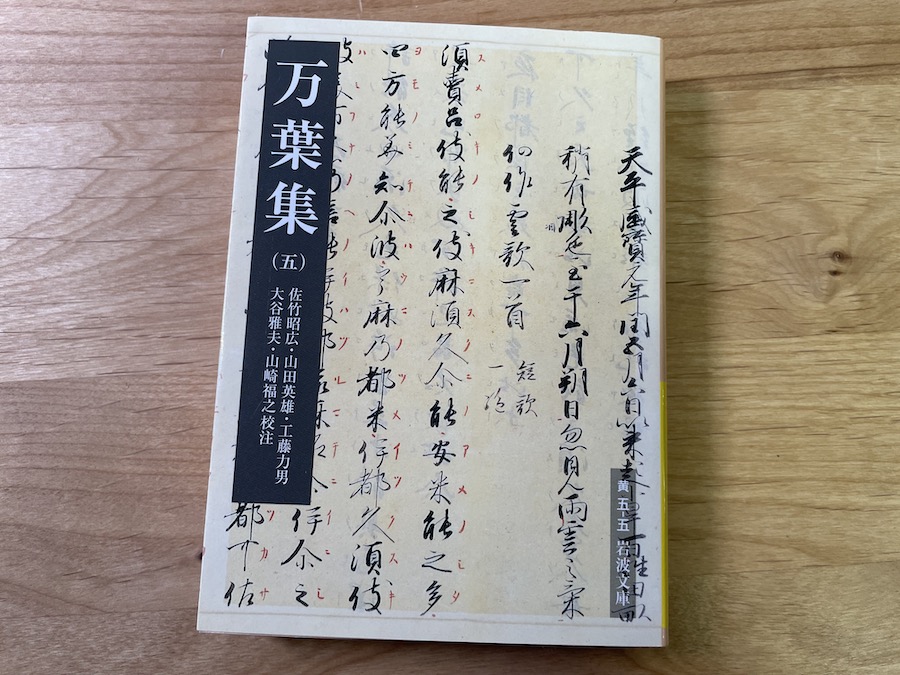
【参考文献】『万葉集(五)』(岩波文庫)
新版 万葉集 現代語訳付き【全四巻 合本版】 (角川ソフィア文庫) 












