大須演芸場で行われた『令和六年春 抜擢昇進 真打昇進披露興行』で、寄席を初体験した本田さん。林家つる子師匠と三遊亭わん丈師匠の落語の他、林家正蔵師匠や林家三平師匠、三遊亭天どん師匠の落語や色物など、豪華な披露興行を楽しみました。なかでも世代が近いつる子師匠と、一回り年上のわん丈師匠の話芸には、大いに刺激を受けたようです。そんな二人へ、本田さんに直撃インタビューしていただきました。
本田さんの寄席体験記事はこちら。
そもそも抜擢昇進とは何ぞや?
本田:落語に詳しくないので「抜擢昇進」という制度があることも知らなかったのですが。お二人は通常であれば、年功序列の落語の世界で、飛び級のように先輩方を追い抜いて真打になられたんですよね。12年ぶりということで、それを聞いた時、率直にどうでしたか。
わん丈:お話を伺った瞬間は、ものすごく嬉しかったんです。僕みたいな若手を落語協会の理事の師匠方が見てくださっていたんだ、と。でもその後は、「最悪や~」という感覚に陥りました(笑)。
つる子:私も電車で自分の落語会に向かっている時に、師匠(林家正蔵)から電話が入っていたんです。「何かしちゃったのかな?」と焦って、留守電を聞いたら「今日、理事会があって。抜擢という真打の話があったんだが、ありがたい話だから受けようと思う。すぐに折り返し電話ください」と連絡が入っていて。もうその瞬間、頭の中が真っ白になりました。
真打になるための修行期間
本田:それは乗り越えないといけないハードルや責任感が一気に大きくなったということですか?
わん丈:そうです。落語の世界は、前座、二ツ目、真打とあって、前座が義務教育、二ツ目が大学生、真打が社会人みたいなイメージなんです。今の世の中、大学生でも起業できるじゃないですか。それと同じで、僕らは二ツ目でも高座に呼んでいただける世代なんです。そういう仕事をいただいている時には、「大学生の割にはうまいよね?」という感覚で見てもらえるんです(笑)。その二ツ目期間がだいたい10年ぐらいあるんですが、真打昇進のお話をいただいた時、まだ6年目だったので、「あと4年は勉強しながら師匠の落語を学ぶ生活を謳歌しよう」と思っていたのに~という複雑な感情がありました(笑)。
つる子:私は、二ツ目になって13年目だったんですが、一昨年の1月ぐらいに、「真打昇進まであと3年ぐらいかかると思うから、それを見据えて頑張っていこうと思います」って高座で宣言していたんです。その矢先の昇進だったので、まさか、こんなに早くにお話が来ると思っていなくて。私も聞いた直後に、不安と恐怖とプレッシャーに襲われました。前回、抜擢で新真打に昇進されたのが、12年前の春風亭一之輔師匠、古今亭文菊師匠、古今亭志ん陽師匠で、それを前座時代に見ていたので、まさか自分の立場で起こるということが信じられなかったんです。
兄弟子を抜いて真打になることで背負うこと
本田:今回の「抜擢昇進」で、つる子師匠が12人抜き、わん丈師匠が16人抜きと、周りの方たちからの反応はどうでした?
わん丈:そりゃ、揉めますよ(笑)。みな、一人社長の世界ですから。「わん丈に負けているわけがない」とみんな思っていますから。落語家をやっていくのが厳しい時代に、なんで抜擢制度なんて残しているんだろうと苦々しく思ったほどです。
つる子:私もお客さんから「抜擢なんだ」という目で見られるし、先輩方からの視線もあり、私に出来るんだろうか、それに見合う真打になれるんだろうか、と不安がすごかったです。
周りからの期待、プレッシャーを自身の芸で返す
本田:そのプレッシャーをどう跳ねのけたんでしょうか。
わん丈:ここが落語界の良いところなんですが、披露興行が始まってしまえば、みな、お客様に喜んでいただくために一丸となって、先輩方も動いてくださるんです。東京での真打昇進披露興行は40日間以上もあるので、僕が高座に集中できるように、いろいろ気を遣ってくださいました。
つる子:私は師匠が「出る杭は打たれるから、打たれて強くなればいい」と言ってくださったことが励みになりました。師匠も過去に抜擢で真打になられ、さらには襲名もされて、世間からいろいろな声をいただいた経験があったので、私の気持ちを理解してくださってたんです。「流れってものは誰しも来るものではないから、流れに乗れ。追い抜いた先輩たちに、『あいつに抜かれたんならしょうがない』と言われるような高座をやるんだという覚悟を持ちなさい」と言われました。その言葉が今も金言となっています。応援してくれるお客様のためにも良い高座をしようと気持ちを切り替えました。
本田:40日間、1か月以上の興行ってすごいですね。どのくらいの準備期間があったんですか。
わん丈:1年ぐらいはありました。精神的な準備期間と、物理的な準備期間の両方なんですが、あっという間でしたね。
つる子:私も真打昇進は、一生に一度だと思うと、あれもやりたい、これもやっておきたいと欲張りすぎて、結局自分の首を締めることになっちゃったんですが(笑)。
二人それぞれの落語にかける情熱
本田:芸事って、試験があるわけでも点数が付けられるわけでもないので、どういったことが基準になっていくのですか。特に努力していた点とかありますか。
わん丈:基準は僕らにもわからないんです。ただ、僕は古典落語も新作落語もやっていて、江戸時代の噺だから、時代的にどうしても合わないジェンダーとか、ハラスメントとかの問題もあるじゃないですか。それをアレンジした噺をやっていました。わかりやすい落語を目指していたので、落語好きな方にも、初めての方やお子さんにも、両方に受けるような噺をやろうと考えていたところはあります。
本田:落語をアレンジしていいというのを初めて知りました。つる子師匠はどうですか。
つる子:私も古典の筋は変えないんですけど、女性ならではの視点からの落語があってもいいなと思って、アレンジした落語がいくつかあります。古典落語には男性の主人公が多いのですが、今でいうスピンオフみたいに、描かれていないおかみさんの立場から噺を作りました。その時も師匠が「女性の噺家にしかできない噺もあると思う。だから、お前がやりたいと思った挑戦はしてみてほしい」と背中を押してくださったんです。
先輩から学ぶこと、自分なりに工夫すること
本田:そういうお二人なりの工夫ってすごいなと思います。落語というと昔の話と思いがちだけれど、そういう現代の視点に合わせて作り変えてくれたりすると、馴染みやすいですね。子どもから大人までアプローチしていく時に、どういうところに重点を置いていくんですか。
わん丈:この言葉はわかるだろうか、ということを気にかけています。古典のままだと伝わらないけれど、なくしてしまうと、音の持つ響き、日本語の良さが伝わらなくなってしまう。そうであれば、分かりやすく伝えるにはどうしたらいいかを考えたんです。
例えば、「普請(ふしん)」という言葉、今はあまり使わないですよね。家をきれいにして、建て替えることなんですが、それを「牛ほめ」という古典落語で、
「与太郎、今度、おいさんな、普請をしたから」と言うところを「与太郎、分かるか、おいさん普請をしたんだ、家をな、きれいにしたってことだよ」
と、与太郎が分からない設定にして、お客さんに伝える工夫をしているんです。劇中で、登場人物が分からないとすることで、お客さんに恥ずかしい思いをさせず、噺を作り変えるんです。
本田:なるほど! その言葉を知らないお客さんにも、自然と分かるように伝える、すごく勉強になります。ところで寄席ってたくさんの落語家さんと一緒になるじゃないですか。そういう時に他の人の落語のどういうところを注目して見ているんですか。
わん丈:僕の場合は、受けたところは忘れるようにしています。どうしても自然と真似をしてしまうと思うんで。真似したところで、オリジナルに勝てるわけないですし。だから、僕は受けていないところを注目するようにしているんです(笑)どうして受けなかったかを考えます。そしてそれを自分に活かします。落語家って、ほとんどの人が普通に使っている言葉、会話というものを生業にしているじゃないですか。だからそれをプロとしてやるためには一癖ある工夫をしなきゃいけないと思っています。
本田:確かに、目から鱗が落ちました! 僕も同業者のステージに立たせてもらうことが多いのですが、どうしても受けている人が気になってしまっていました。

落語を初心者が楽しむには?
本田:今回、僕にとって初めての寄席体験だったんですが、本当に面白いな~と思えたんです。今後新しく見に来る方にどういう見方をしたら楽しいよというのはありますか。
つる子:何の準備もせず~、ふらーっと来ていただくのが一番いいな、と思っています。昔の言葉も出て来たりもするんですが、噺の組み立て方も工夫されているので、何も分からないってことは絶対なくて。逆に分からない言葉が出てきたら、それを調べる楽しさもある。それに、今も昔も変わらない感情っていうのが、落語の中には残っていると思うんです。私は、大学に入って、勧誘されて落研に入り、初めて落語を知ったんです。その時、「こんなに笑えるものなんだ」とか、「感動できる噺があるんだ」と驚きました。落語って昔の噺だけど、人の感情ってあまり変わっていないんだということに気づかされたんです。そこに一番感銘を受けました。噺を聴いて、江戸時代の人も同じ噺で笑っていたということにロマンを感じるんです。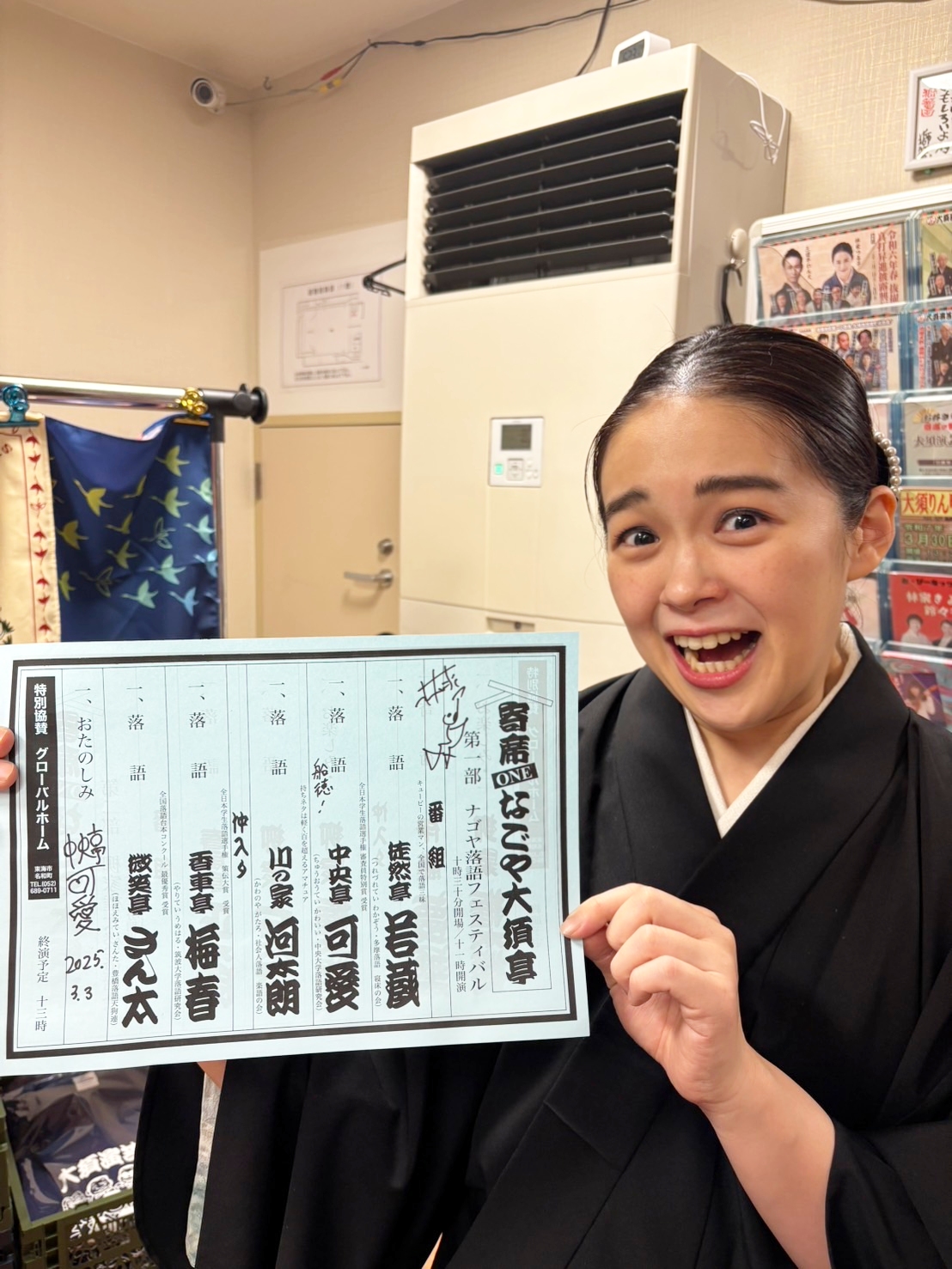
本田:落語って笑い噺が多いと思っていたんですが、感動したり、励まされたり、救いになる噺もあるんですか。
つる子 多いですよ。うまくいかない人とか、弱い立場の人が主人公になっている噺が多くて。そういう人たちがどんでん返しを起こしたり、笑いを起こすんです。それを聴いて、今の自分の状況と似ているなと思ったり、悩んでいたことも、笑い飛ばしていいんだと思えたり。落語って人の心に寄り添うものだなと思います。
わん丈:落語って、一つのネタで老若男女を笑わせられる。こういうものって、なかなかないなと思うんです。僕がやりたかった「みんなに笑ってもらう」ができるのが落語なんじゃないかと。だから最高の話芸だと思っていて、自分でも落語と出会えて本当に良かったなと思います。
本田 そういう気持ち、すごくわかります。今後、落語界をどのようにしていきたいですか。
つる子:とにかく若い方に知ってもらうことが私たちの使命かなって思っています。もちろん、今まで支えてきてくださった常連のお客様も大事ですが、これからの世代に、日本の伝統芸能で、「こんなに身近で、わかりやすいものがあるのに、知らないで終わってしまうのはもったいないよ」と。だから1回は見たことがあるという人を増やしたいんです。そのために、YouTubeやSNSも使って、どんどん発信していきたいです。
取材を終えて
僕自身、ステージに立ってMCをやったり、トークイベントもする中で、ジャンルは大きく違いますが、日本古来の話芸ってやっぱすげえ、と思いました。枕といわれる、ちょっとした小咄から落語の噺へと入っていく流れ、持っていき方も見事ですし、現代のことを話していたのに、すっと江戸時代の噺になっていて、これぞ、名人芸だなって思いました。参考にしたいけれど、参考に出来ないレベルの高さに感動しました。今日初めて寄席で落語見たのに、「やっぱり日本の話芸ってすごい」と、僕自身、胸を張りたくなりました。ぜひ、寄席に足を運んで、見てもらいたいと思います。
林家つる子プロフィール
群馬県高崎市出身。平成22(2010)年に九代林家正蔵に弟子入り。平成18(2015)年、二ツ目に昇進。令和6(2024)年3月21日真打昇進。古典落語の滑稽噺から人情噺、現代を舞台にした自作の新作落語にも取り組んでいる。名作「子別れ」「芝浜」「紺屋高尾」の登場人物であるおかみさんや遊女を主人公にして、その視点から落語を描く挑戦を行っており、その挑戦が、2022年にテレビで取り上げられると、新聞、雑誌等でも大きな話題となった。ぐんま特使、高崎アンバサダーとしても活躍中。youtubeをはじめ、SNSでも積極的に発信を続けている。
三遊亭わん丈プロフィール
滋賀県出身。平成23(2011)年に三遊亭円丈に入門。円丈没後、天どん門下となる。平成28(2016)年、二ツ目昇進、令和6(2024)年3月に真打昇進。平成25(2017)年にNHKラジオ「真夏の話術2017」で優勝、令和5(2023)年第1回公推協杯全国若手落語家選手権大会で大賞など、数々の受賞歴がある。古典と自作の二刀流で年間1500席の高座をつとめる。埋もれてしまった古典や上方落語の再編、「牡丹灯籠」通し公演、三題噺なども好評を得ている。通常の落語会のほか、団体や観光、産業をお題にした創作落語の制作・披露、学校寄席やSDGs環境落語会の仕事などにも精力的に活動。
Photo/松井なおみ
協力:大須演芸場
本田剛文プロフィール
愛知県出身 1992年11月3日 生まれ。弓道弐段 世界遺産検定2級 。新撰組や戦国時代が大好きで、猫愛好家でもある。実家は江戸時代から続く老舗仕出し屋で継げば11代目となる。 NHK Eテレ「キソ英語を学んでみたら世界とつながった。」 に4年連続レギュラー出演中 。地元東海圏のテレビ局に多数出演し、MCや情報番組のレポーターとしても活躍。トーク力に定評あり。西川流家元が主宰する舞台劇「名古屋をどりNEO傾奇者」で3年連続出演した。












