「最近、なんか……」
カメラマンが訝しげにコチラを見る。
「……気持ちに変化が?」
一体、どういう意味だ?
「今日の取材って『河童(かっぱ)』っしょ?」
だから?
「この前から『人魚』に『羽犬』に、今回は『河童』。それも『ミイラ』。超常現象専門ライターに転向したのかと」
確かに。
言われてみれば、オカルト系専門雑誌の記者のようである。
ただ、補足すると。決して興味本位で見たいワケではない。
どちらかというと、来歴、つまり、いかにして世にも不思議なモノが私たちの前に現れることになったのか、その背景が知りたいだけのこと。歴史の中に埋もれた幾つもの事実を拾い集め、推理することが好きなのだ。
そして、今回の取材も。
「河童のミイラ」と「酒蔵」。
この妙な取り合わせに、そして、当事者だけが知りうるであろうビハインドストーリーに心惹かれた。
ということで。
向かった先は、佐賀県伊万里市。
JR伊万里駅から松浦鉄道で10分ほど揺られて、楠久(くすく)駅に到着。そこから歩いて10分弱の場所にあるのが、創業300年を超える老舗の蔵元、「松浦一酒造(まつうらいちしゅぞう)」である。
さて、今回は「河童のミイラ」にまつわる、どんなぶっ飛び話が聞けるのやら。
早速、ご紹介していこう。
※本記事の写真は、すべて「松浦一酒造」に許可を得て撮影しています
※この記事に掲載されているすべての商品価格は、令和7(2025)年2月末現在の価格となります
田尻家に古くから言い伝えのある珍しいモノ
民芸茶屋のような入口を抜けると。
まず目に入ったのが、突き抜けるほどの高い天井。最近ではなかなかお目にかかれない、ご立派な丸太がそのまま剥き出しで組まれている。
「ここは、元々、酒を仕込む蔵だったんです」
こう話すのは、松浦一酒造株式会社社長の田尻泰浩(たじりやすひろ)氏だ。

松浦一酒造は、正徳6(1716)年創業。じつに300年以上もの歴史がある老舗の蔵元だ。そんな蔵元の舵取りをされているのが、田尻家18代目の泰浩氏。サラリーマンを経て、27歳の時に家業を継いだという。
「一番古い蔵なんですけど。でも一番安心できる。この辺は熊本の地震もそうだし、福岡の西方沖地震もかなり揺れたんですよ。でも、大丈夫でしたね」
さすが築250年以上というだけあって、その頑丈さはお墨付き。
だが、それだけではない。
この酒蔵には味があるというかなんというか。つい目を奪われてしまう。薄暗いかと思ったが、適度に柔らかい光が差し込み、意外と風通しもよい。初めて訪れた場所なのに、何故だかとてもしっくりくる。これまで歩んできた時間の流れをそのまま閉じ込めたような、そんな雰囲気のある蔵である。
「私からすれば会社なんですけど。それこそ、ここで飲むお酒が一番美味しく感じるっていうのがありまして。この酒蔵がいらなくなった時に連絡くださいって、名刺を置いて帰られた方もいらっしゃるんですよ」
解体して移築したい。それほどまでに惚れ込んだ人もいるのだとか。
そんな蔵の中はというと。「観光酒造」という名の通り、入口左手より古道具がズラリと並ぶ。これらは実際に松浦一酒造で酒造りに使っていた道具だとか。他にも農機具などすべて合わせれば、展示品は200点余り。その数は膨大だ。
様々な展示品に目を奪われつつ、先へと進む。
すると、一番奥に少し雰囲気の異なる場所が見えた。中央にあるのは真っ暗な空洞。大きな円がすっぽりとくり抜かれたような不思議な空間だ。その上にはしめ縄が飾られており、左右に榊(さかき)と灯りが見える。下にはお神酒やお供え物など、様々なものが所狭しと置かれていた。
次第に近付くにつれ、それが祭壇だというコトが分かる。
そして、目線のちょうど、ど真ん中。
空洞部分に置かれていたのは、透明のショーケース。
恐らく、中にあるのが「河童のミイラ」といわれる躯体だろう。
「酒樽の中でお祀りしているんです。見つかったのは昭和28(1953)年。それははっきりしてるんですけど、いつ頃からうちにあって、どっから持ってきたかっていうのは分かってないんです」
なるほど。
明確な来歴は分からないということか。確かに、古ければ古いほど遡るのは困難だろう。
「発見された経緯というのは、うちの母屋の瓦の葺き替え作業をしてる時にですね、大工の棟梁さんが、梁(はり)のところに箱が置いてあったのを持ってきたんですね」
それは黒い箱だったという。
埃をかぶり、ぼろぼろの紐でくくられていた奇妙な箱。
だが、すぐに開けることはしなかった。
「じつは瓦の葺き替え作業という一大イベントをやってたんで、それどころじゃないって。そのままちょっと置かれてたみたいです。で、作業が終わって落ち着いて『そうだ、これが見つかったんだ』って持ってきて蓋を開けたら、入ってて。それで初めて、ようやく大騒ぎになったんですけど」
最初は、何か分からなかったという。
だが、よく調べてみると、見つかった黒い箱には「河伯(かはく)」という墨書きの文字があった。
「『河伯』が、河童のことを指すということが分かって。それで初めて、これは河童じゃないかってなったんです」
「それまでは、このうちに何か珍しいものがあるよって言い伝えだけあったんですよ。代々ずっと言われてて」
田尻家で代々言い伝えられてきた「珍しいモノ」。
だが、それが何かを調べることはなく、そのまま時が流れたという。瓦の葺き替え作業がなければ、恐らく発見されることはなかっただろう。梁の上で、今でも人知れずひっそりと存在していたに違いない。
ただ、振り返ってみれば。
じつにヒントは、すぐそばにあった。
というのも、田尻家では、毎年12月1日に「水神様の祭り」を行うのが恒例となっていたからである。
「本格的にお酒の仕込みに入る12月にですね、今年もいいお酒ができますように、どんどんいい水が出てきますようにっていうことで、これまでずっと水神様の祭りを、うちだけでやってたんですね」
確かに、酒造りに「きれいな水」は欠かせない。
そもそも「河伯」とは、中国の神話に出てくる北方系の水神だ。川の神、河川を守る神として有名で、「きれいな水」とは切っても切り離せない関係ともいえる。日本では「河童」の別称として使われることもあるようだが、水神としての意味合いを考えれば、まさしく酒造の現場で「水神様の祭り」がずっと行われていたのも頷ける。

「祖父の代で(河童が)見つかってからは、河童は水神様とも言われてますんで。12月1日のお祭りの日のみ、祭壇を設けて、箱から(河童のミイラを)取り出してお祀りしてました。先代も先々代もちょっと頑固者で。11月30日に来たら、ちょうど準備してるんで、運が良ければ見れるんですけど。12月2日だと、もう片付けちゃったもんで見れなかったですね」
1年に1回だけ。
箱から出して人の目に触れた河童のミイラ。
だが、今は違う。
それにしても、どうしてこのような常設展示となったのか。
「平成になってからですね。近くにレストランがあって、そこに観光バスが止まってたんですけど。他に見るところがなくて。(河童を)一般に公開することで、お客さんもたくさん来ますよ、この辺りの活性化にも繋がりますよって言われて。ちょっと考えてみようかって、やり始めたのが最初です」
河童の意外なご利益とは?
それでは、ここでようやくのご対面である。
先から話題となっている「河童のミイラ」とは、一体、いかなる姿かたちなのか。
ずいっと前に乗り出て、その姿を確認する。
うん?
えっ。
まず驚いたのが、その姿勢。
ガッツリと、こちら向きである。
もし目があれば、絶対に目と目が合っている、そんな状況だ。
「発見された時、こう、こっちを向いて。こういう状態で見つかったんです」

事前に予告されている私でさえ、一瞬、ギョギョッと動きが止まったのだ。
初めて箱を開けられた田尻家の皆さんは、さぞかし腰を抜かすほど驚かれたであろう。そんな様子が容易に想像できる。
体長は約70cm。
背中は一見甲羅のようでもあるが、よく見ると16個の背骨が突出しているという。
確かに、河童と言われれば、そう思うのだが。いかんせん、見たことがないから、肯定も否定もできず。そのまま受け止めるしかない。
「ちょっと照らしてみると、これ、顔ですよね。一番特徴的なのがここ、おでこのところがVの字に見えますよね。その向こう側、脳天のところに窪みがあるんです。で、その窪みが俗にいう河童のお皿かと。そういう風に見えます」
「あと、顔の下に入れてるのが『左の手』です。ちょうど犬とか猫が伏せてる状態ですよね。この左の手、指が5本ありまして。その形は、私ら人間とほとんど変わらない手なんです」
なるほど。
研究者でもないのでさっぱり分からないが、顔は鳥のようでもあり、目が異様に離れていて、なんとも判別しがたい。ただ、手は人間と同じという。不思議な生き物には違いないだろう。
「足の方は指が3本で、とっても指が長いんですよ。もちろん手の方にも足の方にも、指の付け根に、水かきみたいな何かついてたあとがあって」
手の指は5本で、足の指は3本。
指の本数が手と足で違うのも謎だ。
それに、手足の指の間に水かきのような跡があるのならば、恐らく「水」に関係する生き物の可能性が高い。
「右の方に『への字』みたいになってるところがあるんですが。これ『骨盤』ですよね。で、お尻から左の方に下りていくと『膝』。その膝から右の方に下りていくと、端にあるのが足の指なんですよ」
「ここには、超常現象専門の方とか、いろんな方が取材に来られて面白いですよ。やっぱり皆さん、正体が気になったりして。調べたいから貸してくれないかっていう方もいらっしゃるんですけど。もちろん、すべてお断りしています。うちの蔵としては、お酒の神さんとして大切にしていますんで」
まさしく、おっしゃる通り。
現に、こうして大切にお祀りされているのを見れば、正体も何も関係ないのは言うまでもないだろう。酒造りの神様として、これからも松浦一酒造を見守り続けてくれるに違いない。
ただ、一瞬。
ほんの少し、ある疑問が頭をよぎった。
そもそも梁の上で大切に箱の中にしまわれていた「河童のミイラ」。こうして人目に触れても問題ないのだろうか。逆に、意図的に隠されていたというコトはないのだろうか。
そういう意味で、「発見されてから何か変わったことはないか」と尋ねたところ、意外な答えが返ってきた。
「ああ。ありました。まあ、河童さんのお陰かどうかわからないですよ。わからないんですけど……」
こうして田尻社長は、極めて個人的な事情を話してくれた。
「うちの家っていうのが、私で18代目と言いましたけど。私の父親、つまり17代目の社長から遡って7代も養子なんですよ」
正直、話がどこに向かうか分からなかった。
聞くところによると、田尻家は11代目から17代目までが養子。さらに15代目まで子どもができなかったという。
「祖父の代までが養子で。男の養子を取ってから、嫁をもらったっていう形なんですよ。この時点で子どもが5人授かってるんですが、5人とも女性なんですよ。その5人目の女性が生まれた後にこれが見つかったんです。で、見つかった後で一番最初にできた子どもが『男』だったんです。今までずっとできなくて、女性ばっかりだったのに、急に『男』が生まれて、それも男の双子だったんですよ」
ふむ。
確かに、養子続きだった家系に子ども、それも男の子が生まれるとなると、何かしら見えない力が働いたと思わないでもない。
「そこで終わると単なる偶然じゃないかって。でも、この双子の方にまた子どもができたんですけど、また双子だったんです。だから、(河童が)見つかってから養子にピリオドが打てて、なおかつ、双子が2代続いてますよっていう話があるんです」
こうして話し終わると、田尻社長はおもむろに色紙の下にある箱を取り出した。
箱には「子宝祈願」の文字が見える。

「(箱を色紙の下に)隠しちゃってるんですけど。子孫繁栄が河童さんのお陰じゃないかってことで、同じように子どもができない悩みを持ってらっしゃる方が、お参りに来られるんですよ」
子孫繁栄。
まさかの「河童」の意外なご利益に驚いた。
実際に、コチラの箱の中には、子宝祈願をされた方のお名前が書かれた紙が入っているという。それもかなりの数だとか。結果として子どもを授かった方も少なくなく、その話はテレビや口コミで広がり、祈願の方が後を絶たないそうだ。
「『ここにお参りに来て大丈夫ですか?』と連絡をもらったり。で、実際に来られたり。また、じつは娘が全然子どもができないんでって、その親御さんが来られたり。それも結果的に娘さんに子どもができたんですよ」
箱から出た河童サマ。
ここぞとばかりに、本領発揮という感じだろうか。
まさかの意外なご利益だが、誰もが喜ぶのであれば、それも有難い効果といえるだろう。
河童とお酒は切っても切れない関係?
それにしても、謎である。
通常であれば、なかなか「河童のミイラ」など手に入るものではない。
いかにして、田尻家に持ち込まれたのだろうか。
「佐賀県でいうと、何ヵ所か河童の伝説があるんですけど。ここら辺に関しては、全く何もないんですよ。それに、どちらかというと海なんですよ、ここは。川ではなくて海」と田尻社長。
なるほど。
とすれば、現在の酒蔵のある場所はあまり関係がないというコトか。それよりも遥か昔にまで遡る必要がありそうだ。これに関しては、田尻氏の歴史を紐解かなければならないだろう。
どうやら戦国時代の田尻氏は、筑後国(現在の福岡県)田尻村の豪族だったとか。当時の「筑後」には多くの国衆(こくしゅう、簡単にいえば地域的領主)が存在しており、まさに田尻氏も「筑後十五城主」の1人に数えられる一族であったようだ。
戦国時代の九州は、まさに群雄割拠の時代。
肥前(佐賀県)の龍造寺氏、豊後(大分県)の大友氏、そして北上を続けながら勢いを増した薩摩(鹿児島県)の島津氏の三つ巴となり、勢力図は刻一刻と様変わりしつつあった。
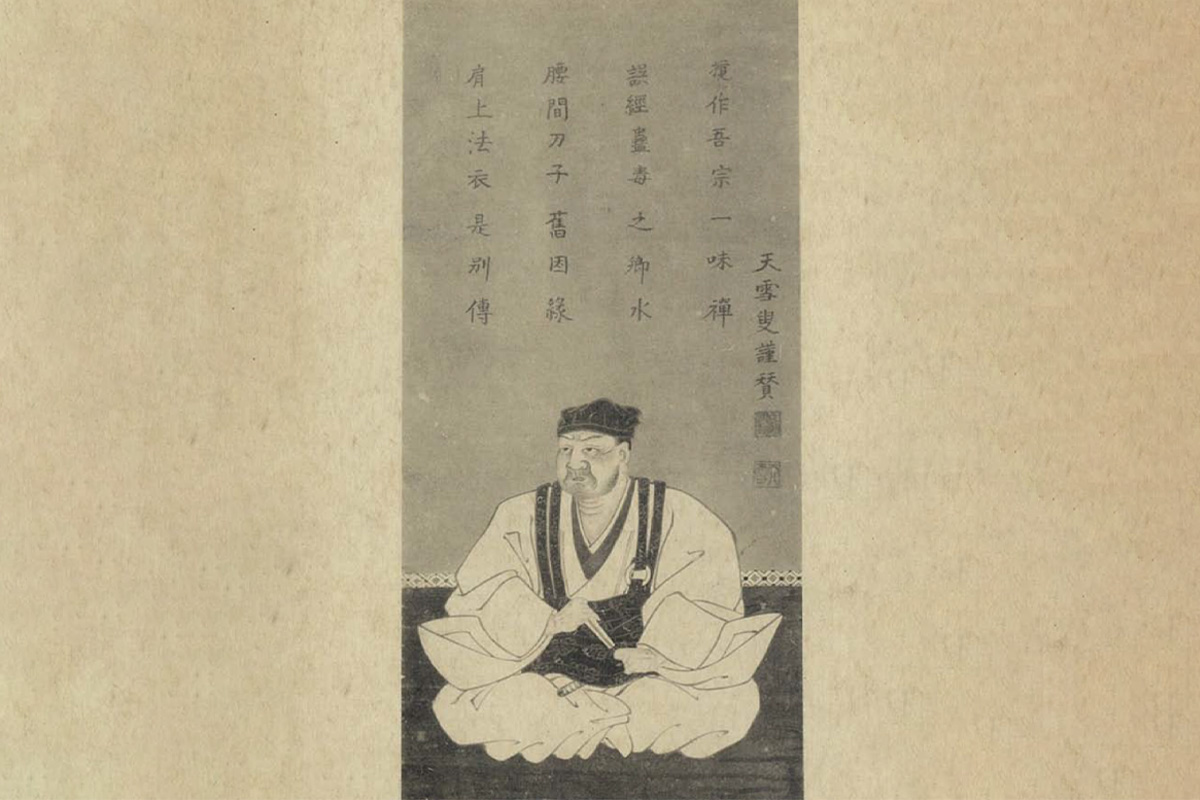
そんな混沌とした時代に、田尻氏はどの戦国武将に忠誠を誓うかで、かなり苦労したようだ。大友氏から龍造寺氏、果ては島津氏と、その都度、情勢を見極めつつ決断。最終的には龍造寺隆信の重臣で、母の再婚を機に義弟となった鍋島直茂に従属。
田尻家文書によると、豊臣秀吉の九州国分けの際には、鍋島氏への従属を理由に、所領配分を固辞したとされている。こうして田尻氏は、鍋島直茂により、肥前国下松浦郡山代村(現在の伊万里市山代町)に所領1659石を与えられたとされている。
さて、少し話が長くなったが。
注目すべきは、田尻氏が移住前にいた筑後国田尻村(現在の福岡県みやま市高田町付近)だ。じつは、この付近を流れる「飯江川(はえかわ)」には、河童伝説が残されているという。そのため、17代目、現在の田尻社長のお父様は、田尻村から山代村に移住する際に、河童のミイラを持って来たのではないかと推測されている。
となると、やはり酒造りと関連してというコトか。
確かに、酒造りに「きれいな水」は欠かせない。当時であれば、きれいな井戸水を掘り当てたいと、水神様にその願いを込めたと考えることもできる。だからなのか、松浦一酒造の看板や販売されている酒のラベルには、水神様としての「河童」の姿がちらほら見受けられる。
ただ、一方で。
気になる話もある。
「これは平戸(ひらど、長崎県平戸市)の方の話なんですけど、昔の平戸の古い家で、その家の一番高い梁のところに、河童の絵とか河童の置物を置く習慣があったみたいなんですよ。平戸の方は海にまつわる産業が多いもんで。つまり『水』の仕事から家を守る、人を守るということで。平戸はそんな遠くないんで、同じような意味合いもあったのかなと」
実際、河童のミイラが入った箱は、コチラの梁の上で見つかっている。
田尻社長曰く、家の中心の位置にあり、家全体を見渡せる場所なのだとか。

正直、何が正解かは分からない。
ただ、酒造りであれ、家内安全であれ。
どちらにしろ、「河童のミイラ」は田尻家をずっと守ってきた。その事実に変わりはない。
そして、今なお、酒樽の中で田尻家の行く末を静かに見守っている。
これぞまさしく、一族の守り神。
再度、河童のミイラに手を合わせて。
無事に取材が終了した。
取材後記
さて、ここからは。
松浦一酒造が誇るウマい酒を、ちょこっとだけご紹介しよう。
「松浦一」という文字が目を引く銘柄の数々。
壁一面に飾られている賞状もかなり気になるところだ。蔵の中には松浦一酒造の銘柄の酒がすべて揃っており、その場で購入することができる。もちろん、試飲も可能だ。雰囲気のある蔵でしっかりと味わって、自分好みの酒を選びたい。
まずご紹介するのが、松浦一酒造の「梅酒」。
「うちのおばあちゃんがずっと梅酒を作ってたんですよ。それが日本酒をベースにした梅酒で、めちゃくちゃ美味しかったんで。おばあちゃんの梅酒を商品にしようっていうことで造り出したのがこれです」
確かに、日本酒ベースの梅酒は珍しい。使用する梅は、伊万里梅園の「南高梅」と「古城梅」。使う梅の種類によって出来上がる梅酒も異なる。「南高梅」は完熟梅の甘みが、「古城梅」はスッキリとした梅本来の酸味が特徴とのこと。
田尻社長が太鼓判を押すコチラの梅酒。
甘口が好きな私にとおススメされたのが「プリュム(南高梅)」。
左から4番目が「プリュム(古城梅)」720ml(税込1,850円)/ 1,800ml(税込3,650円)
2枚目:さらに梅と日本酒にこだわり、海外のコンテストで受賞した「大吟醸梅酒」720ml(税込4,950円)
「農家さんに、完熟させて漬け込むとすごく香りも高くなるし、味も美味しくなるんじゃないかっていう話をされて。で、試しにつけたら、めちゃくちゃ美味しいのができたんですよ。天気のいい日に、朝、完熟した梅を収穫して持ってきてもらって、その日のうちに漬け込むんです」
早速、家でゆっくりといただいた。
正直、甘いといわれていたが、ホワイトリカーやブランデーベースのものと比べると、くどいほど甘くはない。ホントに完熟梅の自然の甘さがちょうどよい。梅の爽やかさも残しつつ、最後は日本酒のかすかな味わいが残る逸品だ。初めて日本酒ベースの梅酒を飲んだが、まさかのドハマり。後味が気に入った。是非ともおススメしたい1本である。
そして、さらに。
松浦一酒造の売り上げ1位となるコチラのお酒もご紹介したい。
その名も「特別純米 松浦一」である。

佐賀県有田産山田錦を100%使用。こちらも家でいただいたが、とにかく一口目からその濃さに驚いた。見れば、アルコール度数は16度。一般的に日本酒は15度前後だから、特別高いというワケではないのだが。酒が弱い身としては、ロックで飲むのがおススメ。香りもよく、のど越しに余韻が残り、芳醇な旨味が持続する。酒好きにはたまらない1本だろう。
最後に。
「河童のミイラ」とは聞いていたが。
まさかあそこまで、全身がそのまま残っているとは思わなかった。
「屋根に置かれてたってことで、一番湿気が少なくて、風通しが良くて。それに何が一番良かったかって。私は人間が触らなかったのが一番良かったと思うんですよ。だから、きれいな状態で残ったのかなって」
ちなみに松浦一酒造は、旅行会社が主催する「ミステリーツアー」の周遊地の1つだとか。観光客は、酒蔵に到着して「河童のミイラ」が迎えてくれるとは思いもしないだろう。
謎多き「河童のミイラ」は、まさに「ミステリー」ともいえる。
ただ、個人的には。
今回の取材で、また異なる意味の「ミステリー」を感じた。
そもそも「河童」は、人間に悪さをするイタズラ好きの想像上の生き物だったはず。
それが、今。
偶然が重なって、全身が揃った状態で私たちの前に現れたのだ。
そのうえ、悪さではなく、逆に良いご利益を与えてくれるという。
酒造りには欠かせない「水」を守り、子孫を繁栄させるというご利益だ。
我が国も「水質汚染」や「少子高齢化」の問題に悩む。
じつは、今の日本にとって。
一番必要な神様かもしれない。
撮影:大村健太
参考文献:『戦国武将列伝11 九州編』 新名一仁編 戎光祥出版 2023年7月
基本情報
名称:松浦一酒造株式会社
住所:佐賀県伊万里市山代町楠久312
公式webサイト:http://www.matsuuraichi.com/












