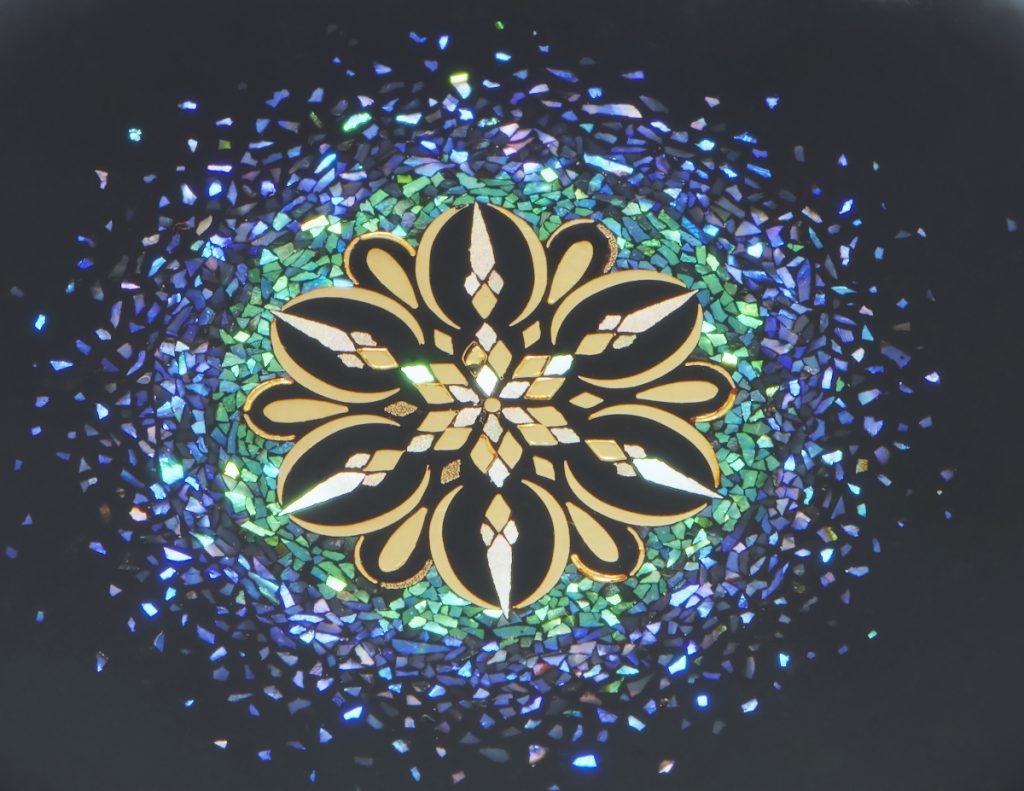この器を見てまずおもしろく感じられるのは、上部のふくらみに対して下部が極端にスリムになっている造形だろう。細い首のようなものも付いているので、胸板が著しく厚い人間のように見えなくもない。にもかかわらず、脚に当たる部分は、見事なまでにきゅっとしている。形そのものは中国の陶磁器に源流があるとも言われているが、この作品の造形はものすごく洗練されている。何といってもラインが絶妙だ。目で追うだけで、うなってしまう。

日本人の漆愛の本質
さらに注目すべきは、色合いだ。現代でも、漆器といえば朱(赤)か黒のものが多い。江戸時代以前の作と目 されるこの漆器は、朱漆が表面に塗られている。そして、長い間使われてきた証左 としてところどころに「かすれ」とでも言うべきすり減りが生じており、下地に黒漆があることがわかる。すなわち、朱と黒の両方を使っているのだ。
さて、じっくりと鑑賞することで、そろそろ漆愛が高まってきた頃ではないだろうか。少々驚くべきことがある。日本人はそのかすれまで愛するようになったというのだ。いわば「かすれの美学」というべきか。それが今日の本題である。
瓶子は、神事で使用される酒器である。「瓶子」という単語の中にある「子」という文字は、小ささを想起させる。とはいっても、この器は高さが30センチ超。器としては決して小さくはない。中に酒を入れれば、それなりの重さになりそうだ。ただし、宴席でこの器を誰かが持って人々に酌をして回ったわけではなかったようだ。酒を捧げる相手は神様。供えるために酒を入れて神像などの前に置いておくというのが、正しい使い方だったと想像できる。神様が相手ということであれば、ふさわしい品格が求められる。研ぎ澄まされた感性で美の造形を究めようとした漆芸職人の姿が目に浮かんできた。

サントリー美術館の大城杏奈 学芸員によると、「この瓶子は2つ対で作られたと考えられており、本展では隣り合わせで展示した」という。少しだけ離れたショーケースに、もう1点があった。MIHO MUSEUM所蔵の「瓶子」だ。神事の際、神前には2点が少し離れた位置に置かれていたと考えられている。もともとは1組だった器の再会には、神様も喜んだに違いない。
朱漆の下に黒漆が塗られていた理由
神事に使われることからもわかるように、「瓶子」のような根来は高級品だった。中世に和歌山県の根來寺で作られていたと言われる「根来塗」は、制作には26の工程を要したという。朱漆を塗る前に黒漆を塗ったのは、強度を増すためだった。漆器は化学反応の産物である。漆の樹液中のウルシオールという化学物質が空気中の成分と結びついて硬化するという。さらに、黒漆を作る際に混ぜる鉄分も硬化に寄与する。神事で使う大切なものゆえ、強く、そして美しく作る。朱漆と黒漆を重ねた理由もそこにあった。

朱漆と黒漆を重ねて塗った漆器が「根来」と呼ばれているのは、根來寺で平安時代末期から安土桃山時代に同じ手法の漆器を作っていたことと関係があるという。しかし、根來寺は豊臣秀吉に攻められて破れて衰退した歴史を持つ。「江戸時代になって人々の記憶が結びついて同じつくりの朱漆器全般を『根来』と呼ぶようになったのではないか」と、大城学芸員は言う。

もう一つ言えるのは、「根来」という呼び方に、使ってきた人々の親しみが込められているということだ。「根来」と呼ぶことによって、由緒正しきものとして大切に扱う。そんな行動が、自然に人々の間に生まれていたのではなかろうか。
朱漆の見事なできばえを自作で検証した黒田辰秋

朱漆の根来ができたばかりの時にどのくらい見事だったかを知りたいという好奇心を持つ人もいるだろう。実際に自分で作って確かめた工芸家がいる。黒田辰秋 (1904〜82年)だ。『根来塗平棗 』という小さな器なのだが、朱があまりにも鮮やかである。
新品においては鮮やかな美しさを楽しみ、経年で変化したら古びに興じる。使われるために生まれてきた工芸品ゆえ、人々はさまざまな思いをもって扱い、美を感じ、愛でてきた。そこには、「使う」歴史を経てきたからこそ展開した日本人特有の感性が生きている。
柳宗悦の唱えた「用の美」と根来
ただ鑑賞するだけでなく「使う」ことを前提として作られた工芸品に「用の美」が宿っていることを唱えたのは、大正から昭和にかけて民藝運動で大きな存在感を示した思想家の柳宗悦 だ。

「かすれ」が道具を使った結果生じることは、明白である。普段はしまっておき、必要な時に出して使う。道具とはそんなものである。一方で、色がはげ落ちたなら塗り直せばいいという考え方もあるだろう。しかし、である。考えてみれば、現代人でも、使い倒すことによって古びが出てきた革のかばんにいとおしさを感じるようなこともあるのではないか。あるいは、古着をおしゃれに着こなす力も、現代の日本人にはある。
根来の「かすれ」には、歴史が詰まっている。摩耗した朱の隙間から黒が顔を覗かせる光景を親しみを込めて愛でる人々。人間の感じ方というのは、実に面白いものだ。そして、その美は、柳宗悦という先達がすでに発見していたのである。
根来から美術品収集を始めた黒澤明監督

昭和時代の映画界の巨匠、黒澤明監督は、根来から美術品の収集を始めたという。この展覧会に出品されている2点の旧蔵品は、どちらも黒漆のほうが面積が広い。もはや、朱と黒が併存する状態をよしとして制作されたのだろうか。そのコントラストが、実に絶妙だ。じっと眺めていたら、黒澤監督の審美眼の素晴らしさが心に響いてきた。
日本人は古びを大切にする。根来への愛もまた、その一つの表れだ。それは、愛の長続きの秘訣でもあるのではないだろうか。

『楯 』は実戦用ではなく儀式用だったと推測されている
展覧会情報
展覧会名:NEGORO 根来 — 赤と黒のうるし
会期:2025年11月22日~2026年1月12日
会場:サントリー美術館
公式サイト:https://www.suntory.co.jp/sma/exhibition/2025_5/