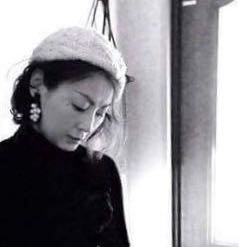創業は昭和40年の大須演芸場の歴史に迫る!
「大須演芸場のすぐそばにある大須商店街にはよく来ているのに、大須演芸場でちゃんと舞台を見るのは初めてなんです」と開口一番、少し緊張気味の本田さん。今回、3月3日~5日に『令和6年春 抜擢昇進新 真打昇進披露興行』開催にあたり、ぜひ、本田さんに寄席体験をしていただこうと企画。雨の降る中、さわやかなスーツ姿で登場してくれました。
大須観音や商店街も近く、昔ながらの雰囲気を漂わせる、ここ大須演芸場は、昭和40(1965)年に開館し、寄席所として賑わいを見せていました。かつては明石家さんまやビートたけしなどの数々の有名芸人、落語家がこの舞台に立っていました。しかし、時代の変化とともに、演芸場に通うお客さんも減り、経営状態が悪化。さらに老朽化も激しく、平成26(2014)年2月に閉館を余儀なくされたのです。しかし長年続いてきた大須の町を象徴する演芸場であり、芸能の火を消したくないとの思いから、再生に立ち上がったのが、現在の支配人である矢崎通也(やざきみちや)さんや、広報を担当する橋本浩宗(はしもとひろむね)さんたちでした。その結果、社団法人による運営体制へと切り替え、平成27(2015)年、新生「大須演芸場」が再スタートしたのです。
名古屋の大須演芸場は、東京と関西の落語、どちらも楽しめる?
この話を聞いて、歴史の深さや大須を思う人々の思いに深く感銘を受けた本田さん。早速、広報の橋本さんに寄席初体験者としてお話を伺いました。
本田:現在、寄席の興行っていうのはどのくらい催されているんですか。
橋本:毎月1日~7日まで、寄席として開演しています。ここ名古屋は江戸落語と大阪のいわゆる上方落語の中間にあるので、東京と関西、そして地元名古屋の落語家が共演する唯一の演芸場なんです。
本田:え、それはどういうことですか。
橋本:東京は、現在、落語協会と落語芸術協会の2つの団体があり、それぞれの団体に所属する噺家さんが、自分の所属する協会主催の演芸場に出演する仕組みになっています。わかりやすくいうと、野球のセリーグとパリーグのようなもので、同じ舞台に出ることはないんですよ。また、普通は、東京の寄席に、上方の寄席が交わることもありません。それが、名古屋だとそういったルールがなく、同じ寄席で見られる。だから、ここ大須演芸場は、セパ両リーグ、さらに海外チームが出ているような、おいしい演芸場なんです(笑)。
本田:それはびっくりです。中間地点だからこその強みといいますか、めちゃくちゃお得感がありますね! 大須演芸場なら、いろいろなタイプの落語家さんを一度に見ることができてしまうということなんですね。
一度は閉館した演芸場の復活の影に人々の寄席を愛する思いが!
本田:ところで、大須演芸場って、一度、閉館されたんですよね。それをどのようにして、ここまで再生されたのですか。
橋本:現在の矢崎支配人のご実家がもともと東京で芸能プロダクションを経営されており、そのお父様が亡くなられて事務所は閉じられたんです。それで現在理事である次男の信也さんが、大須演芸場を再生するにあたり、お母様が知人である林家正蔵師匠、三平師匠のお母様の海老名香葉子さんに声をかけてくださって。そうしたら「すぐに息子をよこしなさい」と言っていただき、香葉子さんが、再生のために最高顧問となって、バックアップをしてくださったんです。それと同時に、株式会社エディオンの前社長で現在、相談役の岡嶋昇一氏が代表理事に、東京にいた三男の通也(みちや)さんが支配人として就任しました。この大須演芸場で、寄席ができるのも、林家一門から、舞台の作り方、作法、すべて教えていただいたお陰なんです。噺家が落語をやれる場をなくしたくない、寄席を残したい、そういった人々の思いが集結して、再生できているんですよ。大須商店街連盟の役員の方々も協力してくださり、理事にもなっていただき、地域一体で盛り上げようとしてくれました。
本田:落語や寄席を大切に思う人々の気持ちが素晴らしいですね。伝統芸能を受け継いでいこうという気持ちも伝わってきて、僕たちも地元の宝を大切にしていかないとと思いました。
演芸場は和のワンダーランド?和菓子や弁当、手ぬぐいや扇子も買える!
演芸場の歴史や寄席について理解したところで、入口でチケットを購入し、いざ、扉を開けて中へ。 1階ロビーでは、お弁当やお菓子、お茶などを販売するブースと、今回出演する噺家さんのグッズが売られるブースに分かれています。
1階ロビーでは、お弁当やお菓子、お茶などを販売するブースと、今回出演する噺家さんのグッズが売られるブースに分かれています。
本田:場内に入ると、ちょっと昔にタイムスリップしそうな雰囲気がありますね。そういえば、入場チケットのことを「木戸銭(きどせん)」と呼ぶそうですが、それはどういう意味があるのですか。
橋本:昔は木戸の出入り口があったことから、今もその名残で木戸をくぐる時の入場料の意味の木戸銭を使っています。
本田:そういう習慣的なことも受け継いでいるんですね。僕は初めて演芸場で寄席を見るんですが、しきたりとか、マナーってありますか。
橋本:例えば席を立つ時は、演者さんが変わるタイミングにしてもらうとか、噺の途中で声をかけないとか、私語をしないとか、基本的なマナーだけです。あとは食べたり、飲んだりも自由ですし、気楽に楽しんでいただければ大丈夫です。そもそも、寄席って、「ついでに行こうか」とか「ふらりと寄ろうか」という気軽な場所。一人ひとりの芸も10分~20分と短いですから、ちょっと空いた時間のタイミングで、見ることができるんです。全体の番組も1時間半~2時間ですから。
本田:その番組表は誰が作られるんですか。
橋本:番組のことを「顔づけ」っていうんですが、演芸場の支配人が作ります。順番や流れを決めて、噺家さんや色物さんに声をかけていきます。だから、同じ番組になることはなくて、番組が発表されると、それを見て贔屓の落語家さんの出る日に行くようになります。
本田:色物ってなんでしょうか。
橋本:落語と落語の間にやる手品だったり、曲芸や紙切り、音曲などです。噺だけでなく、こういったいろいろな芸能が楽しめるのも寄席の楽しいところです。
『真打昇進披露興行』は落語界にも、落語家にとっても一世一代のイベント!
本田:外は開演前からすごい人ですね。こんなにたくさんの方が来るのは、特別な興行だからですか。
橋本:そうです。やはり今日のような『真打昇進披露興行』は、ビッグイベントですし、今回真打になられた林家つる子師匠と三遊亭わん丈師匠のお二人は、抜擢昇進といって、とび級のようにたくさんの兄弟子さんをとび越えて、真打になられた方なんです。だからお客さんの気合も入っていて、前売り券は完売しました。そういう意味でも、今回の昇進披露興行は、感慨深いものがあります。普段は、このように満席になることはなく、どちらかというと、時間が空いたから寄席でも見るかという感じで、のんびりしたムードです。だから前売り券より、当日券の方がよく売れるんですよ(笑)。
本田:これって、すごく貴重な機会なんですね。初心者で、寄席初体験なのに、贅沢すぎますね(笑)。
橋本:最高峰から見ていく感じですね。口上といって、真打昇進の挨拶を師匠たちがしてくれるんです。林家正蔵師匠と弟の三平師匠の兄弟がそろって舞台で見られるのも貴重ですよ。
名古屋にも来てちょ~。芸処名古屋の寄席の楽しみ方
本田:大須演芸場ならではの楽しみ方ってありますか。
橋本:小屋自体が小さいので、演者さんとお客さんの距離が近いんです。中入り(休憩時間)で、演者さんたちが出てきて、場内で、グッズを売っていたり。これは複数の師匠たちから聞いたんですが、演じる側からしても、小屋の大きさとか、客席の位置や目線が合いやすいらしく、やりやすいんだそうです。この大きさだからこそ届く生の声というのも楽しめますし、ホールでは味わえない雰囲気がありますよ。
本田:落語を生で聴くのも、紙切りの色物を見るのも初めてでしたが、見ごたえがあり、あっという間の2時間でした。「名人芸!という世界をこれだけたっぷり見られて、3000円台って、お値打ちだぞ!」と本当に思います。
橋本:そうやって若い方が感じてくださると、自分たちも頑張ってきたかいがあります。
本田:落語って、耳にも気持ちいいリズムになっていて、自然と日本人が心地よくなるエッセンスが詰まっている気がしました。噺も演技も面白かったし、感動したりもするんだけど、聴いていると、五七調や語感の良いワードがチョイスされていたからか、ドーパミンが出てきた気がします(笑)。耳が幸せになるというか。落語がこんなに長く愛されてきたのには、日本人にとって心地良いリズム感だったことも関係しているんでしょうね。日本人で良かったと誇りに思う瞬間でした。
取材を終えて
今日、初めて寄席で落語を聴いて思ったのは、ふらっと来て楽しめる場所であると同時に、伝統芸能の奥深さもしっかり感じられるものだということ。伝統芸能って、自分たちで勝手にハードルをあげてしまいがちなんだけれども、新作もあるし、僕たちにもわかりやすい現代的なストーリー仕立てになっていたり。古典的な噺でも人間という生き物が潜在的に持っている「あるある」や、心情の変化は、時代を越えて、共感できるものだと、改めて感じました。江戸時代の人と同じ感覚で滑稽に感じたり、笑えたりするのも、目から鱗が落ちたといいますか。これを機会に自分の中のハードルを取っ払って、いろいろな寄席に行って、落語家さんの噺を聴いてみたいと思います。そして、僕と同世代、あるいは更に若い世代の皆さんにも、面白いからぜひ、寄席で生の落語に触れてほしいです!
協力/大須演芸場
Photo/松井なおみ
真打昇進のお二人のインタビューは後編へ。近日公開予定!
本田剛文プロフィール
愛知県出身 1992年11月3日 生まれ。弓道弐段 世界遺産検定2級 。新撰組や戦国時代が大好きで、猫愛好家でもある。実家は江戸時代から続く老舗仕出し屋で継げば11代目となる。 NHK Eテレ「キソ英語を学んでみたら世界とつながった。」 に4年連続レギュラー出演中 。地元東海圏のテレビ局に多数出演し、MCや情報番組のレポーターとしても活躍。トーク力に定評あり。西川流家元が主宰する舞台劇「名古屋をどりNEO傾奇者」で3年連続出演した。
▼本田剛文さんの他の記事はこちら。
弓道を通して己を磨く「BOYS AND MEN」 本田剛文。自分を見失わない技と心の整え方とは?
今、男性アイドルが日本舞踊の舞台に立つ理由。「BOYS AND MEN」本田剛文、三十の手習い
本田剛文もうっとり♡斬るだけじゃない、刀剣の意外な役割と美に迫る!