「剣豪将軍」と呼ばれた征夷大将軍(せいいたいしょうぐん)がいる。
武士だけに絞ると、将軍は鎌倉時代に3人、室町時代に15人(重複含む)、江戸時代に15人いるが、剣豪と呼ばれるのは、たった一人だ。
その人物とは、室町幕府13代将軍足利義輝(あしかがよしてる)。
2020年の大河ドラマ『麒麟がくる』で、向井理が演じ、話題を呼んでいる。
義輝の時代は、家臣の細川氏や三好氏が政治の実権を握り、将軍がたびたび京都を追われる事態となっていた。しかし、義輝はそれに屈することなく、あくまで武家の棟梁(とうりょう)であろうとし、自ら剣の極意を会得したという。その後、襲ってきた大軍に壮絶な最後の戦いを挑んだ若き義輝が、目指していたものは何であったのか。実像を探ってみよう。
柳生宗矩が認めた天下に5、6人もいない兵法者
雲林院弥四郎(うじいやしろう)という剣士がいる。江戸時代の初め、肥後熊本藩主の細川忠利(ほそかわただとし)が弥四郎の腕に惚れ込み、召し抱えようとするが何度も断られた。そこで忠利は弥四郎について、江戸の将軍家兵法指南役を務める柳生但馬守宗矩(やぎゅうたじまのかみむねのり)に問い合わせたところ、次のように宗矩は返した(なお、この返書は現存する)。
「弥四郎は大変な兵法者です。父親(雲林院出羽守)は塚原卜伝(つかはらぼくでん)の弟子で、足利義輝、北畠具教(きたばたけとものり)など(と並ぶ)、天下に五、六人もいない兵法家です。そのすべてを弥四郎は相伝していて、鑓(やり)にかけては、当代随一だと思います」
注目すべきは柳生宗矩が、天下に5、6人もいない(卜伝の剣を受け継ぐ)兵法者として、足利義輝の名前を挙げている点である。足利義輝の剣の腕に関する史料は少なく、そのため「剣豪将軍」と称されるのは、あくまで小説の類の話であろうと疑うむきもあるが、少なくとも柳生宗矩が、義輝を傑出した兵法者として認識していたことが事実だとわかる。
 柳生宗矩像
柳生宗矩像
手紙にある塚原卜伝とは、「剣聖」と呼ばれる兵法者。義輝も、北畠具教も、卜伝より剣を学んだと伝わる。それについては追々紹介するとして、まずは義輝が生まれた頃の時代状況から見ていこう。
なぜ足利将軍は力を失っていったのか
弱い存在となっていた将軍
12代将軍足利義晴(よしはる)が、7年ぶりに近江(現、滋賀県)から京都に戻ったのは、天文3年(1534)9月のことだった。義晴は京都の東郊外にある南禅寺の塔頭(たっちゅう、子院のこと)に入り、御座所とする。
義晴が長期間、近江にいたのは、将軍を支える有力大名・細川家の内紛に巻き込まれて、京都を追われたからであった。やむなく、近江の大名・六角(ろっかく)氏に庇護(ひご)を求めたのである。やがて、内紛の末に細川晴元(はるもと)が実権を握ると、晴元と和睦して、義晴はようやく帰京することができた。とはいえ、いつ晴元が心変わりするかわからず、用心のために京都の中心部ではなく、近江に近い東郊外に御座所を置いて、万一の際にはすぐに近江に逃げ、六角氏を頼れるようにしたのだという。将軍ともあろう者が、なぜこれほど弱い存在になってしまったのだろうか。そこには、室町幕府と足利将軍の構造的な問題があった。
 南禅寺
南禅寺
実は足利義晴の頃の将軍は、直轄領も直轄軍も、ほとんど所持していない。つまり経済力も軍事力もないに等しかった。従って、実力のある家臣と対立すれば、当然ながら自力では勝てない。他の有力家臣の支援を得なければ、何もできなかった。そのため家臣間で内紛が起きた際、一方に味方して、他方が勝つと、将軍は敗れた側とともに、京都を追われる事態が生じるのである。義晴の場合も、まさにこのケースであった。
本来は全国が足利将軍の直轄領
とはいえ、足利将軍が最初からそうした弱い存在だったわけではない。
後醍醐(ごだいご)天皇の政権を倒した足利尊氏(あしかがたかうじ)が、室町幕府の初代将軍として征夷大将軍に任ぜられたのが延元3年/暦応元年(1338)のこと。足利将軍は「天下諸侍の御主(おんあるじ)」(武家の棟梁)となり、全国の武士たちの頂点に立った。12代将軍足利義晴の、およそ200年前のことである。
 足利尊氏像
足利尊氏像
初代将軍足利尊氏の直轄領は、日本全国であった。もちろん、将軍一人で全国の武士を支配することは物理的にできない。そこで将軍は、各国を支配する「守護(しゅご)」というポストを置いた。いわば将軍の代理人で、そのポストには功績のあった有力武将たちをつけた。細川、斯波(しば)、畠山(はたけやま)、山名(やまな)、赤松(あかまつ)、一色(いっしき)、土岐(とき)などの面々である。彼らは一時的に国を預けられた管理者に過ぎず、任期が過ぎれば交代して、中央に戻らなければならない。あくまで全国の所有者は将軍である、それが足利将軍の認識だった。
守護から守護大名、そして戦国大名へ
ところが、守護となった武将たちはそう考えなかった。守護として統治する国は、これまでの働きの恩賞として、将軍から与えられたものである。従って、子々孫々に伝えるべき我が領国であると解釈し、またそうなるように願った。室町幕府草創期は南北朝の争いがまだ続いており、将軍は多くの武将を味方につなぎ留めておくためにも、彼らの希望をむげに斥(しりぞ)けることはできなかった。結局、国は守護に預けたものではなく、与えたに等しいものになっていく。
それでも足利将軍家に大きな混乱がなく、守護たちが幕臣として将軍を全面的に支えていた時期は、室町幕府も機能していた。全盛期は、3代将軍義満(よしみつ)から6代将軍義教(よしのり)の頃までといわれる。しかし将軍義教が重臣に殺害されて以降、足利将軍家の混乱が始まった。片や守護たちは、将軍から自立して領国を経営する大名になっていく。いわゆる「守護大名」である。
 応仁の乱勃発地碑
応仁の乱勃発地碑
さらに8代将軍義政(よしまさ)の時に応仁(おうにん)の乱が起こり、全国の守護大名らが東西両軍に分かれて、延々と戦いが続いた。混乱を機に、守護大名たちは将軍を支えるために詰めていた京都を離れ、国元に帰ると、領国を独立国化させていく。守護大名は「戦国大名」へと変質し、また守護を補佐する立場だった守護代(しゅごだい)や、それ以外の者が下剋上(げこくじょう)で、守護から実権を奪って戦国大名となるケースも少なからずあった。彼らは、必ずしも将軍に従順ではない。一方の将軍の手元には、直轄領も直轄軍も残っていなかった。12代将軍義晴や、その息子で13代将軍となる義輝が生きたのは、まさにそうした将軍にとって受難の時代である。
細川家の内紛と将軍の座を脅かす者
なぜ幼少より御所に参内したのか
さて、将軍義晴が京都に戻ってからおよそ1年半後の天文5年(1536)3月10日、南禅寺の御座所にて嫡男が生まれた。これが後に13代将軍となる義輝である。幼名は菊幢丸(きくどうまる)。母親は公家の近衛(このえ)家の出身だった。ちなみに義輝は同時代を生きた上杉謙信(うえすぎけんしん)より6歳年下、織田信長(おだのぶなが)より2歳年下である。

その翌年の正月、義晴はまだ生後1年に満たない菊幢丸を伴って、御所に年賀の参内(さんだい)をした。赤子を政治の舞台に連れ出すことは、歴代将軍家の中でも異例である。また天文11年(1542)には、7歳の菊幢丸を一人で参内させている。このように義晴が、幼い息子を度々参内させるのには、菊幢丸が自分の後継者であることを、内外に認めさせる目的があったらしい。というのも、実は義晴には、将軍位を脅かすライバルがいたのだ。
将軍位をねらう義維
義晴の父である10代将軍義澄(よしずみ)には、2人の息子がいた。一人はいうまでもなく義晴で、もう一人は義維(よしつな)といって、弟であるという(一説に兄)。義晴の兄弟であれば、義維が将軍位に就いてもおかしくなく、義晴はそれを恐れていたのである。
義維は幼少時、幕府管領(かんれい、将軍に次ぐ最高職)を務める細川氏のもとで養育されていた。一方の義晴は、播磨(現、兵庫県)守護の赤松氏のもとで育っている。やがて細川家中で内紛が起こり、義維を擁する細川晴元が敗れ、細川高国(たかくに)が実権を握った。高国は義晴を招いて、12代将軍の座に据える。
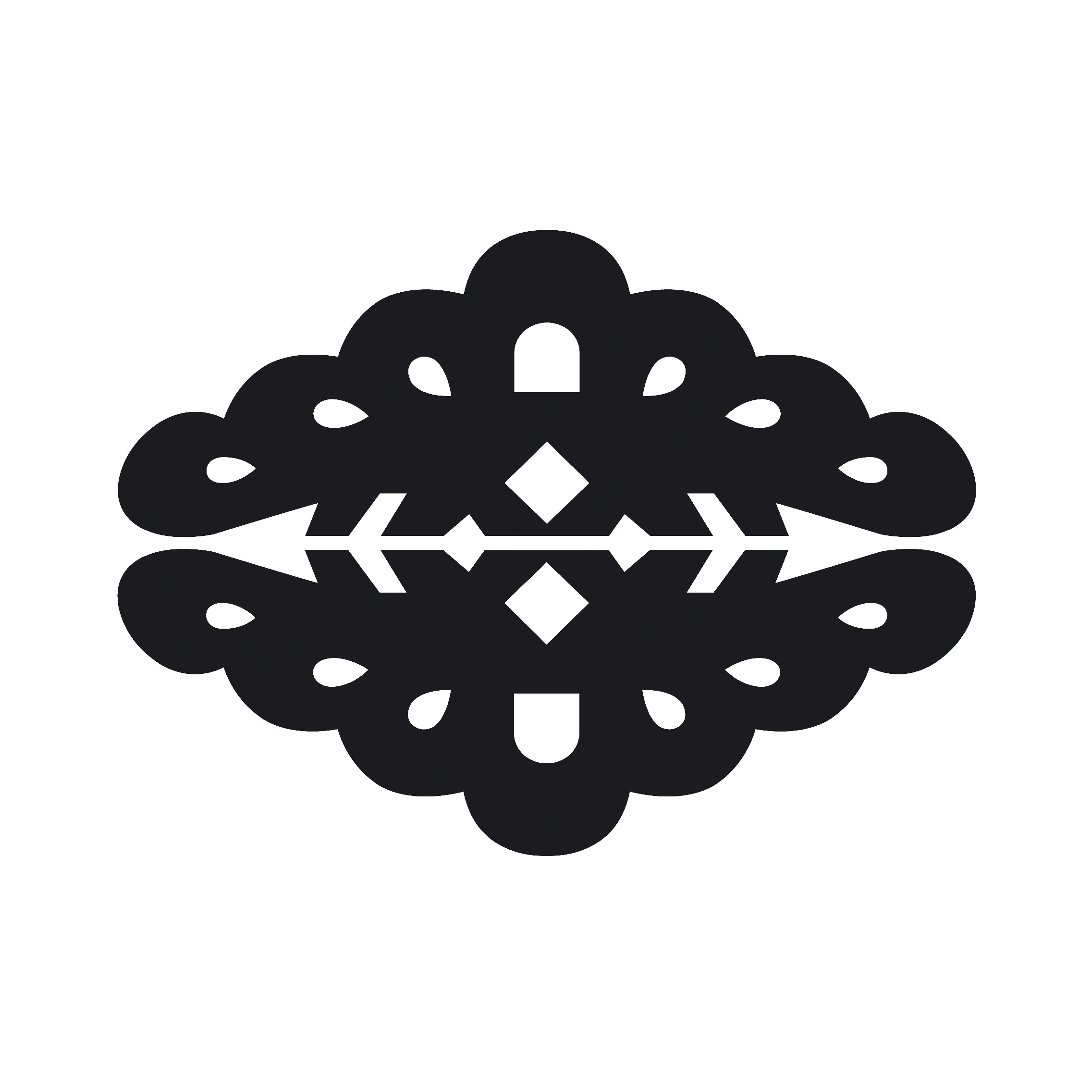 細川氏の家紋の一つ「松笠菱」
細川氏の家紋の一つ「松笠菱」
しかしその後、再び内紛が起こり、細川高国は京都から追われた。将軍義晴もこの時、近江に逃げたのである。反高国勢力は、高国のライバルだった細川晴元と結び、晴元が京都の実権を握ることになった。晴元には、養育してきた義維を将軍にする選択肢もあったが、将軍義晴との和睦を選ぶ。こうして前述したように、義晴は7年後に京都に戻ることができたのだが、細川晴元がその気になれば、いつ将軍の座を追われ、義維にとって代わられるかもしれなかった。義晴が幼少の菊幢丸を参内させ、懸命に将軍後継者のアピールに努めたのは、このためである。
結局、この頃の足利将軍家の血筋は、家臣たちが自らを正当化するための御輿(みこし)として利用されていたといえるだろう。また義維の子の存在が、のちのち菊幢丸の運命にも関わることになる。
ひたすら翻弄される若き将軍
13代将軍就任と三好長慶の台頭
天文15年(1546)12月19日、菊幢丸は11歳で元服する。当初、義藤(よしふじ)と名乗るが、本記事では義輝で統一したい。烏帽子親(えぼしおや)は近江の有力大名・六角定頼(さだより)が務めた。烏帽子親には古来、元服する者を将来にわたり支援する意味がある。元服式が執り行われたのは京都ではなく、近江日枝神社の神官屋敷であった。京都ではまた細川家に内紛が起こり、将軍義晴と義輝父子は近江に難を避けていたのである。そして元服式の翌日、朝廷から勅使が派遣され、義輝は13代将軍に任命された。
翌年、細川家の内紛は、細川晴元が再度実権を握ることで終息し、六角定頼の仲立ちにより、晴元と将軍義輝が和睦することで、将軍と細川家の対立も解消。天文17年(1548)に将軍義輝は京都に帰ることができた。
 三好長慶像
三好長慶像
ところが、またもや細川家で内紛が起こる。細川晴元重臣の三好長慶(みよしながよし)が台頭し、これを快く思わない晴元と対立、ついに合戦に及んだところ、なんと三好長慶が勝利したのだ。晴元は京都を追われ、晴元とともに将軍義輝も、都に戻ってわずか1年で近江に落ちることになる。
父・義晴の死と三好勢に喫した惨敗
義輝とともに近江に落ちた父・義晴は、ほどなく病の床についた。苦しむ父を静かに療養させるためにも、都を奪回しなければならない。14歳の義輝は、細川晴元や六角定頼と協力して、三好長慶への反撃の準備を進める。天文19年(1550)2月には、東山の山上に中尾城を、同年4月には北白川(現、京都市左京区)にも城を築いて、三好との戦いに備えた。
ところが同年5月、三好との戦いを待たずに父・義晴が病没してしまう。京都への帰還を果たさぬまま、近江での客死であった。享年40。15歳の義輝は、復仇の念にかられたであろう。前将軍である父の無念を晴らすためにも、三好長慶を倒し、京都を取り戻さなければならない、と。
その時は、義晴の死から2ヵ月後の7月に訪れた。三好長慶が、義輝らが築いた城に攻め寄せたのである。これに対し、細川晴元、六角定頼が迎え撃ち、激しい戦いが展開されるかと思われたのだが……。どうしたことか細川勢の士気が振るわない。三好勢が大軍を動員したことに細川勢は圧倒され、細川晴元はなんと、陣を捨てて越前(現、福井県)へ逃げてしまうのである。
 朽木谷付近(写真:寿福 滋)
朽木谷付近(写真:寿福 滋)
これでは義輝方も防ぎようがなく、11月に三好勢4万が攻勢に出ると、義輝は城を捨てて琵琶湖の北西、朽木谷(くつきだに、現、高島市)に身を潜めざるを得なかった。義輝が初めて味わう惨敗である。さらに近江に落ちた直後、追い打ちをかけるように義輝の重臣である伊勢貞孝(いせさだたか)が裏切り、京都の三好のもとに走った。若き将軍のプライドは、ズタズタにされたことだろう。
流浪の中で見出した将軍の価値とは
何のための征夷大将軍か
天文21年(1552)、義輝の烏帽子親で、京を追われるたびに匿(かくま)ってくれた近江の六角定頼が没する。跡を継いだ息子の六角義賢(よしかた)は、義輝と三好長慶の和睦を仲介し、義輝は同年に京都に帰った。が、すぐに長慶と対立し、敗れて再び近江朽木谷に舞い戻るはめになる。
「足利一門の細川どころか、細川の被官にすぎぬ三好などに都をほしいままにされ、何もできずに近江に身を隠さねばならぬとは、何のための征夷大将軍か。将軍など無用の長物ではないか」
 旧秀隣寺庭園。足利義晴の築庭ともいう(写真:寿福 滋)
旧秀隣寺庭園。足利義晴の築庭ともいう(写真:寿福 滋)
18歳の義輝は周囲の近臣たちに、憤懣(ふんまん)をぶつけることもあっただろう。朽木谷時代の義輝に従っていた近臣は40人ほどとされるが、それが誰であったか、正確にはわからない。ただ、おそらく行動を共にしていたと思われるのが、亡き義晴の時代から従っていた三淵晴員(みつぶちはるかず)である。晴員の子である三淵藤英(ふじひで)、細川藤孝(ふじたか)の兄弟も側にいた可能性は高い。ちなみに細川藤孝が三淵姓でなく細川姓なのは、和泉(いずみ)細川家の養子となったからで(異説あり)、もともと三淵晴員も和泉細川家の出身だった。なお藤孝は義輝より2歳年上であり、晴員の息子たちは、義輝のよき相談相手であったかもしれない。
将軍の重要性を再認識させるために
そして想像をたくましくすれば、憤懣やるかたない義輝に対し、三淵晴員はこんな言葉をかけたのではないか。
「上様。仰せのように、将軍職がまこと無用の長物であるのならば、幕府など疾(と)うの昔に消え失せておりましょう。しかし、上様はご健在であり、我ら幕臣も微力ながらお仕えしております。何ゆえか。それはひとえに上様が、武家の棟梁にておわすがためです。すべての武家に号令できるのは、天下広しといえど上様のみ。細川も三好も、京都を牛耳ることはできても、諸国の大名たちを心服させることはかないませぬ」
「とは申せ、率いる軍勢も財力もない将軍に、大名たちが心服するとも思えぬが」
「そのことでござる。上様は武家の棟梁。すべての武家は上様の家来でありますゆえ、軍勢の数を競う意味はござりませぬ。むしろ上様にしかできぬ手立てで、家来を心服させればよいのです」
「!」
 朽木の朝霧(写真:寿福 滋)
朽木の朝霧(写真:寿福 滋)
上記のようなやりとりが実際にあったかはともかく、この頃から義輝は、諸国の大名間の紛争の調停や和睦に積極的に関与していく。弘治2年(1556)には加賀(現、石川県)の一向宗徒の元締めである大坂の石山本願寺と越前朝倉氏を和睦させ、翌年には信濃(現、長野県)をめぐる武田晴信(たけだはるのぶ)と長尾景虎(ながおかげとら)の争いを調停した。また豊後(現、大分県)の大友義鎮(おおともよししげ、後の宗麟)の要請に応え、肥前(現、佐賀県、長崎県)守護に任命している。将軍による紛争調停は、当事者たちにとって戦いを止める口実となり、ありがたいものだった。また守護任免は将軍の特権である。義輝は、諸国の大名に将軍が重要な存在であることを再認識させて支持をとりつけ、それによって、京都の三好らも容易に手出しができぬようにしたのである。
鹿島新當流・塚原卜伝
「剣聖」との出会い
ちょうどその頃、朽木谷の義輝を訪ねてきた一団がいた。中心人物は70歳前後の老人で、塚原卜伝(つかはらぼくでん)と名乗る。3度目の廻国修行中の剣士・塚原卜伝とその家来たちであった。
伝説的な剣の達人、「剣聖」とも称される兵法者・卜伝の訪問に、義輝は驚喜したことだろう。当時、剣術を志す者で、卜伝の名を知らぬ者はいない。また卜伝は廻国修行をしていた若い頃、京都で義輝の祖父である10代将軍義澄(よしずみ)に拝謁し、なりゆきから義澄を助けて対抗勢力と戦ったこともあるという。それも義輝は耳にしていたかもしれない。
 塚原卜伝(イラスト:本山賢司)
塚原卜伝(イラスト:本山賢司)
「御尊顔を拝し、恐悦至極に存じあげます。上様の英気に接し、愚老もいささか安堵いたしました」。朽木谷で不遇の日々を送る義輝を案じて、卜伝はわざわざ足を運んでくれていたのである。
真剣試合19回、戦場に臨むこと37回
ここで簡単に卜伝の人物と、その剣について触れておこう。
卜伝とは号であり、塚原新右衛門高幹(しんえもんたかもと)が本名である。常陸国(現、茨城県)鹿島城主の鹿島氏の重臣、卜部吉川(うらべよしかわ)家に生まれた。卜部吉川家は鹿島神宮の神官でもある。卜伝は同じ鹿島氏重臣の塚原家に養子に入り、塚原姓を名乗ることになった。
 鹿島神宮奥宮
鹿島神宮奥宮
建御雷神(たけみかづちのかみ)を祀る鹿島神宮は古来、香取神宮と並ぶ武神として尊崇されている。古代の防人(さきもり)たちは、鹿島神宮に詣でて武運を祈るとともに、鹿島に伝わる武術を身につけて西国に向かったともいう。その旅立ちを「鹿島立ち」と呼んだ。
やがて鹿島に伝わる武術は「鹿島七流」「関東七流」などと呼ばれ、畿内の「京八流」と双璧と見られることになる。卜伝も幼い頃より、実父から吉川家に伝わる鹿島中古流(かしまちゅうこりゅう)を、また塚原家の義父からは香取神道流(かとりしんとうりゅう)を学び、精妙を極めるに至った。
やがて卜伝は諸国武者修行に出かけ、実戦の中で剣に磨きをかけることになる。その内容はおよそ、次のようなものであったと記される。
「17歳にして洛陽清水寺に於(おい)て、真剣の仕合(しあい)をして利を得しより、五畿七道に遊ぶ。真剣の仕合19度、軍(いくさ)の場を踏むこと37度、一度も不覚を取らず、木刀等の打合、惣(そう)じて数百度に及ぶといへども、切疵(きず)、突疵を一ヶ所も被(こうむ)らず。矢疵を被る事六ヶ所の外、一度も敵の兵具に中(あた)ることなし。凡(およ)そ仕合・軍場共に立会ふ所に敵を討つ事、一方の手に掛く212人と云(いえ)り」(『卜伝遺訓抄』)
「剣豪将軍」への道
一の太刀
30歳の頃、鹿島に戻った卜伝は、鹿島神宮に千日間参籠(さんろう)祈願した末、鹿島の太刀の極意というべき「一(ひとつ)の太刀」を体得する。また「心新たにして事に當(当)たれ」との神示を受けて、己の剣を「鹿島新當流(かしましんとうりゅう)」と名づけた。
 鹿島新當流 面(おもて)の太刀 相車(あいしゃ)
鹿島新當流 面(おもて)の太刀 相車(あいしゃ)
その後、再度廻国修行に出る一方、多くの弟子に剣を伝授。このたびの3度目の廻国は、老境の卜伝自身、最後の修行と承知しており、極意を伝えるべき逸材と出会うことを願っての旅でもあった。
「一の太刀とはいかなるものであろうか」。義輝の問いに卜伝が応える。「一太刀で敵の死命を制する秘術でありまするが、決まった型ではございませぬ。上様がお望みとあらば、ご指南いたしますが」「よいのか」「ただし、体得できるか否かは、上様のご尽力次第と思(おぼし)召せ」
最大の敵は己の内にあり
卜伝と弟子たちが、どれぐらいの期間、朽木谷に逗留していたのかはわからない。半年から長くても1年程度だろうか。その間、義輝は日々、卜伝から鹿島新當流を学んだ。義輝は京都にいた頃、京流の剣を学んでいたが、鹿島新當流は全く異なっていた。その技は、敵が甲冑(かっちゅう)を身につけていることを前提としている。裏籠手、頸動脈、喉、上帯通しなど、甲冑で守れず、致命傷となる部分をねらう、動きに一切無駄のない、極めて実戦的なものだった。
卜伝はすぐに、義輝に剣の天稟(てんぴん)があることに気づいたはずである。しかし、面に出さず、「殿様芸」ではない、実戦で活用できる技を伝えていった。同時に、心のあり方についても語っただろう。

「上様にとって最大の敵とは?」
「やはり、三好であろうか」
「なんの。最大の敵は、上様の心の内におり申す」
卜伝は、心の弱さが相対する敵を大きく見せてしまうこと、敵もまたこちらが大きく見えていること、自分の内に巣食う疑念や邪念、怖れを取り払えば、相対する敵のありのままの姿が見えてくることを説いた。「敵のありのままの姿を見極めて戦え、か」……義輝は何かを悟る。
卜伝の逗留が1年近くになろうという弘治4年(1558)1月、23歳の義輝は卜伝に挙兵を相談した。義輝の真意を知った卜伝は、うなずく。「三好の置かれた状況を見極めてのご判断、妥当と存じます。また稽古もちょうどよき頃合い。長居をいたしましたが、愚老もそろそろお暇をつかまつります」。卜伝の暇乞いに、義輝が「一の太刀には、届かなんだか」と残念そうな表情を浮かべると、「上様。極意はすでにお伝えしておりますぞ」と微笑み、「一つ付け加えるならば、兵法の最善は戦わずして勝つこと。愚老の伝えた剣は、己の内なる敵を討つために用い、上様御自ら敵に剣を振るう機会のなきことを、願っております」。その言葉を置き土産に、卜伝は飄然と朽木谷を去っていった。
将軍として京都に返り咲く
石山本願寺との連携
弘治4年は2月に年号が変わり、永禄元年となる。永禄元年(1558)3月13日、義輝は朽木谷で打倒三好の兵を挙げた。六角義賢の支援に加え、5年前の戦いで敵前逃亡した細川晴元も駆けつけてくる。義輝は手勢5,000を率い、6月には如意ヶ嶽(にょいがたけ、京都市左京区)に布陣した。そして付近の勝軍山(しょうぐんやま)城を守る三好勢を追い落とす。これに対し三好長慶は、家中の松永久秀(まつながひさひで)、三好長逸(ながやす)らに1万5,000の兵を与えて、進撃させた。以前であれば、これで義輝方の腰が砕けてしまったかもしれない。だが、今回は違った。

実は2年前に義輝が越前朝倉氏との和睦を図ったことで、大坂の石山本願寺が義輝支持を表明したのである。本願寺が三好勢に挙兵したわけではないが、地勢的に本願寺は、西から三好勢の背後を衝くことができる。三好長慶にすれば常に後ろが気になるわけで、義輝との戦いに集中できない。これこそ卜伝が賛同した、三好の置かれた状況を見極めた上での義輝の判断だった。結局、戦いは膠着(こうちゃく)し、両者は和睦。同年12月、義輝は5年ぶりに京都に帰るのである。
天下を治むべき器用あり
京都に帰還した義輝は、思い切った手を打つ。対立していた三好長慶の厚遇であった。本来、細川晴元の家臣に過ぎず、また父・義晴を客死させた仇敵であったが、義輝はそうした感情を取り払い、長慶を幕府の相伴衆(しょうばんしゅう、管領に次ぐ高い席次)に引き立て、桐紋(将軍家の家紋)を与えたのである。それだけでなく、長慶の息子義興(よしおき)も相伴衆に、さらに長慶の弟・三好実休(じっきゅう)や長慶家臣の松永久秀を御供衆(おともしゅう、将軍の近臣)に任じるなど、破格の厚遇で報いた。これによって三好家のステータスは大いに上がり、面目を施した長慶は一転、義輝を重んじるようになる。ある意味、義輝は戦わずして相手に矛(ほこ)を収めさせたのである。

実はこの措置は、義輝にとってもう一つプラスの面があった。主家の細川家を凌ぎ、下剋上で京都の実権を握った三好長慶だが、幕府高官に任じられたことで、将軍義輝との上下関係が誰の目にも明らかになったのである。以後も長慶は権力を握り続けるが、幕臣として常に将軍の顔を立てねばならず、義輝と長慶の関係は、危ういながらも絶妙のバランスを保っていくことになる。『萬松院殿穴太記(まんしょういんどのあのうき)』は義輝を「天下を治むべき器用あり」と評した。
越後の龍・長尾景虎
澄んだ目をした男
義輝が京都に戻った翌年、永禄2年(1559)には2月に尾張(現、愛知県西部)の織田信長が少数の供を連れて上洛し、義輝に拝謁した。またその少し後には美濃(現、岐阜県)の斎藤義龍(さいとうよしたつ)が上洛、領地の一部を将軍に寄進し、義輝は義龍を相伴衆に任じてこれに報いている。各地の大名が短期間とはいえ上洛し、将軍にコンタクトを取ってくるのは、義輝の存在価値を大名たちが改めて再認識したからであろう。
そして4月、義輝にとって運命的な出会いが訪れた。越後(現、新潟県)の長尾景虎(後の上杉謙信〈うえすぎけんしん〉)が、精兵5,000余りを率いて上洛したのである。さすがに5,000の兵を京都に入れることは三好が嫌がり、景虎は兵を近江に留め、供回りのみで、京都の義輝に拝謁した。
(なんと、澄んだ目をした男か……)。義輝は景虎と対面するなり、そう感じた。師と仰ぐ塚原卜伝の目も澄んでいたが、卜伝の目が深山の泉のような静けさをたたえているのに対し、景虎の目は迷いがなく、心の内の炎を映しているかのような力強さがあった。
 長尾景虎(イラスト:諏訪原寛幸)
長尾景虎(イラスト:諏訪原寛幸)
景虎が義輝に公式拝謁した目的は、大きく二つ。一つは義輝の京都帰還への祝いであり、もう一つは、関東管領(かんとうかんれい)・上杉憲政(うえすぎのりまさ)が望んでいる、関東管領職と上杉家を景虎が継ぐことへの、将軍義輝の許可を得ることだった。しかし、それだけであれば5,000の兵を引き連れる必要はない。実は景虎にはもう一つ、将軍義輝に内々に伝えたいことがあった。
景虎の覚悟
景虎の上洛は、3ヵ月以上の長きに及ぶことになる。その間、将軍義輝とは何度か私的に、ごく少数で酒席を囲む機会を得た。そこで景虎は、義輝に次のように伝えたという。
「たとえどのような状況になっても、相応の御用を命じて下さるのならば、私は領国のことなど一切捨て置き、無二、上意様(義輝)の御前をお守りいたす所存です」
驚愕した義輝の表情に、みるみる感動の色が浮かんだことだろう。領国を捨ててまで、将軍を守るという大名が目の前にいるのだ。義輝はこれほど温かく、頼もしい言葉を今まで聞いたことがなかった。義輝は後日、書状に「(景虎の)覚悟に感じ入るばかりだ」と記し、この時の喜びを伝えている。
 景虎の毘の旗
景虎の毘の旗
「そのために越後の兵を連れて参ったのか」「御意。わが兵をもってすれば、いかなる敵をも退治してご覧に入れます」。景虎の言う敵が、実権を握る三好一族であることは明らかだった。越後の龍と恐れられる景虎が采配を取れば、確かに三好勢を粉砕するかもしれない。しかし最終決着には時間がかかるだろう。その間に景虎の領国越後や、関東が失われては元も子もない。義輝は景虎に感謝しつつ、今は兵乱を起こすことを望んでいないと伝え、酒席に一人の貴人を迎えることにした。
人生を賭けた「大望」
その貴人とは、関白近衛前嗣(このえさきつぐ、後に前久〈さきひさ〉)。義輝は前年、近衛家より正室を娶(めと)っているが、前嗣はその弟で、義輝の義弟にあたる。年齢は義輝、前嗣ともに24歳。景虎は30歳であった。
近衛前嗣は関白という要職にある上、豪胆かつ行動力のある人物で、景虎ともすぐに昵懇(じっこん)となる。そしてこの時、3人の間で密約が結ばれたのではないかとする説がある。

すなわち、関東管領となった景虎が関東平定に臨む際、関白近衛前嗣も関東に下向して、朝廷の権威をもってそれに協力する。将軍義輝も争乱を調停しつつ、関東が景虎の元にまとまることを支援する。そして関東平定が成った暁には、景虎が関東の大軍を率いて上洛、三好勢を駆逐して幕府を建て直し、戦乱の世に終止符を打って、諸国に秩序を取り戻す、という壮大な計略であった。
これを裏づける史料はないが、その後、実際に近衛前嗣は関東に下向して景虎に協力しており、また義輝も景虎を支援していることから、決して絵空事ではなかったことがわかる。義輝らはこれより、人生を賭けるに値する「大望」に向かって、突き進んでいったのではないだろうか。
存在感を増す義輝、凋落する三好
着々と地歩を固める
長尾景虎は越後に帰国した翌年の永禄3年(1560)、関東に出兵して上野(現、群馬県)を制圧。翌永禄4年(1561)には関白近衛前嗣も景虎軍に加わり、11万5,000もの大軍で北条(ほうじょう)氏の小田原城を囲んだ後、鎌倉で関東管領職に就任。名を上杉政虎(まさとら)と改めた。さらに信濃に向かい、川中島で武田信玄と死闘を演じることになる。
 川中島古戦場
川中島古戦場
同じ頃、京都でも争乱が起きていた。六角勢が三好勢と戦い、一旦は破ったものの三好勢の巻き返しにあい、六角勢は退去した。この争いの中で、かつて義輝を裏切った伊勢貞孝が討たれる。これを機に義輝は、伊勢氏の世襲であった政所頭人(まんどころとうにん)を、将軍近臣に切り替えた。政所は幕府財政や土地をめぐる訴訟を扱う機関で、伊勢氏は莫大な権益を手にしていたといわれる。しかし近臣に替えたことで、権益は義輝のものとなり、将軍の地位を強固なものとしたのだ。
また義輝は川中島に向かう前の上杉政虎に対し、武田信玄によって追われた信濃守護・小笠原長時(おがさわらながとき)の帰国支援を要請し、政虎の信濃進攻を正当化した。さらに政虎に「輝」の字を与え、政虎はその後、上杉輝虎(てるとら)と名乗ることになる。いずれも政虎に対する支援であった。このように義輝は、着々と地歩を固め、また手を打っていたといえる。
三好長慶の死
一方、三好家では異変が起きていた。永禄3年に長慶の弟・十河一存(そごうかずまさ)が病没。永禄5年(1562)に長慶の弟・三好実休が戦死。さらに永禄6年には長慶の一人息子・義興が22歳の若さで病没してしまう。凶事の連続、特に息子の死に長慶は激しく落胆し、倒れてしまった。
永禄7年(1564)5月、長慶は弟の安宅冬康(あたぎふゆやす)を居城に呼び出して、討った。これは重臣である松永久秀の讒言(ざんげん)を信じたためで、後でそのことを知った長慶は深く後悔し、病がさらに篤くなってしまう。さしあたり、十河一存の息子義継(よしつぐ)を養子として迎えるが、長慶が回復することはなく、7月に失意のうちに没した。享年43。

凶事が続いた上に、当主長慶を失った三好家の凋落(ちょうらく)は誰の目にも明らかだったが、それは将軍義輝と長慶の間で保たれていた絶妙のバランスを崩すことでもあった。三好家では養子の義継を松永久秀と三好三人衆(三好長逸、三好政康〈まさやす〉、岩成友通〈いわなりともみち〉)が補佐するかたちをとるが、長慶が健在だった頃のようには、自由に振る舞うための押しが利かない。一方で、将軍義輝は諸国の大名からの支持をとりつけ、将軍主導の幕府体制を築き始めている。特に、越後の龍と呼ばれる上杉輝虎が、義輝に応じて再び軍勢を率いて上洛してきたら、三好勢はひとたまりもない……。松永や三好三人衆は義輝が目ざわりであり、また怖れを抱いてもいた。
永禄の変、勃発
三好の真のねらい
永禄8年(1565)5月19日午前8時頃。勘解由小路烏丸室町(かでのこうじからすまむろまち、現在の平安女学院付近)の将軍御所を、突如1万の軍勢が取り囲んだ。三好義継、松永久通(ひさみち、久秀の息子)、三好三人衆らである。彼らは「公方(くぼう)様に訴訟いたしたき議あり」と口々に叫んだ。「御所巻(ごしょまき)」である。御所巻とは室町時代の奇習で、大名が軍勢でもって将軍御所を取り囲み、将軍に圧力を加えて訴訟する。ただし将軍には危害を加えないことが不文律で、そのため謀叛(むほん)とは見なされない。これまでの御所巻は将軍側が大名に屈し、要求を容れることで収まったのだが、しかし、この度はそうはいかなかった。

取次役を務める幕府奉公衆の進士晴舎(しんじはるいえ)が交渉に臨むが、三好側の要求は常軌を逸していた。すなわち「将軍の妻妾、大身(の側近、おそらく進士晴舎自身)の処刑」だった(フロイス『日本史』)。妻妾とは正室近衛氏及び側室の小侍従(こじじゅう、進士晴舎娘)を指す。罪のない妻妾の処刑を、義輝が認めるはずもなかった。しかし、おそらく三好側の真のねらいは、最初に受け入れ難い要求を突きつけた上で、代わりに別の要求をのませることにあったのではないか。それは「義輝が将軍位を退き、足利義栄(よしひで)に譲る」ことである。義栄とは、義輝の父・義晴が存在を危惧していた弟・義維の息子で、義輝のいとこにあたる。御し難い義輝の代わりに、意のままに操れる義栄を将軍に据えて、政治の実権を握り続けることこそが、三好の本心であっただろう。
己のなすべきことは何か
交渉はまとまらず、進士は事の次第を義輝に報告した上で、腹を切った。三好側の要求に進士とその娘の処刑が含まれており、自分たち父娘の存在が義輝を窮地に陥れたことに責任を感じたのであろう。なお、この進士晴舎の息子が明智光秀であるという説もある。進士の切腹と同時に、三好の鉄砲隊が乱入してきたところを見ると、三好側にどこまでまともに交渉する気があったのか。これを将軍近臣の奉公衆たちが阻止しようとし、御所の庭先で小競り合いが始まった。

この間、義輝は静かに考えをめぐらせていた。御所内の人数は60人ほど。正室、側室、生母などもいる。常識的に判断すれば三好勢に対して勝ち目はなく、将軍退位をのめば、己の命は助かるかもしれない。しかし、それでよいのか? 家来の恫喝(どうかつ)に将軍が命欲しさに屈するようでは、上下の秩序など無きに等しい。これまで諸国の大名に再認識させてきた将軍の存在価値を、自ら否定することにもなる。将軍とは、「武家の棟梁」であろう。ならば今、己のなすべきことは何か。
我が名をあげよ
「兵を退かせよッ」
庭先の小競り合いが本格的な戦闘に変わりつつある中、義輝は女性や武士以外の者を屋外に逃がすよう命じ、周囲にいた近臣およそ30人に別れの盃(さかずき)を与えた。そして「なろうことなら、兵を退かせよ。くれぐれも犬死はするな」と告げる。覚悟を決めて敵に向かう義輝の忠臣たちの働きは、凄まじかった。数で勝る敵に一歩も引かず、鑓(やり)で数十人を討った者もいたという。
(戦わずして勝つ兵法を心がけて参ったが、その工夫も、もはや尽きたようじゃ。卜伝、今こそ、そなたより伝えられた鹿島の太刀を遣わせてもらうぞ)
義輝は心の内で、そう呼びかけただろうか。

ふわりと庭先に降り立った義輝の手には、薙刀(なぎなた)が握られていた。義輝の姿に、侮った敵兵が次々と斬りかかるが、籠手や脛(すね)を斬られて、崩れ落ちる。卜伝から学んだ鹿島新當流はいわば総合武術で、剣以外にも小刀、棒、薙刀、格闘術も含んでいた。義輝はあえて致命傷を与えず、敵兵を戦闘不能にしていく。その数はたちまち十人を数えた。「兵を退かせよッ」。義輝が大喝(だいかつ)すると、敵兵は威に打たれたのか、一瞬動きを止めた。三好方の将に多少でも正気が残っていれば、この時点で兵を退くこともできたかもしれない。しかし直後に、御所内から女性の悲鳴が上がる。室内になだれ込んだ敵兵が、見境なく義輝の生母や妻妾らを斬ったのだ。もはや三好勢を支配しているのは、狂気だった。義輝は薙刀を捨てると、佩刀(はいとう)を抜いた。
敵兵が怖れをなす
「左京大夫(さきょうのだいぶ、三好義継のこと)、女まで手にかけるとは、三好も落ちたものよの。公方に歯向かう以上は天下を敵に回す覚悟、できておろうな。わが鹿島の太刀、存分に味わうがよい」
 舞台「剣豪将軍 足利義輝」で染谷俊之演じる義輝
舞台「剣豪将軍 足利義輝」で染谷俊之演じる義輝
義輝の呼びかけに三好義継からの返答はなく、代わりにけしかけられた敵兵が義輝に群がった。義輝は、もはや容赦しない。敵兵の太刀筋を読んで刃を打ち合わさず、頸動脈、喉、脇など、急所を一太刀で斬ってゆく。薙刀よりも少ない動きで、確実に相手を倒す。そして刀身に脂が巻くと、座敷の畳に何本も突き立てた足利家重代の太刀と交換し、闘い続けた。フロイス『日本史』はこう記す。
「義輝は自ら薙刀を振るって戦い、人々はその技量の見事さにとても驚いた。その後はより敵に接近するために薙刀を投げ捨て、刀を抜いて戦った。その奮戦ぶりはさながら勝利を目前にしている者にも劣らなかった」
また『足利季世記』は、次のように記す。
「公方様御前に利剣をあまた立てられ、度々とりかへ切り崩させ給(たも)ふ御勢(おんいきおい)に恐怖して、近付き申す者なし」
『足利季世記』は軍記物なので、「利剣をあまた立てられ、度々とりかへ」というくだりは信憑性が低いとされるが、御所における戦いは2時間以上に及んでおり、義輝が奮戦するには、何らかの方法で太刀の交換は必要だったろう。いずれにせよ、義輝の鬼神の如き闘いぶりに敵兵は怖れをなし、進んで斬りかかる者がいなくなった。一説に義輝と近臣たちで、200人近い敵を討ったともいう。

しかし、近臣たちのほとんどが討死し、義輝の疲労も限界に達する。一瞬の隙をついて、薙刀で足を払う者がいた。義輝がバランスを崩したところを、敵兵が畳や障子戸を上からかぶせて倒し、身動きを封じた上で、数本の槍を突き立てた。ここに、義輝は絶命する。享年30。
将軍御所には三好勢によって火がかけられ、すべて炎に包まれた。夕刻。焼け跡に、にわかな夕立が沛然と降り注いだという。
足利義輝の魅力
戦国時代の足利将軍というと、大名の傀儡(かいらい)だったイメージがあるが、少なくとも義輝はそうではなかった。たびたび京都を追われ、屈辱を味わいながらも、決してあきらめず、将軍として前に進もうとした。そして塚原卜伝に剣を学び、人間的にも成長。宿敵三好長慶を半ば自家薬籠中のものとし、長尾景虎との出会いで大きな志を抱く。もう少し彼に時間があれば、政治手腕に長けた英主として名を残したかもしれない。まさに、志半ばにして斃(たお)れた若者だった。

義輝は生涯、将軍はどうあるべきかを求め続けていたのではないだろうか。あらゆる武家の頂点に立つ「武家の棟梁」。将軍の座が揺らげば、すべての武家の秩序が揺らぐ。棟梁として将軍主導の幕府政治、秩序再建を願う彼だからこそ、三好の恫喝に屈するわけにはいかなかった。最後まで「武家の棟梁」たらんとし、誇りを守るために戦ったのである。そのまっすぐな生き方には爽やかな魅力を感じるのだが、皆さんはいかがだろうか。最後に義輝の辞世の句とされるものを紹介しよう。
五月雨は 露か涙か 不如帰(ほととぎす) 我が名をあげよ 雲の上まで
参考文献:山田康弘『足利義輝・義昭』、近藤瓶城編『足利季世記』、今福匡『上杉謙信』、吉川常隆「鹿島新當流剣術」(『日本古武道振興会 流儀解説書』所収) 他












