文豪・夏目漱石の妻、鏡子(きょうこ)は、ソクラテスの妻に並ぶほどの悪妻だったと言われています。朝寝坊で料理が苦手、占い好きで浪費家とされ、漱石の死後、弟子たちによって悪評を立てられました。
一方、英国留学中に神経衰弱を発症した漱石は、家の中でたびたび癇癪の発作を起こして暴れ、鏡子たち家族はそのたびに怯えて息をひそめていたといいます。
鏡子が漱石の死後に語った言葉を記録した『漱石の思い出』という本には、胃潰瘍で死線を彷徨う漱石を、鏡子が全身血まみれになりながら支えたり、夏目家に集まる弟子たちを大らかにもてなしたりと、むしろ良妻ではないかと思われるエピソードも登場します。
鏡子はなぜ、悪妻と呼ばれるようになったのでしょうか?
知られざる文豪の夫婦生活を垣間見てみましょう。
奥様は朝寝坊。朝食抜きで出勤する漱石
後に漱石の妻となる中根鏡子は、明治10(1877)年、貴族院書記官長をつとめる父のもとに生まれました。虎ノ門の官舎で、何不自由ない裕福な娘時代を過ごします。
2人が出会ったのは明治29(1896)年。漱石29歳、鏡子19歳のときでした。漱石は当時、『坊っちゃん』のモチーフとなった愛媛県の松山中学校で英語教師として働いていました。お見合いで知り合った2人は、翌年結婚。同時期に漱石は熊本の第五高等学校(現在の熊本大学)に職を得て、2人の新婚生活も熊本でスタートすることになります。
新婚の妻に、漱石はこんな言葉をかけたといいます。
「俺は学者で勉強しなければならないのだから、おまえなんかにかまってはいられない。それは承知していてもらいたい」
夫のほかに頼る人のいない新天地での新婚生活は、鏡子にとって楽しいだけのものではありませんでした。お嬢様育ちで家事を切り盛りした経験もなく、さらに土地勘もないため、買い物ひとつするにもひと苦労。お正月に集まってきたお客さんへの料理が間に合わず、「泣きたくなった」と鏡子は語っています。
加えて鏡子は、自他ともに認める朝寝坊でした。漱石が朝食をとらずに出勤したことも、一度や二度ではなかったようです。後年、漱石は『漱石日記』の中で、鏡子の朝寝坊についてこう書いています。
「妻は朝寝坊である。小言をいうとなお起きない。時とすると九時でも十時でも寝ている。(中略)普通の家庭で細君が九時頃起きて亭主がそれ前に起きるのは極めて少ない」
どうしても朝寝坊が直らない鏡子に、漱石はこんなことも言っています。
「おまえの寝坊で、おれがどれだけ時間の不経済をやっているかわからない、おれは一時間も前から目をさましているんだが、細君より先に床を離れるのは不見識だから、おまえが起きるまで床を離れない。これを長い間に見積もるとたいへんな損害だ」
隣に寝ている奥さんより先に目が覚めてしまって、けれど無理やり起こすわけでもなく、布団の中で奥さんが目覚めるのを1時間も待っている漱石の姿を思い浮かべると、何だかユーモラスで笑いがこみ上げてきます。マイペースな鏡子を、漱石は「オタンチンノパレオラガス」と造語で呼んでからかいました。当時の一般的な夫婦の形とは違っていたかもしれませんが、仲のいい新婚時代を送っていたようにも思えます。
着物も布団もボロボロ…漱石留学中の貧乏生活

明治33(1900)年、漱石は、文部省から2年間のイギリス留学を命じられます。この留学が、夫婦の運命を大きく変えることになりました。
熊本での4年間に引っ越しを繰り返したこともあり、夏目家にはまったく貯金がありませんでした。2人そろって、貯蓄があまり得意ではなかったようです。漱石がイギリスにいる間、鏡子は実家で暮らすために子どもを連れて里帰りをしましたが、その上京費用さえままならず、実家の父に借金をしたほどでした。
漱石の留学中に支給されるのは、最低限の費用のみ。漱石はロンドンの安下宿に暮らし、食費も切り詰めて本を買い、ひたすら勉強する日々を送りました。
残された鏡子は、裕福な実家を頼るつもりでいましたが、鏡子の父が職を辞し、相場に手を出したために、実家の援助も期待できない状況になってしまいました。漱石が帰国する頃には、着物も布団もぼろぼろに破れ、買い替えるお金もなかったといいます。
さらに漱石不在の中、鏡子は2人目の子供を出産。「悪妻」というよりは、本当に大変でしたねと声をかけたくなる苦労妻ぶりですが、漱石の帰国後、鏡子にはさらなる試練が待ち受けていました。
漱石の癇癪と、離婚の危機
明治36(1903)年、2年4ヶ月ぶりに鏡子のもとへ帰国した漱石は、留学中のストイックな生活がたたって胃を病み、重度の神経症を患っていました。この2つの病気が、後々まで漱石と鏡子を悩ませることになります。
帰国してからも漱石の神経症は回復せず、夜中に癇癪を起こして家の中のものを投げつけたり、子供が泣いたと言って怒ったり、鏡子に「里へ帰れ」と言ったりするようになります。現代ならば、DVと言われかねない状況です。鏡子によると、幻聴や幻覚などの症状もあったようです。
漱石は、鏡子の実家に、鏡子と離縁したいという主旨の手紙を繰り返し送りました。実家に帰ってきなさいという母親を、鏡子はこんなふうに言って諭します。
「夏目が精神病ときまればなおさらのこと私はこの家をどきません。(中略)私一人が実家へ帰ったら、私一人はそれで安全かもしれません。しかし子供や主人はどうなるのです。病気ときまれば、そばにおって及ばずながら看病するのが妻の役目ではありませんか」
しかもこの時期、鏡子は3人目の子供を出産しています。新婚時代の世間知らずだったお嬢様ぶりは影をひそめ、妻として母として、たくましく成長している様子がうかがえます。
『吾輩は猫である』が大ヒット!

漱石の神経症が一進一退を繰り返す中、夏目家に1匹の子猫が迷い込んできます。この出来事をモチーフに、明治38(1905)年、漱石が初めて発表した小説が『吾輩は猫である』でした。
猫を語り手にするという斬新な視点とユーモアあふれる文章が大評判になり、漱石は『坊っちゃん』『草枕』と次々にヒット作を生み出していきます。少しずつ原稿料も入るようになり、結婚8年目にして、夫婦の生活はようやく落ち着き始めました。
一躍人気作家になった漱石のもとには、ひっきりなしに訪問客が訪れるようになります。執筆時間を確保するため、漱石は木曜日を客と面会する日と定めました。木曜日、漱石の書斎には作家や出版界の要人が集まって語り合い、いつしか「木曜会」と呼ばれるようになりました。
集まる若者たちを、鏡子は大らかにもてなしました。木曜会に参加した人々は口をそろえて、漱石が穏やかな紳士であったと証言しています。神経症の症状が出ていないときの本来の漱石は、実際、子煩悩でやさしく、あたたかな人柄だったようです。
▼『吾輩は猫である』Amazonで全文無料で読めます!
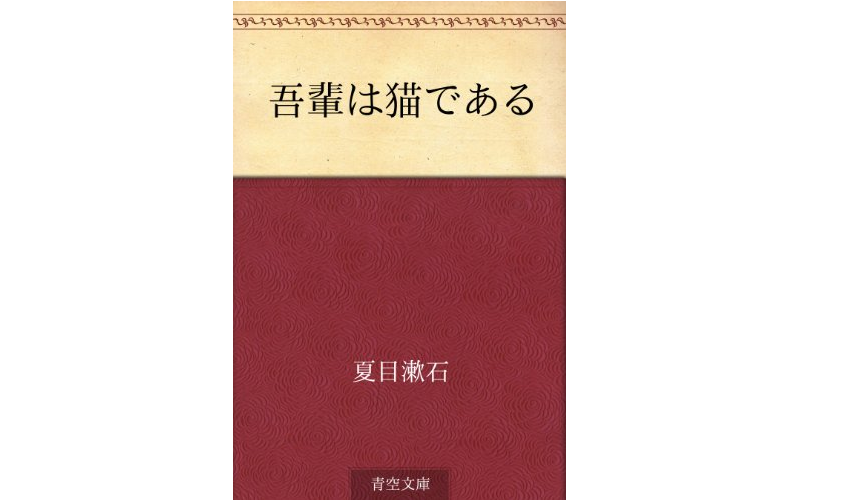
瀕死の漱石を、全身血まみれになって看病
作家生活に入って以来、漱石の神経症は小康状態を保っていましたが、今度は胃痛が悪化、胃潰瘍と診断されます。明治43(1910)年には、療養のために訪れた伊豆・修善寺で倒れてしまいました。
電報を受け取って駆けつけた鏡子の体につかまって、漱石はおびただしい量の血を吐きました。鏡子の着物の胸から下は、漱石の血で真っ赤に染まったといいます。意識を失い、一度は生死の境をさまよった漱石ですが、奇跡的に一命をとりとめます。鏡子はろくに食事もとらず、献身的に漱石を看病しました。
この病気をきっかけに、漱石は癇癪を起こすことが減り、家族の前でも、あたたかく穏やかな本来の姿を見せるようになります。けれど、夏目家に訪れた平和な時間は、長くは続きませんでした。大正2(1913)年頃には、再び神経症が悪化してしまったのです。
▼上記のシーンがでてきます。
坊っちゃんの時代 : 5 不機嫌亭漱石 (アクションコミックス)

夫に内緒で占い、おまじない… 鏡子の迷信
当時の家の中の様子を、鏡子はこんなふうに振り返っています。
「みんな(中略)警戒して、さわらぬ神に祟りなしと注意に注意をしておりますと、夏目は夏目で一生懸命きき耳を聳(た)てて、あらぬ妄想を構えて、疑いの上に疑いを築いて、根堀り葉掘り飛んでもないことを考えるらしいのです」
夫の病気に悩んだ鏡子は、漱石に内緒で占いに凝りはじめます。「天狗」と呼ばれる占い師に頼んで吉凶を見てもらったり、漱石の体調が悪いときには祈祷を頼んだりしていたようです。
漱石の癇癪がひどい時期には、虫封じのお札をもらってきて、柱に打ちつけていました。漱石が郵便を投函するため外出するわずかな隙をねらって、鏡子がお札を留める釘を金づちで打つという一種のおまじないをしていたところ、音を聞きつけた漱石が戻ってきました。
「私は妻の手からそのカナ槌を奪い取った。そうして虫封じの箱をすぐたたき壊した。それでもまだ腹が立つので外の虫封じ(皆で四つ五つ、中には虫封じでないものもあったかも知れない)を片っ端からぶちこわした。そうしてその破片をまとめて裏の芥溜(ごみため)へ投げ込んだ」
発作が起こるとき、漱石は、おかしいのは自分ではなく鏡子を含む周りの人間だと感じていたようです。自分を病人扱いして、占いやおまじないに頼る鏡子の一挙手一投足が気に入らなかったのでしょう。
虫封じのお札を捨てられた鏡子は、めげることなく、占い師の助言で「毒掃丸」という便秘薬を漱石の薬にこっそり混ぜるようになります。便秘の治療ではなく「頭にのぼった毒をおろすため」というあやしげな理屈です。これも漱石に見つかって「小っぴどく怒られた」と鏡子は語っています。
出口の見えない苦しさの中で、鏡子はわらにも縋りたい思いだったでしょう。とはいえ、妻が毎日柱に釘を打ちつけたり、知らない間に薬を飲まされたりして、疑心暗鬼になる漱石の気持ちもわかります。
この頃の漱石の日記には、鏡子のことが繰り返し書かれています。
「元妻妻(原文のママ)は毎日のように按摩をする。聞けば肩がこるのだそうだが、そうかと思うとよそへ行く時に肩が凝るからといってやめた事はない。しゃしゃとして出て行く」
「妻は万事こんな風に凡て自分に都合のわるい事は夫に黙っている女である。そうして出来る限り夫を甘く見、また甘く取り扱えば夫が自分の資格でも増すように考えている女である」
「妻はヒステリーに罹るくせがあったが、何か小言でもいうときっと厠の前で引っ繰り返ったり縁側で斃れたりする」
鏡子の行動ひとつひとつを詳細に観察し、記録していく様子はさすが稀代の天才作家ですが、神経症のためか被害妄想的になっている部分も少なくありません。鏡子が繊細でくよくよした性格だったら、夫婦生活は到底続かなかったでしょう。漱石の緻密さとは正反対に、細かいことにこだわらない女性が妻だったからこそ、漱石は自分のすべてをさらけ出し、苦しい時期を乗り越えることができたのかもしれません。
漱石の死後10年。鏡子はなぜ「悪妻」と呼ばれたか
大正5(1916)年、漱石は糖尿病を患い、さらに持病の胃潰瘍が悪化して、49歳でその生涯を閉じます。
鏡子が「悪妻」であるという評判が世の中に広がったのは、漱石の死から10年あまりが過ぎてからです。漱石の弟子であり長女の夫である松岡譲氏が、「漱石の思い出を語ってほしい」と鏡子に依頼したことがきっかけでした。
松岡氏は、鏡子が語った内容を『漱石の思い出』として1冊の本にまとめ、出版しました。そこには、世間の一般的なイメージだった「紳士的で穏やかな文豪」の姿だけでなく、癇癪を起こして家族を悩ませる人間・夏目漱石の姿が赤裸々に綴られており、世間は騒然となります。
中でも生前から漱石と親しく付き合い、死後も一途に尊敬し続けていた「木曜会」の弟子たちは、「許すべからざる冒瀆」「死者に鞭打つとは何事か」とカンカンに怒って鏡子を非難します。
大らかでオープンな性格の鏡子は、朝寝坊ですぐ迷信に頼る自分の欠点や、上手に家事を切り盛りできなかった新婚時代のエピソードも隠すことなく語りました。さらに漱石の死後、鏡子が夫の著作の印税で家を買い、家族と共に贅沢な暮らしをしていたことも、火に油を注ぎました。漱石に激しい一面があったことを信じたくない人たちは「とんでもない悪妻だ」「先生が癇癪を起こしたのは妻のせいだ」と鏡子に怒りの矛先を向けたのです。
漱石の弟子たちは、漱石の文才のみならず、紳士的であたたかな人柄に心酔していました。鏡子の「告発」により、自分たちにとって神聖な存在である漱石の人格が汚されるようで、許せないと感じたのかもしれません。
弟子たちの心情もわかりますが、鏡子にとっては、きっと穏やかでやさしいときの漱石も、病気のせいで癇癪を起こす漱石も、まるごとひとりの人格として、ほかの誰にも代えがたい、愛しい存在だったのではないでしょうか。だからこそ、最後まで漱石の側を離れなかったのでしょうし、結婚生活をありのままに語ったのだとも考えられます。
若き日の漱石は、留学先のロンドンから、鏡子にこんなラブレターを送っています。
「おれの様な不人情なものでも頻りにお前が恋しい。これだけは奇特といって褒めてもらわなければならぬ」
漱石の直截な愛の言葉に、鏡子もこんな返事を送っています。
「私もあなたの事を恋しいと思いつづけている事は負けないつもりです」
夫が病に苦しんでも見捨てることなく、世間から「悪妻」と呼ばれても、決して漱石の悪口を言ったり、反論したりしなかったという鏡子。典型的な「良妻賢母」ではなかったかもしれませんが、さばさばした性格ではっきりとものを言う、近代的な魅力を持った女性だったようです。そんな真っ直ぐな気性の妻を、漱石もまた愛し、頼りにしていたのではないでしょうか。
漱石の孫でエッセイストの半藤末利子氏は、鏡子のこんな言葉を聞いたことがあるといいます。
「いろんな男の人をみてきたけど、あたしゃお父様が一番いいねぇ」
夫婦の形は百人百様。真実は2人にしかわかりません。文豪ではなくひとりの男性として漱石を生涯愛し続けた鏡子は、世間が何と言おうと、とても純粋な心の持ち主であるように、私には思えてならないのです。
▼夏目漱石についてもっと知る!
文豪たちの酔っ払い伝説!太宰治は酒好き、夏目漱石は下戸だった!
参考文献
夏目鏡子述・松岡譲筆録『漱石の思い出』(文春文庫)
鳥越碧『漱石の妻』(講談社文庫)
夏目漱石『漱石日記』(岩波文庫)
※文中、夏目漱石の画像は国立国会図書館ウェブサイト、
『吾輩は猫である』挿絵は国立国会図書館デジタルコレクションより転載












