昭和の時代、「ピッカリコニカ」(小西六→コニカミノルタ)というカメラがあった。光学機器にうとい私でも名前を憶えているくらい、爆発的にヒットしたカメラだった。フラッシュ内蔵のコンパクトカメラで、カメラ初心者でも手軽に撮影ができるという、実に大衆ウケのする製品だったのだ。
このカメラを一躍有名にした人物がいる。岐阜県の徳山村という、ほとんど福井県との県境にあった山深い村に住んでいた増山(ますやま)たづ子さんという女性だ。
増山さんは60歳で初めてカメラを手にして故郷を撮り始めた。彼女が最初に使ったカメラがピッカリコニカだったのだ。
増山さんの生まれた徳山村はもはやこの世に存在しない。
ダムの底に沈んでしまった。
増山さんも2006年に88歳で亡くなり、すでに16年が経つ。
なぜ、増山さんは60歳になって写真を撮り始めたのか。増山さんは写真を撮ることで何を残したかったのだろうか。
※アイキャッチの画像は晩年の増山さん。この頃はすでに「ピッカリコニカ」は製造されなくなっており、増山さんが手にしているカメラは別の機種である。
「増山たづ子の遺志を継ぐ館」(代表・野部博子さん 以下同)撮影・提供
生前の増山さんとの出会い―このおばあちゃんはただ者ではない―
私は一度だけ、生前の増山さんにお会いしたことがある。
20年以上前だったと思う。
当時私は大垣市にあった小さなタウン誌の編集室にいた。そこへ一人の女性が「徳山村の増山たづ子さんという人が語る昔話を広く世の中に知ってほしいので、広報面で力を貸してほしい」と来られたのだ。その女性は野部博子(のべ ひろこ)さんといって当時、滋賀県立大学の先生をしておられた。野部さんは伝承文化の研究者として徳山村を訪れるうちに増山さんと親しくなり、彼女の語る昔話を後世に伝えるべく、CD化に踏み切られたのだった。
野部さんについては後ほど、詳しくお話しする。
この出会いがきっかけで、私は増山さんにお話が聞けることになった。当時増山さん一家はダムの底に沈む故郷を離れ、岐阜市の郊外に家を建てて住んでおられた。その時のことは『ふるさとの転居通知』(情報センター出版局)という本に詳しい。
増山さんは80歳を越えておられたと思うが、すこぶるお元気で、ご自分のお部屋にはこれまで撮影された大量の写真があった。何よりビックリしたのはご自分の部屋に黒電話を引いておられたことである。むろん、携帯電話などはない時代である。同居の家族に迷惑がかからないよう、マスコミなどの取材対応もすべて自分でされていたのだ。
なぜ、写真を撮り始めたのか、かつての徳山村での暮らしについてなど、昔のことをお尋ねしたと思うが、増山さんの記憶力のすばらしさにも舌を巻いた。何十年も昔のことなのによどみなくきちんと答えられ、詳細に語られた。(このおばあちゃんはただ者ではない)と思った。
この時、増山さんは盛んに「あんたに言うとく、あんたに言うとく(あなたに話しておく)」とおっしゃった。「あんたに言うとく」と言われても、私には何の力もないし、増山さんのこともまだよく知らない。
このおばあちゃんはいったい何をそんなに伝えたいのか。
当時の私はとまどうばかりで、せいぜいこの時のことを短くて拙(つたな)い記事にする事しかできなかった。
たった一度の出会いだったが、増山さんの人懐っこい笑顔とその熱のこもった話しぶりは長く印象に残った。

写真で見るイラ(私)の故郷・徳の山(徳山村)
その後、増山さんは❝徳山のカメラばあちゃん❞として、たびたびマスコミに登場した。全国各地で写真展も開催され、時の人となった。
後半生、アマチュア写真家として取り上げられることの多かった増山さんだが、私は増山さんは写真家ではなかったと思っている。
それどころか、採算など度外視して徳山村とその人々の写真を撮り続けた。
現像代が1カ月で26万8千円になった時もあったという。
もちろん、撮影した写真を売るなんてことは考えもしなかった。
まずは増山さんが撮影した当時の徳山村のありのままの姿を見ていただこう。
※以下はすべて、「増山たづ子の遺志を継ぐ館」提供。





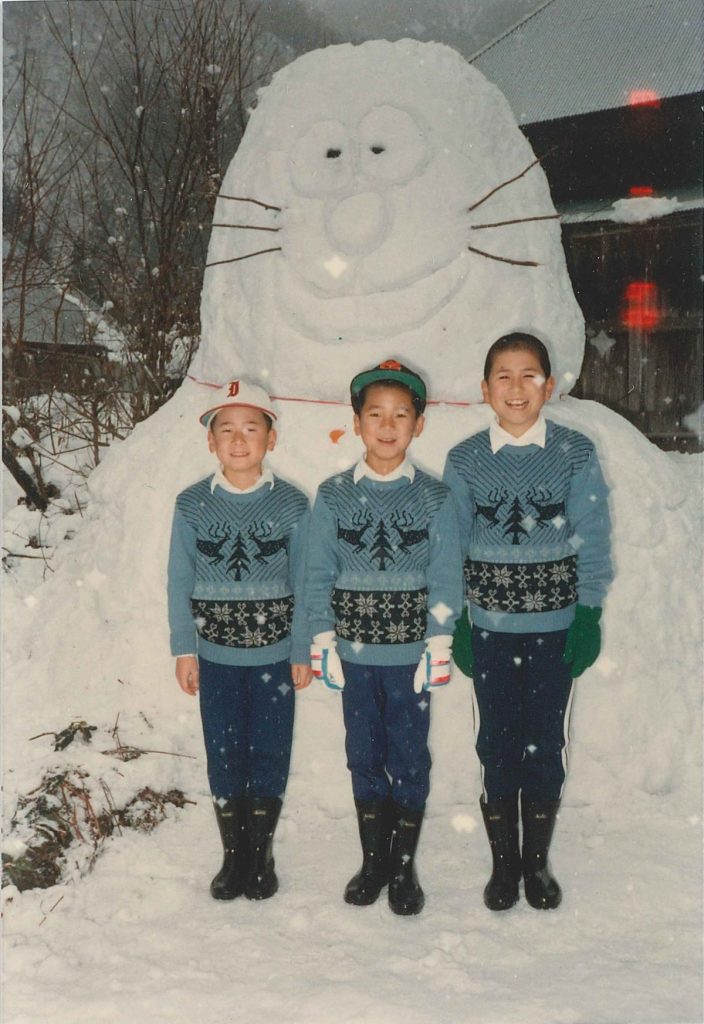



ター(増山さん)はカメラを持つとむちゃくちゃになる
どの写真の人物も生き生きとした表情で、語りかけてくる。
徳山弁で交わす会話がいまにも聞こえてきそうだ。
風のささやきが、盆踊りの唄が、人々の足音や無心に遊ぶ子どもたちの笑い声が、数十年の時を経てよみがえる。
これらは増山さんでなければ撮れない写真だった。
被写体になった村人たちも、撮影者がター(増山さんのこと)だからこそ、心を開いたのだ。
増山さんはカメラを手にすると、人が変わったようになった。
そんな自分を次のように振り返っている。
カメラを持つとイラ(私)はむちゃくちゃになるで。
夜明けの村を撮りたいと思ったらな、もう四時半ごろから山に登って行って日の出を待っとるしな。
雪ん中でも雨の日でも、もんぺに長ぐつはいてれば、どこへでも行けるでな。
かっぽう着にフィルム入れといてな、写真撮り終わったら、かっぽう着のポケットをまさぐるようにして、フィルムを交換するんだで。-中略-。
イラはな、自分の励みのために写真を撮ってるんだな。
「あんたに言うとく」 増山さんが❝徳山のカメラばあちゃん❞になるまで
28年間という写真活動の中で、増山さんは約10万点のプリント写真とネガフィルム約3900本、アルバム約600冊を遺した。
現在、写真とその著作権はすべて「増山たづ子の遺志を継ぐ館」代表・野部博子さんが管理している。
近年は昨年、東京五輪・パラリンピックの開催に合わせて開催された「Walls&Bridges(壁は橋になる) 世界にふれる、世界に生きる」(東京都美術館)に増山さんの遺作を出品、また、この6月、増山さんの故郷に近い揖斐川町の歴史民俗資料館で写真展が開催され、野部さんも増山さんについての講演を行った。
現在はフランスのパリで写真展が開催されている。
増山さんは「あんたに言うとく」と、すべてを野部さんに託して逝った。
そこまでして増山さんを駆り立てたものはなんだったのか。
徳山村の歴史と増山さんの生涯を駆け足で追ってみた。
周囲を1000メートル級の山々に囲まれた徳山村 その始まりは縄文時代
増山さんの故郷・徳山村はかつて、岐阜県揖斐郡の山奥に存在した。
周囲には冠山(かんむりやま)や金草岳(かなくさだけ)など1000メートル級の険しい山々が屏風のように立ちはだかり、隣はもう福井県だ。
今、岐阜県と福井県を最短で結ぶ国道417号「冠山峠道路」の建設が進んでおり、順調にいけば2023年には開通の予定だそうだ。
徳山村の総面積は約253.6平方キロメートル。
その中に下開田(しもかいでん)・本郷・上開田(かみかいでん)・戸入(とにゅう)・門入(かどにゅう)・山手・櫨原(はぜはら)・塚という八つの集落が存在していた。増山さんは戸入の出身である。
徳山村には旧石器時代から人が住んでいたらしい。
縄文時代の遺跡も何カ所か見つかっている。
江戸時代には旗本で地元の土豪であった徳山(とくのやま/とくやま)氏の知行地だった。


岐阜市でおくった少女時代
増山さんが生まれたのは1917年。
叔父さんは川口半平(かわぐち はんぺい)さんといって、岐阜県では有名な教育者で児童文学者でもあった。
第二次世界大戦後は県の教育長を務め、1972年には「岐阜児童文学研究会」のメンバーだった岸武雄(きし たけお)さんや赤座憲久(あかざ のりひさ)さんらとともに『コボたち』という児童文学雑誌を創刊した。
川口夫妻には子どもがなく、姪だった増山さんが養女となるはずだった。
そのため普段は岐阜市の川口家に住んで勉強しながら洋裁を習い、農繁期になると徳山村の実家に戻って農作業を手伝っていたそうである。
増山さんの並外れた教養や知性、そして感受性の豊かさは、川口さんの影響によるところが大きいようだ。

知らない間に決まってしまった結婚
増山さんの旧姓は平方(ひらかた)さんといった。
1936年、19歳のたづ子さんは同じ戸入出身で6歳年長の増山徳治郎さんと結婚した。
徳治郎さんは名古屋で堂守大工の仕事をしており、結婚後は名古屋と徳山村を行ったり来たりしていたようだ。
結婚話は増山さんが知らない間に一方的に決まってしまった。
昔のこととはいえ、川口さんの薫陶(くんとう)を受けて育った増山さんにとって、これはかなりショックだった。
叔父や兄の影響でな、イラは❝自由主義❞だったからな。
自分がやったことは自分で責任持たなあかんと思っとった。その時代では珍しかったで。
だから知らんうちに嫁にくれられてまうような封建的なのは嫌いだったしな、
もっと勉強したかったからな、「いやじゃ、いやじゃ、いやじゃ」って一週間泣いとった。 『ふるさとの転居通知』増山たづ子 情報センター出版局
婚約中、どうしてもまだ結婚したくなかった増山さんは理由をつけて、神戸から船に乗り、兄のいた旅順(りょじゅん 中国の遼東半島の南端にある大連市の一部)に旅立った。逃げたのである。
ところが4カ月の旅順滞在期間中、婚約者の徳治郎さんからは1週間に2回、4、5通ものラブレターが届いた。
しまいにはとうとう「帰ってこなければ迎えに行く」というたよりが来るようになったため、兄に諭され、帰国。
帰ったその日に二人は結婚した。
戦争から帰って来ないおとうちゃん
やがて日本は太平洋戦争に突入。二人の結婚生活は、わずか4年半に過ぎなかった。
イラとお父ちゃんがな、一番長く一緒におったのは四ヵ月だな。初めの召集が来る前のひと冬、名古屋で過ごしたんだな。
菜種の花が咲いているあぜ道を、ゆっくりと歩いとったな、二人で。お父ちゃんは東海林太郎(しょうじ たろう)の『野崎参り』の唄をくちずさんでな。
イラは日傘をクルクル回しながら、後をついて行ったな。『ふるさとの転居通知』増山たづ子 情報センター出版局
冬を越して、翌年の春、徳治郎さんに初めての召集が来た。
ちょうど長女の尚子さんが生まれた頃だった。
いったんは無事に戻ってきたが、二度目の召集で徳治郎さんはビルマへ。
これが二人にとって永遠の別れとなった。
二回目の召集のときはな、イラは尚子の手を引き、生まれたばっかりの好平(こうへい)を負んでたな。
ちょうど半紙ぐらいの旗を持って、村中で兵隊を送るんだけどな。
柿の木の葉が落ちてな、晴れた青空に実だけが美しかったな。
子供たちはなんも知らなんでな、旗を一所懸命振ってたな。
昭和二〇年五月二九日、敗戦の色が濃くなったころだで。
お父ちゃんは、ビルマのインパール作戦に行ったまんま、戻って来ない。
『ふるさとの転居通知』増山たづ子 情報センター出版局

❝友達の木❞に支えられて
徳治郎さんが戦争に行った後、増山さんは徳山村に戻って農業をして暮らしていた。
短気で働き者だったお義父さんの下で、ずいぶん辛い思いをすることもあったようだ。
そんな時、増山さんはよく❝友達の木❞に話しかけた。
❝友達の木❞は川端に生えていたコナラ(増山さんはホウソの木と呼んでいた)の老木で、長い間増山さんの心の支えになってくれた木である。
いやなことや辛いことがあると、増山さんは友達の木にだけ自分の心を打ち明けた。
人に話すことはできなかった。
この木は増山さんが徳山村を離れる少し前に枯れてしまったという。

「増山たづ子の遺志を継ぐ館」提供
金華山の裏から飛んで死のうと思った
戸入からは20人ほどが出征したが、11人が戻って来なかった。その中には徳治郎さんや増山さんの弟の正(ただし)さんもいた。
姉のたづ子さんが増山家に嫁いだため、正さんが川口家の養子になった。とても聡明な人で、周囲からも将来を期待されていた。
増山さんとは一番仲が良かったという。しかし、終戦後、やっとたどりついた広東の病院で栄養失調で亡くなった。
増山さんは戻って来ない徳治郎さんをずっと待っていた。
生きているのか死んでいるのかさえわからない。
当時、このような女性は日本中にいた。
戦死といわれて遺骨をもらいにいっても、中に入っているのは骨ではなく石ころであったり、空であったりした。
私の伯父も終戦の2ヶ月ほど前にフィリピンのミンダナオ島で亡くなったという。
もちろん遺骨は戻って来なかった。
祖母はずいぶん長い間、伯父の写真に陰膳(かげぜん)を備えていたらしい。
陰膳というのは不在者の安全を願って用意する食事のことだ。
遺体を見たわけではなかったから、ひょっとしたらどこかで生きているかもしれないという親としての思いもあったのだろう。
増山さんもとうとう遺骨を受け取りにいかねばならなくなり、たった一人で白木の箱を受け取りにいった。
泣くこともできず、しばらく虚脱状態が続いた。
泣くことができたのなら、どんなによかったことだろう。
ノイローゼになった増山さんは一年ほど、死ぬことばかり考えていたという。
そして、とうとう岐阜市にある金華山の裏から飛び降りて死のうと思い、村を出た。
だが叔母さんの機転で遺書が見つかり、叔父さんに連れ戻された。
ふだん温厚な川口さんが烈火の如く憤った。
そこで初めて目が覚めた増山さんは、死んだつもりで生きようと決意したのだった。
消滅する村の記録者として 人々の生きた証を残すために
村がダムになる
戦後、増山さんは農業のかたわら民宿「増山屋」を始めた。
当時の村長さんが、「この戸入にも気楽に泊まれる宿屋が一軒くらいあってもいいな。
おまえんとこはうちは広いしな、やれ、やれ」っていうからな。そんで始めたな。
山菜採りや釣りに来た人とかな、ダムの調査とか、方言や歴史の研究に来た人とかな、富山や滋賀から来た薬屋さんも泊まっていってくれたな。
―中略―ここへ来る人は一回や二回じゃないで。
みんなが自分の在所(ざいしょ)のようにしてくれてるな。
みんな、ふるさとというものを欲しがってるのかな。
『ふるさとの転居通知』増山たづ子 情報センター出版局
村が総貯水量6億6千万トンという日本最大規模のダムになるという話が持ち上がったのは、1957年のことだった。
終戦(1945年)から12年が経っていた。
1955年には国民総生産(GNP)が戦前の水準を上回り、1956年には経済企画庁が経済白書の中で「もはや戦後ではない」と記述した。
日本は高度経済成長時代に入っており、発電や工業用水に水が必要となって、山間地には多くのダムが造られた。
当時の徳山村は人口1500人足らずで戸数は470戸。
しかも周囲は高い山々や森林に囲まれ、冬には2mから5mもの雪が積もった。
水量は豊富である。
ダムにするには持って来いだったのだ。
大事なのは村の記録を残すこと
村というのは良くも悪くも運命共同体である。
人々は互いに助け合って生きている。
それは都会とは異なる交通の不便さや経済活動の低迷を補うための手段であり、生き抜くための知恵だった。
うちのお父ちゃんが戦争からまんだ帰ってこんうちに、村がのうなってまうのは大変だってな、真剣になって反対したな。
ダムになっちゃかなわんてな、初めは村一丸となって反対したんだけど、途中から割れたな。
若いもんがどんどん町へ出ていくという過疎の問題があってな、この際ダムになったほうがいいという促進派とな、大事なふるさとを水底に沈めてまったら、ご先祖様に申し訳がないという反対派に分かれたな。
‐中略‐(村をダムにすると言われて)二八年目だよ、ことしで。
‐中略‐長い年月がな、人間の心を変えてまうんだな。
‐中略‐イラもな、こんなバカげたことをやっているよりは、これは少しでも、自分の大事な村のことを残しておかなだめだとな、そういう気持ちに変わったな。
『ふるさとの転居通知』増山たづ子 情報センター出版局
徳山ダムの計画の話が出て、実際にダムが完成したのは2008年。実に51年の歳月が経っている。
半世紀にわたって、徳山村の人々はダムに翻弄され続けた。
村が浮いてまうから音を録(と)る
村がなくなってしまうという危機感は、増山さんはじめ徳山村の人々に思いがけない効果をもたらした。
増山さんの家は人々が集まる会場となり、篠田先生という若い人を中心に徳山村で出土した土器のことや珍しい方言、俳句、短歌、昔話や薬草のことなど、徳山の文化を記録した『ゆるえ』という冊子を発行したのである。ゆるえとは囲炉裏(いろり)という意味だそうだ。
そして「みんながバラバラにならないうちに、残せるものを残そう」と決意した増山さんは、カセットテープレコーダーで村人たちの音声を録音し始めた。
記録のためというより、村を出て知らない所へ行って自分が寂しくなった時に、みんなの懐かしい声を聞いて心の支えとするためだった。
お祭りや盆踊り、徳山の民謡、昔話など500巻ほど録ったという。
徳山村の人たちは、ダムができて村が沈むとは決して言わなかったという。
その代わりに、❝浮いてまう(浮いてしまう)❞という言葉を使った。
自分たちの暮らしをつなぎとめていた根っこがなくなって、生活が❝浮いてまう❞(浮きあがってしまう)ということらしかった。
ピッカリコニカ―猫がけっころがしても写る写真機―との出会い
諸事情によりダムの話はなかなか進展しなかったが、1972年から立ち入り調査が始まり、’77年には補償基準が出るらしいという話が聞こえてきた。
「これはいよいよ…」と感じた増山さんは音声だけでなく、徳山村に生きる人々の姿を撮りたいと思うようになった。
『ふるさとの転居通知』(情報センター出版局)に増山さんはその時のことを次のように書いている。
「いまのこの便利な世の中にな、プロの人たちが持ってる、クソ重たくて、眼鏡をかけねばわからんほど細かな数字がいっぱいあって、何十万とする高いものでなくてな、もっと安くて、便利な写真機が出てもよかりそうなもんに」
あるとき、イラは名古屋でカメラ屋をやってる伊藤さんに、そうグチをいうたんだな。そしたらな、
「おばあちゃん、あるある。いまは猫がけっころがしても写る写真機がある」といってな、
ピッカリコニカを持ってきてくれたのが、写真を撮りだした始まりだったな。
増山さんがピッカリコニカで初めて撮影したのは❝友だちの木❞だった。

お父ちゃんが帰って来た時、この村の状況を知らせたい
それまでカメラを触ったこともなかった増山さんは、フィルムの入れ方も知らなかった。
誰でも撮れるピッカリコニカとはいえ、デジカメではなく、ネガ用フィルムを入れないと写らないアナログカメラだった。
伊藤さんは撮り方は教えてくれたが、フィルムの入れ方までは教えてくれなかったのだった。
村民体育大会では人に頼んでフィルムを出し入れしてもらった。その数は10本以上にも及んだようである。
プロのカメラマンからは「そんなの写真にもなんにもなっとらへんで」と言われたが、実際焼いてもらったらきれいに写っていた。増山さんは嬉しさのあまり、飛び跳ねて喜んだという。
村の人々を一人残らず、このふるさとをすみからすみまで、イラはとりつかれたように撮ったな。
うちのお父ちゃんが帰って来たとき、なんとしてでもこん村の状況を知らせたいしな。
それに、お父ちゃんはこん村にあまりおったことがないから、すこしでもむかしの思い出を残しておいてあげたい、という思いもあってな。
イラも、「ああ、この生まれ育ったふるさとがのうなってまう」と思うとな、いてもたってもいられなくてな。
『ふるさとの転居通知』(情報センター出版局)
増山さんが撮影した写真は半年で3千枚にも及んだ。そして出来のいいのはキャビネ版に引き伸ばして村の人々にあげた。


初めての写真展から写真集の出版まで
1978年、増山さんにとって初めての個展が名古屋のカメラ屋さんの2Fで始まった。
あまりにも増山さんが大量に写真を撮ってきて現像に出すため、その理由を知った関係者によってトントン拍子に開催が決まったという。
写真展は好評を博し、最初は二週間の予定だったが、1カ月に延び、その後はあちこちで開催されるようになった。
増山さんが撮影した写真の中に、徳山村の元服式の写真がある。
徳山村では室町時代から15歳になると男子は元服式を行う習慣があった。
元服というのは成人になった証の儀式である。
親は一人前になったわが子を見て感激し、子どもは育ててくれた親に感謝する。
人生の節目の一つでもあった。
元服式の写真を見て多くの人々が涙を流したという。
元服式は旧徳山村の人々の移転先の一つである本巣市文殊(もんじゅ)の徳山神社で、中学3年生の男女を対象に現在も行われている。
やがて増山さんにとって初めての写真集『故郷 私の徳山村写真日記』(じゃこめてい出版)が発刊された。
ピッカリコニカのメーカー「小西六(現コニカミノルタホールディングス株式会社)」が東京で出版記念の写真展を開催してくれた。

写真が教えてくれた村のほんとうの姿
ダムになろうがなるまいが、季節は巡り来る。
そして増山さんも憑りつかれたように写真を撮った。
四季折々の山里の美しさやそこに生きる人々の表情の豊かさを撮り続けた。
写真というのは妙なもんでな、写真を通してな、いままで気がつかなかった村の美しさ、それから人の表情の美しさというのがわかったな。
ますます好きになってまったで、こん村が。『ふるさとの転居通知』(情報センター出版局)

民宿増山屋にやってきた人々
増山さんは民宿のおかみさんだったが、決して愛想をふりまく人ではなかったらしい。
ぶっきらぼうで飾り気のない人というのが本当のところのようだ。
しかし、増山さんを慕って全国から実にさまざまな人がやってきた。
俳優で民話の研究をしている山口崇(やまぐち たかし)さん、詩人の石垣りんさんもその一人だ。
石垣さんは増山さんの最初の写真集『故郷 私の徳山村写真日記』のあとがきに『村の形見に』と題して、次のように書いている。
増山たづ子さんが手にした「猫がけっころがしても写る」一台の写真機の目は、時の流れにけっころがされながら懸命に生きて来た者が、どたんばでこちらを振り返った目のようでもあります。
なんと鋭い指摘だろう。
民宿増山屋には詐欺師もやってきた。ルポライターと名乗り、『アサヒグラフ』で特集を組んであげようと言ったらしい。
マスコミ関係に知り合いも多く、見事に騙された増山さんだったが、詐欺師は1カ月後、上野駅でつかまった。
15歳で詐欺師を始め、前科8犯とのことだった。
つかまった詐欺師に宛てて、増山さんは「あんたもその知恵と才覚をな、もっといいほうに使ってな、そして幸せになってください」と手紙をしたため、撮影した写真も送った。増山さんの真心は詐欺師に届いたのだろうか。
映画『ふるさと』にも出演
1982年、徳山村を舞台にした映画『ふるさと』のロケが行われた。
監督は神山征二郎(こうやま せいじろう)さん、主演は加藤嘉(かとう よし)さん、そして映画の原作となったのは、増山さんの甥(おい)で、徳山在住の教師・平方浩介(ひらかた こうすけ)さんが書いた『じいと山のコボたち』(童心社のちフォア文庫)である。
加藤さんはこの映画でモスクワ国際映画祭最優秀主演男優賞を受賞した。
増山さんには「自分が主役をするのはこれが最後だろうから、自分が仕事をしているところを撮ってほしい」と頼んだ。
増山さんはロケの間中ずっと加藤さんやスタッフを追いかけた。
そして、❝写真ばあちゃん❞として映画にも出演した。
映画にはエキストラとして多くの村民も出演した。
ラストで加藤さん演じる主人公が亡くなり、雪が降りしきる中、人々は徳山村に別れを告げ、村を後にするのだが、そのシーンはいつ見ても胸に迫るものがある。
徳山村の人々にとって、村との別れはまさに現実のものになろうとしていた。
「エイボン功績賞」受賞 からっぽの宝石箱に入れるもの
1984年、増山さんは「エイボン功績賞」を受賞した。
同賞は化粧品メーカー、エイボン・プロダクツ(現エフエムジ―&ミッション株式会社)が、社会のために有意義な活動を続け、功績を挙げた女性に対して贈る賞である。
イラはな、ダムで沈む村を写真に撮り続けてきたということでな、八〇〇人の候補者の中の五人に入れていただいたんだけど、これは自分の実力じゃないな。
イラのことを支えてくれた人たちのおかげだで、ありがたいことだと思ったな。
エイボン功績賞では賞金とともに、ニューヨークのティファニー宝石店で作られた銀製の小箱が贈られた。
賞金はすべて寄付し、ティファニーの小箱の使い道を聞かれた際、増山さんは次のように答えた。
「わたしは宝石は入れません。
これは、自分の実力でいただいたものじゃないから、みなさんの温かいご厚意を入れます。
だから。からっぽです」
湖の下にも人々の営みが息づいている
さようなら、徳山村 最期(ミナシマイ)の日々
1985年7月、増山さんは住み慣れた故郷を後に岐阜市の郊外へ転居する。
新居の近くには鉄塔があり、増山さんは知人、友人に向けて
「わが庵(いお)は高圧線の下にあり 上を見ずして下で明るく」
と転居通知を書いて出した。
上ばっか見とってもしようがないでな。
こう、下で明るい電灯がつくために、上を鉄塔というのが走っとるんだからな。
だれかがその下で、幸せになってくれるとうれしいなと思っとる。『ふるさとの転居通知』(情報センター出版局)
増山さんは徳山で咲いていた草花をいっぱい持ってきた。
鉄塔の下には畑を作った。
孫たちに苗木の栽培の仕方や薬草についての知識、自然を大事にする心を教えたいと思ったのだ。
もちろん時々村に戻ったり、人々の移転地に行って写真を撮ることも忘れなかった。
徳山村では人々だけでなく、いろいろなものとの別れが始まっていた。
家屋敷、学校、田畑、見慣れた風景、共に暮らした動物たち、そして神社や道場も…
道場とは寺院としての格はもたないが、人々が集まってお参りをしたり、念仏を唱える場所をいう。
徳山村では大きな法要(ほうよう)などがあると、福井県鯖江(さばえ)市にある浄土真宗誠照寺(じょうしょうじ)派の本山・誠照寺などから住職がお参りに来ていたようだ。
村人たちが住まなくなった家は壊されたり、焼かれたりした。
みんな泣きながら見とったよ。「ああいう立派な家が壊されるのは、もったいないこっちゃな」といいながらな。大蛇みたいな、お化けのような機械がな、引っ張ったりバンバンと叩いたりするんで、家はユラユラ揺れてたな。そして、キイキイと泣きながら倒れていったな。『ふるさとの転居通知』(情報センター出版局)

徳山ダム 湛水(たんすい)
増山さんはダムの湛水が始まる直前、2006年3月7日に亡くなった。
88歳だった。
私は新聞でそれを知った。
ああ、とうとう亡くなったのかと思った。
徳山村の写真をずっと撮ってきた増山さんが、村の最期を見届けることなく亡くなったことが、なんだかとても不思議だった。
湛水が始まってまもなく、私はそれまで行ったこともなかった徳山村に足を向けた。
揖斐川町から徳山ダムに至る道はきちんと整備されていた。
しかし、思った以上に遠かった。
ダムの上から下を見ると、ヒタヒタと少しずつ水は溜まっていたが、本郷にあった徳山小学校はその時点では水没していなかった。
小学校は村の象徴だ。
ニュースの影響もあってか、たくさんの人々が湛水の様子を見に来ていた。
その多くは徳山村ゆかりの人々ではなかったのだろうか。
少しずつ水に埋もれていく村を見ながら、人々の胸によぎるものはなんだったのだろう。
増山さんの写真が私達に語りかけるもの
語り部としての増山さん
「増山さんが遺したかったのは、徳山村に多くの命が懸命に生きていたという証だと思います」
こう語るのは、「増山たづ子の遺志を継ぐ館」代表を務める野部博子さんだ。
徳山村の民話研究調査のために民宿・増山屋に泊まり込んだのが縁で、二人は親しくなった。
普通は調査研究が終わればそれ以上に縁が続くことはない。
しかし、野部さんと増山さんはそうではなかった。
「私の住む神戸町(ごうどちょう)から徳山村は距離的にも比較的近かったんです。
昔は徳山から神戸まで行儀見習いに来ている人もあったりして、私にとっての徳山村は決して遠い存在ではありませんでした。
徳山村に赴任しておられる学校の先生は❝土帰月来(どきげつらい)❞といって、一週間が終わると土曜日に神戸の家に戻り、月曜日になると徳山の学校に行くという生活スタイルでしたね。友達のおばあちゃんの実家も徳山村でした」
野部さんは北海道の真刈村(まっかりむら)への入植者調査にも出かけている。
真刈村は❝蝦夷(えぞ)富士❞と呼ばれる羊蹄山(ようていざん)の南山麓にあり、かつて徳山村の門入から入植した人々がいた。
伝承文化の研究者である野部さんにとって、増山さんは世間の人がいうようなアマチュアカメラマンではなく、徳山村の文化を伝承する貴重な語り部だった。
野部さんが増山さんから昔話を採話するうち、二人の間には強い信頼関係が生まれ、増山さんも語り部として成長していったという。
「徳山村は八つの集落がありましたが、それぞれが独立しており、違った文化を持っていました。
特に増山さんが生まれ育った戸入には、ほかではすでに失われてしまった独特の言葉が残っていましたね。
その言葉が残っている所は全国で6カ所しかありません。
言葉というものは目に見えません。でも、そこに生きていた人々が育んできた貴重な文化遺産です。
増山さんの語りを残すことで、私は徳山村を遺したいと思ったのです」
野部さんが企画・構成を担当した増山さんが語る昔話は、「たぁばぁちゃんの昔がたり ダムに沈む昔話の世界 : 増山たづ子・旧徳山村の昔話」として、1999年、岐阜市の増山さん宅で録音され、「人間の足跡をたどる会」から出版されている。
増山さんがシャッターを切った❝エモい❞写真は、今も私達を魅了する
増山さんの写真で、「雪の中のひまわり」という作品がある。
離村した増山さんがその冬、徳山村に戻ってきた時、あり得ない自然現象が起こっていた。
真っ白な雪の中に真夏の花・ヒマワリが咲いていたのだ。
「ヒマワリの花は増山さんが来るのを待っていてくれた。
『よう待っててくれた』と、増山さんは万感の思いを胸にシャッターを切ったんです」
自らも地元のアマチュア写真団体「写団望(のぞみ)」の代表を務める野部さんは、増山さんがなぜそこでシャッターを切ったかということに意味があるという。
最初は村の記録を残さなければという使命感にかられ、あらゆるものにカメラを向けていた増山さんだが、回数を重ねるにつれ、少しずつ変化が見られた。
自分の中にある感情をオーバーラップさせて写真を撮るようになったのだ。
現代風にいうなら❝エモい❞写真である。
写真を撮ることでその被写体だけでなく、当時の感情までがよみがえる。
だからこそ、増山さんの❝エモい❞写真は、今も私達の心の琴線を震わせるのかもしれない。
徳山村はダムの底に姿を消した。
しかし、増山さんが遺した写真によって、私たちは村人たちがどんな思いでそこに暮らし、厳しい自然を時には楽しみながら、生き抜いてきたかを知ることができる。


【取材・写真提供】
野部博子さん 「増山たづ子の遺志を継ぐ館」代表
【参考文献】
『ふるさとの転居通知』増山たづ子 情報センター出版局
『ありがとう徳山村』増山たづ子写真集 影書房
『故郷』私の徳山村写真日記 増山たづ子 じゃこめてい出版












