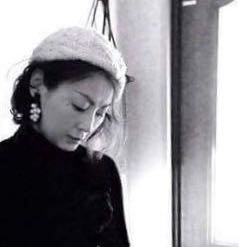1枚の紙と1本のハサミが生み出すシンプルな芸術
大正時代に、初代林家正楽師匠※1が始めた「寄席の紙切り」※2は、二代目、三代目と、3人の名跡を生みました。現在はその弟子含め、6人の紙切りが活躍しています。
今回は、その三代目正楽師匠※3の一番弟子である林家楽一(はやしやらくいち)さんに、紙切り芸の面白さ、魅力を、伝統とは裏腹な?ロックなスピリッツで、語っていただきました!
―― あのスピードで、どこも切り落とさず、どんな絵が出来上がるのか全く想像がつかないのですが、どうやってハサミを入れていくのですか。
林家楽一(以後、楽一):紙には線など書かず、いわゆる一筆書きの要領で切っていくんです。それが一番早く絵が作れて、きれいにできるコツなんです。ハサミを動かすというより、ハサミは固定して、紙を動かして切っていく感じです。切り抜いた跡も一枚の絵になっているという、そこも見せ場となっています。
―― 本当、二つのタイプの絵を見せられると、マジックを見ているような不思議な気分になります。よく紙切りの方が体を揺らしているのは、ハサミを動かさないからなんですね。
楽一:そういう人もいますが、私は揺れません。たまに、客席からヤジで「揺れろ」とか言われるんですが、そういう時は「揺れてるのが好きな方は、ご自身で揺れてください」と言ったりしています(笑)。天邪鬼なので、言われると、絶対に揺らすもんかと、ジッとして切っています。
―― それが己のスタイルを貫く、楽一流でいいですね。楽一さんのお客さんとのやり取りは、見ていてなかなかシュールです(笑)。
楽一:そもそも芸なんて、人それぞれだし、こうでなきゃいけないってのはないんですよ。失敗しても、「失敗しちゃったんで、ちょっとやり直しますね」と言って、やり直せばいいんです。構えることなく、舞台にあがり、お客さんとの掛け合いを楽しみながら切っています。師匠に「こうやりなさい」って言われたこともないんですよ。絵の作り方、切り方は教えてもらいましたが、後は自由。師匠に言われたのは「紙切りは芸であり、サービスである。ただ上手に切るだけでなく、楽しませる工夫が必要」ということでした。ですので、私なりのやり方でお客さんを楽しませたいなと思っています。
―― わかります! そのゆる~いスタンスが、なんだかほっとさせてくれるんですよね。
公務員志望から寄席芸人・紙切りへ
―― 伝統芸能や演芸の世界の師匠と聞くと、頑固で怖いというイメージがありますが、三代目正楽師匠は、ご本人も饒舌ではないし、朴訥とした雰囲気の方でしたね。
楽一: 紙切りを習いたくて、師匠のところに伺った時、師匠は50代半ばだったんです。でも、世間でいう50代とは違って、全然偉そうじゃなくて。人柄というか、それが紙切りにも出ていて、軽妙洒脱で、シンプルながらも、どこかに温かみを感じさせてくれる。「こういう生き方も面白いな」「こういう人でも生きていける世界って素敵だな~」と思わせてくれたんです(笑)。だから私も20年以上、続けていられるんです。
―― そもそも家業でもない演芸の世界に足を踏み入れたきっかけはなんだったのですか。
楽一:兄の結婚式の余興を考えていた時、テレビで師匠の「紙切り」を見て「こんなに楽しい芸があるのか!」と思ったのがきっかけです。実際、兄の結婚式でやって、受けました。本来ハサミは結婚式には縁起悪いんですけど(笑)。
―― 確かに! 普通、切るはご法度ですね(笑)。それでそのまま弟子入りされたんですか?
楽一:いえ、そもそも家は、代々、消防士をしている公務員の家系だったんです。自分もそうなると思って、大学時代は、公務員試験を受けるための学校にも通っていました。だから趣味として習いに行っていたんです。それが、だんだん紙切りができるようになって、面白くなり、修行と称して、京都の宿坊に集中的に籠って、紙切りをやったこともありました。1日6~7時間、自分の部屋でひたすら、紙を切っているんです。隣では、大学生のグループが楽しそうにしていましたけど(笑)。私の場合、大学1年の頃から人生を諦めていたのかもしれません(笑)。友達もいなかったし、一人でいることが多かったり。
―― そんな大学時代だったんですね。自分がなんとなくイケていないと感じる時、どうやってメンタルを立て直していたんですか?
楽一:う~ん(しばし考えている)。最初は趣味で習いに行っていた紙切りが、どんどんできるようになって。そこには、試験もないし、何年でこれができるようにならないといけないという目標もない。カリキュラムもないし、人それぞれ、進度も違うから、自分のペースでできたのが良かったんですね。心の支えは、師匠に教えてもらった紙切りかな。それがうまくできると嬉しいし、毎日それだけを考えながらやっていました。
生活のためのアルバイトも気づけば紙を触る仕事
―― 紙切りだけで食べられない時代はどうしていたんですか。
楽一:郵便局でアルバイトをしていました。本業が紙切りで、アルバイトが公務員。一応、バイトですけど、公務員の仕事はできていたわけです(笑)。小さい郵便局だったので、5年間、郵便関係の仕事は、窓口から集荷まで何でもやりました。はがきや封筒も紙じゃないですか。だから、日々紙を触るということでは同じだなと思ってました。自慢は、封筒を持っただけで重さがわかるんです。師匠も本屋さんでアルバイトをしていまして、店長にまでなっていましたから。そこで女将さんとも出会って。本屋さんで働いているから、いろいろな本が読めるので、雑多な知識がすごくある方でした。それがまた寄席で生きたんですよね。
―― なんか良いお話ですね。最近はこうじゃなきゃダメという縛りが多すぎて疲れます。でも、一度も辞めたいというのもなかったのですか?
楽一:それがなかったんですね。毎日が楽しいし、寄席も楽しみ。紙切りって、最初に1枚披露して、その後は、客席からお題をいただいて切るわけです。即興でやるから、毎回、自分自身にチャレンジしているんです(笑)。そういうのが楽しいのかな~と。
―― 公務員を目指したところから、真逆の世界に進んだことでの不安はなかったんですか。
楽一:いや、不安は毎日ですし、今も不安です(笑)。親にも大反対されていましたし。ただ、これだけ長く続けられたことって、他にないんです。これしかできないってことなのかな~とも思います。定年もないですし、逆にお声がかからなかったら終わり。だからこの仕事なくなったら、その辺フラフラしているかも。その時は助けてください~(笑)。
―― いや、芸が身を助けるので大丈夫ですよ! 安定した仕事は、不安は少ないかもしれないけれど、毎日同じことの繰り返しになりがちで……。楽一さんのように、毎日、変化に富んでいる仕事っていうのはうらやましいですよ。
これぞ、神業!Web上紙切り体験
ここで寄席の雰囲気をWeb上で再現! まずは、定番の「相合傘」を切っていただきました。
これは、鈴木春信の浮世絵「雪中相合傘」※4に通じる抒情的な男女のシーンです。モノクロだからこそ引き立つ、哀愁や美が感じられます。
 続いては、編集者と私でお題を投げさせていただきました。まずは、季節ネタで「雛祭り」。
続いては、編集者と私でお題を投げさせていただきました。まずは、季節ネタで「雛祭り」。
正面からかと思いきや、横から見た雛飾りが斬新です! 「普段見る、雛飾りとはまた趣が違う~」と編集者が叫ぶと、「15段全部は切れませんから」とすかさずツッコミで返す楽一さん。こういうお客さんとのやり取りが、ライブの面白さといえます。次も季節に絡めて冬の華、「フィギュアスケートの浅田真央」。
モノクロの世界だからこそ、より、優雅な美しさが際立って見えますし、自分の想像するイメージを重ねて楽しめますね。
―― お題をいただく時に、やりにくいなというものはありますか。
楽一:最近は時世のゴシップネタなどが多いです。そういうのはやりにくいですね(苦笑)。漢字、苗字とかもあります。子どもさんからは、知らないキャラクターを言われるので、そういう時は、お客さんの持ち物を見せてもらって、それを見て切ります。いろいろ変わった注文も多いです。同じネタが続くことがあって、「パンダ」が3回続いた時には、「動物園で本物見てきてください」って言ったりしました(笑)。
自分と対峙する芸の磨き方
―― 練習時間というのは、どのくらいなんですか。
楽一:1日の練習時間というのはなくて、常に頭の中で切り方を考えているんです。街で目に入ってくる看板やポスター、自然の風景などを見て、形がどうなっているのか、どうやったらうまく切れるかを考えながら歩いています。だから、いつも頭の中はパンパンです。
―― そうやって、見えないところで、常に対象物と格闘しているんですね! 楽一さんの中で、好きなネタ、得意なネタはなんですか。
楽一:やはり師匠に稽古をつけてもらった伝統的なテーマが好きですね。「藤娘」のような歌舞伎の題材だったり、季節の行事だったり。長年にわたって、三代の師匠をはじめ、みんなが切ってきたものなので、だんだんと工夫が生まれ、完成された美しさがあり、一番、洗練されています。
―― 紙切りから歌舞伎や舞踊に興味が出る人もいるかもしれない。そういう日本文化の連鎖っていいな~と思います。楽一さんが思う紙切り芸の魅力ってなんでしょう。
楽一:紙切りの美しさって、余白というか、出来上がった絵に、自分の考える余地が残されているところだと思うんです。悲しい表情なのか、嬉しい表情なのか、どんな関係なのかとか、見る人によって見方が変わる。それが日本文化らしいなと。全部をひけらかさない。金屏風だって明るい照明の下で見たら、味わいもない。昔の薄暗い家屋の中で、ボーっと灯りが浮かびあがるように見えるから、幻想的というかね。今は、全部見せちゃうというか、裏までも見せすぎです。

インド人もビックリ!お客さんとのコミュニケーションが面白い
―― お客さんとの思い出のエピソードってありますか。
楽一:いろいろあるんですが、この間、おじさんがすっと立ち上がって、通路まで出て、こっちに近づいてくるんです。「え、何? やばい?」と思ったんですが、落ち着いて、「何か注文がありますか?」って聞いたら、「うちの妻が誕生日なので、妻の似顔絵でやってください」って。奥さんのために必死に訴えてきた。
―― 普段はそんなこと言わない年配の男性がそういうこと言えちゃうのも、寄席の和気あいあいとしたムードがあるからなんですね。海外などでも人気がありそうですが、そういう経験はありますか。
楽一:インドのゴアというところに日本企業の工場があって、そこで「ジャパンナイト」を開催するっていうので、余興で呼ばれたことがあったんです。インド洋の海岸の前にイベント会場があって、そこに舞台があるんですけど、私の出番の前にバンドが演奏しているんです。その人たちはゲストでもなくて、勝手に上がってバンド演奏をしていて、そんな場所だったんですね。紙切りに興味あるのかなと思ったんですけど、お題は、「富士山」とか普通の日本の有名なものが出てきました。それがだんだん「仏陀が瞑想しているところに、芸者がしなだれかかっているところ」とか言い出す人が出てきて。宗教を冒涜していいのか、と思いましたけど、一応作りました(笑)。すごく、喜ばれたし、ノリもすごかった。あとは、ペンダント持ってきて、奥さんの似顔絵で切ってくれと言われて、横顔のイメージで切ったら、感動して。それを見た人たちが、次々に並んじゃった。でも、全部同じ顔に見えちゃうんで、みんな同じ顔で作りました(笑)。
―― 楽一さんの話を聞いていると、何でもありだし、考えすぎず、人生も即興って感じで、面白いですね。悩みも吹き飛びそうです。
紙切りの様子は動画でもご覧ください
人生紆余曲折の楽一さんによるお悩み相談
―― 取材陣がすっかり楽一さんの思考回路にハマり、突如、お悩み相談タイムとなりました。 ―― 老後の資金が2000万円とか言われる時代に、お金持ちになるには、どうすれば良いでしょうか。
―― 老後の資金が2000万円とか言われる時代に、お金持ちになるには、どうすれば良いでしょうか。
楽一:お金持ちになんてならない方がいいです。だって、お金持ちになると、目つきがやばくなる。
(一同大爆笑) 一刀両断ですね。確かに、最近の話題の人たちを見ると考えさせられます。続いては30代の編集者のお悩み。
―― これからおばさんになっていくと思うと、どうしようと不安になります。
楽一:「おばさんだから」って、言っちゃったほうが気が楽になります。何でも、「おばさんだから」で済ませちゃう。そういうのを嫌う人がいますけど、こっちからしたら「勝手に言わせろって」感じですよ。言うか、言わないかは、本人の勝手! そうやって開き直った方が楽に生きられます。
―― 50代のカメラマンなんですが、これからの進路に悩んでいて。
楽一:ガラッと人生変えた方がいいです。もう辞めてもいいじゃない。やり切ったんだから、次のステージに行きましょう。その後は、失敗も成功もないんです。
―― 迷解答、いや、名解答に、全員すっきり! 楽一さんは、受け継がれていく芸を背負っているという意識はありますか?
楽一:ないです。ただ紙切ってるだけですから(笑)。寄席は、伝統芸能というより、大衆芸能だと思っています。ありがたがるのは違うな、と。寄席って、日本の風土そのものって感じがするんです。昔は、お風呂からあがって、浴衣を着て、フラッとに行ける場所だったわけだし。今も、そうやって気負わずにフラッと来てほしい。寄席に来るお客さんは、何気なく、一人で来て、一人で座っていて。おじさんたちが少しずつずれながら、一人ずつ座っているのを舞台から見ると、きれいにズレたおじさんたちの顔が全員見られて面白いです。ぜひ、気楽に遊びに来て下さい。こんなおやじたちがいると、気持ちが楽になるかもしれません(笑)。
取材を終えて
この企画を出した時、私自身、人間関係とか、ITの進化とか世の中の不安とか、すごく疲れてしまっていたんです。そんな時、空いた時間にフラッと寄席に入って、紙切り芸を見ていたら、全身からふわっと力が抜けました。楽一さん曰く、紙切りは落語と落語の合間にリラックスしながら、耳を休める時間だそうです。コスパもタイパも行き過ぎると、人間らしさがどんどん失われていく気がします。のんびり、ゆったり、人間らしさが寄席には溢れていました。バカバカしい笑いや息抜きを求めて、いざ寄席へ!
写真/篠原宏明
林家楽一 (はやしや らくいち)
神奈川県横浜市鶴見区出身、昭和55(1980) 生まれ。平成13(2001)年に三代目林家正楽に入門。平成18(2006)初高座、平成27(2015)落語協会に入会
公式ホームページ