一介の油売りから、美濃(みの、現、岐阜県)の国主にまで成り上がったとされる梟雄(きょうゆう)・斎藤道三(さいとうどうさん)。梟雄とは、下位の者が上位の者を倒す下剋上(げこくじょう)を平然と繰り返す、残忍かつ勇猛な者をいう。
しかし近年、道三の国盗(くにと)りは道三一人で行ったのではなく、油売りだった父・松波庄五郎(まつなみしょうごろう、庄九郎とも)が美濃守護土岐(とき)家の小守護代(こしゅごだい)・長井(ながい)家に仕官し、そこで立身出世したのち息子の道三があとを継いで、父子二代で国盗りを成し遂げたとする説が定着した(なお父の松波庄五郎こと長井新左衛門尉については、「斎藤道三は2人いた!? 親子で成した新説『国盗り物語』の記事をご参照ください)。
本記事では、父親のポジションを継承した道三が、いかにして国盗りを実現したのか、その足跡を追ってみよう。
天文2年美濃、国盗りの始まり
主君・長井長弘を討つ
天文2年(1533)、主家である長井の姓を拝領し、長井新左衛門尉(しんざえもんのじょう)と称していた松波庄五郎が逝去。そのあとを息子の道三が継いだ。主家の長井家は守護代(守護の補佐役)斎藤氏の家老を務める家柄で、亡き庄五郎は長井家当主・長弘(ながひろ)と常に行動を共にし、篤く信頼されていたという。庄五郎は、長弘に次ぐポジションであったようだ。当時、道三は長井新九郎規秀(しんくろうのりひで)と名乗っていたが、本記事では道三で統一したい。
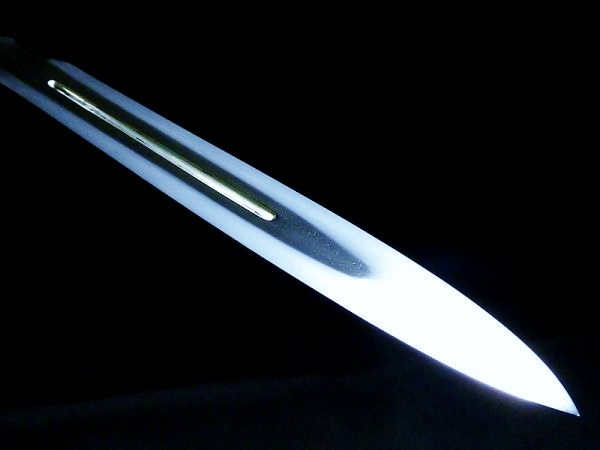
道三は明応3年(1494)、美濃の生まれといわれるので、この時、40歳(異説あり)。もちろん、庄五郎存命の頃からすでに長井長弘のもとに出仕し、土岐家の後継者争いでは、土岐頼芸(よりのり)方の中心人物の一人として、その兄・政頼(まさより、頼武とも)方と何度も戦い、頼芸の信任も得ていた。
大永6年(1526)、道三33歳の頃には、頼芸の愛妾(あいしょう)・深芳野(みよしの)を与えられているのもその証であろう。なお深芳野は翌年、男児を生む。これが道三の長男で、のちの斎藤義龍(よしたつ、高政)である(異説あり)。
さて、父・庄五郎が没した天文2年、主君の長井長弘も死去している。庄五郎の死の2ヵ月前で、なんと上意討ちであったという。一説に、長弘が越前に逃げた土岐政頼と内通しているかどで、土岐頼芸が庄五郎、または道三に長弘を討つよう命じたというのだ。しかし、長年政頼方と戦い、ようやく頼芸を守護に据(す)えた長弘が、今さら政頼に内通するだろうか。また、長弘に仕えてきた庄五郎が、大恩のある主君を討つのも考えにくい。まして当時、庄五郎は病床にある。それらを勘案すると、これは頼芸を操った道三による、上意討ちの体裁をとった長弘謀殺ではなかっただろうか。
長井氏の小守護代の座を奪う
長井長弘と庄五郎が相次いで没したことで、小守護代の地位は長弘の息子・景弘(かげひろ)が継ぎ、頼芸を支えた従来の長弘・庄五郎体制が、景弘・道三体制にスライドした。それを裏づけるのが、同年11月の景弘・道三の連署書状である。ところが翌年以降、書状の署名は道三のみとなり、景弘の名前は現れなくなる。僅か1年で景弘が隠居するとは考えにくく、失脚か、死亡したのか。道三による謀殺の可能性もあるが、正当な理由がなければ長井一族が黙っていないはずである。
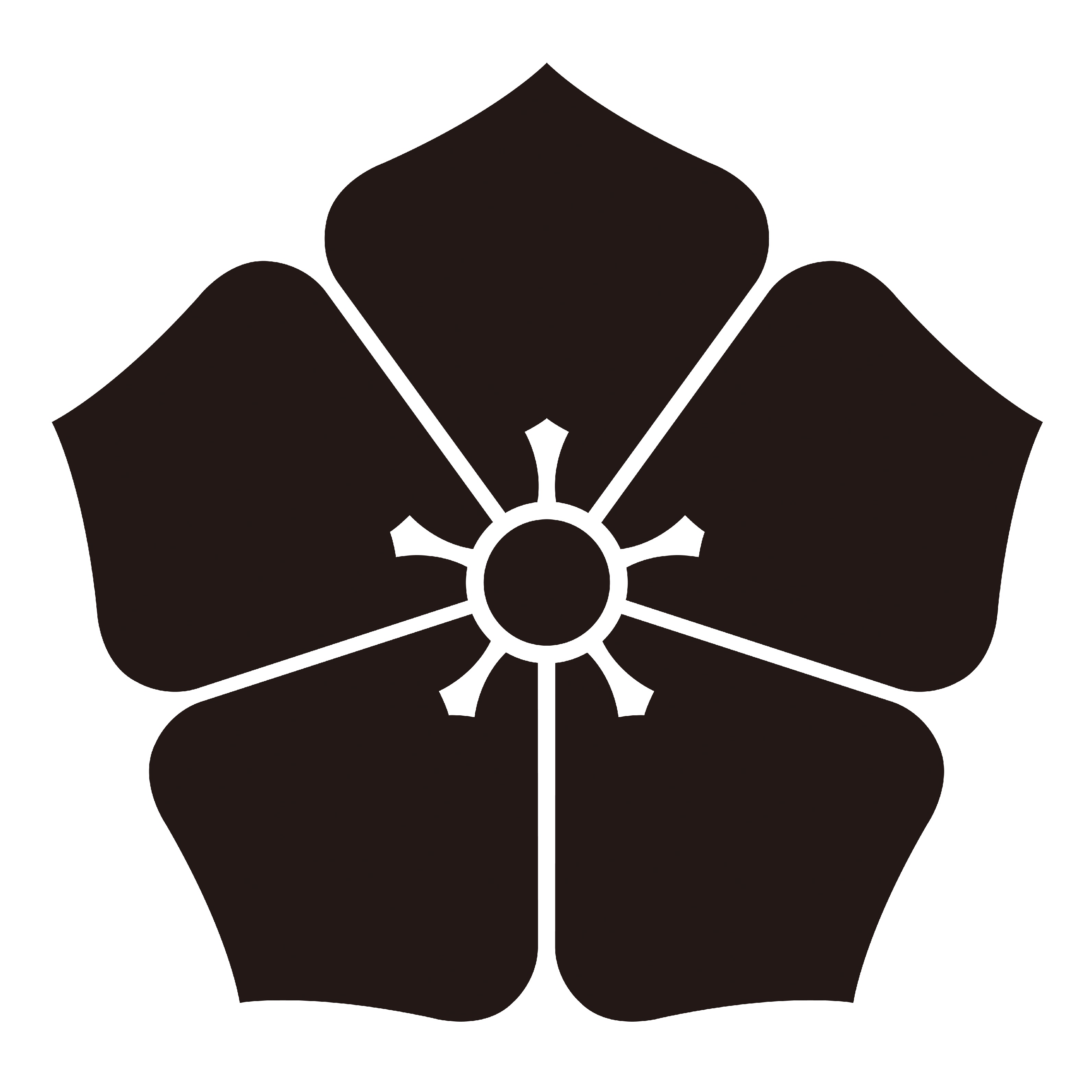 土岐氏の家紋・桔梗紋
土岐氏の家紋・桔梗紋
理由は不明ながら、景弘が不在となったことで、道三は小守護代の座につくことになった。早くも父・庄五郎を超えたわけで、そこには道三を頼りにする土岐頼芸の意向も強く働いていたのだろう。
美濃奪回を目指す土岐政頼
天文4年(1535)4月、土岐頼芸は亡父政房の法事を居館の枝広(えだひろ)館で執り行い、自分が後継者であることを内外にアピールした。それを補佐したのは道三である。その2ヵ月後、美濃で大洪水が起こり、川に近い枝広館は流されてしまう。頼芸は道三に助けを求め、道三が居城としていた稲葉山城内に転がり込んだ。頼芸が何かにつけて、道三を頼りにしていたことがうかがえる。
 大桑城跡
大桑城跡
一方、頼芸の兄・政頼は、まだ美濃奪回をあきらめてはいなかった。美濃の北には頼芸が守護となることをよしとしない勢力も根強く、政頼はその支援を受けて、美濃北方の大桑(おおが)城(岐阜県山県市)に入る。そして同年8月、政頼は攻勢に出て、頼芸・道三軍と衝突。越前(現、福井県)の朝倉(あさくら)氏、近江(現、滋賀県)の六角(ろっかく)氏も政頼に協力したため、戦いは翌年にまでもつれ込む大乱となった。道三の台頭を危険視する者も、少なくなかったのだろう。
守護代の同名衆・斎藤新九郎利政の誕生
その混乱の最中、道三は守護代斎藤氏の同名衆(どうみょうしゅう)となり、斎藤新九郎利政(しんくろうとしまさ)と名乗りを改めた。つまり小守護代長井氏が仕える守護代斎藤氏の一族となったわけで、混乱に乗じ、巧みに長井氏の格上に立ち、かたちの上では長井一族を指揮できる立場となったのである。
天文5年には道三がかつぐ土岐頼芸が正式に美濃守護となり、結果的に土岐政頼の美濃奪回はならなかった。しかし、その勢力は侮れず、美濃の大桑城に留まることは道三らも認めざるを得なかった。なお一説に、この時、政頼はすでに没しており、大乱を起こしたのは政頼ではなく、13歳の息子頼純(よりずみ、頼充とも)だったという見方もある(他に政頼の別名が頼純とする説もある。当時の美濃の人物については、良質な同時代史料が少ないこともあり、不明瞭な点が多い)。
軍事力を生むための経済力
美濃のマムシ
ところで、斎藤道三の異名(いみょう)が「美濃のマムシ」であることは、よく知られる。マムシはいうまでもなく毒蛇であり、その毒はハブよりも強く、咬まれれば大人でも命を落とすことがある。そんな怖ろしさから、マムシという異名をつけられる者は、粗暴で陰険な性格であることが多いようだ。道三が、周囲にどう思われていたかがうかがえる。また、マムシは獲物を咬んで、毒で身動きを封じてから、ゆっくりと丸呑みする。その様子が、美濃一国を丸呑みしようとしている道三とよく似ているのかもしれない。
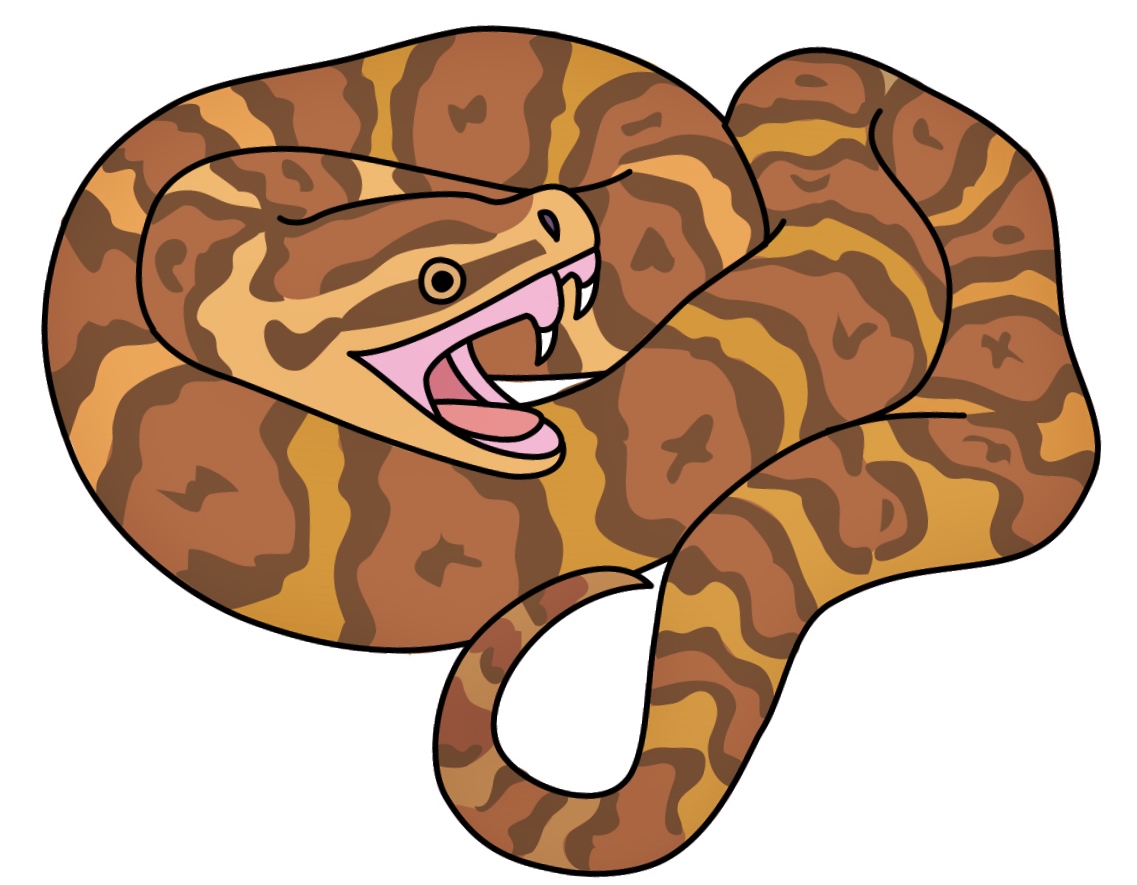
とはいえマムシとあだ名され、政治的謀略に明け暮れる人物のもとに、人は寄りつかないだろう。まして道三は、父の代に美濃に来た新参者である。代々の家臣がいるわけでもない。そうした美濃の人々の感情の機微を、道三自身もよく承知していた。そこで、町づくりを始める。
稲葉山城下を商業都市に
まず金華山(きんかざん)の山頂にある稲葉山城と、山麓の居館を整備するため、天文8年(1539)、山麓の丸山にあった伊奈波(いなば)神社を井口洞(いのくちほら、現、岐阜市伊奈波通り)に移転。稲葉山城の備えを強化するとともに、城下町の七曲通(ななまがりどおり、現、岐阜市本町周辺)に井口村の百姓に町屋を作らせ、百曲道(ひゃくまがりみち、現、上大久和町周辺)には大桑から町人を移住させて、新たに町を設けた。
 稲葉山城跡から城下を望む
稲葉山城跡から城下を望む
稲葉山城の麓(ふもと)には、土岐頼芸の守護所も構えられる。そして町全体を堀と土塁で囲み、防衛力を強化した。「惣構(そうがま)え」である。商人や職人が戦火を恐れずに商売ができるようにしたわけで、さらに道三は楽市楽座(らくいちらくざ)を宣言し、稲葉山城下での自由な商取引を認めた。これは織田信長に先駆ける画期的なもので、噂を聞いて諸国から商人が集まり、井口は美濃きっての商業都市になっていく。市場が賑わえば、当然ながら城主の道三の懐もうるおうことになった。
経済的に余裕が生まれれば、自ら兵を養うことができる。当時、傭兵(ようへい)を集めることは容易であり、良い条件を示せば、美濃の国侍たちも在所とは別に、稲葉山城下の井口にも館を持ち始める。自然、彼らは守護代の同名衆である、稲葉山城主の道三の指揮をあおぐことになった。つまり経済力は、軍事力に直結するのである。こうした商業的な感覚は、亡き父・庄五郎から受け継いだものであったかもしれない。また、この頃から道三は、斎藤左近大夫(さこんのたゆう)利政と名乗っている。天文10年(1541)頃からは、守護代家の没落をうけ、実質的な守護代として振る舞っていたようだ。
織田・朝倉軍を撃退した道三の強さ
尾張の織田信秀
天文12年(1543)の末頃、道三は土岐頼芸の同意を得て挙兵、大桑城に拠る土岐頼純(亡兄・政頼の子)を攻めた。道三軍の前に頼純はひとたまりもなく、越前へと逃げる。しかし頼純は反撃を画策(かくさく)し、越前の朝倉氏と、尾張(現、愛知県西部)の織田(おだ)氏に支援を要請した。一方、道三方には、近江の六角氏、浅井(あざい)氏が味方することを約束している。
 織田信秀像
織田信秀像
織田家の軍勢を率いるのは、織田信秀(のぶひで)であった。信長の父親である。尾張の守護は斯波(しば)氏だが、美濃同様、尾張でも守護は力を失い、守護代の織田氏が、伊勢守(いせのかみ)家と大和守(やまとのかみ)家の二家に分かれて対立していた。信秀は清洲(きよす)城を本拠とする、織田大和守の3人の家老の一人に過ぎない。それが大和守家や守護の斯波家を凌(しの)ぎ、尾張半国を従えて、美濃の道三や、駿河(現、静岡県)の今川義元(いまがわよしもと)ら強豪と争うほどの力を持つに至っているのだから、彼もまた下剋上の申し子、梟雄(きょうゆう)というべきだろう。
加納口の戦い
越前の朝倉孝景(たかかげ)は織田信秀と連携し、天文13年(1544)8月に美濃へと南下を開始。土岐頼純も同陣していただろう。これに対し道三は、近江の六角、浅井らに朝倉勢への牽制(けんせい)を頼むが、9月19日、美濃赤坂で頼純方の徳山次郎右衛門(とくのやまじろうえもん)と戦って、敗北。赤坂周辺の城を明け渡して、稲葉山城へと撤退した。これに勢いづいた織田信秀は、一気に道三の稲葉山城下へと攻め寄せる。

9月22日、惣構えに守られた井口を破ろうと、織田軍は村々を焼き払い、町の入口をこじ開けようとした。その間、道三方は防戦するのに精一杯の様子である。敵を軽く見た織田軍は、日没となったので兵を引き上げ始めた。道三が攻勢に転じたのは、この時である。城門を開くや、織田軍の背後から美濃の軍勢が怒濤のように襲いかかった。油断していた織田軍はたちまち切り崩され、大損害を出し、信秀は弟や家老を失いながら、少数で居城の古渡(ふるわたり)城に逃げ帰ったという。織田軍の大敗に、南下中だった土岐頼純と朝倉勢は形勢不利と見て、越前に引き返す。これが加納口(かのうぐち)の戦いと呼ばれるもので、道三の鮮やかな勝利であった。一説に19日の赤坂の敗北も道三の計略で、敵を城下におびき寄せるための作戦だったという。なお加納口の戦いは天文13年説と16年説があり、本記事は前者で記したが、大河ドラマ「麒麟がくる」は後者を採っている。
国盗りへの布石
『信長公記』が記す暗殺劇
その後も道三と土岐頼純方との小競り合いは続いたが、朝倉孝景が京都の幕府に働きかけて、天文15年(1546)、ようやく講和することになった。講和の条件として、頼純を次期守護とすることがとり決められた可能性があり、また道三の娘・帰蝶(きちょう)が頼純に嫁いだという。これで、ようやく美濃国内の対立の火種は消えたかに思われたが、道三に、そのつもりはなかったようだ。

『信長公記』に、次のような記述がある。
「土岐殿(頼芸)のご子息に次郎殿、八郎殿というご兄弟があった。新九郎(道三)はかたじけなくも、その次郎殿を婿とし、ご機嫌をとり結び、すきを見て毒を盛って殺害。また、自分の娘を『蓆(むしろ)直し(後妻の意)になさい』と、無理やり八郎殿に進上したのである。道三みずからは稲葉山城に住み、八郎殿をその山下に住まわせて、三日か五日に一度は参上し、『お鷹狩りに出かけてはいけません。馬に乗るなどとんでもないこと』と、籠の鳥のように遇された。そこで八郎殿は雨の夜に、馬で尾張を目指そうとしたところ、追いかけて腹を切らせてしまった」
出家して道三と称する
頼芸の子息次郎とあるが、これは頼芸の兄・土岐政頼の子息次郎、つまり頼純である。『信長公記』は、道三が娘婿で24歳の頼純を毒殺したと記す。次期守護の存在を抹殺したのだ。また頼純に嫁いでいた帰蝶を、八郎の後妻にしたという。八郎は頼芸の子ではなく、弟の頼香(よりたか)を指すと考えられ、彼は確かに切腹したというが、天文13年のこととされるので時期が異なる。帰蝶が頼純に嫁ぐ前に、すでに頼香は死んでいるのだ。『信長公記』の記述がどこまで信用できるかは不明だが、六角承禎が記した条書にも同様の記述があるので、当時、こうした話が諸国に伝わっていたのだろう。いずれにせよ天文16年(1547)、道三は守護候補の土岐頼純を殺し、国盗りの布石を打った。その直後、出家して斎藤左近大夫道三と名乗るのは、寝覚めの悪さがあったからだろうか。
織田家との婚儀
織田信秀の再侵攻と道三の戦略
翌天文17年(1548)8月、再び織田信秀が美濃に侵攻。4年前の屈辱を晴らすべく、一隊を大垣城に向かわせ、本隊は大野郡(現、揖斐〈いび〉郡大野町)に攻め込んだ。道三は国衆(地域領主)らとともにこれを迎撃するが、11月25日の饗庭(あえば)合戦で敗北。勢いづいた信秀は、谷汲(たにぐみ)の牧野でも道三方を破って、長瀬城を落とした。信秀の強さにさすがの道三も舌を巻くが、抜かりなく手を打っている。すなわち信秀を快く思っていない尾張守護代をそそのかし、信秀の留守城を攻めさせたのだ。これには信秀も大いに驚き、道三方に連戦連勝していながら、尾張へ引き上げざるを得なくなる。道三の戦略が、一枚上手であったということだろう。
 帰蝶像
帰蝶像
信長と帰蝶の縁談
そんな矢先、尾張から思わぬ話が舞い込む。信秀の老臣平手政秀(ひらてまさひで)が、信秀の息子・三郎信長と道三の娘・帰蝶との縁談を持ちかけたのだ。これには織田信秀の切実な事情がある。東海一の弓取りと呼ばれる駿河の今川義元の尾張への圧力が強まり、万一、今川が道三と結ぶようなことがあれば、信秀はひねり潰される。そこで先手を打って道三と結び、まず尾張国内の対抗勢力の一掃を図ろうとしたのだ。一方の道三も、これから進めようとする国盗りにあたり、反道三勢力が信秀と結ぶようなことがあれば、いささか面倒になる。信長と帰蝶の縁談は、両者にとってメリットのある話だった。かくして天文18年(1549)春、帰蝶は信長に輿入(こしい)れするのである。
国盗り、ついに成る
守護土岐頼芸の追放
帰蝶の輿入れにより織田家との和議も整い、美濃と尾張の間は平穏になった。信秀の支援で反道三の姿勢をとっていた者たちも、討たれるか帰順するかで美濃国内も整理されていく。この頃から道三は、斎藤山城守(やましろのかみ)と称していたようだ。そして、そろそろ頃合いと見たのか、道三は天文19年(1550)末、国盗りの仕上げにかかる。美濃守護土岐頼芸の追放であった。
 鷹
鷹
この頃、頼芸は、亡き兄や甥がいた大桑城にいたとも、別の美濃北方の城にいたともいう。政治の中枢からは外れており、鷹の絵を描いて日々を送る生活だったらしい。道三によって、身内が殺されたことに心中穏やかでない部分もあったろうが、一方で道三を頼る気持ちもあったのかもしれない。放っておいても害のない存在であったように思えるが、道三は追放に踏み切った。やはり「国主」の座を求めたのだろうか。稲葉山城下には何者かによって、次の落首が掲げられたという。
主をきり 婿をころすは 身のおはり むかしはおさだ いまは山しろ
(主君を斬り殺し、婿を毒殺するのは道に外れた行いであり、身の破滅である。昔でいえば主君の源義朝〈みなもとのよしとも〉を討った長田忠致〈おさだただむね〉、今でいえば斎藤山城がそれだ)
いずれにせよ守護頼芸を国外に追放した道三は、天文19年末には美濃国主となり、美濃の全権を掌握したのである。時に道三、58歳。下剋上、ここに極まれり、というところだろうか。
下剋上は悪なのか
美濃を追われた土岐頼芸は、妹の嫁ぎ先である近江の六角氏を頼った。頼芸に対する道三の仕打ちについては、「暴虐の臣によって国を奪われ、太守は江州に牢籠せり」と批判する同時代史料がある一方、道三と和議を結んだ織田家の反応は異なる。当時の織田家の外交を担当していた織田寛近(ひろちか)は、頼芸の息子・小次郎頼次(よりつぐ)への手紙で「土岐殿のこの度の追放はやむを得ないことで、あなたの身の上は問題ないと山城守殿は言っている」と、伝えているのだ。下剋上を肯定しているわけではないが、現状では仕方のないことだと言い含めているのである。
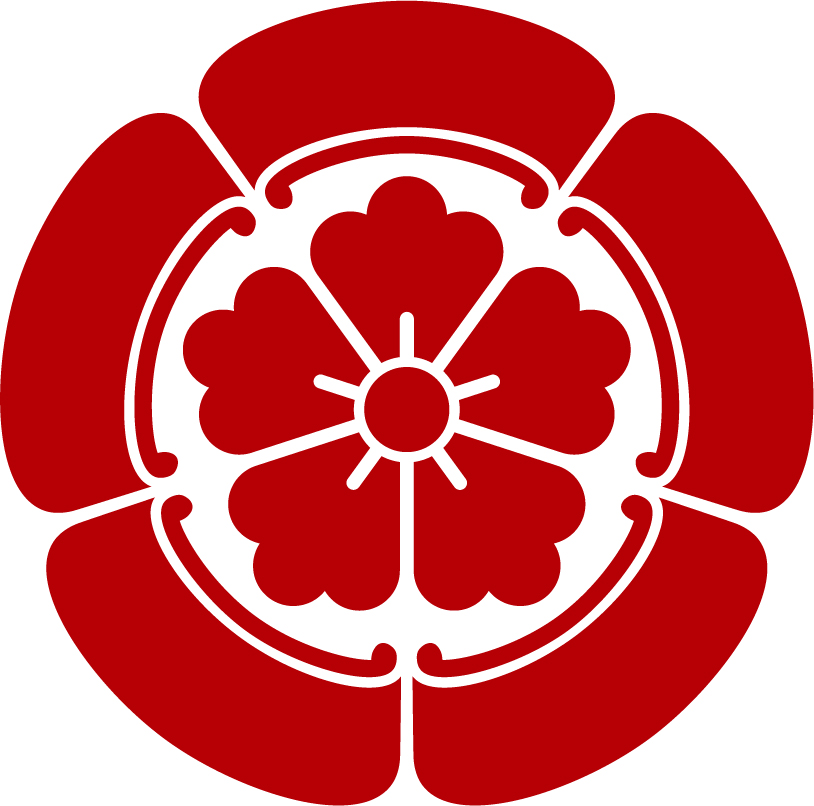 織田家家紋の「五つ木瓜(もっこう)」
織田家家紋の「五つ木瓜(もっこう)」
実際、尾張でもこの4年後に、守護の斯波義統(しばよしむね)が小守護代に討たれる事件が起きる。そうした下剋上がいつ起きてもおかしくない状況であり、むしろ油断する方が悪いということかもしれない。当の織田信秀も主君を討つことはしていないものの、他の守護代や奉行たちと争い、勢力は守護や守護代を上回っていた。実力のある者が力を発揮しなければ、たちまち他国に呑み込まれる時代なのである。もちろん美濃も同じで、もし道三がいなければ、越前の朝倉や近江の六角、浅井、あるいは尾張の織田信秀に蚕食(さんしょく)され、最終的には奪われていたかもしれない。
ところが尾張では、その信秀が病に倒れ、天文21年(1552)に42歳の若さで世を去った。あとを継いだのは道三の娘婿、信長である。
織田信長との出会い
尾張の大うつけ
道三と信長といえば、有名なのが聖徳(正徳、しょうとく)寺の会見であろう。信長の父・信秀が逝去した翌年の天文22年(1553)、道三は娘婿の信長と対面することを望んだ。あの信秀が選んだ後継者である一方、他国にまで伝わっているのは「大うつけ(大馬鹿者)」という噂である。道三とすれば信長の器量をその目で確かめ、噂通りならば尾張を奪うことも辞さない腹積もりであったという。
会見場所は濃尾国境の富田(とんだ)村聖徳寺(現、一宮市)。『信長公記』によると、道三は会見前に、信長の行列を小屋の中からひそかに見物した。馬上の信長は、髪は茶筅(ちゃせん)に結い、萌黄(もえぎ)色(黄緑色)の平打ち紐(ひも)で髻(もとどり)を巻いていた。湯かたびらの片袖を外し、虎と豹の皮を四色に染めた半袴を着けている。腰の太刀と脇差の鞘(さや)は金銀ののし付きで、長い柄(つか)にはわら縄を巻いていた。太い麻縄を腕輪にし、腰には火打ち袋と、ひょうたんを7つも8つも付けている。うつけと呼ぶにふさわしい、大いに傾(かぶ)いた風体(ふうてい)といえるだろう。

しかし道三の目を奪ったのは、それだけではない。信長が率いる槍隊の槍が、異様に長いのである。また鉄砲の数もおびただしい。『信長公記』の500挺は誇張だとしても、相当な数を揃えていた。
門前に馬をつなぐ
対面の場で、道三はさらに驚かされる。先ほどの風体とは打って代わり、髪を折髷(おりまげ)に結い直し、褐色の長袴を着け、美しい小刀を差した折り目正しい姿で信長が現れたからである。対面場所の縁側の柱にもたれて座った信長は、道三が現れても知らん顔で、たまりかねた側近が「こちらが山城守でござる」と声をかけると、初めて「であるか」と声を発し、対面の儀に臨んだという。
対面は短時間で済み、道三は「またお目にかかりましょう」と言って散会となった。帰途についた道三の表情は、終始苦々しげであったという。家臣が「上総介(かずさのすけ、信長のこと)は、やはりたわけでありましたな」と言うと、道三は「口惜しいが、わしの子らは、あのたわけの門前に馬をつなぐ(家臣になる)ことだろうよ」と答えた。道三は、信長が只者でないことを見抜いていたのである。

信長もまた、父・信秀が勝てなかった道三に対し、畏敬の念に近いものを抱いていた。また利害が一致している限り、道三は協力するとも信長は読んでいたらしい。
対面翌年の天文23年(1554)1月、信長は今川方が尾張に築いた村木砦(むらきとりで)を攻めるにあたり、居城の那古野(なごや)城の留守を道三に頼んでいる。周辺には同族が多くいるにもかかわらず、わざわざ美濃に援兵を頼むのも奇妙だが、実は同族に頼む方がよほど危険で、特に清洲城の守護代・織田信友(のぶとも)などは、城を奪おうと虎視眈々(こしたんたん)と隙をうかがっていた。その点、道三は、娘婿の信長が勢力を拡大する方が、諸事都合がよい。道三が派遣した1,000の兵に那古野城を預けた信長は、鉄砲を活用し、1日で村木砦を攻略。同時に信長のバックには美濃勢がいることを、尾張の同族たちに見せつけたのである。帰国した将兵から信長の鮮やかな手腕を聞いた道三は、「凄まじき男だ。隣にいやな奴がいるものよ」ともらしたという。
マムシの後継者
道三の息子たち
隣国尾張の信長が、21歳にして大器の片りんを見せ始める中、62歳の道三も後継者を考えなくてはならなかった。そして信長の村木砦の戦いから2ヵ月後、隠居して家督を28歳の長男義龍(高政)に譲った。義龍は正室小見(おみ)の方との子ではなく、土岐頼芸の愛妾だった側室深芳野(みよしの)との子で、庶子である(異説あり)。長男の庶子よりも、正室が生んだ弟を優先して家督を継がせる例は、当時、いくらでもあった。そうした中で、道三はなぜ義龍を後継者としたのだろう。
道三には義龍の他、孫四郎(まごしろう)、喜平次(きへいじ)、利堯(としたか)、利治(としはる)の計5人の男子がいた(他に僧籍の者が2人)。また一説に、道三の弟とされる長井道利(ながいみちとし)は、実は義龍よりも早く生まれた庶子であるともいう。義龍と長井道利を除く、残る4人が小見の方の子なのか、深芳野の子なのかは、実はよくわからない。ただ、義龍には異説もある。父親は道三ではなく、守護土岐頼芸である、というものだ。
義龍は土岐頼芸の子なのか
土岐頼芸が道三に深芳野を与えた際、すでに彼女が頼芸の子を懐妊していて、それが義龍であったという説はよく知られている。しかし、そのことを裏づける同時代史料はなく、義龍が頼芸の子であったとする史料はいずれも江戸時代のものであるため、一般的には史実ではないとされている。

ただ想像するに、道三はそうした噂を逆手にとって利用しようとしたのではないだろうか。道三の後継者が実は美濃守護の落胤(らくいん)であれば、反道三勢力も納得して従うだろう。道三は義龍を前面に立てることで美濃の人心を掌握する一方、背後で実権を握り続けるつもりではなかったか。その裏づけとして、義龍に家督を譲った以後も道三が指示を出し、義龍が追認している書状が見られるという。義龍にすれば父親の傀儡(かいらい)になっているようなもので、面白くないだろうし、庶子であるだけに、いずれ廃嫡されて弟が家督を継ぐのではと、疑心暗鬼にかられたかもしれない。
稀代の梟雄の最期
反道三勢力の結集
弘治元年(1555)12月頃、義龍は名を范可(はんか)と改めた。范可とは、唐(とう)の時代にやむを得ず父親を討った者の名前であり、いわば義龍の道三への宣戦布告であったろう。『信長公記』によるとその直前の11月23日、義龍は病気と偽って、道三が可愛がる孫四郎、喜平次の二人の弟を稲葉山城に呼び出し、城内で斬り殺したという。かねてより道三は義龍を愚か者と呼び、二人の弟を溺愛していたというのだが、土岐家の後継者争いが混乱を招いたことをよく知る道三が、果たして同じ轍(てつ)を踏むだろうか。なお『黄耈雑録(おうこうざつろく)』は、討手は日根野備中守弘就(ひねのびっちゅうのかみひろなり)だったと記す。
 稲葉山城跡(現、岐阜城跡)
稲葉山城跡(現、岐阜城跡)
また『岐阜軍記』は、道三の弟(庶子ともいう)の長井道利が、「君が旗上げのときは、斎藤、長井一族がこぞって馳せ参じ、道三と戦うつもりである」と義龍を激励したという。土岐家の血を引くと噂される義龍と道三の対立は、反道三勢力にとっては願ってもないことで、義龍を旗頭にして結集し始めたのである。さすがの道三もこの事態には慌て、隠居城にしていた鷺山(さぎやま)城を離れて、いったん北方の大桑城へと逃れた。
美濃一国譲り状
年が明けて弘治2年(1556)4月18日、織田信長とも連絡を取った道三は、義龍方を破るため挙兵。城田寺(きたいじ)山の東の天嶮(てんけん)、鶴山に布陣した。その数、およそ2,700。また舅(しゅうと)の道三を支援すべく、信長も美濃の大良(おおら、現、羽島市)へ進軍する。一方、稲葉山城下に集結した義龍軍は1万7,500。戦う前から勝敗は見えている。が、道三は逃げなかった。
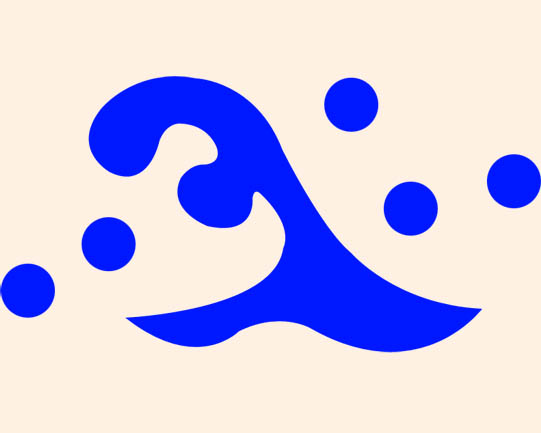 二頭波紋。道三が作った紋で、戦術の極意を寄せては引く波で表現したともいう
二頭波紋。道三が作った紋で、戦術の極意を寄せては引く波で表現したともいう
4月19日、道三は陣中で「美濃一国譲り状」をしたため、一通を信長に、もう一通を京都の妙覚寺に入る息子に送ったという。「美濃は信長にまかせる」という内容で、遺言状といってもいいだろう。書状の真偽については議論が続いているが、わが物とした美濃の将来を、いっそ息子たち以上の大器と認めた信長に託そうという道三の心情は、わかるような気もする。
長良川の戦い
20日、義龍軍が長良川南岸に進むと、道三はあえて鶴山の天嶮を捨て、長良川北岸に進んだ。道三にとってもはや勝敗は問題ではなく、国盗りにささげた生涯の幕をどのように下ろすかが、最大の関心事だったのではないか。
戦いが始まり、義龍軍の先手が猛然と攻めかかるが、道三の指揮は冴え、先手の軍勢を壊滅させて大将を見事に討ち取る。圧倒的な兵力差がありながら、序盤は道三軍が優勢だった。道三が戦巧者であったのは、間違いないだろう。
 長良川
長良川
しかし乱戦になると数の差はいかんともし難く、ついに道三本陣にも敵がなだれ込む。長井道勝(みちかつ、道利の息子)が道三を生け捕りにしようと組みついたところを、小牧源太(こまきげんた)が横槍を入れ、道三の脛(すね)を薙(な)ぎ、倒れたところで首を打った。生け捕りにしようとしていた長井はこれに激怒し、自分が真っ先に組みついた証として、道三の鼻を削(そ)いだという。道三、享年63。
一方、信長は大良河原で義龍軍と戦うが、道三討死の報せが届くと、信長自ら殿軍(しんがり)を務め、鉄砲で義龍軍の追撃をさえぎりながら、尾張へと引き上げた。信長が、道三より譲られた美濃をその手にするのは、これより11年後のことである。
信長に先駆けた「時代の申し子」
道三が生きた時代の価値観
道三の生涯を、推測もまじえながら追ってみた。美濃の国盗りは、旧来の秩序や価値観が崩れる乱世であったからこそチャンスが生まれ、成就したといえる。とはいえ身一つの庶民から大名にまで上り詰めた者は、いかに乱世でもめったにいない。その意味で松波庄五郎・斎藤道三父子は、稀有(けう)の存在といってもいい。
下剋上を繰り返し、のし上がっていった者を梟雄と呼ぶのは、後世の価値観もまじっているのかもしれない。たとえば君臣の忠義を重んじる儒学が盛んであった江戸時代は、道三は悪逆非道の者として語られ、非業の死は因果応報とされた。そのイメージが定着し、道三イコール悪人として浸透していった部分があるだろう。しかし、歴史は後世の価値観をあてはめて評するものではない。
そして、庄五郎や道三が生きた時代の価値観は、また異なる。激変する時代の中で、求められたのは才能のある者であった。だからこそ出身にとらわれず、実力があれば高みを望むことも許された。

道三と信長に共通するもの
庄五郎は長井氏の家臣として生涯を閉じたが、道三は父が築いた地盤を足掛かりに、己の才覚で長井氏、斎藤氏を膝下(しっか)に置き、土岐氏のものだった国主の座を奪って、大名となるのである。ただ、その上昇が急であったため、時に謀殺や暗殺といった手段も織り交ぜることがあり、少なからぬ反感を買って、美濃の人心を掌握するところまではいかなかったのも事実だろう。
実父に織田信秀、義父に斎藤道三を持った信長は、こうしたタイプの男を好んだように思える。いや、そもそも信長自身、同じタイプの男ではなかったろうか。のちに松永久秀が信長を何度か裏切っても、その都度、信長は許した。それは久秀に、信秀や道三と同じ匂いを感じていたからではないかとも想像できる。一世代あとの信長は、軍事、経済、文化など多くの面で(反面教師とした点も含めて)、彼らが生み出したものを吸収しながら、ついには天下人となった。
道三と信長に共通するのは、乱世だからこそ輝いた「時代の申し子」である点だろう。そして道三は、「信長に先駆けた男」とも呼べるかもしれない。皆さんはどうお感じになるだろうか。
参考文献:横山住雄『斎藤道三と義龍・龍興 戦国美濃の下克上』、桑田忠親『斎藤道三』、太田牛一『原本現代訳 信長公記(上)』、司馬遼太郎『国盗り物語』 他












