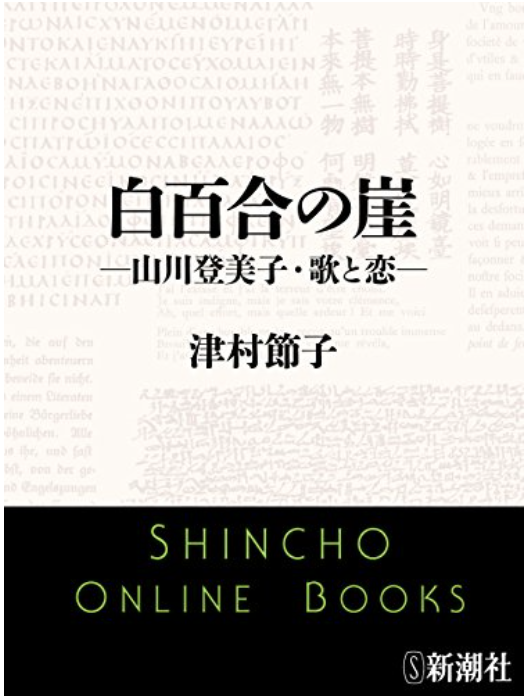「みだれ髪」や「君死にたまふことなかれ」など情熱的で華麗な歌で知られる天才歌人、与謝野晶子。彼女には、同じ男性を崇拝し、共に歌を詠み、「白萩」「白百合」と呼び合って青春を共にした親友がいました。山川登美子。与謝野晶子とならび、明治の文壇に一大センセーションを巻き起こした雑誌『明星』の歌人として、与謝野鉄幹に愛された女性です。
晶子が鉄幹の妻となり、名声を手に入れた一方で、登美子は不本意な結婚をし、夫の死により未亡人となり、さらに夫から感染した病のため、29歳の若さでこの世を去ることになります。
ライバルだった2人は、作風もまた対照的です。たとえば、同じ京都の祇園を舞台にして、2人はそれぞれこんな歌を詠んでいます。
清水へ祇園をよぎる桜月夜こよひ逢ふ人みなうつくしき(晶子)
木屋街は火(ほ)かげ祇園は花のかげ小雨に暮るゝ京やはらかき(登美子)
登美子の歌には、晶子のようなきらきらした総天然色の豪華さはありませんが、名人が描く水墨画のような、しっとりした魅力があります。
残酷な運命の波に翻弄される中で、皮肉なことに登美子の歌は深みと輝きを増していきました。限られた時間の中でひとつの頂点を迎えた山川登美子の「別れの美学」を、作品と共にご紹介していきましょう。
忘れられない「粟田山の一夜」

明治33(1900)年11月5日。
大阪のミッションスクール、梅花女学校(現在の梅花女子大)に研究生として通っていた21歳の山川登美子は、「お姉さま」と慕う1つ年上の鳳晶子(のちの与謝野晶子)、そして師と仰ぐ与謝野鉄幹と3人で、紅葉の京都、栗田山麓の永観寺に宿をとりました。
半年前に鉄幹が創刊した雑誌『明星』に自作の短歌が掲載され、社友となった登美子は、鉄幹に恋をしていました。小浜(福井県)の裕福な士族の家に生まれ、良家の子女として大切に、しかし籠の中の鳥のように育てられてきた登美子にとって、『明星』とその主宰者である鉄幹は、大空に羽ばたく自由を与えてくれる翼のような、まぶしい憧れの対象でした。
その情熱を隠すこともなく、登美子はこんな歌を『明星』7号に寄せています。
あたらしくひらきましたる歌の道に君が名よびて死なんとぞ思ふ
歌を詠む喜びとまっすぐな情熱が伝わってくる歌ですが、若々しい高揚感が少し気恥ずかしいような、くすぐったい気持ちになります。
登美子が花を添えて送った恋文に対し、鉄幹もまた、こんな思わせぶりな返歌で応じています。
やさぶみに添へたる紅のひと花も花と思はず唯君と思ふ
在原業平も真っ青!恋多き男、与謝野鉄幹
恋をしていたのは、登美子だけではありません。
晶子もまた、鉄幹に恋をしていました。どこか少女のような現実離れしたところのある登美子の歌に比べ、晶子の歌は直截的です。
かならずぞ別れの今の口つけの紅のかをりをいつまでも君
晶子のこの歌に対し、鉄幹の返歌がまた、一段と情熱的です。
京の紅は君にふさはず我が噛みし小指の血をばいざ口にせよ
「京都の口紅など君にはふさわしくない。私が噛んだ小指の血で唇を染めなさい」とはなかなか危険な香りのする歌いぶりですが、当時の鉄幹には林滝野という妻がいて、長男も生まれていました。滝野は、教師だった鉄幹の元教え子です。さらにいえば、鉄幹は以前にも、教え子の女性とスキャンダルを起こしています。
鉄幹は登美子、晶子とのやりとりを、『明星』誌上で赤裸々に公表しました。初期『明星』の発行兼編集人として名前を連ねていた妻の滝野は、一体どんな思いで夫と女性たちの贈答歌を読んだでしょうか。在原業平も真っ青なプレイボーイぶりですが、鉄幹には、プロデューサーとしての「思惑」があったと考えられます。
いつの世も、スキャンダラスな恋は人々の耳目を集めます。新しい歌のかたちをつくるという理想に燃えていた鉄幹には、自分に心を寄せる2人の才能あふれる歌人の気持ちを十分に知ったうえで、3者のやりとりをあえて公にすることで、『明星』を盛り立てたいという思惑があったでしょう。
和歌の世界では、平安貴族の時代から、時にドラマチックな歌を詠んで役割を演じ、場を盛り上げるという伝統がありました。当時27歳の鉄幹は、そのことも明確に意識していたはずです。
けれど、夢見る恋に酔っていた21歳の登美子に、鉄幹を取り巻く「大人の事情」に思いを馳せる余裕はありませんでした。敬愛する師と、親友と過ごす幸福な一夜は、登美子にとって、別れの夜でもあったからです。登美子は実家の父が決めた相手と結婚するため、郷里へ戻ることになっていました。
結婚すれば、これまでのように歌を詠んだり、鉄幹や晶子と会うことも叶わなくなるー
青春の夢と恋を同時に失うことになった登美子は、その夜、針で指を突いて血書をしたため、二度と会えなくても歌と共に生きていくと2人に誓いました。後に登美子は、『明星』8号にこんな歌を発表しています。
それとなく紅き花みな友にゆづりそむきて泣きて忘れ草つむ
紅く華やかな花は、みんなそれとなく友達に譲ってしまった。私は自分の心にそむき、泣きながらひっそりと忘れ草をつんでいる。
最初の別れー夫の死
切ない歌を残し、引き裂かれるような思いで郷里へ戻った登美子は、翌年に上京し、同郷の山川駐七郎と結婚します。
失意の中で新婚生活をスタートした登美子を、さらなる衝撃が待っていました。
『明星』11号に、晶子はこんな歌を載せていたのです。
みだれ髪を京の島田にかへし朝ふしてゐませの君ゆりおこす
乱れた髪を結い直し、眠っている恋人を揺り起こす朝。
あの粟田山の宿で、晶子が鉄幹と再会したのだと、登美子にはすぐに分かりました。紅い花はみんな友に譲った、と詠んだときには、どこか物語の中の悲恋に酔っている風情があった登美子が、生身の男女である鉄幹と晶子を明確に意識し、本当の意味で失恋したのは、もしかするとこのときだったかもしれません。

その年、歌集『みだれ髪』を刊行して一躍有名歌人となった晶子は、生家を捨てて鉄幹の元へ走り、妻滝野と離婚した鉄幹と夫婦になります。
一方、同じ年の暮れ、登美子の夫駐七郎が結核を発症。療養のため夫婦は伊豆に引っ越しをし、さらにふるさと小浜に移りますが、わずか1年ほどで駐七郎は逝去。夫の死を悼み、登美子はこんな歌を詠んでいます。
君は空にさらば磯回(いそわ)の潮とならむ月に干(ひ)て往ぬ道もあるべし
あなたは空に去ってしまった。月の満ち欠けは潮を招くという。私は磯の潮となってでも、あなたがいる月への道を探したい。
当初は本意ではなかった縁談。けれど夫婦として過ごした短い月日の中で、登美子の中には、たしかに駐七郎への情が芽生えていたのでしょう。「君は空にさらば」という歌い出しには力強ささえ感じられます。世間知らずのお嬢様だった登美子が、結婚、そして夫との死別を通じて急速に歌人としての幅を広げていることが、この挽歌から読み取れます。
同時に、一度は恋に破れ、筆を折って立ち去った『明星』に夫を悼む歌を投稿することで、歌人としての自分の立ち位置をもう一度確立しようとする登美子の姿が、行間に見えるような気がするのです。
感情の赴くままに歌うのではなく、自分の心を取り出して、手のひらにのせじっと観察したのち、静かに歌い出すような醒めたまなざしを、登美子は短い結婚生活を通じて手に入れたのではないでしょうか。
登美子の上京。そして晶子の嫉妬

夫の死後、登美子は教師として身を立てていくことを目指し、明治37(1904)年、上京して日本女子大学の英文科に入学。同時に『明星』での活動を再開しました。
かつては『明星』の花形歌人として並びたたえられ、「白百合の君」「白萩の君」と互いを呼び合って恋に夢中になった登美子と晶子の立場も、3年の間に大きく変化しています。
歌人として確固たる地位を築き、鉄幹との子を授かって、順風満帆に思える晶子ですが、文学がすべてに優先する暮らしは非常に貧しく、生まれた赤ん坊に新しい産着を作ることもままならない状態でした。
さらに晶子と結婚した後も、鉄幹は変わらず、社友の女性歌人たちとの恋歌のやりとりを誌上に掲載し続けました。
登美子もまた、鉄幹への思いを堂々と『明星』に寄せています。
歌やいのち涙やいのち力あるいたみを胸は秘めて悶えぬ
未亡人となって上京し、鉄幹の視界に現れるようになった登美子の思いに触れ、妻の座にある晶子も心中穏やかではなかったでしょう。鉄幹と登美子の間に特別な親交があったのかどうか、今となっては知るすべがありませんが、かつて林滝野が味わった猜疑と嫉妬の苦しみを、今度は晶子が味わうことになったのです。
晶子の中にこんこんと湧き、きらびやかな歌を生み出す源泉となっていた豊かな情熱は、嫉妬に姿を変えて彼女を苛みました。
生涯たった1冊の歌集が出版停止。大学を停学に
そんな折、鉄幹の発案で、与謝野晶子と山川登美子、そして同じく『明星』の歌人である増田雅子が、3人の連名で歌集を出すことになりました。
タイトルは『恋衣』。連名ではありますが、登美子の生前に出版された唯一の歌集です。
この歌集には、晶子の有名な詩「君死にたまふことなかれ」も収められました。戦地にいる弟を案じるこの作品は、体制に反旗を翻すものであるとして論争を巻き起こし、『恋衣』の出版は一時中止されることとなります。登美子と雅子も、通っていた日本女子大から停学処分を受けました。
登美子は一連の出来事への抗議の意を込めて、こんな歌を詠んでいます。
おとなしく母の膝よりならひ得し心ながらの歌といらへむ
幼いころ、母の膝に抱かれながらひとつひとつ教えてもらった「心からの歌」を詠むことに、何のやましいことがあるというのでしょう。
かつて「あたらしくひらきましたる歌の道に」と詠んだときのような若い気負いは影をひそめ、素直な思いがすっと心に入ってくる歌だと思います。自分の心の声に耳を澄ませ、自然体で言葉を紡ぎながら、ひとりの歌人として発言していこうという、登美子の静かな闘志が感じられる一首です。
病に倒れ「氷に眠る」
歌人として、学生としてようやく自分の人生を歩き始めた登美子ですが、幸せな時間は長くは続きませんでした。上京の翌年、登美子は体調を崩し、ついには大学を退学することになります。かつて夫の命を奪った病に、登美子の体もまた侵されていたのです。
死を予感した登美子の歌が、ゆっくりと変わり始めていきます。
わが死なむ日にも斯(か)く降れ京の山しら雪たかし黒谷の塔
私が死ぬその日にも、雪よ降れと歌う登美子のまなざしは、既に今生きている現実のあれこれを離れ、自分の死後も続いていく時間の流れ、より大きな世界へと向けられています。
わが柩まもる人なく行く野辺のさびしさ見えつ霞たなびく
20代の若さで、このような境地にたどり着かざるを得なかった登美子の運命の苛烈さを思うと、胸が痛みます。
明治41(1908)年、京都にある姉の嫁ぎ先で療養生活を送っていた登美子は、父が危篤との知らせを受け、大雪の中、無理をおして小浜の実家に帰省します。父は亡くなり、登美子自身の容態も悪化。そのまま実家で床についてしまいました。
自らも病床にありながら、父の死を悼み、登美子はこんな歌を詠んでいます。
山うづめ雪ぞ降りくるかがり火を百千(ももち)執らせて御墓まもらむ
山を埋めるように雪が降ってくる。かがり火を百も千もたいて、父の墓を守り続けたい。
複雑な思いはあったけれど、大好きだった父の死を悼む凍てつく雪山のような深い悲しみが、まっすぐに伝わってきて心を打たれます。
当時、不治の病とされた結核は肉親からも恐れられ、登美子の闘病生活は孤独で苦しいものでした。そんな日々の中でも、登美子はこんなユーモアのある歌を詠んでいます。
おつとせい氷に眠るさいはひを我も今知るおもしろきかな
「氷に眠る」とはどういうことでしょうか。
辛い闘病生活、過酷な運命、あるいは迫りくる死の隠喩かもしれません。
それらすべてを「幸い」「おもしろきかな」と、半ば強がりであっても言い切ってしまう奇妙に安らいだ場所に、29歳の登美子は立っていました。
恋に破れ、大切な人を相次いで失い、新たな夢も叶えられないまま旅立とうとしている時間の中で、登美子の感性は研ぎ澄まされていきました。彼女の作品は当初、鉄幹や晶子の影響を強く受けていましたが、晩年の登美子の歌には、誰の真似でもない、肩の力が抜けた山川登美子らしさが表れていると思います。
登美子の死と3冊のノート
明治42(1909)年4月15日、山川登美子はその短い生涯を閉じました。当時の風習で、病で亡くなった人の物はすべて燃やすと決められていたため、登美子の着物も、布団も、死の直前まで枕元に置いて短歌の草稿やメモを書きつけていた3冊のノートも、みな庭に放り出されたといいます。
登美子の弟は、親類に気づかれぬようそっと庭に降りて、そのノートを救出しました。
登美子逝去の知らせを聞いた与謝野鉄幹は、愛した女性の死を悼んでこんな挽歌を詠みました。
君なきか若狭の登美子しら玉のあたら君さえ砕けはつるか
「砕けはつる」という表現から、才能ある若い歌人の命を奪った残酷な運命に対する、鉄幹の慟哭が伝わってくるようです。
最後にたどり着いた場所

与謝野晶子が近代の日本を代表する歌人のひとりとして、他の追随を許さない圧倒的な才能を開花させたことは、疑いようのない事実です。
ただ、恋をして夢を抱き、自分なりの表現を模索し続けた山川登美子の作品には、晶子の恋のライバルという文脈だけには収まりきらない、独自の魅力があるように思います。
大原女のものうるこゑや京の町ねむりさそひて花に雨ふる
たとえば、京都の何気ない風景を詠んだこんな一首には、物語の始まりのような気配があって、登美子ならではの穏やかな世界観が感じられます。
歴史はいつも、勝者の視点から語られます。権力や名声を手にした人。健康や幸運に恵まれ、チャンスをつかんだ人。けれど、勝った人がいれば、必ず敗けた人がいる。そして、去ってゆく人が苦しみながら、深く潜って探した言葉に、時代を超えて救われることがあります。
山川登美子の別れの歌は、100年後を生きる私たちに、いずれおとずれる別れの時に向かって何を大切に生きるのか、静かに問いかけているように思えてなりません。
父君に召されていなむとこしへの春あたゝかき蓬莱のしま
(山川登美子・辞世の歌)
山川登美子についてもっと知りたい方へ
山川登美子の生涯や作品について、もっと知りたい方におすすめの本をご紹介します。
竹西寛子『山川登美子』(講談社文芸文庫―現代日本のエッセイ)
小説家の竹西寛子が、山川登美子の足跡を丁寧にたどりながら、歌の魅力をたっぷりと紹介している随筆です。登美子の歌の世界に触れたい方に。