明智光秀(あけちみつひで)といえば、織田信長(おだのぶなが)を討った謀叛人としてのイメージが強い。しかし織田家に仕えて後、信長が最も有能な家臣として期待していたのが光秀であったことは、あまり知られていないかもしれない。信長はこう語っている。
「丹波国(たんばのくに、現、京都府中部、兵庫県北東部、大阪府北部)平定における光秀の働きは、織田家の面目を天下にほどこすものであった。それに続くのが羽柴秀吉(はしばひでよし)で、功績は数ヵ国に比類がない」
つまり光秀の働きは天下に誇るべきもの、秀吉の働きは数ヵ国一のものと、後に天下人となる秀吉を上回る評価を光秀に与えているのである。信長が激賞した光秀の活躍とはどんなものであったのか。本稿では信長家臣時代の光秀の軌跡を紹介するとともに、そんな光秀がなぜ本能寺の変に向かうのか、原因も探ってみたい。
歴史の表舞台に躍り出た光秀

本圀寺の変
異変は、冷え込みの厳しい夜明けに起きた。永禄12年(1569)1月5日、京都六条堀川の本圀寺(ほんこくじ、当時は本国寺)を、三好三人衆(みよしさんにんしゅう)の軍勢が取り囲んだのである。本圀寺は、織田信長の後押しで昨年上洛し、室町幕府15代将軍の座についた足利義昭(あしかがよしあき)が、幕府の奉公衆(ほうこうしゅう、将軍の近臣)や織田家の人数らとともに仮の御所としていた。本圀寺を囲んだ三好三人衆とは、かつて将軍をしのぐ権勢を誇った三好長慶(みよしながよし)の家臣らで、長慶亡き後も政治の実権を握ろうとし、それを拒んだ13代将軍足利義輝(あしかがよしてる、義昭の兄)を4年前に暗殺している。昨年、足利義昭を奉じた信長が大軍で上洛すると、京都から逃げ出したが、信長が岐阜城に戻ったのを見計らい、再び将軍を亡き者にしようと本圀寺を襲ったのだ。
この時、明智十兵衛光秀は本圀寺内にいた。彼は将軍義昭の奉公衆であるとともに、織田家の家臣になっていたといわれる。三好三人衆の軍勢が攻めかかると、防御機能のない本圀寺はひとたまりもないはずであったが、光秀をはじめ、寺内に詰めていた奉公衆や織田家の者たちが奮戦し、三好の軍勢をたびたび撃退、寺内に入れないまま1日をもちこたえた。翌日になると危急を知った織田方の軍勢が駆けつけ、三好三人衆は桂川で合戦に及ぶが、敗れて退散する。この将軍義昭を守るための戦いが、明智光秀が良質の史料(『信長公記』)に初めて登場する瞬間であった(なお光秀の前半生については、「2020年大河ドラマ主人公・明智光秀とは何者なのか? 謎に包まれた前半生に迫る」の記事をあわせてご参照ください)。
 京都
京都
京都奉行への抜擢
1月6日に将軍義昭襲撃の報を受けた信長は、酷寒の中、岐阜城から馬を飛ばして京へ急行、普通ならば3日かかる道のりを2日で走破した。将軍の無事を確認した信長は、寺の防備を固めて、敵を寄せ付けなかった光秀の働きを認め、信頼を深めたのではないだろうか。義昭を守ったことで、将軍を立てて畿内を制圧した信長の体制は揺るがなかったのである。
明智光秀が一次史料(同時代史料)に初めて登場するのは、同年4月14日付の山城国(現、京都府)賀茂荘に宛てて、400石の納入と軍役を命じる連署奉書(れんしょほうしょ)である(異説あり。なお『信長公記』は良質とはいえ厳密には同時代史料といえず、二次史料とされる)。連署奉書とは奉行的立場の者が連名で発した命令書で、この時は光秀と木下秀吉(きのしたひでよし、後の羽柴秀吉)であった。秀吉が日付の下に署名しているのに対し、光秀がその後に署名しているので、光秀の方が秀吉よりも身分が高かったことがわかる。
またその4日後には、光秀、秀吉に丹羽長秀(にわながひで)、中川重政(なかがわしげまさ)を加えた4人連署で文書を発給しており、当時、これら4人が京都や畿内の政務を担当する「京都奉行」であったことがわかるという。つまり光秀は、織田家に仕えて僅か1年で、生え抜きの家臣である丹羽長秀と肩を並べる奉行に抜擢されていたのである。
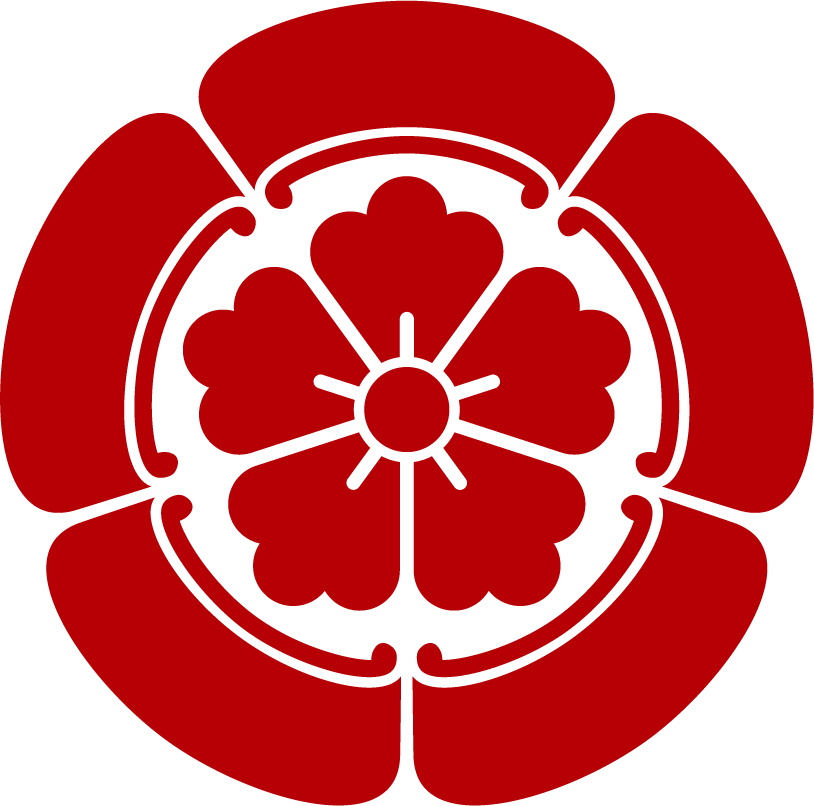 織田木瓜(おだもっこう)
織田木瓜(おだもっこう)
将軍と信長に仕えていた光秀
光秀が京都奉行に就任した背景には、彼が信長の家臣であるとともに、将軍義昭に仕えていることも大きかったろう。同時に二人の主人に仕えるのは奇妙に感じられるが、たとえば室町時代に美濃守護代の家に生まれた斎藤明椿(さいとうみょうちん)は、美濃守護・土岐(とき)氏の被官(ひかん、従属する武士)でありながら、幕府奉公衆として将軍にも仕えている。想像するに光秀も、それに近い感覚ではなかっただろうか。
信長にしても、将軍の近臣に光秀がいることは好都合だった。光秀を通じて京都の情勢、将軍の動向が逐一つかめるだけでなく、信長の意向を将軍に確実に伝えることができるからだ。やがて対立する信長と将軍義昭だが、義昭が将軍としての実権を取り戻そうとさまざまな策謀をめぐらしていることも、光秀を通じて信長には筒抜けであったと思われる。なお、光秀の生年は不明だが、『明智軍記』の、本能寺の変を起こした時に55歳であったという記述に従えば、初めて史料に登場した永禄12年には42歳。信長より6歳年上であった。
信長家臣最初の「一国一城の主」
 金ヶ崎城の麓にある金ヶ崎宮
金ヶ崎城の麓にある金ヶ崎宮
金ヶ崎撤退戦の殿(しんがり)
翌元亀元年(1570)4月20日、信長は大軍を率いて朝倉義景(あさくらよしかげ)の越前(現、福井県)に攻め込む。将軍義昭名義で2度、朝倉義景に上洛(じょうらく)を命じたにもかかわらず無視したためというが、それは口実で、実際は地勢的に京都と岐阜城の連絡を脅かす越前の朝倉が目ざわりだったようだ。織田軍は朝倉方の城や砦(とりで)を次々と落とすが、金ヶ崎(かねがさき)城(敦賀市)を攻略したところで、凶報が届く。
信長の妹婿(いもうとむこ)で同盟関係にあった近江(現、滋賀県)の浅井長政(あざいながまさ)が裏切り、織田軍の背後に迫りつつあるというものだった。このままでは、朝倉勢と浅井勢の挟み撃ちに遭ってしまう。信長は金ヶ崎城に殿(しんがり、最後尾で敵の追撃を防ぐ役割の部隊)を残すと、いち早く脱出。織田軍全体もそれに続いた。
この時、金ヶ崎城には木下秀吉が残り、困難な殿を務めて朝倉勢の追撃を食い止めたという話が知られるが、実は池田勝正(いけだかつまさ)と光秀も殿として残っている。秀吉よりも立場が上の二人の奮戦があったからこそ、朝倉勢を押し返すことができたはずなのだが、天下人となった秀吉が『太閤記』などで自分の手柄として大いに喧伝したため、光秀や池田の殿としての働きはほとんど伝わっていない。
 比叡山延暦寺
比叡山延暦寺
比叡山焼き討ちを止めようとしたか
金ヶ崎の危機を脱した信長は、態勢を整えると、同年6月28日に浅井・朝倉連合軍に戦いを挑む。姉川(あねがわ)の合戦である。戦いには勝利したものの、浅井・朝倉勢の息の根を止めるころまでには至らず、その後も浅井・朝倉勢は比叡山延暦寺(ひえいざんえんりゃくじ)と結んで、信長に対抗した。さらに摂津(現、大阪府)では三好三人衆、大坂の石山本願寺(いしやまほんがんじ)が、伊勢(現、三重県)では長島の一向一揆(いっこういっき)が打倒信長の旗を掲げる。あたかも信長を包囲するかのような共闘戦線で、「信長包囲網」と呼ばれるが、背後で糸を引いていたのは、実は将軍足利義昭であった。
敵対勢力に囲まれ危機的状況の中、信長は元亀2年(1571)、反撃に転じる。ねらいは「各個撃破」だった。まず5月に大軍で伊勢長島を攻めるが、一揆勢を崩すことはできず退却。次に攻撃対象としたのが、比叡山であった。従来の小説やドラマなどでは、教養人の明智光秀が「平安の御代(みよ)より王城鎮護をになう延暦寺を焼くなど、もってのほか」と信長を諌(いさ)めたとされてきたが、最近の研究でそうではなかったことが判明している。

撫で斬りにせよ
焼き討ち10日前の光秀の手紙には、次のように書かれていた。「仰木(おおぎ)の事は、是非ともなでぎりに仕(つかまつ)るべく候(そうろう)」。仰木とは比叡山麓の村落(現、大津市仰木町)で、「織田に従わない仰木の者たちは、撫で斬り(皆殺し)にせよ」と光秀は命じているのである。光秀は率先して、比叡山焼き討ちに臨んでいたことがわかるのだ。
同年9月12日に行われた総攻撃では3万以上の織田軍が動員され、延暦寺の堂塔伽藍(どうとうがらん)は焼失、僧兵はじめ僧俗合わせて数千人が殺されたという。『信長公記』には「(信長は)年来の御胸朦(ごきょうもう、うっぷんのこと)を散ぜられおわんぬ。さて志賀郡明智十兵衛に下され、坂本に在地候なり」とあり、破格の褒美として延暦寺のある志賀郡が光秀に与えられた。そのことからも、光秀が大いに働いたことが容易に想像できる。
 坂本城跡と明智光秀像
坂本城跡と明智光秀像
坂本城主に
明智光秀といえば文化や伝統を重んじ、残虐なことを好まない教養人のイメージを持つ人が多いかもしれない。そのため、比叡山焼き討ちを積極的に行った姿は意外に映るだろうが、信長配下の有力武将であれば、それは当然の選択だった。また比叡山を屈服させれば、信長を苦しめる包囲網の一角に大きな穴が開くことを、光秀は冷静に読んでいたと思われる。実際、比叡山焼き討ち以後、浅井・朝倉勢は南近江にまで兵を進めることはできなかった。
信長より与えられた志賀郡は、石高でいうと約5万石にあたるという。光秀はその年の暮れ頃より琵琶湖畔に新たな城を築き始めた。約1年半以上をかけて完成した城は、坂本城と呼ばれる。小なりとはいえ「一国一城の主」となったのは、信長の家臣の中で光秀が最初であった。柴田勝家(しばたかついえ)、佐久間信盛(さくまのぶもり)、丹羽長秀ら生え抜きの家臣を差し置いて、いわば「途中入社」の光秀が最初に選ばれたのは、信長がいかに光秀を買っていたかの表われであろう。なお坂本城は琵琶湖の水運を活用できる広大な城で、京都にも近い。天主(てんしゅ)もあがっていたとされ、宣教師のルイス・フロイスは「信長が安土山に建てたものにつぎ、この明智の城ほど有名なものは天下にない」と記している。
難攻の丹波攻略戦の始まり
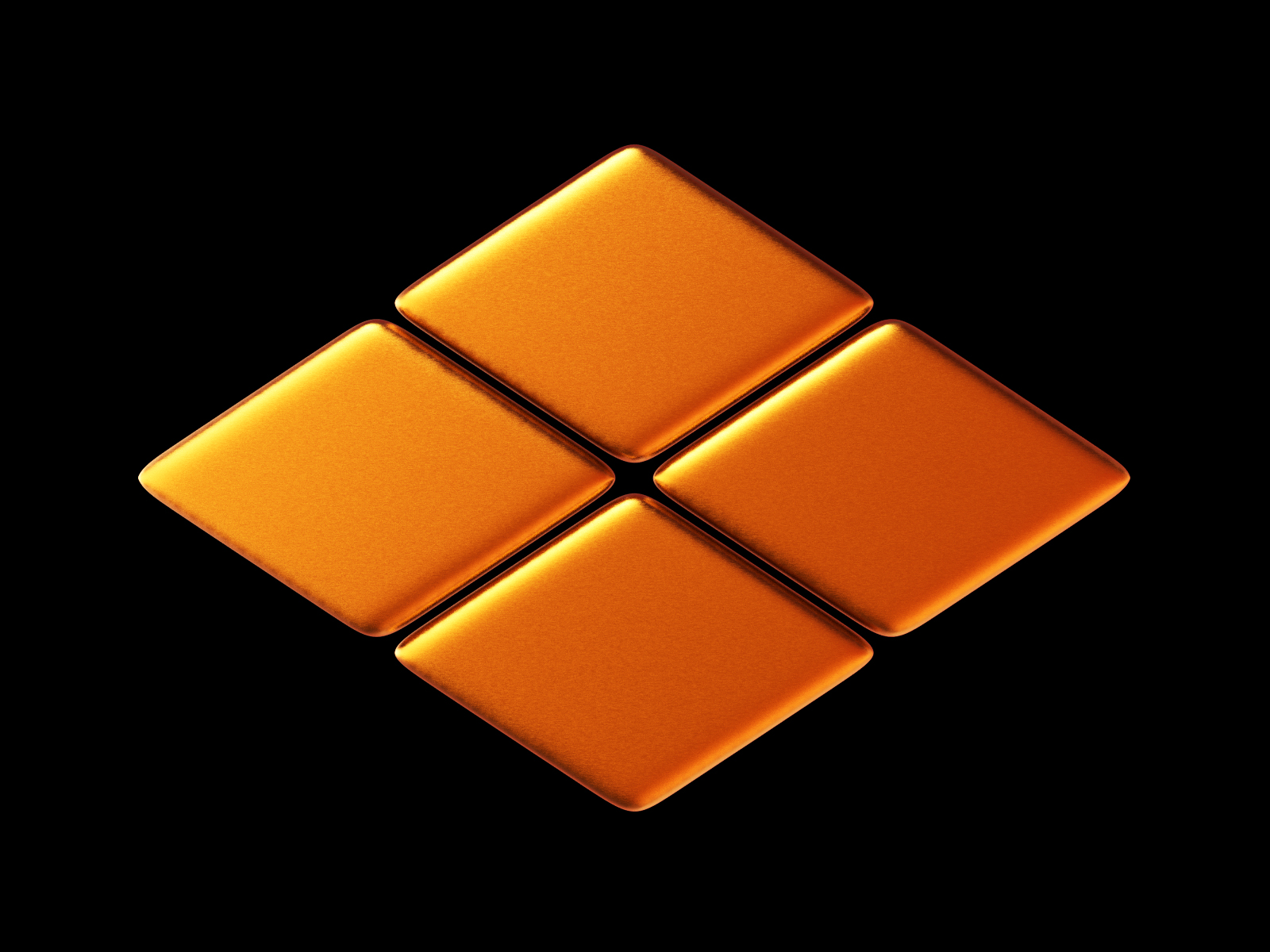 武田菱
武田菱
室町幕府の滅亡
光秀が坂本城を築いていた元亀3年(1572)秋、信長と将軍義昭との対立は修復困難となっていた。信長に不満を抱き、打倒するための包囲網を画策した張本人が義昭なのだから、無理もない。信長と義昭の両者に仕える光秀は、すでに前年、「暇(いとま)乞い」の手紙を義昭の側近に送り、義昭のもとを去って信長につくことを表明している。
しかしその頃、信長は大きな危機を迎えていた。甲斐(現、山梨県)の武田信玄(たけだしんげん)が西上作戦を始め、信長と同盟する徳川家康(とくがわいえやす)を破り、信長の領国尾張(現、愛知県西部)に迫りつつあったのである。越後(現、新潟県)の上杉軍とともに当時最強と呼ばれる武田軍の進撃に、将軍義昭は大いに喜んだ。元亀4年(1573)には自らも挙兵、信長との対決姿勢を鮮明にする。ところが……。
元亀4年4月、信玄は陣中で病没。三河(現、愛知県東部)まで来ていた武田軍は領国に引き上げてしまう。信長は京都に進軍し、義昭に圧力をかけた上で和睦を結んだ。が、あきらめきれない義昭は、3ヵ月後に再び槇島(まきしま)城(京都府宇治市)で挙兵。この時点では細川藤孝(ほそかわふじたか)ら多くの幕臣もすでに義昭を見限り、信長に従ったという(その後、多くが光秀の配下になる)。単独挙兵で信長に勝てるはずもなく、義昭は間もなく降伏。信長は将軍足利義昭を京都より追放し、ここに室町幕府は事実上滅亡した。
 長篠設楽原(ながしのしたらはら)古戦場
長篠設楽原(ながしのしたらはら)古戦場
惟任日向守(これとうひゅうがのかみ)の誕生
元亀4年は7月に改元され、天正元年となる。信長は同年8月に朝倉義景を、9月に浅井長政を滅ぼし、包囲網を大きく崩した。一方、光秀は西近江を平定するとともに、京都所司代に就任した村井貞勝(むらいさだかつ)を補佐して、京都奉行の任も果たしている。光秀は公家の吉田兼見(よしだかねみ)らとも親しく、朝廷や幕府の関係者、文化人などの人脈が、統治の難しい京都で役立ったのだろう。武将としても京都統治の文官としても有能な人物は、織田家中において光秀の右に出る者はなく、信長にとって得難い存在だったはずである。
とはいえ信長は、武将としての光秀をより買っていた。天正2年(1574)に光秀は、河内(現、大阪府)高屋城攻めに参陣。翌天正3年(1575)4月に再び高屋城を攻め、5月には三河の長篠(ながしの)合戦、8月には越前一向一揆攻めと諸方を転戦、武功を上げている。
特に長篠合戦で武田勝頼(たけだかつより、信玄の息子)に大打撃を与えたことは、信長にとって東方の脅威の激減を意味し、意識を西に向けることができるようになった。すなわち京都がある山城国に接する丹波国の平定である。そして信長は、丹波平定の総大将に光秀を任じた。なお同年、信長のはからいにより、光秀は朝廷から「惟任(これとう)」の名字を賜り、従五位下(じゅごいげ)日向守(ひゅうがのかみ)に任官している。光秀にすれば名誉なことで、以後、光秀は明智日向守、もしくは惟任日向守と名乗ることになる。

立ちはだかる「丹波の赤鬼」
江戸時代に記された武田氏の軍学書『甲陽軍鑑(こうようぐんかん)』に、名高き武士として徳川家康、長宗我部元親(ちょうそかべもとちか)と並んで、赤井直正(あかいなおまさ)の名がある。丹波黒井城(兵庫県丹波市)の赤井直正(荻野〈おぎの〉直正とも)は通称悪右衛門(あくえもん)、異名は、「丹波の赤鬼」。武勇で知られ、丹波きっての勢力を誇った。
丹波の諸勢力は、信長が足利義昭を奉じて上洛した際、これに従ったという。ところが信長が将軍義昭と対立すると、赤井直正らが反信長の立場をとり、「信長包囲網」の一角に加わる。信長が光秀に命じた丹波攻略の要となる最大の敵は、間違いなく赤井直正であった。
天正3年11月、光秀は丹波に攻め込む。軍勢には丹波の第二勢力である八上(やがみ)城主の波多野秀治(はたのひではる)ら、多くの丹波勢も加わっていた。光秀は守りの固い黒井城を包囲し、赤井直正を兵糧攻めにする。光秀の包囲は厳重で、次第に赤井勢が追い込まれつつあった天正4年(1576)1月、突如、味方していた波多野秀治が裏切り、赤井氏と通じて光秀軍を襲う構えを見せた。どうやらこれは、赤井直正と波多野秀治が最初から仕組んでいた計略だったらしい。不利を悟った光秀は、やむを得ず退却。第一次丹波攻略戦は失敗に終わった。光秀にとって、信長に仕えてから初めての挫折であったろう。
第二次丹波攻略戦と包囲網の打破
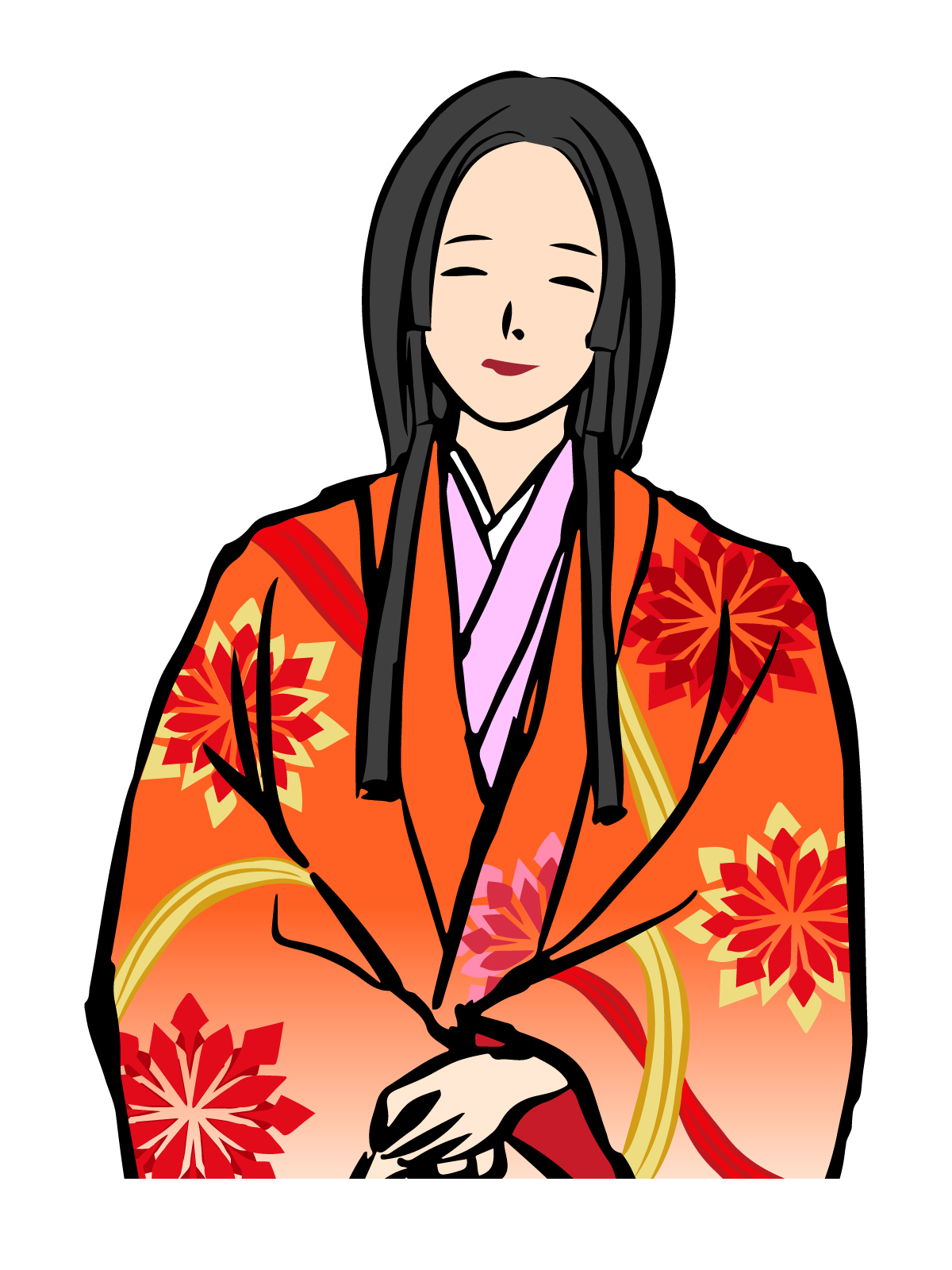
光秀の正室・煕子
いったん居城の坂本城に帰った光秀だったが、兵を休めている暇はなかった。丹波攻めだけでなく、別方面の戦いにも動員されたからである。4月末には石山本願寺との天王寺の戦いに出陣、5月に本願寺の反撃で主将の塙直政(はなわなおまさ)が討死し、光秀も守備する砦(とりで)を逆襲されてあわやというところを、駆けつけた信長に救われる一幕もあった。
その直後、光秀は過労で倒れる。光秀を看病したのは正室の煕子(ひろこ)であったという。煕子は光秀と親しい公家で神官でもある吉田兼見に、平癒祈願の依頼もしている。煕子の実家は美濃(現、岐阜県)守護だった土岐氏の庶流・妻木(つまき)氏とされる。それが事実であれば、出自(しゅつじ)が不明とされる光秀が、同じ土岐氏庶流の明智氏であることの傍証になるかもしれない。なお煕子の看護の甲斐あって光秀はほどなく回復するが、同年秋に煕子が亡くなってしまう。愛妻家であったともいう光秀の落胆は、大きかっただろう。
 亀山(亀岡)城跡
亀山(亀岡)城跡
荒木村重謀叛と包囲網
翌天正5年(1577)、光秀は2月の紀州雑賀(きしゅうさいか)攻め、10月の信貴山(しぎさん)城(奈良県生駒郡平群町)攻めに参戦するかたわら、再度丹波攻略の準備を進めていた。そして信貴山城落城直後、内藤氏の丹波亀山城(京都府亀岡市)を攻撃。3日3晩の激戦の末、降伏開城させる。並河掃部(なみかわかもん)、四王天政孝(しおうてんまさたか)ら多くの丹波衆が光秀の家臣となり、以後、亀山城は丹波攻略の最前線基地となった。
明けて天正6年(1578)3月、黒井城の赤井直正が病没。反信長の丹波勢には大きな衝撃だったろう。光秀は波多野秀治の八上城(兵庫県丹波篠山市)を孤立させるべく、4月に園部(そのべ)城(京都府南丹市)を攻略。その後、信長の命で播磨(現、兵庫県)攻めをしている羽柴秀吉の応援に向かい、6月末に神吉(かんき)城(加古川市)を落とす。そして丹波攻略に戻ろうとした矢先の10月、驚くべき知らせを受けた。摂津有岡(ありおか)城(兵庫県伊丹市)の荒木村重(あらきむらしげ)が石山本願寺と結び、信長に叛旗を翻したのだ。
これは単に荒木ひとりの謀叛では収まらない意味があった。本願寺と村重が結ぶことで、光秀が攻めている波多野氏ら丹波勢や、秀吉が対峙する播磨三木(みき)城(兵庫県三木市)の別所(べっしょ)氏に、後方からの支援が可能になる。さらに西からは中国を制した毛利(もうり)氏も迫っていた。信長はまたも包囲網に直面したのである。さらに、光秀個人にとっても憂慮すべき問題があった。荒木村重の嫡男村次(むらつぐ)に、光秀の娘が嫁いでいたのだ。
 八上城のある「丹波富士」こと高城山
八上城のある「丹波富士」こと高城山
事態を打開した八上城攻略
荒木村重はもともと池田勝正の家臣で、その後、信長に仕えて数々の武功をあげ、摂津一国を任されていた。織田家の重臣と認めるからこそ、その息子に光秀は娘を嫁がせていたのだろう。光秀は自ら有岡城に赴き、村重を説得するが、交渉は決裂。光秀の娘は離縁のうえ帰された。この事態に信長も自ら出馬、有岡城周辺に多数の付城(つけじろ、城攻めのための城)を築いて、外部との連絡を遮断する。しかし、村重謀叛に便乗し、丹波では八上城の波多野秀治が攻勢に転じた。光秀は亀山城に置いた遊軍に命じ、八上城攻めの支援に向かわせて、八上城と黒井城の連絡を封じる。
12月に光秀は、丹波に近い荒木方の三田(さんだ)城(兵庫県三田市)周辺に付城を築かせて、丹波への支援を断ち切ると、八上城の周囲を堀、柵、塀で完全に封鎖する。兵糧攻めであった。翌天正7年(1579)1月、八上城の波多野勢が反撃に出て、光秀方の指揮官・小畠越前守(こばたけえちぜんのかみ)が討死する戦いとなるが、そこまでだった。食糧が枯渇した八上城の戦意は急速に落ち、城内で内紛も起こって、6月に落城。波多野秀治らは捕縛、安土に連行されて磔(はりつけ)に処された。俗説では光秀が老母を人質として八上城内に送り、波多野の降伏を促すが、信長が約束を破って波多野を処刑したため、老母は城内で殺されたという。しかし実際は、老母を送るまでもなく八上城は落ちていたのである。
 有岡城跡
有岡城跡
八上城落城は丹波国内に衝撃を与え、8月には最後の牙城(がじょう)・黒井城も落ち、ここにようやく光秀の丹波平定は成った。そして丹波平定は、反信長勢力を一掃するほどの影響を与える。特に波多野秀治が磔に処されたことは荒木村重を動揺させ、村重は有岡城を見捨てて別の城に遁走。また秀吉が攻囲していた三木城の別所長治は、「波多野や荒木のような見苦しい進退は望まない」と翌天正8年(1580)1月に自刃し、開城した。丹波勢、荒木、別所が包囲網から脱落すると、孤立した石山本願寺は8月に信長と講和(事実上の降伏)、11年続いた本願寺との戦いも終わり、信長を包囲していた勢力はついに消滅したのである。その大きなきっかけとなったのが、光秀の丹波平定であった。
なぜ本能寺の変を起こしたのか
 桔梗紋
桔梗紋
丹波領有と畿内方面軍司令官
光秀の丹波平定について、信長は「丹波国日向守働き、天下の面目をほどこし候。次に羽柴藤吉郎、数ケ国比類なし」として、光秀に対し、激賞といってよい評価を与えたことは本稿の冒頭でも紹介した。それだけでなく信長は、光秀に従来の近江の領地に加えて、丹波一国約29万石を与え、居城として坂本、亀山の二城を認めている。破格の褒美といっていいだろう。それほど光秀の丹波平定は、信長にとって価値のあるものだったことがわかる。
さらに光秀は組下大名として、摂津の池田恒興(いけだつねおき)、中川清秀(なかがわきよひで)、高山重友(たかやましげとも)、大和の筒井順慶(つついじゅんけい)、丹後(現、京都府北部)の細川藤孝らを従えることになり、畿内方面軍司令官というべき立場になった。組下大名の石高を合わせると、最大で240万石に相当する軍勢を動かせることになる。これらが本能寺の変の2年前のことであった。
 岐阜の織田信長像
岐阜の織田信長像
なぜ信長を討たなくてはならなかったのか
翌天正9年(1581)に京都で行われた信長の馬揃えでは、光秀が総括責任者を務め、晴れがましい舞台を成功させている。また同年6月に光秀が定めた家中軍法の結びの言葉には、「瓦礫(がれき)の如く沈んでいた私を信長公が召し出され、多くの軍勢を預けて下さった。一族家臣は子孫に至るまで、信長公への感謝を忘れてはならない」とある。そんな光秀が僅か1年後に謀叛を起こすなど、誰が予測できただろう。
本稿では信長に仕えて後の光秀の歩みをたどってみたが、その過程で、本能寺の変につながる材料を何か見出せただろうか。確かに信長の命令は過酷であり、光秀が倒れたこともあったが、それ以上の十分な見返りを光秀は受けていたように感じられる。むしろ光秀の足跡をたどったことで、逆に本能寺の謎が深まった感すらある。
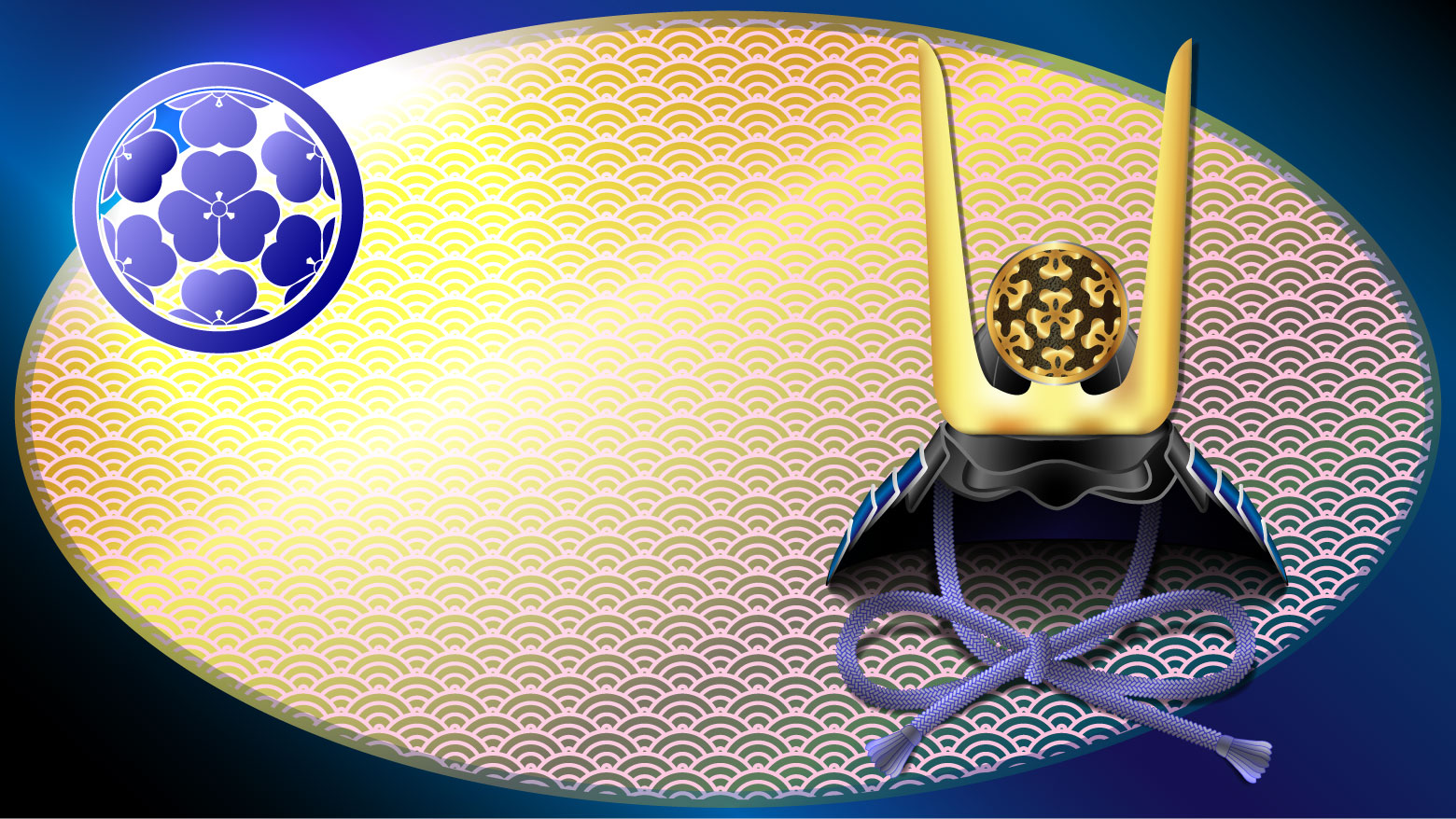 長宗我部元親のイメージ
長宗我部元親のイメージ
四国征伐は方針転換だったのか
では、本能寺の変直前の信長に、何かそれまでとの変化はあったのだろうか。一つの想像として、四国征伐があるかもしれない。従来、光秀が土佐(現、高知県)の長宗我部氏の取次役を務め、明智家中と長宗我部氏は姻戚関係になっていたにもかかわらず、信長はそれを無視し、長宗我部氏支援の姿勢から一転、討伐対象としたことで、光秀が板挟みになったとされてきた。だが、それもさることながら、信長の四国攻めは光秀から見て大きな方針転換だったのではないか。
それまでの信長は、追放した足利将軍に代わって「天下静謐(せいひつ)」をもたらすことを目指し、それに従わないものを屈服させるために戦ってきた。だからこそ光秀も納得して、力を発揮することができたのだろう。しかし長宗我部氏は、信長の敵対勢力ではない。にもかかわらず四国攻めを強行することは、「天下静謐」ではなく、四国を奪う野望のための戦いを意味する。すでに目ぼしい敵がいなくなった信長が、これからは野望のために戦うと方針転換をするならば、これは止めなくてはならない……。光秀は、そう考えたのではないか。しかし、それを裏づける証拠は何もない。
信長が最も高く評価し続け、目覚ましい活躍を続けてきた明智光秀。彼はなぜ本能寺で信長を討ったのか。皆さんはどうお考えになるだろうか。
参考文献:小和田哲男『明智光秀と本能寺の変』、渡邊大門『明智光秀と本能寺の変』、太田牛一原著、榊山潤訳『原本現代訳 信長公記』 他












