国語の授業で習ったはずなのに、松尾芭蕉がどんな人なのか、「おくのほそ道(奥の細道)」がどんなものかすっかり忘れていませんか? 大人になるとおもしろさや感動も格別なので、学び直しのきっかけにお読みください。
松尾芭蕉「おくのほそ道」をざっくり解説
まず、「おくのほそ道」をざっくり説明すると、「俳諧(はいかい)紀行文」です。作者は松尾芭蕉(まつおばしょう)。長い江戸時代のうち中期の元禄7(1694)年ごろに成立し、芭蕉の死後の元禄15(1702)年に出版されました。一般的には「奥の細道」と漢字交じりに表記されますが、原文は「おくのほそ道」です。
さて、俳諧とは?
俳諧の語源は「滑稽」であり、「滑稽な和歌」という意味になります。上の句と下の句を別の人が詠み合い、遊びの要素が強いものでした。
約150日で全行程(2400キロメートル)の旅
「俳諧紀行文」ということは、旅を記録したものです。その旅の内容がなかなかすごい。
元禄2(1689)年3月27日、芭蕉は弟子の河合曾良(かわいそら)を連れて、江戸・深川を出発します。その後、奥州(青森、岩手、宮城、福島、秋田県の一部)や北陸の名所旧跡を巡り、大垣(岐阜)を経て、伊勢(三重)へと向かいます。行程は、約600里(約2400キロメートル)。
旅は約150日間で、約2400キロメートル。1日平均では、約60キロメートルにもなります。人は毎日、そんな長距離を歩けるものなのでしょうか。この超人的な健脚ぶりから、「芭蕉忍者説」も生まれています。芭蕉は忍者のふるさとである伊賀上野(三重)出身というエピソードも、忍者説を裏づけているような気もしてきます。
もっとも、「おくのほそ道」自体、実際の旅をもとに書かれた紀行文ではなく、フィクションであるという考えもあります。
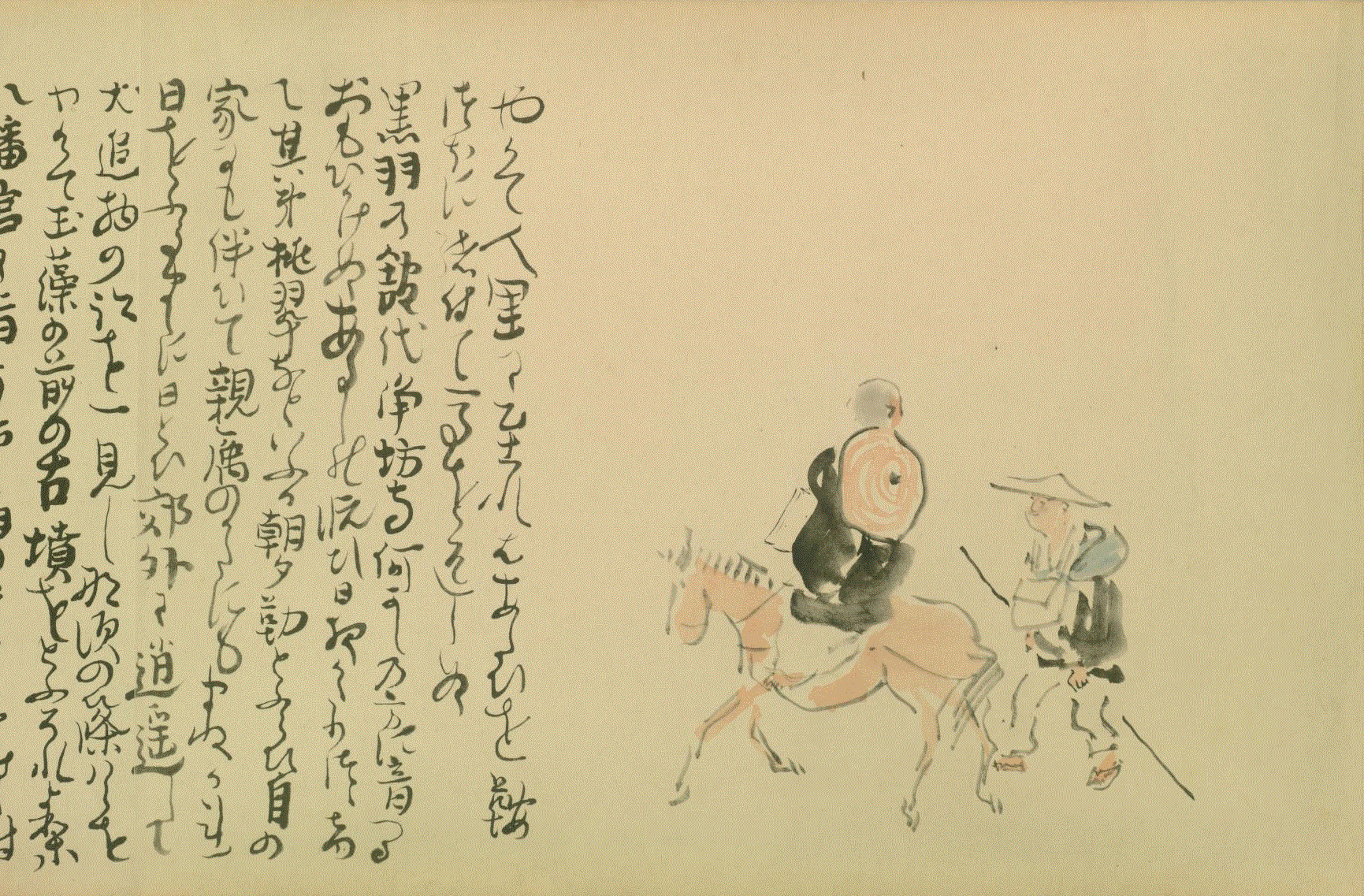
与謝蕪村が『おくのほそ道』を書写し、俳画を描き加えたもの
「おくのほそ道」有名作の一つを現代語訳つき紹介
旅を克明に記録した紀行としても、また、フィクションを織り交ぜ、練りに練った文芸作品としても、旅を続ける主人公の姿や自然の移ろいの描写には心を打たれます。
収録された俳句のうち、「聞いたことがあるかも」という作品を一つ、現代語訳つきでご紹介します。
「行春や鳥啼魚の目は泪」
(ゆくはるや とりなきうおの めはなみだ)現代語訳:春は去る。鳥は鳴き、魚の目には涙が浮かぶ。
旅といっても、今のような娯楽目的ではありません。江戸の旅は、厳しい関所や悪路もある徒歩の旅で、時に命の危険だってあります。これは、旅立ちの心細い思いが込められた句なのです。
天地自然の移ろいを見て、人生のはかなさを知る……。時空を超えて、芭蕉の言葉が聞こえてきそうな句の数々は、大人になった今だからこそ胸に迫ってきます。「おくのほそ道」は、数ある俳諧紀行文の中でもトップクラスに優れた作品なのではないでしょうか。
参考文献
日本国語大辞典
小学館 全文全訳古語辞典
日本大百科全書(ニッポニカ)
アイキャッチ画像
『肖像集 8. 嵐雪・松尾芭蕉』国立国会図書館デジタルコレクション
▼漫画でわかりやすく
まんがで読む 徒然草・おくのほそ道 (学研まんが日本の古典)













