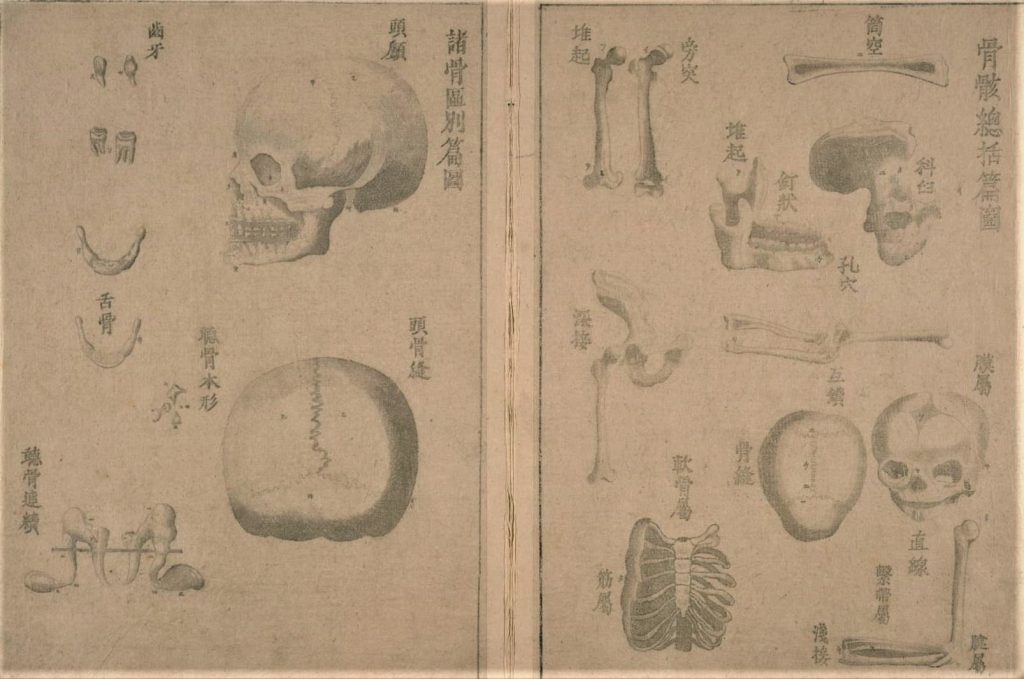移りゆく桜と人の関係性
和歌を見れば、時代によって移り変わる桜と人との関係性がわかります。『万葉集』の最初のころは、桜といえば、野山に咲く山桜でしたが、次第に里に降りてきて、貴族が庭に植えるようになることも見てとれます。そして、平安時代、たくさん桜の歌が詠まれるようになった『古今和歌集』の、素性法師(そせいほうし)の歌から目に浮かぶのは、都の大路の街路樹になった柳と桜の光景です。貴族だけでなく、源義家(みなもとのよしいえ)のように武士も和歌を詠み、旅先の桜や地方の桜が紹介されるようにもなりました。
平安末期の戦乱を経て、鎌倉時代に編纂(へんさん)された『新古今和歌集』の中の桜は、源平争乱後の荒れた都に咲く桜。式子内親王(しょくしないしんのう)の「花は散りその色となくながむればむなしき空に春雨ぞ降る」は、桜の花に、心のむなしさ、内面の暗さを重ねています。江戸時代は秀歌が乏しい時代。特筆すべきは本居宣長(もとおりのりなが)の「敷島(しきしま)の大和心(やまとごころ)を人問わば朝日ににほふ山桜花(やまざくらばな)」ですが、大和心といわれる本質的な精神は朝日に匂う山桜のように明るく匂いたつような優しさだということです。その後、桜は軍国主義に利用されてしまいます。
戦後、私たちはなかなか桜が歌えませんでした。ようやく桜の歌を歌えるようになって、今日を生きる感銘とともに桜の花に心の内を託すようになりました。「ちる花はかずかぎりなしことごとく光をひきて谷にゆくかも」(上田三四二 うえだみよじ)、「てのひらをくぼめて待てば青空の見えぬ傷より花こぼれ来る」(大西民子 おおにしたみこ)。痛切な思いが込められた秀歌です。(談)

見渡せば柳桜をこきまぜて都ぞ春の錦なりける
素性法師
「街を見渡してみると、柳と桜が混じり合って、都は春の錦のようだなぁ」。『古今和歌集』から桜の時代が到来。桜の歌が多く詠まれるようなった。
吹く風をなこその関と思へども道もせに散る山桜かな
源義家
「勿来(なこそ)=来るなという関の名のように、吹く風が来ないでほしいと思うが、道に散っていく山桜であることよ」。武士の義家が白河の勿来関の桜を詠み、地方の桜を紹介した。
ねがはくは花の下にて春死なむそのきさらぎのもち月のころ
西行法師
「かなうなら、桜の花の下で春に死にたいものだ。2月の満月のころに」。桜をこよなく愛した西行は、数年後、本当に2月の満月の日(現在の3月後半)に亡くなって、西上人(さいしょうにん)と呼ばれた
▼西行に関する記事もどうぞ
亡くなる日を歌で予言!ベストセラー歌人、西行のドラマティックな生涯
花は散りその色となくながむればむなしき空に春雨ぞ降る
式子内親王
「花は散り、桜の色はなくなったところを眺めていると、むなしさがこみ上げる空に春雨が降っている」。戦乱の世を経た後の暗い心情を感じる一首。
桜ばないのち一ぱい咲くからに生いのち命 をかけてわが眺めたり
岡本かの子
「桜の花が生命いっぱいに全力で咲くから、私も生命をかけて眺めるのだ」。彼女の体当たり的な人生を感じさせる、桜との情熱的な対話。岡本かの子は小説家、歌人。漫画家・岡本一平と結婚し、芸術家・岡本太郎を生んだ。

馬場あき子
歌人。1928年東京生まれ。学生時代に歌誌『まひる野』同人となり、1978年、歌誌『かりん』を立ち上げる。歌集『桜花伝承』『葡萄唐草』、著書『式子内親王』『鬼の研究』ほか多数。読売文学賞、毎日芸術賞、斎藤茂吉短歌文学賞、朝日賞、日本芸術院賞、紫綬褒章など受賞歴多数。『和樂』にて「和歌で読み解く日本のこころ」連載中。映画『幾春かけて老いゆかん 歌人 馬場あき子の日々』(公式サイト:ikuharu-movie.com)。全国の桜を見て詠んできたが、忘れられないのは「どうしようもないほどに吉野の桜です」。
構成/高橋亜弥子
※本記事は雑誌『和樂(2020年4・5月号)』の転載です。