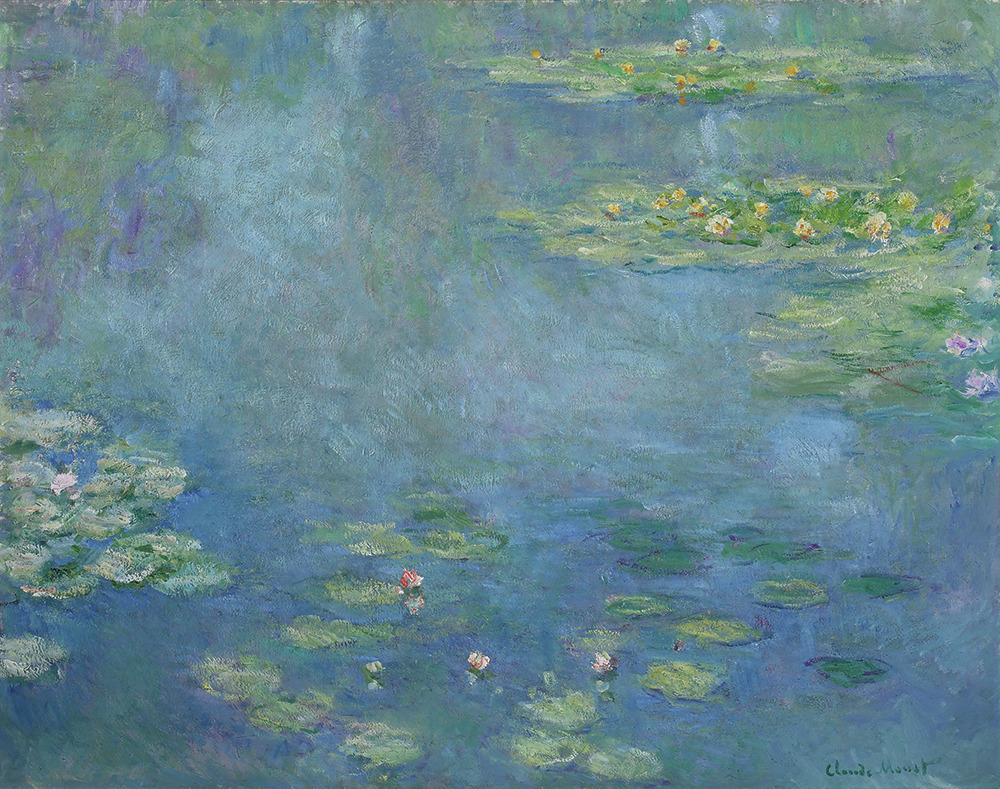亡くなった子どもを育てている母親の幽霊で、赤ん坊を抱いていることもある。江戸時代は子育て幽霊の話が広く伝わり、親の愛情を説く題材として用いられた。
しかし、今回ご紹介するのは母親ではなく、赤ん坊のほう。あまり知られていない、赤ん坊にまつわる奇妙な話を集めてみた。自然の御業か怪談か、はたまた狐と狸の仕業か。恐ろしく、ときに可笑しい。そして悲しみを誘う、赤ん坊奇譚の世界へようこそ。
バラバラ胎児が臍から出てきた
文化4(1807)年のこと。
鍛冶屋六兵衛の妻は、どうやら妊娠しているらしい。しかし出産する様子がない。
医者に診てもらい、腸癰(ちょうよう)の薬を処方してもらったので服用していたが、あるとき臍が腫れあがってきた。
針の先ですこし破ってみたところ腫れものの中から水が二升ほどでてきて、数日すると黒い水も出てきた。さらに紐のようなものがちらり。
一週間ほどすると、今度はバラバラになった胎児が出てきた。胎児の手、足、陰茎がちぎれちぎれになって次々と出てくる。しかし孔が小さすぎるのか、頭がひっかかってしまった。どうしたものかと悩んでいると、くしゃみの勢いで飛び出してきた。
そんなことがあり、腫れものの穴はずいぶんと広がってしまい、胎児をとり出したあとの穴からのぞくと、肋骨の一部が見えるほどだった。
その後、傷口に軟膏をよく塗り、治療をつづけていたところ傷口もふさがり、妻はすっかり回復したという。(『一話一言』より)
生まれてすぐに話す赤ん坊
文化5(1808)年のこと。
ある男の妻が男の子を出産した。その男の子は生まれるとすぐにものをいい、食べ物をねだったそうだ。この騒ぎに亭主も親戚も驚いて、話を聞きつけた名主に役人までやってきた。
「その赤ん坊を連れてまいれ」
そう命じられて夫婦は赤ん坊を連れて役所へ出向いた。しかし役所の門を入るやいなや、さっきまで口をきいていた赤ん坊がすっかり口を閉じてしまった。名主がなだめすかしてみたが、どうしても口を利かない。
「ちっとも話をしないじゃないか。いい加減なことをしてくれたな。狐狸の仕業だろう。もう帰りなさい」
役人に叱りつけられて、しぶしぶ帰宅する夫婦。
「お前が黙っているから、怒られちゃったじゃないか。どうしてお役所でものをいわなかったんだい?」
夫婦がそう聞くと、赤ん坊はにやにや笑って答えた。
「役人どもが上座にいて、私を下座に置いたからさ」
夫婦がふたたび赤ん坊を役所へ連れて行くと、今度は上座に据えてもらった。そして役人が下座に直って平服すると赤ん坊は満足したようすで言った。
「私は加賀中納言なり。早々本城へ遣わすようにいたせ!」
驚愕した役人一同。本城へ飛脚をもって届け出ると「心あたりがある」と返事が返ってきた。赤ん坊はさっそく乳母をつけられたという。(『街談文文集』より)
石像の子を産んだ女
惣兵衛の妻みち、は子どもがいないのを嘆いて夫には内緒で地元のご神体の石に毎夜参詣していた。
「どうか子どもを授かりますように」
すると間もなく身重になったので、さてはご神体が私の願いを聞き入れてくださったにちがいない、と夫にも祈願のことを打ち明けた。夫婦は喜び、安産の日を指折り数えて待っていた。
そのうち出産日が近づいたが、生まれる気配がいっこうにない。赤ん坊はすでに一年もお腹の中にいた。ようやく生まれてきた子どもは、石だった。
五体はそろっているが顔はすこし青い色をしており、全身は堅い石像だった。あまりに奇怪なことなので夫婦は赤ん坊のことを役所に届け出た。この話は、その届出に書かれていたことである。(『兔園小説』より)
旅先で知り合った娘が孫に生まれ変わった話
隠居善八は旅好きで、いつも旅へでかけていた。これは旅先での話である。
ある時、行く手から若い娘が歩いてきたと思いきや善八の前で倒れてしまった。そのまま放っておくわけにもいかず介抱していると、ようやく目を覚ました。
「危ないところだった。なんだって一人で歩いていたんだい?」
「本当にありがとうございました。じつは誘拐されたところを逃げてきたんです。申しわけないのですが、どうか私の実家まで送ってはくれませんか。」
善八は娘を不憫に思った。急ぐ旅でもない。承知して、送ってやることにした。帰ってきた娘に両親は大喜び。善八はたいそうなもてなしを受けた。別れ際、娘が言った。
「これもなにか前世のご縁でしょう。恩を忘れないために、なにか記念にいただけませんか。それをあなたと思って、朝夕、お礼を申します。」
善八は懐中の守袋に入れてあった観世音の御影を手渡して去って行った。
旅を終えて善八が帰宅すると、ちょうど孫が生まれたところだった。その赤ん坊は不思議なことに、あの娘に託してきた観世音の御影を握って生まれてきた。
さっそく娘に手紙をだしてみたが、かの娘は善八が去って間もなく病死したとのことだった。
赤ん坊は善八によく懐いた。もしかすると娘の生まれ変わりかもしれない。不思議な因縁に驚いた善八であった。(『兔園小説』より)
花に生まれ変わった女の子
文化12(1815)年のこと。
せい、と名乗る娘がいた。せいは幼い時から和歌を詠むのが好きで、利口で、容姿も美しかった。しかし娘はささいな風邪をこじらせて、そのまま世を去ってしまった。
娘を玉のようにいつくしんでいた両親の嘆きは言うまでもないことで、毎日涙を流して暮らした。
翌年の秋のこと。
娘が生前に使っていた小箱のなかから、大切に紙に包まれた朝顔の種が出てきた。母親は、せめて庭にまいてやろうと小さな鉢に種をまいて朝夕、水を注いで大切に育てた。
いつしか葉が出て、蔓がのび、しかし花は咲かなかった。それでも母親は一生懸命にお世話した。
ある日、一人娘と朝顔のことを思い出しながらうつらうつらとしていたら娘の声が聞こえた気がした。
「おかあさま、花が咲きました」
外へ出て朝顔の鉢へ寄ると、美しい一輪の花が咲きだしていた。この花は昼夜咲きつづけて、翌朝までしぼまずにいたという。夫婦は花がしぼむまで、二人で花を見たという。(『兔園小説』より)
赤ん坊の幽霊代表「子泣き爺(こなきじじい)」

葛飾北斎「百物語 こはだ小平二」(The Metropolitan Museum of Art)
赤ん坊の姿をした怪異、と聞いてまず思い出されるのが水木しげるの漫画でおなじみの「子泣き爺」である。
人里離れた山中で聞こえてくる赤ん坊の泣き声。声は聞こえるが、姿がない。辺りはうす暗く、寂しい。
抱き上げてみると、老人の顔をしている。赤ん坊はしがみついて離れない。そのうえ、どんどん重くなっていく……
その赤ん坊は離してくれないばかりか、しまいには人の命まで取るというから恐ろしい。
子泣き爺は「児啼爺」と書くこともある。
これから行こうとしている道の上に赤ん坊が転がっていて、素通りできる大人はそういないだろう。ましてや声だけが聞こえてきたら、どこにいるのだろうと探さずにはいられない。赤ん坊にまつわる話は、大人の心の柔らかな部分を鷲掴みにするからたちが悪い。
子育て幽霊代表「産女(うぶめ)」

一方、子育ての幽霊として日本でもっとも有名なのは「産女」だろう。産女は、平安時代に成立したとされる『今昔物語集』にも登場しているくらい、歴史のある怪異だ。
産女は産褥で亡くなった母親の幽霊とされている。そして、どういうわけか死んだ赤ん坊と一緒に現れるのが通例で、出会った人に赤ん坊を抱かせようとしてくる。
産褥で死んでこの世に思いを残した亡霊なら一人で出てきてもよさそうなものだが、そうはしない。
おそらく、母親は自分の死を嘆いているのではなくて、赤ん坊の死を受け入れられずに怨霊になってしまったのだ。そう考えると、子どもを何としてでも抱かせようとしてくることにも理由がいく。
もしかすると、自分の腕から他人に引き渡すことで赤ん坊だけでも生者の世界へ残していきたい、救いたいと望んでいるのかもしれない。でも、死の世界のものを生の世界のものが受け取るのはご法度だ。だから、赤ん坊は重くなっていく。
おわりに

子育て幽霊の話の背景には、親の愛情の深さが説かれている。でも、疑問も残る。
子どもと母親の幽霊が一緒に出てくるとき、主役は本当に「お母さん」なのだろうか? 産女は産褥で亡くなったと伝え聞くけれど、子どもを連れて現れる理由はそれだけだろうか?
子育て幽霊の話で赤ん坊の心情が描かれることはないから真実は分からないけれど、もしかすると、主役は赤ん坊の方かもしれない。と、私は個人的には考えている。古い時代には、事情があって間引きされた赤ん坊もいただろう。そんな赤ん坊たちの怨念が、母親の幻を携えてこの世に姿を現しているのかもしれない。
たとえそうだったとしても、母と子のあいだには分かちがたい愛着がある。それが愛情であれ憎しみであれ、子育て幽霊の話が悲しみを誘うことには変わりない。
【参考文献】
富岡直方『日本猟奇史 江戸時代篇』国書刊行会、2008年