超人気漫画『鬼滅の刃』。人気と聞いていたけれども、まさか書店で購入点数が制限されたり、インターネット上であの『ONE PIECE』よりも検索されているとは! たしかに…読むとメチャクチャおもしろい。テレビのバラエティ番組で椿鬼奴さんが作品のことを話しているのを観て、なんとな〜く手を出したのが最後、思わず一気読みしてしまいました。
それにしても、なぜここまで多くの人の心を掴むのか? キャラクターデザインやマーケティング的な要因も多々あると思いますが、この記事では、和樂webらしく、日本の民話や鬼に関する資料を参考に考察してみます。※ネタバレは含みません。
『鬼滅の刃』とは?
「週刊少年ジャンプ」で2016年から連載中の吾峠呼世晴による漫画。舞台は大正時代。主人公が家族を殺した「鬼」と呼ばれる敵や鬼と化した妹を人間に戻す方法を探すために戦う姿を描く。累計発行部数は2019年11月時点で2500万部を突破している。
哀れと残酷の日本民話
連載当初『鬼滅の刃』は悲観的なストーリーや設定、数多く登場する死の描写に「これは長く続かないだろう…」なんて声もあったそうです。しかし、これこそが多くの人の心を掴む要因のひとつになっているのではないか? と考えられます。
小さいころに読んだ日本の民話や昔話はどんな展開だったでしょう?海外の童話『シンデレラ』や『眠り姫』のような「困難の末にハッピーエンド!」といった展開が多くないことに気づくはずです。例えば『鶴の恩返し』や『かぐや姫』のラストシーンは、いずれも愛する人が主人公の元から去っていきます。『姥捨山』『舌切り雀』『かちかち山』『浦島太郎』…思い返せば、恐ろしい描写が多いかも? 厳しい自然と季節の変化に加えて、災害大国でもある日本。物語の哀愁や残酷な描写に親しみを覚えるのは、日本人ならではの感覚であるといえます。

さてこの感覚をふまえて『鬼滅の刃』のストーリーに注目してみると、少年漫画のいわゆる王道ストーリー「主人公がミッションのために成長し敵を倒していく」といった展開でありながら、「哀れと残酷」の描写に気がつきます。
『鬼滅の刃』の物語
復讐の物語。主人公の成長物語を柱にしつつ、登場人物ひとりひとりの挫折、屈辱、恨み、死などネガティブなエピソードが多く描かれている。悲観的な展開やシリアスな場面の合間にギャグ要素を挟むことで、暗い印象をおさえている。『ONE PIECE』の物語
冒険物語。主人公の成長物語の中に登場人物たちの喜怒哀楽のエピソードが描かれている。上記のようなネガティブなシーンもあるが、あくまで仲間との絆や明るい展開に着地する。安心感ある時代劇的展開。
『鬼滅の刃』も『ONE PIECE』も、前向きな主人公の成長を描いていますが、その内容は正反対。ベースにあるのは、復讐と冒険。復讐の物語である『鬼滅の刃』が今人気を博していることは、近年日本に蔓延する生きづらさや社会への不満と、どこか呼応しているようにも感じられます。
日本の伝承における鬼の正体
こういったネガティブな物語のほか『鬼滅の刃』の人気において欠かせないのが「鬼」の描写です。
人間が鬼に変身する設定は古典においてもメジャーですが、多様な能力・容姿・物語をもつ鬼たちは、私たちがイメージするような赤鬼青鬼のイメージとは様子が異なります。
また、主人公の妹・禰豆子(ねずこ)は鬼でありながら理性を持ち、主人公たちと共に鬼と闘う「希望」の存在として描かれています。そもそも鬼とは「悪しきもの」ではないのでしょうか? 鬼の正体について、歴史をたどってみましょう。
鬼は神霊的存在だった
鬼の発祥は定かではありませんが、日本ではじめて鬼のような存在が描かれたのは『古事記』。「鬼」という漢字が現れた最初の文献は『日本書記』(720年)などが挙げられます。この時点での「鬼」の読みは「オニ」ではなく、意味も異なっていました。また『万葉集』(奈良時代末期〜)などでは「鬼」という漢字を「モノ」と読ませることがありました。ここで言う「モノ」とは、直接に口に出すことがはばかられる、目には見えない超自然的な力。鬼が神様に近い存在であったことが、うかがい知れます。
このように古くから民俗学的には、鬼が福の神のような存在として扱われる祭りや言い伝えは全国各地にあり、強大な力をふるうことのできる神霊のひとつとしてとらえられてきました。『鬼滅の刃』における禰豆子の存在や力も、中世以前の鬼のイメージに近いのかもしれません。
可視化され制御される鬼
「オニ」という読みが日本に定着しはじめたのは、平安時代以降のことです。すでに「悪しきもの」として描かれていましたが、その多くは目には見えない恐ろしい存在(超常現象的なもの)でした。しかし中世になると、仏教などからの影響を受けて、鬼は「異形のもの」へと変容していきます。儀式においては「ハレ」を呼ぶための「ケガレ」として扱われ、能楽の世界では人の怨霊と化したものや地獄のものとして描かれ、昔話では悪者の役を負わされることが定型となっていきました。
もともとは形をなさない「力」だった存在が、芸能や儀式を通じて人間が演じられる「目に見えるもの」に変容。これにより、わかりやすく「悪しきもの」と定義づけられていった結果、鬼は人間がかんたんに制御できる存在となったのです。
ところが『鬼滅の刃』で描かれる鬼たちは人間が制御できないほど強い。制御できない鬼たちとどうやって戦うか? 倒せない鬼に苦戦するのです。私たちにとって定番である「鬼退治のストーリー」を覆すところが、物語の意外性やスリリングなおもしろさに繋がっているのです。
鬼は社会不安の幻影であり期待でもあった
「鬼はなぜ生まれるのか?」「鬼とは何か?」その答えのヒントをみつけました。小松和彦さんの『呪いと日本人(角川ソフィア文庫)』では、鬼の正体について「人の概念を否定するもの、社会への反体制、反秩序」と説かれています。
主人公の宿敵、鬼舞辻無惨(きぶつじ むざん)の部下である十二鬼月(強い力を持つ鬼たち)は、もともと人間でありながら、人間への絶望と社会への恨みから、鬼へと変わることを決意した者たちでした。目には見えなかった絶望や恨みといった力が、目に見えるかたちになったものが、彼ら鬼の正体であり、根源であることは、まさに小松さんの説いているヒントと合致します。
また作中で鬼舞辻無惨が鬼に変容したのは平安時代とされていますが、日本に「オニ」という読みが定着しはじめた時期とも重なります。
平安時代の鬼にまつわる物語は、摂関政治とともにはじまりました。政治的に重要な拠点であった朝廷の場で鬼が人間を喰らう話など、民衆の社会不安の幻影として、あるいはわずかに加害者の喜びを共有するように、人々が鬼に不思議な期待の情をかたむけていたことがうかがい知れます。鬼舞辻無惨を困窮する人々の期待や希望としての側面もあるのではないか?と推測しながら読むと、物語の世界を深く楽しめるかもしれません。
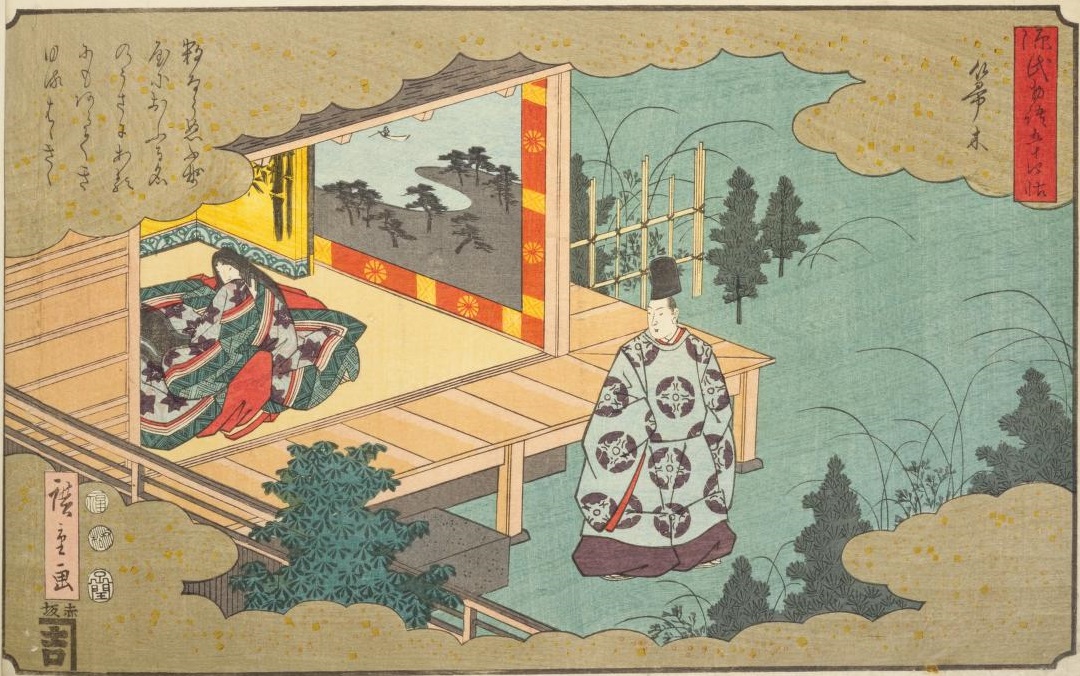
『鬼滅の刃』は令和時代の新しい民話
馬場あき子さんの『鬼の研究(ちくま文庫)』の最後に、こんな一節がありました。
機械化の激流の中で衰弱してゆくほかない反逆の魂の危機を感ずる。〈日常〉という、この実りすぎた飽和様式のなかで、眠りこけようとするものを醒すべく、ふしぎに〈鬼〉は訴えやまないからである。
同著の中では、近代において「鬼は滅びた」と書かれており「近世の鬼をあげるとしたら鶴屋南北の四谷怪談。それはそのまま現実の地獄、鬼たる人間の生き様を描いている」と続きます。さらにカフカの『変身』における「主人公が虫に変身してしまう理由」を複雑な人間関係や社会機構における人間回復の過酷な手段と考察したうえで、現代の鬼の姿として説いています。
『鬼滅の刃』は時代こそ大正ですが、そこに描かれている鬼の物語は、令和時代に突入した現代社会の軋みや人間関係の歪みに通じるものがあります。主人公たちが戦っている鬼たちは、可視化された現実問題。そう捉えると、私たちは、弔われていく鬼たちや問題に立ち向かう主人公たちの懸命な姿に現代社会で戦う自分を重ねて、無意識に共感しているのです。













