明治を代表する女性作家のひとりである樋口一葉。
5千円札に描かれた肖像で見覚えがある方も多いと思いますが、一葉自身の後半生は、決して金銭的に豊かな暮らしではありませんでした。
生活苦の末、24歳の若さで病死した一葉は、亡くなる直前、「奇跡の14ヶ月」と呼ばれる短い間に、『たけくらべ』『にごりえ』など数々の名作を世に送り出します。
地味で引っ込み思案だった文学少女の一葉を、押しも押されもせぬ一流作家へと生まれ変わらせたのは、師匠であった半井桃水(なからいとうすい)への熱烈な恋でした。
雪の日に、半井邸をたずねた一葉が「泊まっていきなさい」と引きとめられて恥じらう場面は、2人の恋のハイライト。小説の中にも描かれています。
一葉の日記を読むと、2人の関係はプラトニックだったようにも思われますが、真相はどうだったのでしょうか。一葉の、生涯ただ一度の熱烈な恋のゆくえを見ていきましょう。
■和樂web編集長セバスチャン高木が解説した音声はこちら
着物はみすぼらしくても、歌の才能では誰にも負けない
樋口なつ(後の一葉)は明治5(1872)年、東京の官吏の家に生まれます。父が副業で高利貸をしていたため、裕福な子ども時代を過ごします。小柄で色が黒く、赤毛の少女だったようです。
聡明な少女として成長した一葉は、11歳のとき、小学校高等科を首席で修了しますが、「女に学問は必要ない」という母、多喜の方針で、それ以降学校に通うことはありませんでした。
明治19(1886)年、14歳になった一葉は、当時著名な歌人だった中島歌子の歌塾「萩の舎」に弟子入りします。萩の舎には、皇族や華族などトップエリートのお嬢様が集まっており、一葉にとっては気後れすることも多かったようです。
萩の舎の新年会には、塾生たちが豪華絢爛な衣裳を身に着けて出席します。一葉も、多喜が用意してくれたお古の晴れ着で参加しますが、スケールの違うお金持ちの令嬢に囲まれて、うっかり変身せずに舞踏会へ来てしまったシンデレラのような気持ちだったでしょう。
けれどその日、60人以上が集まる歌会の席で最高点を取ったのは、一葉が詠んだ歌でした。このときの気持ちを、一葉はこんなふうに日記に書き記しています。
「おののきおののきよみ出しに、親君の祈りてやおはしけん、天つ神の恵みや有けん」
和歌を一首作るのに「親君の祈り」「神の恵み」とは、ずいぶんドラマティックな表現です。14歳の文学少女らしく、ちょっと自分の才能に酔っている感じもします。「着物はみすぼらしくても、歌の才能ではお金持ちのお嬢様たちに負けないわよ」という一葉の勝ち気な一面も垣間見えます。
19歳。憧れのイケメン作家に一目惚れ
一葉の少女時代が終わりを告げたのは、明治22(1889)年、一葉17歳のときのことです。事業に失敗して借金を抱えた父親が、病死してしまったのです。母の多喜と妹のくに、女3人の暮らしが、戸主となった一葉の肩にのしかかってきました。一家は着物の仕立てや洗濯をして生計を立てようとしますが、大黒柱を失った樋口家の暮らしは日に日に困窮していきます。
萩の舎の先輩だった田辺龍子(三宅花圃)が『藪の鶯』という小説を書いてデビュー、原稿料で父の借金を返したことを知っていた一葉は「私も小説を書いて家族を支えよう」と思い立ちました。
妹くにの友人のつてで、一葉は、当時東京朝日新聞の小説記者だった半井桃水に面会することになります。
初めて会った桃水の印象を、一葉はこう記しています。
「色いと白く面(おも)ておだやかに少し笑み給へるさま、誠に三歳の童子もなつくべくこそ覚ゆれ」
(色白で穏やかなほほ笑みを浮かべたようすは、3歳の子どもでもあっというまに懐いてしまうくらい魅力的だわ)
19歳の一葉は、31歳の世慣れた小説家に一目惚れしてしまったようです。一方、初対面の一葉について、桃水はこんなふうに書いています。
「(着物の)縞がらと言ひ色合ひと言ひ、非常に年寄めいて(中略)、頭の銀杏返しも余り濃くない地毛ばかりで小さく根下りに結つた上、飾といふものが更にないから大層淋しく見えました」
日本髪を結うときには「かもじ」と呼ばれる一種のかつらのようなものを添えて、髪のボリュームを出すのが一般的ですが、当時の一葉にはそんな経済的余裕も、時間のゆとりもありませんでした。
桃水は、愛妻を病で亡くした後、花柳の女性たちとも交際がありました。艶やかな女性を見慣れた桃水の目に、世間知らずの貧しい文学少女の姿はとても地味に映ったのでしょう。それにしても19歳の女性をつかまえて「年寄めいて」とは、当時の一葉が聞いたら泣き出してしまいそうな言い草です。
一葉はひどく緊張し、三つ指をついて丁寧な口上を述べたきり、ほとんど口をきくこともできない有様だったようです。憧れのイケメン作家を前に、声も出なくなってしまったのでしょう。その日はろくな話もせずに帰宅し、数日後あらためて「小説の書き方を教えてほしい」と桃水に申し込みをしました。
「同性の友人のようにお付き合いしましょう」
桃水は、一葉の申し出を一度断っています。けれど、一家の生活を背負った一葉は、簡単には引き下がりません。
「針仕事では、母と妹を養うことができないのです。どんな厳しいお言葉も甘んじて受け止めますので、ぜひお願いします」という一葉の真摯さに、桃水は胸を打たれました。
「私には、師匠と呼ばれるような才能はありませんが、相談相手くらいならばいつでもなりましょう。遠慮なくいらっしゃい」と桃水は一葉にやさしい言葉をかけます。それを聞いた一葉は涙をこぼしました。17歳で父を失い、家族を養うため必死に生きていた一葉にとって、桃水のあたたかい言葉は、天から差し伸べられた一筋の蜘蛛の糸のように感じられたことでしょう。
一葉は書き上げた小説を桃水に見せます。けれどそれは、萩の舎で学んだ古典の教養をこれみよがしに散りばめた古めかしい小説で、出版できるようなものではありませんでした。桃水は「売れる小説は、もう少し俗っぽくなければなりません」などと親身に一葉を指導し、2人の距離は近づいていきます。
一葉が桃水を訪ねる日は、なぜかいつも雨が降りました。
ある雨の日、桃水がひとりで滞在していた下宿に、一葉がやってきます。桃水が一葉に手紙を出して、呼び出したのです。
「私も老人というわけではないですし、あなたも若い女性ですから、こうして2人きりでお会いするのはどうも具合が悪いですね」と桃水は一葉に言いました。
これを聞いた一葉は、「おもて火の様に成(なり)て、おのが手の置場もなく、只恥かはしさをもておほほれ」。顔が火のように熱くなり、恥ずかしさで手をどこに置いたらいいかもわからないほど動揺してしまったといいます。
自分で呼び出しておいて、わざわざそんな意地悪を言うなんて、一葉の恋心をわかっていてわざと焚きつけているようにも思えます。桃水はさらに続けます。
「これから私は、あなたを親友の青年だと思って、何でもお話するようにします。ですからあなたも、私を友人の女性だと思って、気がねなく過ごしてくださいね」
31歳の遊び慣れた男性が、明らかに自分を慕っている19歳のうぶな女性に向かって「同性の友人みたいに付き合いましょう」というのは、真面目なのか冗談なのか、誠実なのか残酷なのか、真意を測りかねるところです。一葉の日記に現れる半井桃水という人物は、ときどきそのようなつかみどころのない言動をとることがあります。
桃水が何を考えているのかわからない故に、一葉の恋はますます燃え上がります。小説を書くために桃水を訪ねているのか、桃水に会いたいから小説を書くのか、一葉自身にもわからなくなっていたかもしれません。桃水の家からの帰り道、皇居のお濠端の道をひとり俯いて歩きながら、一葉はふと、身を投げてしまいたい衝動に駆られます。「売れる小説」が思うように書けないことに加え、人生で初めて経験する激しい恋心が、一葉を情緒不安定にしていたのではないでしょうか。
2人は「火鉢ひとつ分」の距離を越えたのか
桃水の周りには、女性の噂が絶えませんでした。生まれ持った美貌に加え、一葉に見せたようなやさしい笑顔で、多くの女性に接していたのかもしれません。一葉の家族や萩の舎の友人たちは、桃水の女性関係の噂を聞きつけては一葉に告げ口します。一葉はその度に胸のつぶれるような思いをし、桃水と離れるべきなのではないかと悩みました。
そんな中、一葉は「片思い」をテーマにした小説のプロットについて相談するため、桃水の家を訪れます。桃水は部屋着で一葉の前に現れ、2人は火鉢ひとつ隔てて向き合いました。
「男性の誠の愛」について自分の考えをひと通り語ったのち、何度会っても緊張した様子の一葉に、桃水は「恐がらないで、友達として気楽に付き合ってください」などと、繰り返し言葉をかけています。
「かたくるしいのは私の性格なのです。私は以前から、あなたを先生ともお兄さまとも思っておりますのに」と一葉。それに対して桃水が「私ほど不幸な人間はいないのです」とやや唐突な言葉を述べたところで、この日の日記は突然ふっつりと途切れています。
一葉の日記は、必ずしも真実をありのままに書き記したものではなく、後世に残ることを意識して書かれた「文学作品」だというのが現在の通説です。後から編集された部分や、意図的に書かなかった事実もあることがわかっています。例えば、ある時期から一葉は桃水の金銭的援助を受けていましたが、その事実も、日記の中では大部分が伏せられています。
片思いを題材にした小説の構想を桃水に話すことは、一葉にとって、事実上の愛の告白だったと考えられます。さすがの桃水も、一葉の意図を理解したでしょう。正面から恋愛論を展開したのは、桃水なりの、一葉への返答だったかもしれません。
途切れた日記の先に何が語られたのか、火鉢ひとつ分の距離を2人が乗り越えたのかどうか、一葉は、あえて真実を書き残さず、胸に秘めることを選びました。100年以上経った今も、一葉の恋の謎が人びとの心を惹きつけてやまないところを見ると、自分の日記を文学として後世に残そうという作家・樋口一葉のたくらみは、見事に成功しているようです。
降りしきる雪の日。「泊まっていきなさい」と言われても…
明治25(1892)年の年明けにも、一葉は桃水を訪ねています。昨夜遅くまで小説を書いていたという桃水は、寝巻に羽織を引っかけたしどけない姿で一葉を迎え、隣から鍋を借りてきて、一葉にお汁粉を作ってくれました。
朝から降り出した雪は、2人が話し込んでいる間にもいよいよ激しくなります。いつまでも桃水と話していたい気持ちを振り切って帰ろうとする一葉を、桃水は「ひどい降りだから、泊まっていきなさい。家には電報を打ってあげるから」と引き止めました。母に叱られるので帰りますと断る一葉に、桃水はなおも「私は別のところに泊まるから。あなたはひとりでここに泊まればいい」と言い募ります。
一葉は桃水の誘いを振り切って、人力車で家に帰ります。このときの心情も、日記に記されています。
「ほり端通り九段の辺、吹かくる雪におもてもむけがたくて、頭巾の上に肩かけすつぽりとかぶりて、折ふし目斗(ばかり)さし出すもをかし。種々の感情むねにせまりて、雪の日という小説一編あまばやの腹稿なる」
しんしんと降る雪の中にいるにもかかわらず、寒さを忘れるほどの高揚感に包まれている一葉の心境が読み取れます。片思いの苦しさに、いっそお濠に身を投げてしまおうかと思いつめていた数ヶ月前とは、ずいぶん違う心境にあるようです。この頃の一葉は、おそらく桃水と気持ちが通じ合っていることを確信していたでしょう。
一葉は、なぜ桃水との別れを決めたのか
3月、一葉のデビュー作『闇桜』が、桃水らが創刊した同人雑誌「武蔵野」に掲載されました。一葉は、これをきっかけに安定した原稿料を得たいと考えていましたが、「武蔵野」の売れ行きは思わしくなく、3号で廃刊となります。この時期、桃水も生活が苦しくなり、一葉に金銭的な援助を続けることがままならなくなりました。さらに、桃水と一葉の関係が萩の舎で噂となります。一葉の歌の師匠、中島歌子は、「桃水はあなたのことを、妻だ妾だと言いふらしているんですよ。そんな男との交際は断ったほうがいい」と一葉に忠告します。
悩んだ挙句、一葉は桃水と絶交することを決めました。
当時の日記には、「彼の人にくゝつらく、哀(あはれ)、潔白の身に無き名おほせて世にしたり顔するなん、にくしともにくし」と記されています。
桃水が「憎くて憎くてたまらない」というのですが、私には、これが一葉の本心だとはどうしても思えないのです。桃水に一目惚れをして、世間からどう見えるかなども構わずに乗り込んでいったのは、どちらかといえば一葉のほうです。ハンサムで遊び上手な桃水に女性関係の醜聞がつきまとうのは、今に始まったことではありません。世間が何と言おうとこの人を信じていくのだという一途さを、ある時期の一葉は確かに持っていたはずです。
一葉は、スキャンダルがあったから桃水との別れを決めたのではなく、小説家半井桃水と、萩の舎の人脈を冷静に天秤にかけて、萩の舎を選ぶことを決めたのではないでしょうか。
女性が職業を持つことが当たり前ではなかった時代、20歳の女性が腕一本で家族を養っていくのは、なまやさしいことではありません。恋だ愛だという前に、自身と家族を食べさせていくことを、一葉は最優先に考えなければならなかったはずです。
一葉がたどり着いた「厭ふ恋」の境地
心の奥底に残っていた、桃水を恋する気持ちを振り切って、仕事の上でも、金銭面でも頼れなくなった桃水に別れを告げた一葉。皮肉なことに、この決断が、一葉の小説家としての才能を花開かせることになりました。
一葉は萩の舎門下の作家、三宅花圃の支援を受け、名門雑誌『文學界』にも作品が掲載されて、新進作家の仲間入りを果たします。そして明治27(1894)年12月以降、憑かれたような勢いで『大つごもり』『たけくらべ』『にごりえ』『十三夜』など、文学史に残る名作を次々に書き上げました。
最晩年の一葉が暮らした丸山福山町の家には、島崎藤村、幸田露伴、斎藤緑雨などの若い作家たちが、一葉の才能と人柄に惹かれて訪ねてくるようになりました。一葉はウィットに富んだ会話と世慣れた態度で彼らをあしらい、魅了したといいます。「晩年」と言っても、一葉は23~24歳。桃水と初めて出会い、口もきけずに三つ指をついて固まっていたあの日から3~4年しか経っていないことを考えると、劇的な変化です。
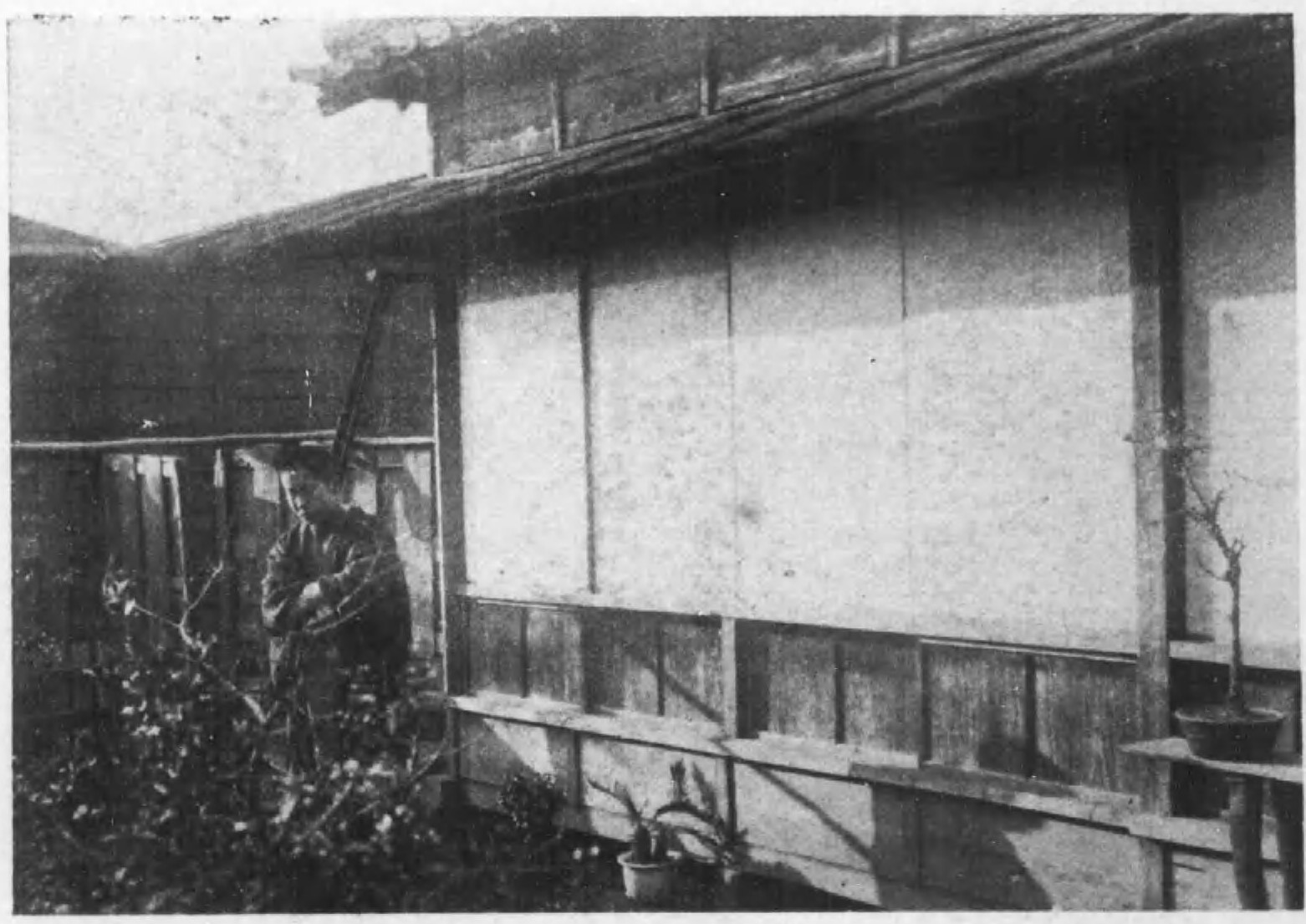
晩年の一葉は、「厭(いと)ふ恋こそ恋の奥成けれ」と日記に記しています。
恋の奥義は厭わしい恋にある。そして「厭ふ恋」とは「みぐるしく、にくゝ、うく、つらく、浅ましく、かなしく、さびしく、恨めし」いものだというのです。
亡くなる日まで、一葉の心の中には、桃水への恋心が消えずに残っていたのでしょう。これは想像ですが、作家として身を立て、家族を養っていくため桃水と別れることを決めた日、一葉の中にいた「一途な恋に生きる女性」が死んだのではないでしょうか。ちょうど、小説『たけくらべ』の中で、遊女になることを宿命づけられた主人公美登利の、少女時代の終わりが描かれたように。
桃水と別れてからの一葉は、ある意味で「余生」を生きていました。世間を外側から眺めるような、醒めたまなざしを手に入れたからこそ、生き生きとした登場人物を描くことができたのかもしれません。文学サロンの女主人のような風格も、萩の舎に入ったころのプライドや自意識を脱ぎ捨て、世捨て人のような心境に至っていたと考えると理解できます。
肺結核を患った一葉のもとに、『文學界』の同人たちが見舞いにやってきます。死を覚悟した一葉は「あなた方の袖に蝶がたわむれていたら、それは私かもしれませんよ」「次にお会いするときには、石にでもなっているかもしれませんね」などと冗談を言いました。自分の死までも、一葉は俗世を離れた場所から静かに見つめているようです。
明治29(1896)年11月23日、樋口一葉は24歳でその生涯を閉じました。
一葉の人生は、とかく「薄幸」「早世」という枕詞と共に語られがちです。でも、本当にそうだったのでしょうか。もちろん、楽なことばかりではなかったはずですが、生涯忘れられない、人生を変える恋をすることも、百年先まで読み継がれる名作を数多く生み出し、20代で世に認められることも、誰もが経験できることではありません。一葉の24年間は、ほかのどんな人生とも比べることのできない、濃密な時間だったのです。
謎が多い一葉の人生を知った上であらためて読み返すと、彼女が残した作品群は、不思議に艶めかしい立体的な魅力を持って、読者の前に立ち上がってきます。ひとつの文章が長く続く独特の文体も、あまり細部にこだわらずリズムに身をまかせると、案外読みやすくなります。ほとんどの作品が、青空文庫やKindleなど、インターネット上から無料で読めるようになっているので、時折行間に現れる一葉の後ろ姿を探しながら、再読してみてはいかがでしょうか。
▼情熱的な恋をした「大正三美人」柳原白蓮の記事もおすすめです。
愛なき結婚?大富豪の美人妻が若者と駆け落ちした理由とは。柳原白蓮の恋と人生
和樂web編集長セバスチャン高木が音声で解説した番組はこちら!
参考文献
和田芳恵『新装版 一葉の日記』(講談社文芸文庫)
瀬戸内寂聴『炎凍る 樋口一葉の恋』(小学館文庫)
※文中、樋口一葉の肖像は国立国会図書館ウェブサイト、
一葉が暮らした家の写真は馬場孤蝶『明治文壇の人々』国立国会図書館デジタルコレクションより転載












