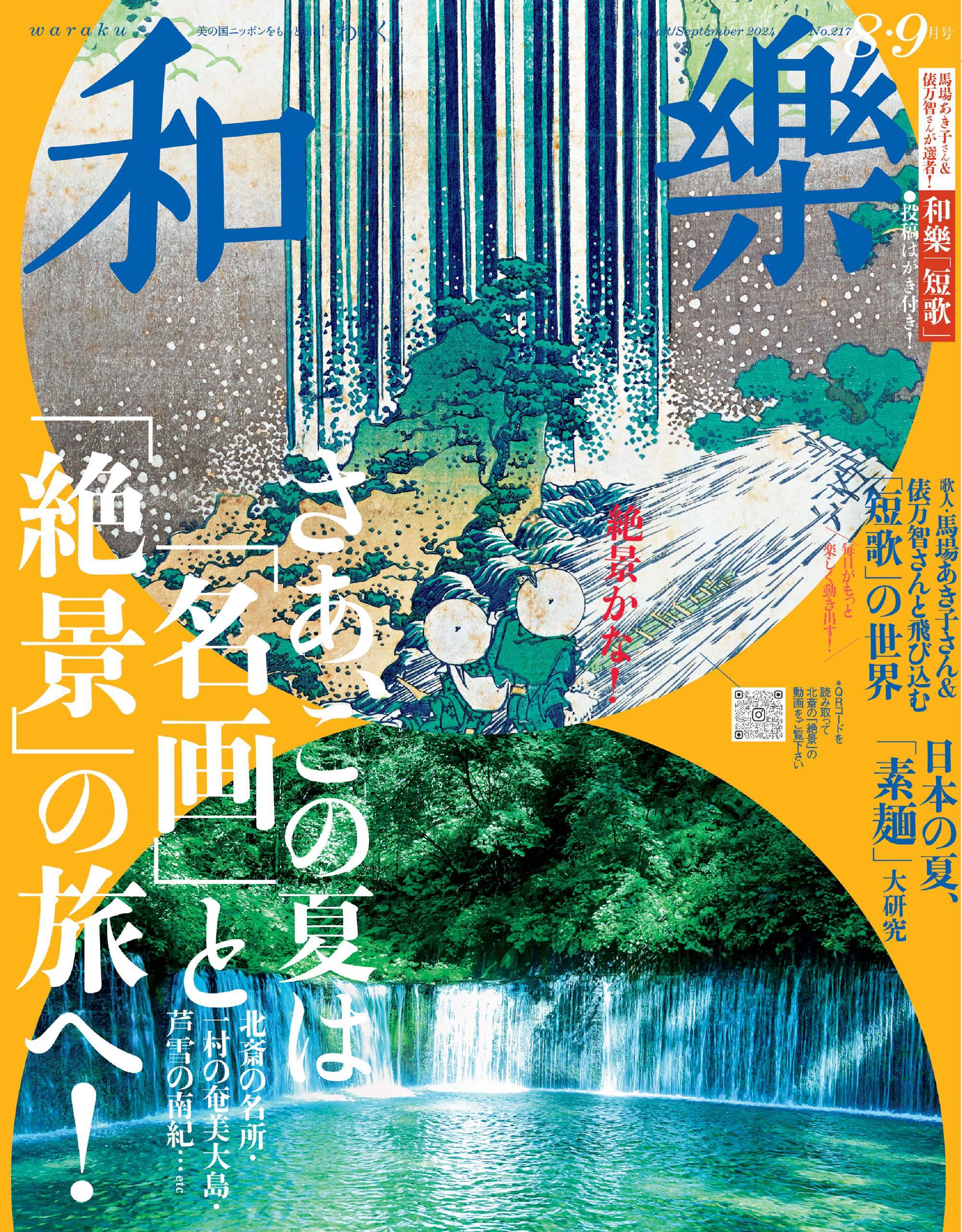あまりにも有名なナポレオンの肖像画。こちらは、ジャック=ルイ・ダヴィッドが描いた『ベルナール峠からアルプスを越えるボナパルト』である。ナポレオンといえば、「余の辞書に不可能の文字はない」などの名言を連発したお方(諸説あり)。さぞや自信満々な人なのだろうと、この絵を見て多くの人がナポレオンという男を認知したはず。
しかし、驚くことに、この肖像画はナポレオンがモデルではない。ややこしい話だが、ナポレオンの肖像画であるのに、当の本人がモデルになることを拒否したからだ。そのため、ダヴィッドは自らのイメージをたくましく膨らませ、かの肖像画を描くしかなかった。ナポレオンも気に入ったこの肖像画。マントの色だけが変わった作品が5枚あるのも頷ける。
さて、戦国時代の武将も多くの肖像画を描かせている。ありのままの姿を依頼する方もいれば、自分の容姿につき多くの注文をこれでもかと積み上げる方も。今回は、そんな戦国時代の肖像画にまつわる話をご紹介しよう。多くの激戦を勝ち抜いてきた戦国武将といえども、コンプレックスはあったのだ。
いや、身長を高くって言われても、限界が…
やはり、容姿についてのコンプレックスという話題であれば、真っ先に触れなければいけないのは、このお方。

おっと。やりすぎました。もとい、こちらのお方。豊臣秀吉である。

豊臣秀吉の肖像画といえば、長い尺を持って威風堂々と座している絵が有名であろう。狩野光信に依頼したとされる肖像画。秀吉の正室・「ねね」ゆかりの寺である京都の高台寺(掌美術館)に所蔵されている。顔がシュッとしていて、目には知性が宿る。そして、なんといっても貫禄がある。体が大きく逞しい男、つまり、偉丈夫(いじょうふ)の代表例のような肖像画なのである。
件(くだん)の肖像画を見れば、秀吉にコンプレックスなどあるはずもないと誤解する。しかし、絵の通りの豊臣秀吉像を、自分の頭の中に作ってしまっては早計だ。これにはからくりがあるのだから。
さて、初っ端からなんだが、とっとと種明かしをしよう。じつは、かの肖像画を描かせる上で、秀吉は事細かに注文をつけていたというのだ。それも3つ。その内容がこちら。
「見栄え良く、威厳のある顔つきで」
「顔を小さくし、首から下を際立って大きくし」
「顔立ちがよく見えて、立ち上がれば六尺(180センチ)はあるであろう、豊かな偉丈夫で描くように」
(丸茂潤吉著『戦国武将の大誤解』より一部抜粋)
もう、全くの別人である。
そもそも、豊臣秀吉の身長は154センチほど。大名の中でも最も低いといわれている。それなのに、180センチとは。さすがにサバを読み過ぎだろう。
確かに、秀吉の気持ちも分からなくもない。織田信長は推定170センチ、前田利家や千利休は推定180センチといわれている。秀吉の側室、淀殿でさえ推定168センチ。こちらは、現在においても女性では身長が高い方に分類されるだろう。そんな淀殿に釣り合うくらいにとでも思ったのだろうか。
そもそも、実際の豊臣秀吉の容姿は、どれほどのものだったのか。
まずは、毛利家の家臣、玉木吉保の自伝『身自鏡(みのかがみ)』から。この中に、ちょうど鳥取に出陣する秀吉に、初めて出会った様子が記録されている。
「赤ひげに猿眼にて空うそぶきてぞ出られける」
また、朝鮮から来た二人の使者、金誠一(きんせいいち)と黄允吉(こういんきつ)は、秀吉の印象をこのように語ったという。
「ネズミのような目」「まるで大猿」
さらに、イエズス会宣教師・ルイス・フロイスの『日本史』。この中で、オルガンティーノが書いた手紙が紹介されている。
「かの暴君の卑劣で下品なこと…中略…かくて彼はもはや、人とは申せなくなり、獣よりも劣ったものとなり果てました」
秀吉の容姿というかなんというか。ここまできたら、もう悪口でしかない。
どちらにしろ、容姿は優れていなかったと推測できる。かつての主君、織田信長も猿やらネズミやらと呼んでいたようであるから、そのような風貌だったのであろう。性格的には人たらしと評される秀吉だが、人一倍、容姿に関してはコンプレックスがあったといえる。
だからこその、あのステキすぎる肖像画となったのだろう。秀吉の夢がいっぱい詰まった肖像画。そりゃ、偉丈夫にもなるがなと、ひとり呟いてしまった。だって、もともとがそういう注文なんだもの。なって当然というか、逆にならない方がまずい。豊臣秀吉の場合、「肖像画」ではなく「理想画」と紹介した方がいいかもしれない。
ええっ。目を作っていいんすか…
次にご紹介するのは、「コンプレックスの塊」つながりの、こちらのお方。伊達政宗である。

正直、驚かれた方もいるだろう。伊達政宗って…あの「伊達男」の語源となる伊達一族じゃん。まさしくおっしゃる通り。しかし、じつのところ、彼は非常に大きなコンプレックスを抱えていたのだ。あの「眼」である。
独眼竜といわれる所以、それは片目を潰したからである。もともと、幼少期の梵天丸(政宗の幼名)は非常に活発で明るく、聡明な子どもだったといわれている。ただ、残念ながら5歳のときに疱瘡(ほうそう、現在でいえば天然痘のこと)を患ってしまう。
顔はあばたで赤くなり、それを気にして性格も一変。自分が醜いと、人前に出ることを嫌ったのだとか。そうこうしているうちに、疱瘡の毒が右目に回ってしまう。眼球自体が腫れあがり、眼窟から押し出されて垂れ下がったという。どうすることもできず、眼球をえぐり出し、結果的に政宗は右目を失った。
このときの様子は『明良洪範』に記されている。
「我、目の玉を切り落としたるときの不覚は、生涯の不覚なり」
それだけではない。じつは、伊達政宗も豊臣秀吉の如く、同じような注文をつけていた。具体的な指示というよりは、70歳の頃に言い残した遺言でのこと。
「もし私の肖像画や、木像を作るようなことがあったら、両眼健全な顔に作ってくれ」
(同上より一部抜粋)
どうして仙台城址(青葉山公園)の伊達政宗像が隻眼ではないのか。じつは、このような事情が裏にあったからである。つい、伊達政宗はド派手なパフォーマーと思いがちだが、非常に繊細な一面も持ち合わせた人物だった。死ぬ間際に、頑として正室の愛姫(めごひめ)に会わなかったのも、ひとえに自身の衰えた姿を見せたくなかったからだ。毅然としていたい。最期まで伊達男ぶりにこだわった政宗。
70歳を過ぎても、隻眼へのコンプレックスは手放せなかったようである。
逆にそんな姿をさらすって…
一方で、ありのままの姿を描いてと依頼するお方も。それがこちら。徳川家康である。

徳川家康像は、多くの場所で見ることができる。幼少の竹千代像は初々しさが残るが、一方で静岡駅に君臨する家康像は、これぞ天下人というイメージ。さらに、駿府城(静岡県)にある家康の鷹狩り像は、でっぷりとメタボ気味。一瞬、西郷隆盛かと見まがうほどである。同一人物とは思えぬ「成長しすぎ感」満載の家康である。



さて、そんな家康像の中で異彩を放つのが、岡崎城にあるこちらの像である。別名「しかみ像」と言われている通り、顔をしかめて憔悴しきった表情だ。この像は、徳川家康の肖像画をもとに作られたもの。いわば、平面を立体化したものである。

もとの肖像画とは『徳川家康三方ヶ原戦役画像』。
家康31歳のとき。元亀3(1572)年12月に、武田信玄と戦って敗走した「三方ヶ原の戦い」。一般的には、この戦いのあとに家康が描かせたものだとわれている。
三方ヶ原の戦いを少しだけ解説しておこう。
武田信玄が遠江(静岡県)・三河(愛知県)へと出陣。まず、信濃(長野県)から南下して、徳川家康の居城、浜松城のすぐ北にある二俣城を攻撃して占領。その後、信玄は浜松城へと向かう。これに備えて籠城する家康。しかし、信玄はわずか3キロまでの距離に迫ったところで方向を転換。なんと、浜松城下を素通りして、静岡県浜名湖の西にある「三方ヶ原」へと兵を進めたのだ。このときの武田信玄の兵は2万5000ほど(諸説あり)。家康の兵は8000と、その兵力差は明らか。家康が信玄に挑むには、無謀といえる状況であった。
しかし、家康は少々、難儀な事情を抱えていた。というのも、この信玄の行為を見過ごせば、今後、周囲の武将から侮られる可能性があるからだ。打って出るにしろ、黙って見過ごすにしろ、どちらにせよ難しい判断なのはいうまでもない。結果、家臣から反対されながらも、家康は出陣を決断。
ただ、残念ながら信玄の方が家康よりも何枚も上手であった。じつは、信玄は、城攻めよりも野戦に持ち込んだ方が有利と考えていたのだ。だからこその、家康の先をかすめる行軍を決行。全ては、家康を城からおびき出すための陽動作戦だったのだ。実際に、信玄は三方ヶ原で停止、反転して家康を迎撃している。
この戦いで、徳川家康は武田信玄の軍に打ちのめされ、敗走。家康の生涯で訪れる危機の中では、一番の冷や汗ものだったとか。一説には、敗走するときに兵が減り続け、数騎しか残っていなかったと伝えられている。あまりの恐怖に馬の上で脱糞したとも。それほどまでの負け戦。討ち取られてもおかしくない戦いだったのである。
さて、話を戻そう。
文化庁が運営する文化遺産オンライン。このサイトでは、日本の文化遺産について、情報が公開されている。『徳川家康三方ヶ原戦役画像』は以下のように解説されている。
家康は後年、この敗戦を肝に銘ずるためにその姿を描かせ、慢心の自戒として生涯座右を離さなかったと伝えられる。威厳のある堂々とした権現像とは異なり、憔悴し切った家康の表情が巧みに描かれており、別名「顰(しかみ)像」とも呼ばれている。
(文化遺産オンライン/文化庁 より一部抜粋)
ただ、近年は家康自身が描かせたものではないとする新説も登場している。もともと、この肖像画は、紀伊徳川家から嫁いだ従姫(よりひめ)の嫁入り道具に入っていたもの。もとをただせば、尾張家初代の徳川義直が、父である徳川家康の苦難を忘れないようにと描かせたのだとか。
真偽は不明だが、誰が描かせたにせよ、家康はこのような渋い顔をしなければいけない状況があったということ。後世にまで伝わる肖像画。ありのままの姿があってもいいと思うのは、私だけだろうか。
人の欲望は果てることがない。
秀吉の肖像画で、最近の画像処理技術のスゴさを思い出してしまった。スマホで撮った写真を色白に美肌修正して、目を大きくして…と欲望のまま美顔作りへ。結果、全くの別人になってしまったという友人談。
写真や肖像画を変えたとしても、実物は変わらない。ましてや、そのギャップに自尊心が傷つくことも。長所も短所も含めて、それが自分である。自分くらいは、自分のことを好きでいたいものだ。
最後は、ナポレオンの名言で締めくくろう。
「肖像画は本人に似る必要はない。その人物の天才性がにじみ出ていればよいのだ」
参考文献
新・歴史群像シリーズ19『伊達政宗』小池徹郎編 学習研究社 2009年6月
『戦国武将の大誤解』 丸茂潤吉著 彩図社 2016年9月
『別冊宝島 家康の謎』 井野澄恵編 宝島社 2015年4月
『完訳フロイス日本史5』 ルイス・フロイス 中央公論新社 2000年5月
『戦国の合戦と武将の絵辞典』 高橋信幸著 成美堂出版 2017年4月
『戦国合戦地図集』 佐藤香澄編 学習研究社 2008年9月
『戦国武将の病が歴史を動かした』 若林利光著 PHP研究所 2017年5月