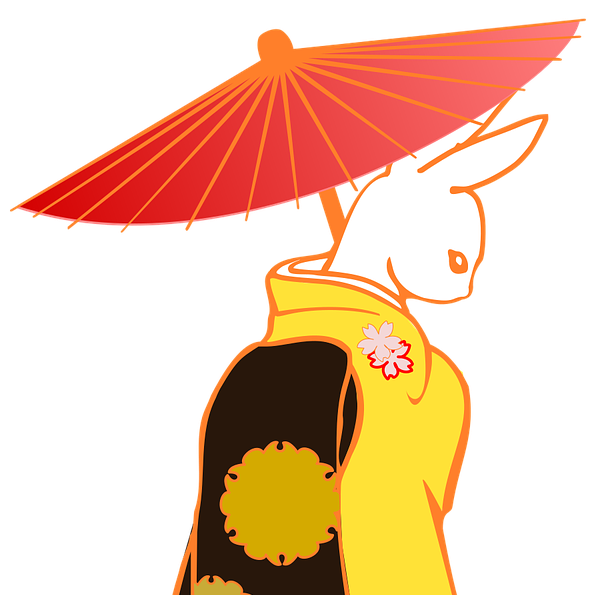──百聞は一見に如かず
ご存知の方も多いだろう。
人から何度聞くよりも、自分の目で一度見るほうが確かでよくわかるという意味だ。
意外に思われるだろうが。
まさにこの言葉が、まったくもって当てはまらなかった今回の取材。
訪れたのは、JR佐世保線三河内駅より2㎞ほど離れた距離にある「三川内(みかわち)地区」。
江戸時代より平戸藩の御用窯(ごようがま、藩の庇護を受けた窯)が開かれ、三川内焼(みかわちやき)が発展してきた場所だ。
三川内焼は約400年続く歴史ある焼き物。
平成28(2016)年には、日本遺産「日本磁器のふるさと 肥前~百花繚乱のやきもの散歩~」の構成文化財として、伊万里焼や波佐見焼などと共に認定されている。
そんな三川内焼の祖「如猿(じょえん)」の子孫であり、「嘉久房(かくふさ)窯」を担うのが、14代平戸悦山(ひらどえつざん)こと今村均(いまむらひとし)氏だ。一子相伝の技術で、冒頭の画像の郷土玩具「舌出三番叟(しただしさんばそう)人形」の焼き物など、多くの素晴らしい作品を作り続けている。
彼の手で作り出された逸品は、
もちろん、一目見ただけで圧倒される。
その「超絶技巧」には、ことさら、ため息しか出ないほど。
だが、この取材を通して痛感したのは、
「百聞は一見に如かず」とは真逆のコト。
「目」だけでは、真の価値が分からない。
どのようにして、この素晴らしい作品が生み出されたのか。
試行錯誤の末に辿り着いた技術。
作品に真摯に向き合う陶工としての生き様。
実際に話を聞き、言葉にある重みを受け止めてこそ。
ようやく「超絶技巧」の本当の意味、その真価を僅かながら理解できることを知った。
この記事で、どこまで伝えられるかは分からないが。
1人でも多くの方に、14代平戸悦山、今村均氏の凄さが伝わることを願う。
それでは、比類なき作品の数々と共に。
今回は前後編にて、たっぷりご紹介していこう。
※本記事の写真は、すべて「嘉久房窯」に許可を得て撮影しています
※この記事に掲載されているすべての商品価格は、令和7(2025)年3月末現在の価格となります
三川内焼の歴史に、この人あり
住宅地を抜けて広がる田園風景。
その先に、ぽつぽつと見えるレンガの煙突。
そんな窯元が軒を連ねる通りを外れ、細い坂道を上がったところに、今回の取材先がある。
ギャラリー併設の「嘉久房(かくふさ)窯」だ。
「昔は『皿板(さらいた)』いうて、6尺の長い板にずらっと(作品を)並べて、ここまで運んできたとですけどね。そうやって町を歩くのが風物詩やった」
こう話すのは、14代平戸悦山(ひらどえつざん)こと今村均(ひとし)氏。
娘である15代のひとみ氏と共に、代々続く「嘉久房窯」を営む、現役バリバリの陶工だ。

「うちだけはここから10歩のところですから。やっぱり棟梁(とうりょう)だからっていう話です」
現在はそれぞれの工房が窯を持つ「単窯」だが、明治時代の始めまでは共同の「登窯(のぼりがま)」で焼き物を焼いていたとか。棟梁は登窯に近い場所に居住していたが、他の陶工は違う。作品を板に乗せ、わざわざ町を歩いて登窯まで運ぶ必要があったのだ。その様子が町の風物詩だったという。

それにしても、1つ疑問がある。
均氏の先祖がどうして「棟梁」だったのか。
これは三川内焼の歴史、ひいては日本の歴史と大きく関係する。そして、間接的だが、まさかのあのお騒がせな天下人「豊臣秀吉」も。
秀吉が2度にわたって朝鮮に出兵した「文禄・慶長の役」。
この戦いに出陣していたのが平戸藩初代藩主の松浦鎮信(まつらしげのぶ)だ。彼は帰国に際し、朝鮮の陶工ら100人ほどを日本に連れ帰ったという。
その中にいたのが、「巨関(こせき、初代)」と息子の「三之丞(さんのじょう、2代)」。
三川内焼には2つの源流があるが、そのうちの1つが彼らであり、今村均氏の祖先でもある。2人は、当初、中野村上椿坂(現在の長崎県平戸市)に窯を開いたが、その後、三川内へと移動。
この三川内では、「陶器(陶土が主な原料)」が作られていたのだが。
寛永10(1633)年に、三之丞が「網代陶石(あじろとうせき)」を発見したことで、三川内の焼き物が「磁器(陶石が主な原料)」へと変わっていく。
これがきっかけで、寛永14(1637)年、平戸藩は三川内で御用窯を開窯。また、その4年後に、三之丞を皿山棟梁代官に任命。ここで初めて「今村」の姓を授けられたとされている。
話はこれで終わらない。
さらに大きく三川内焼を発展させたのが、三之丞の息子「弥次兵衛(やじべえ、3代)」だ。
ひとみ氏が弥次兵衛について説明してくれた。
「3代目の弥次兵衛が『早岐茶市(はいきちゃいち)』で刃物の砥石(といし)として出されていた天草砥石(あまくさといし)を『これは磁器に使える』っていうので、磁器の土に転用する技術を大成しまして」
早岐茶市は450年の歴史を持つ市だ。
交通の要衝であった土地柄、物々交換を行っていたのが始まりだとか。じつに現在も、新茶の季節である5月の週末に市が立つ。
この茶市で、弥次兵衛は「天草砥石」と出会い、網代陶土(あじろとうど)との調合に成功。三川内で磁器生産が本格化していくのである。
なお、純白の磁肌を持つ磁器の生産技術を確立した弥次兵衛は、「三川内焼の祖」として、近くの陶祖神社に祀られている。
「舌出三番叟人形」の由来
さて、この白磁の生産に満足したのは。
もちろんいうまでもない。平戸藩主である。
「『今村』という苗字を名乗らせて、武士でもないのに刀を持つことを許され、代官と同僚の職を与えられて。(弥次兵衛は)大変色が黒くて猿に似てたので、『猿の如し』ということで、『如猿(じょえん)』っていう名前をいただくんですね」とひとみ氏。
これまでの功績を称えられたとはいえ、信じられないほどの好待遇。
もちろん、それはそれで嬉しいが。ただ、さすがに「猿の如し」はない。それも、外見をイジられて命名されたというのも癪に障る。恐らく、3代目弥次兵衛にはそんな気持ちがあったのだろう。
ひとみ氏の説明が続く。
「(弥次兵衛は)すごく名誉なことだと。なので、烏帽子(えぼし)をかぶって、着物を着て、扇と鈴を持って踊る、能や狂言の『三番叟(さんばそう)』をかたどった人形をお殿様に献上するんですけれども。心の中は『あっかんべー』っていうので、舌を出す人形にしたというふうに言われています。で、これが『舌出三番叟人形』、うちが代々作ってるお人形です」

説明を聞いてからよく見ると。
着物をただ身に着けているだけかと思ったが。確かに、衣装はおめでたい感じである。好待遇を祝してというコトか。だが、顔は猿。それも写実的ではなく、ゆるキャラに近いほっこりした印象だ。1体1体、表情が異なり、いずれも味のある顔である。
置物としても十分価値があるが、じつは「舌出三番叟人形」は、その名の通り、舌を出す。
この変化が面白い。
舌を出している時には少し茶化したような顔つきになり、舌をひっこめた時もこれまたおどけた様子で笑いを誘う。おちょぼ口までいかず、中途半端な口の開き方が絶妙だ。平戸藩主への僅かな恨み節を、そっと、このからくり人形に込めたに違いない。ちなみに、予想に反して、献上された平戸藩主は大喜びだったとか。
さらに、である。
驚くのはまだ早い。コチラの人形、じつは舌を出すだけでなく、頭の部分もぐるぐる回る。つまり頭や舌のパーツが固定されず、動く仕掛けなのだ。
世界的に有名なドイツ、マイセン窯のパゴダ人形は、それぞれのパーツを焼いたあとに組み立てる。焼き物の人形はその方法が圧倒的に多い。だが、「舌出三番叟人形」は違う。焼く前の段階で、顔、胴体、舌の3つのパーツを組み立て、この人形を成形する。乾燥や収縮などすべて織り込み済みだ。見るだけでは分からない高い技術を要する逸品なのである。
大政奉還の行われる数ヵ月前。
慶応3(1867)年、第2回パリ万博が開催された際に、日本も初めて正式に参加。幕府と薩摩・佐賀両藩が出品したという。この佐賀藩の出品物の中に「舌出三番叟人形」もあったとか。フランス皇帝ナポレオン3世の皇后がいたく気に入り、多く買い求めたという逸話も残っている。
ただ、可愛いだけではない。
ただ、面白いだけではない。
製法には特別な技術が必要なのだ。
だから、この優れた技術を1人にのみ口伝で伝える「一子相伝」なのである。
「ろくろの技術とかも含めて。やってる仕事の中に、一子相伝の部分っていうのが多いですね。舌出し人形とか、虫かごの接着とか、他の人には流さんですね」と均氏。
そんな「舌出三番叟人形」を、均氏が初めて作ったのは、25、26歳の時だとか。
それまで先代の手仕事をずっと見ながら、一緒に仕事をされてきたという。ちょうど、均氏とひとみ氏の現在の関係と同じだろう。
「(お客さんから)作ってよって言うてこられて。舌出し人形、どがいして作るとかって。『親父、舌出し人形の舌、どがいして作った?』って聞いて。ああ、そういうふうに、ぺろぺろって、さあ、わかったって」
えっ。
ぺろぺろって。
一子相伝だから、詳しくは訊けないが。恐らく舌の動きなのだろうと推測する。そんなざっくりとした感じで分かるモノなのか?
「見よるときには、土の加減とか、硬さの加減とか、そういうのはまるっきり頭に入れておらんわけ。ああやってこうやって作りよると、それはわかる。実際始めるとね、『ええっ?』ていうのが出てくるわけ」
なるほど。
だから必要な部分を聞いて、あとは試行錯誤の連続。
その末にようやく出来上がるというワケか。
「親父からずっと言われたこと。『見て分からん奴には言うてもわからん』って。大体、そうでしょ。すべての技術、見て分からんやつに言うたって。10回言ってもわからんとですけん」
自ら吸収するしかない。
分かってはいたが、やはり厳しい世界なのである。
▼今村均氏の超絶技巧作品と、技術継承についての厳しくもあたたかいまなざしは、後編で
失敗して失敗して、ついに献上品に。14代平戸悦山の超絶技巧と技術継承のリアル【長崎三川内焼・後編】
撮影/大村健太
参考文献
『史都平戸 : 年表と史談』 岡部狷介編 松浦史料博物館 1967年10月
『伝統工芸品銘鑑』 サンケイ新聞年鑑局マーケティング事業部 1983年3月
『講座・日本技術の社会史 第4巻 (窯業)』永原慶二ほか編 日本評論社 1984年12月
『時の動き 30』 内閣府編 国立印刷局 1986年8月
『広報させぼ 2018年2月号』 佐世保市総務部秘書課広報係編、発行 2017年2月
基本情報
名称:工房 / ギャラリー併設[嘉久房/平戸窯悦山]
住所:長崎県佐世保市三川内町692番地
公式webサイト:https://sites.google.com/view/hirado-etsuzan/