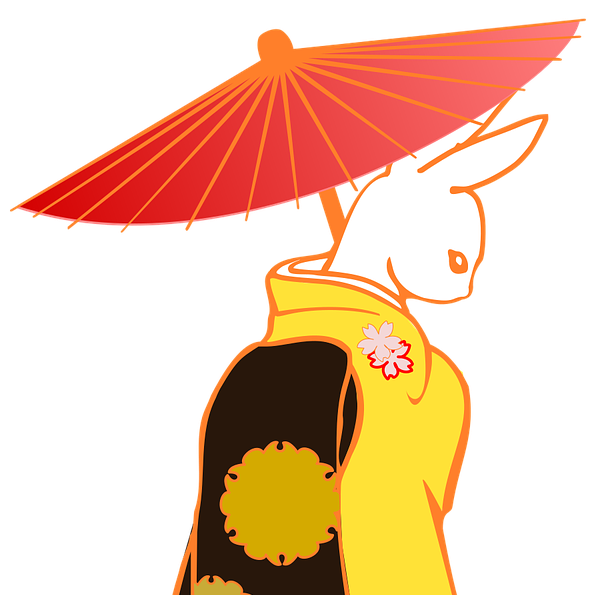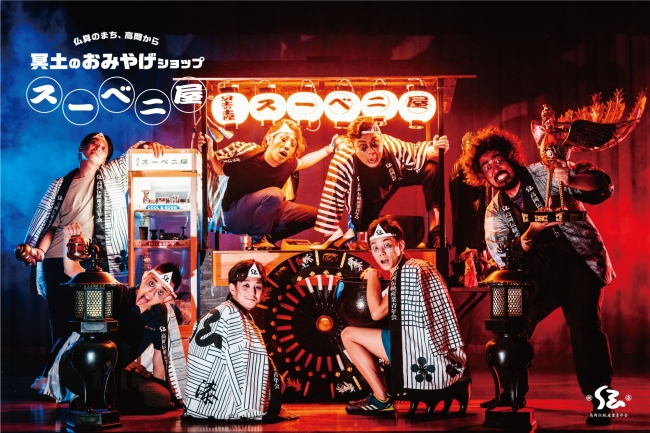長崎県佐世保市三川内(みかわち)地区。
焼き物の町として有名な佐賀県有田町からは、山1つ越えたところにある。この地で、江戸時代初期に平戸藩の御用窯(ごようがま、藩の庇護を受けた窯)が開かれ、三川内焼(みかわちやき)が発展してきた。
今回は、そんな三川内焼の祖として祀られる「如猿(じょえん)」の子孫で、娘とともに「嘉久房(かくふさ)窯」を担う14代平戸悦山(ひらどえつざん)こと今村均(いまむらひとし)氏を取材した。

前編では、400年以上続く三川内焼の歴史を遡り、一子相伝の技術で今なお作られる「舌出し三番叟(しただしさんばそう)人形」の由来を中心にご紹介。
この後編では、何よりもまず。
今村均氏の素晴らしい作品の数々をご覧いただきたい。
もちろん、「目」では分からない真の「超絶技巧」については、均氏のインタビューを中心にご紹介していく。
そこには。
唯一無二の作品が作り出される裏側には。
私たちの想像を遥かに超える彼らの日常、技術継承のリアルな現場があったのである。
▼前編はこちら
「舌出三番叟人形」の由来に愕然…一子相伝の技に込められた悲喜こもごも【長崎三川内焼・前編】
※本記事の写真は、すべて「嘉久房窯」に許可を得て撮影しています
※この記事に掲載されているすべての商品価格は、令和7(2025)年3月末現在の価格となります
目を奪われる超絶技巧の数々
ここからは作品をご紹介しながら。
14代平戸悦山こと今村均氏のお話を中心に進めていこう。
均氏は、令和3(2021)年に、長崎県指定無形文化財「三川内焼細工技術」保持者に認定されている。細工技術の中でも「捻り細工」を得意とするとか。そんな均氏、そしてひとみ氏の作品が併設されたギャラリーにズラリと並ぶ。
やはり御用窯という歴史もあるのか、白磁の作品はどれもこれも上品で惚れ惚れする。
2枚目:「菊尽くしボンボン入れ」サイズ:径10.5×高8.5cm(税込価格:385,000円)
3枚目:「菊置きこまつなぎ香炉」サイズ:径10.4×高11.0cm(税込価格:275,000円)
それにしても、「細工技術」と聞いて、つい、小ぶりのモノが多いだろうと思っていたが。そんな先入観はあっさり裏切られ、サイズもインパクトも大きい作品が目を引く。
「廃藩置県まではね、お殿様にいい作品さえ作ってればご飯が食べれたっていう時代だったらしいです。今は、これはどうですかと見せて売って、それ以上に向こうがこんなのが欲しいっていうのを来たときに作るだけ。最初の提案は全部こっち」
まず最初に目についたのが。
真正面に置かれていたコチラの「白龍」。
迫力もさることながら、白龍そのものが純白で、深い青い目が非常に美しい。三川内焼の特徴である青い顔料の「呉須(ごす)」だ。
実際に龍を見たことはないが、鱗など細かい部分まで非常に丁寧に表現されている。

「(玉を)ろくろで引くでしょ。それで完全にパッと塞いでしまって、1回下ろすでしょ。ある程度硬くなったら、てっぺんに穴を開けるんですよ。空気の膨張収縮で、呼吸させて割れないようにしとって。あとは硬さとの勝負で、龍のちょうど乗っかるような玉の硬さになったときに、上の龍をバーっと作り出す」
ちなみに、下の壺のような部分が「宝玉」。ろくろで作られている。
一方、上の「白龍」の部分は、三川内焼の様々な技法が用いられている。手足はもちろん、角、牙、爪、睫毛などのパーツは、手のひらと指先で作って接着する「捻り細工」だ。また体躯全体にある鱗は、置きあげ技術(筆を塗り重ね、厚く盛り上げ作る)だとか。
「天草の石で作った磁器の土は、気密になっとるもんで、空気が抜けないんですよね。大体、私の感覚で3~4mmぐらいの厚みまでは空気が抜けてくれるんじゃろうと。あの龍、ぐるっと巻いとっと。中身は全部空洞なんです。口のところだけで空気が抜けるように。あれ詰めてしまうと、パリンと割れるんです。焼く時に」
私たちは、出来上がった作品を見るだけだ。
だが、その制作過程を聞くと、恐れ入る。
この「白龍」も、「舌出三番叟人形」と同じく、すべて成形した状態にして焼く。乾燥させながら硬さを見極め、この見事なバランス、宝玉に乗った白龍の造形がなされるのだ。それも焼き上げの途中で割れないよう、膨張収縮を計算してのこと。すべては、これまでの経験と鍛え抜かれた感覚の賜物だといえるだろう。
「昔の人がようやったなって。いつもそれを思いながら、やりよっとですけどね。まあ、今は3個作れば2個ぐらいは確実に上がっていくっていう。今の完成度がそれくらい」
次に「白龍」の左隣にあるのが、これまた作風が異なる大小の蓮の磁器。
平成18(2006)年に『Lotus』(蓮)というタイトルで、イタリアのフィレンツェにあるリチャードジノリ陶磁器美術館に収蔵された作品と同じだとか。
ジノリ博物館に収蔵後も作り続け、今ではこの巨大な「蓮」が進化バージョンというワケである。

「蓮の花が大きくなって、格好がついただけ。蓮の咲いてる感じをパターン化して」
確かに格好はついたが。
一体、これほどの大きな花びらをどのように作るのだろうか。
「丸い花瓶があるでしょ? ああいうのを作って(花びらを)切り出すんですよ。カーブを求めるために。花瓶を11個(ろくろで)引いて切り出して。ほんで、室(むろ)もしくは発泡スチロールの箱の中で硬さを合わせて、ほんでから接着始めて」
つまり、球体のものを作ってから、半分に切って花びらを切り出す。そしてそれを接着する。この作業の繰り返しで、見事な蓮が出来上がるというワケだ。
素人の私だと、つい、何枚もの板状の花びらを作って……となりそうだが。それでは引力により戻ろうという力が発生し、倒れるという。立体的でより生き生きとした蓮の花に近付けるには、球体から花びらを切り出すという方法となったようだ。
これも、度重なる失敗を糧にして、得られた方法だ。
「構想を練って、こういうものを作ろうと思っても、それを実現するのがやっぱ難しいんですよね」
先ほどご紹介した「白龍」も失敗続きであったという。
「龍なんか、どこに逃げたとって。窯から上がったら、龍がぼとっと落ちてたりとかね。玉が割れてたりね。バーンってね。まあ、接着が良くなかったり、いろいろあるね」
そんな父親の姿を、ひとみ氏はこう評する。
「もう何回も何回も作り直してね。お父さんは諦めない人っていうか、できるまでやるっていう。途中でやめることを知らないから」

「今まで構想を練って、着手してからやめたことは?」との質問に、均氏は即答した。
「ないね。子どもの時から」
均氏がさらに言葉を重ねる。
「失敗して諦めたことはない。できるまでやるからね。けど、絶対できるって、そういうのは最初からない。(できないと思えば)構想の段階でやめとるね。手出さないね。構想の部分で不可能やなって感じるんでしょうね。でも、やるぞと思ったら最後までやる」
絶句した私を見て、ひとみ氏が解説してくれた。
「失敗じゃないんだもんね。経験なんだもんね。途中で終わるから失敗になるだけで」
なるほど。
そういうことか。
1回目の失敗も。2回目の失敗も。すべては経験であり、成功する過程の一部でしかない。だから、均氏は失敗したことはない、諦めたことはないと言い切れるのだ。
想像を絶する超難関の「虫かご」のスゴさ
これまで諦めたことはない。
そう言い切る均氏に「かなりを通り越して一番難しい」と言わしめた作品がある。
それが、コチラの「虫かご」シリーズだ。

かごの網目となる柱は非常に細くて繊細だ。中にいるコオロギたちも非常にリアルで、とにかく実物を目の前にすると圧倒される。これが磁器であることが本当に信じられない。これまでの作品と違い、これぞ細工物と思われる逸品だろう。
「日本のあちこちに『虫かご』ちゅうタイトルが残ってるんですよ。昔からの三川内焼の逸品に。それはずっと知っとって。ただ、アメリカのボストン美術館で売られてた平戸三川内焼の本に、すごいのが載ってるのを見て。竹ひごを立てた虫かごの原点やったんです。それを見たときに、ああこいつを一回やってやろうと」
そんな気持ちを持つ均氏に、なんと「虫かご」に挑戦するタイミングが訪れる。
あるお客さんが、台湾にある国立故宮博物院で、翡翠の虫かごを見たというのである。とても素晴らしかったと。でも磁器の虫かごって見たことがない。だから作ってよと。
酒の席での話だったようだが、飲んだ勢いで均氏も承諾したそうだ。
「で、よっしゃ作ろうって思ってから……納品までに5年もかかったね」とひとみ氏。
えっ?
最初の作品に5年……?
本日2度目の絶句である。

じつは、この「虫かご」。
様々な三川内焼の技術を組み合わせた、超難度の高い作品なのである。
土台と上に乗せるドームはろくろで作り、足の部分には彫刻が。中の「茄子(なす)」はろくろと捻り細工の組み合わせ。コオロギたちも指先を使ってパーツを作り、ピンセットで接着。
「普通の竹ではしなりが違うもんで、煤竹(すすだけ)を研いでピンセットにして。それで挟んで触覚つける。触覚が0.3mmぐらいあるかな。ちょうど木綿針を立ててるぐらいです。もう今の年では、触覚きついなと思うとです。みんな拡大鏡つけてやるけど、俺は老眼鏡だけでやるよっとですけどね」
そして、最大の難所が「かご」。
粘土を約2mmの竹ひご状に伸ばして、約70本でぐるりと囲む。
乾燥させながら「虫かご」の状態に成形して素焼き。さらに、釉薬の中を潜らせて、本焼成するという流れだ。
サラッと説明したが、どの工程も高度な技術を要する。

確かに、これまでの作品を思い返せば。
「舌出三番叟人形」も「白龍」も、すべて焼く前に成形している。
恐らく「虫かご」も同じだろう。一体、どうすれば、こんな細い2mmの柱70本で、上のドームを支えられるというのか。普通なら重みで潰れるはずだが、不思議でならない。
均氏曰く「それが技術です」という一言のみ。
30年もの間、「虫かご」と向き合ってきた人間だからこそ言える言葉だろう。
ちなみに、虫かごの中の虫たちは他にも種類があるという。
「コオロギ、鈴虫もいるし、松虫もね、ちょうちょもね。動きを見ながら。あのコオロギぴょんぴょんぴょんっていうのをさっと捕まえてね。で、ペットボトルに穴空けて、水やって。しばらくスケッチする」
リアルさをどこまでも追求する。
そのポリシーは虫だけではない。実在する生き物であれば、必ず観察して作品に反映させるという。
長崎県西彼杵町のながさき伝統野菜「辻田白菜」をモチーフにした作品、蟋蟀は子孫繁栄、白菜は清廉潔白の象徴だとか
「もういやなんかね。ここ1、2年、完成度高くなった。今やっとよ。今やっと窯に入れて、1つか2つ、確実に上がるなっていうのは。10個入れて」
えええええ。
それほどまで年月を重ねても、1個とは。
本日3度目の絶句である。
「まず素焼きの段階で半分ダメ。折れたり。くっついてなくて。バラバラってなって出てきたりとか。で、それに釉薬かけて、1個ぐらいダメになるね。釉薬かけた時に、なんか触覚なくなってるみたいな。いいんですよ。お酒が飲めるから。また失敗したって言って。『ええい、くそう。今日は飲めるぞー』って飲めるけん、よかったです。やけ酒でね」
ちなみに、すべてがダメになる場合もあったとか。
それでも諦めることなく作品を作り続けて、完成度を高めていく。その繰り返しで、最近ではようやく満足できる作品ができるようになったという。
そんな均氏の苦労が、実際に目に見える形で実を結んだのは約6年前。
令和の天皇陛下御即位の時である。
各都道府県から選定されたお祝いの品々。
じつは、長崎県の献上品として選定されたのが均氏の「菊花 虫かご」だ。

真摯に磁器と向き合ってきた当然の結果といえるのかもしれない。
その日は家族揃って乾杯したという。
ただ、年齢を重ねるにつれ、細かい手作業には限界がある。
正直、難しいと感じる部分もあるだろう。
「2年ぐらい前に物が二重に見えることがあって。ああ、もうこれでダメかなと思っとってこうちょっと相談に行ったところで。うん、なんとかなるよって言って。今、やっと元の老眼に戻って、もうちょっとできるかなと」
「目が見える間は作りたい」という均氏。
今も、もちろん新しい作品に挑戦中だ。
構想を終え、形にする途中だ。既に80%まで進んでいるという。
「最初のいっちょめ、今年中にあげたいっていうぐらい。今年中に形にしてから、あとは修正やね」
伝統を受け継ぐというコト
取材の最後に、今後の「嘉久房窯」について訊いた。
もちろん、話題は15代のひとみ氏だ。
均氏の表情が柔らかくなる。
「学校帰ってきたらすぐもう工房に遊びに行きよった子で。土でごちょごちょ、ものづくりやりよったもんで。この道に入ってしもうて。ばーかって」
これが、活字の怖さだろうか。
音声データを書き起こすと、文字通り「ばーか」となるのだが。この言い方が、なんとも愛情に溢れていて、正直、微笑ましかった。
個人的な解釈かもしれないが。
言葉の端々に、15代目を受け継ぐひとみ氏への複雑な心境が表れているように思えた。同じ道を志すことへの嬉しさ。その反面、己が身をもって知る三川内焼の厳しい世界。そこに自ら足を踏み入れた娘への相反する気持ちが、「ばーか」という、この一言に集約されている気がしてならない。
「(娘が継ぐことに)いや、嬉しいとか、嬉しくないって。そういうのは全然なし。あと継ぐ。ああそう。それでおわり。継ぎたい人が勝手に継いでいくだけで。そんな無理なことは言わない。どんだけ器量があるか知らんけんね」
過度に相手に期待しない。
自分は自分、娘は娘。そんな決然とした気持ちも伝わった。
一方、15代のひとみ氏はというと。
「なんかもう気がついたら工房が居心地よかったから、そこにずっといて、お父さんの仕事を見てて面白そうだなって。多分ずっと見てたんでしょうね。それが普通というか。他に選択肢がなかったっていうよりは、それ以外は興味がなかったっていう言い方の方がいいのかな」
そんなひとみ氏に話題が移ると、均氏は饒舌だ。
「小学校4年の時にね、小遣い自分で稼ぎよったけんね。窯の空いたところに、自分の作ったものを入れていって。それで5月の『はまぜん祭り』に、そこの入り口のところに机をちゃんと置いて『ひとみの店』って書いて。箸置きはよう売れたね。ブローチとかね」
それにしても、親子で共に仕事をするのは、大変ではないのだろうか。
身内だからこそ遠慮がなくなる。私の場合は、想像しただけで、いや想像しなくとも、即座にムリとわかるほど。
彼らはどうなのか。
様子を観察すると、2人の会話はこんな感じだ。
娘:「(互いの意見が衝突すると……)いや基本、私が折れるのね」
父:「(互いの意見が衝突すると……)俺がもう黙っとくだけだよね」
娘:「こういう尖った作品をさ、作る人間はさ、尖ってんのよ。何年もかかってものづくりする人って、そういうこだわりが強くないとできないですよね。まともじゃないと思う」
父:「まともじゃないのはわかってる。俺が生きてきたのがもうめちゃくちゃやもん」
阿吽の呼吸とはこのことか。
ただ、親子だからというワケでもなさそうだ。
聞くと、ひとみ氏は3姉弟の末子。長男については「感性」が違うと、均氏はハッキリ言う。
「こっからここまでちょっと作っとってよって頼むんでしょ。で、最初やったのが、お寿司屋の湯飲み。こういうのを作ってくれて頼んどっても、それが上がってこない。向こうの『美』に対する考え方と、俺が見る『美』に対する考え方が、根本がもう、違うたもんで」
件の長男は、コチラの工房より目と鼻の先で焼き物を作っているという。同じ三川内焼でも「ろくろ専門」なのだとか。
「別の窯で自分のやりたいもの作っていく。物は同じで白いけど、やっぱり違う。畑は一緒やけど、育った野菜が違う。そんだけのこと。それはそれでね、いいと思う」

一方でひとみ氏についてはというと。
「(継いでって)そんなこと言うたら後の人は大ごとや。自分が継ぎたいと思うたから切磋琢磨もするやろうし。やっぱり自分の気持ちが大事」
あくまで、当人の気持ちを優先してのこと。
さぞかし、娘がどんどん成長するのを見るのは、嬉しいものだろう。
そう尋ねると予想外の答えが返ってきた。
「そんな、どんどん成長するもんですかい。(成長は)見えるもんでなくて。ちょっとずつでしょうね。10年、20年、それが伝統じゃなかですか」
今回、4度目の絶句。
成長は見えるものではない。
確かに、この言葉に尽きるだろう。
構想から最初の作品として形になるまで数年。
勘が掴めたと言えるまで数十年。
だから、10年、20年と自然に積み上がる。
その歩みが、知らず知らずのうちに「伝統」を織りなすのかもしれない。
これほどまで、何度も絶句し、うーんと唸り続けた取材もあまりない。
三川内焼の伝統にほんの一瞬触れられた、そんな2時間であった。
取材後記
今回の取材で、一番印象に残った言葉がある。
「息子がですね、こんな仕事は辞めたって言って、1回、別の仕事に変えたんですよ。で、そんときはやっぱり『ああ、これでよかった。俺の荷は軽くなった』と。よかったなと思ったんですよ。息子が、あと継がんって言った時が一番嬉しかった」
ちょうど、ひとみ氏が席を外したタイミングでの一言だった。
均氏と私とカメラマンのみ。
そんな中で飛び出したのが、この言葉だ。
正直、意外だった。
自分のあとを継ぐことで、伝統が続く。だから、継がないと言われれば、一般的には落胆するのではないかと、不思議に思ったのだ。
それを聞いた私は、2つの質問をした。
「自身の苦労を知っているからか」
「親心なのか」
今村均氏は、こう答えている。
苦労について。
「やっぱりそれはありますね。こんな仕事やるもんじゃないって。(息子は)全部見て育ってきて、こんな仕事って言いながら、一生懸命やりよるやろ」
親心について。
「親心とかなんとか、わからんけどね。俺はね(厳しい世界だと思う)。他の人は知らんよ。他の人があとを継いでやってるのは知らんよ。ただ俺はね(厳しい世界だと思う)。そんだけ」
均氏が12代悦山、今村鹿男氏の指導を受けたのは昭和36(1961)年。
あれから既に65年近くが経った。いや、恐らくひとみ氏のように幼少期から携わってきたのであれば、三川内焼と向き合ってきた時間はもっと長いはずだ。
そんな均氏が、厳しい世界だと言うのだ。
個人の感性も大いに関わるだろうし、言い方は悪いが適性もあるだろう。ただ、気持ちだけでできる、そんな生半可なものではない。だからこそ、長男が違う道を歩むと決めたことが、人生の中で一番嬉しかったとなったのではないだろうか。
だが、人生は因果なもので。
結局、長男は三川内焼に携わった人生を歩んでいる。
「でも継いだね。焼き物作ってね。それがやっぱり因縁じゃろうね。一生懸命やってますよ。息子。面白いもん作ってる」

それにしても、と思う。
振り返れば、今回の取材は本当に愛に溢れていた。
取材中は、質問や取材の進行に気を遣い、そこまで気付かなかったが。
録音データを改めて聞き直すと。
師匠である、そして父である14代今村均氏の声音が、子どもたちについて語る時にはとても優しかった。愛情ダダ漏れである。
いかなる道を歩んだとしても。
子どもたちがどれほど誇らしいか。
嬉しくもあり、心配でもあり。そのまっすぐな愛情がひしひしと伝わってきた。
その姿を見たせいか。
取材を終えた帰り道、久しぶり父に電話した。
来月にでも京都へ帰ろうか。
「待ってるで」
その声が。
なぜか録音データの声と重なったような気がした。
撮影/大村健太
参考文献
『史都平戸 : 年表と史談』 岡部狷介編 松浦史料博物館 1967年10月
『伝統工芸品銘鑑』 サンケイ新聞年鑑局マーケティング事業部 1983年3月
『講座・日本技術の社会史 第4巻 (窯業)』永原慶二ほか編 日本評論社 1984年12月
『時の動き 30』 内閣府編 国立印刷局 1986年8月
『広報させぼ 2018年2月号』 佐世保市総務部秘書課広報係編、発行 2017年2月
基本情報
名称:工房 / ギャラリー併設[嘉久房/平戸窯悦山]
住所:長崎県佐世保市三川内町692番地
公式webサイト:https://sites.google.com/view/hirado-etsuzan/