織田信長との出会い
 南蛮寺
南蛮寺
死傷者が出るほどヒートアップした弥助見物
当時の国際貿易港である堺に到着した一行は、船から馬に乗り換え、紋章旗や十字架を掲げながら京を目指した。そんな一行が物珍しく、群衆が取り囲む。特に「黒い大男」弥助の姿は、多くの日本人を驚かせた。一行は摂津(現、大阪府)高槻(たかつき)城主でキリシタン大名である高山右近(たかやまうこん)の歓待を受けた。のちに信仰を守って国外追放となり、フィリピンのマニラで生涯を閉じる右近だが、このときは織田信長の有力な配下である。右近は、ヴァリニャーノらが速やかに信長に拝謁できるよう祈ったという。
そして、事件は彼らが京都に到着し、教会堂(南蛮寺)に入ったところで起きた。黒い大男の噂は一行が到着するよりも先に京都に届いており、その姿を見ようとする群衆(1,000人を超したとも)が教会堂に押し寄せたのである。宣教師たちは建物が壊されるのを恐れ、門扉(もんぴ)にとりついた群衆の中には、押しつぶされて死傷する者まで出た。騒ぎは、京都に滞在していた信長の軍勢が派遣されて、ようやく収まったという。信長は、騒動の原因となった黒い大男の正体を知りたがり、自分のもとに連れてくるよう命じた。図らずもヴァリニャーノ一行は、上洛直後に信長への拝謁のチャンスを得たのである。
 本能寺跡碑
本能寺跡碑
信長に気に入られた「黒い大男」
信長が京都で宿所としている本能寺は、教会堂から徒歩5分程度の近距離にあった。弥助を含むヴァリニャーノ一行は、織田家の武士たちに守られながら信長のもとへ赴いたのだろう。その謁見の様子を、織田家家臣の太田牛一(おおたぎゅういち)は次のように記す。
「二月二十三日、キリシタン国から黒坊主が参上した。年のころは二十六、七歳でもあろうか、全身の黒いことは牛のようである。見るからにたくましく、みごとな体格である。その上、力の強さは十人力以上である。伴天連(バテレン、ヴァリニャーノらのこと)がこの男を召し連れて参上し、信長公に、布教のご許可にたいしてお礼を申し上げた(以下略)」(太田牛一『信長公記』の現代語訳)。
また宣教師ルイス・フロイスは、弥助を見た信長の反応を次のように記録している。
「大変な騒ぎで、(信長は)その色が自然であって人工でないことを信ぜず、帯から上の着物を脱がせた」
信長が弥助の体を洗わせたという説もあるが、そこまでせずとも着色でないことはわかっただろう。弥助が正真正銘の「黒い大男」だと知れると、信長も居並ぶ家臣たちも、敬意をもって彼に接したようだ。『信長公記』には弥助が「十人力」であると記されており、その腕力を見せる機会もあったのかもしれない。しかし弥助の振る舞いはあくまで礼儀正しく、信長はすこぶる上機嫌で、弥助に褒美として銭一万(十貫文)をその場で与えている。

後日、ヴァリニャーノは再び信長に拝謁し、西洋の様々な品物を献上するが、その際に、政治的配慮で信長気に入りの弥助も献上されたのではないかと、『信長と弥助』のロックリー氏は推測する。また初対面後、信長自ら教会堂に出向き、弥助と再会したことをうかがわせる記録もあり、信長がヴァリニャーノに弥助を譲るよう求めた可能性もある。いずれにせよ弥助の意思に関係なく、その身柄はイエズス会から信長の下に移ることになった。しかし信長は彼を、お飾り的な「黒い大男の従者」にするつもりはなかったのである。
戦国の覇者の小姓「弥助」
 復元された安土城天主
復元された安土城天主
「いずれどこかの領主になるのでは」
なぜ織田家で弥助と名づけられたのかは、よくわからない。ロックリー氏は、ヴァリニャーノ一行が彼を「イサケ(ユダヤ名イサク)」と発音するのを聞いて、「ヤスケ」にしたのではとする見方とともに、彼の出身がモザンビーク北方の「ヤオ」族で、それを聞いた信長が日本男性の名前に多い「助」を加えて、「ヤオ助→弥助」にした可能性も紹介している。
織田家の家臣となった弥助は、主君に従って近江(現、滋賀県)の安土に赴くと、小姓(こしょう)に任じられた。信長の小姓といえば森乱丸(蘭丸、もりらんまる)が有名だろう。常に主君の側近くに仕え、身の回りの世話を焼くだけでなく、使者として信長の意を伝え、ときに自分より格上の部将に指示を与えることもあった。そんな要職に異国人が抜擢されるのは破格のことだが、合理的な信長が理由もなく弥助を小姓にするとは考えにくく、弥助が多少は日本語で会話できたこと、また軍事奴隷(ハブシの戦士)として、ヨーロッパの最新の軍事知識と技術を身につけていたことが高く評価された可能性があるという。
弥助は信長の太刀持ちなどを務め、常に側近くに控えていたようである。また扶持(ふち、給与のこと)を与えられ、装飾付きの短刀、さらに安土城内に私宅まで下賜された。たまに従者を伴って安土城下を歩くこともあり、城下の人々は弥助が信長の寵愛を受けていることを知って、「いずれどこかの領主になるのでは」と噂したと伝わる。外国人領主が現実的であるのかはともかく、小姓が城持ちの領主となる可能性は十分にあった。たとえば森乱丸は、本能寺の変の直前に5万石を領し、小姓を務めながら大名になっている。日本初の外国人侍である弥助は、運命の変転にとまどいながらも、信長の厚遇に感謝していただろう。
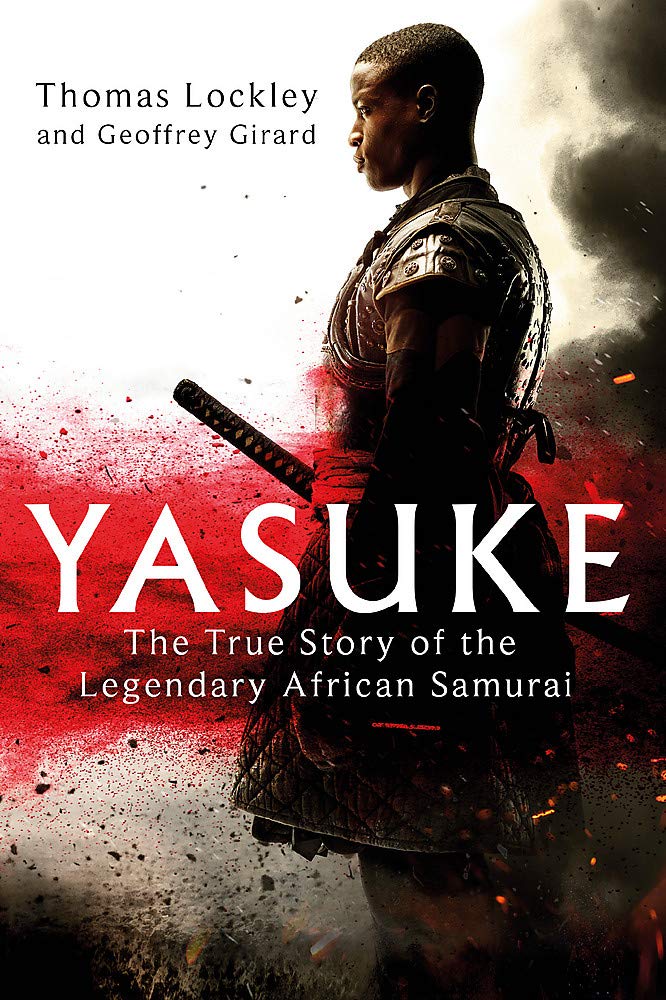
信長とともに戦場にも赴く
次に弥助が記録上に現われるのは、天正10(1582)年4月19日である。長年の宿敵であった甲斐(現、山梨県)の武田氏を滅ぼした信長は、戦場の視察に赴くが、その傍らに弥助の姿があった。信長と同盟を結ぶ徳川家康(とくがわいえやす)の家臣・松平家忠(まつだいらいえただ)が、信長主従を記録している。
「信長様が、宣教師から進呈され、扶持を与えたというくろ男を連れておられた。身は墨を塗ったように黒く、身長は6尺2分(約182cm)。名は弥介というのだそうだ」(『松平家忠日記』の現代語訳)
すでに決着はついていたとはいえ、信濃(現、長野県)、甲斐の敵地に乗り込む以上、不測の事態が起きることは十分にあり得た。信長に近侍(きんじ)する弥助は、いざという時には主君の楯(たて)となり、敵を撃退するという重大な任務を負っていたはずである。記録にはないが、弥助も甲冑(かっちゅう)姿であっただろう。信長が小姓の一人として、弥助に信頼を置いていたことがうかがえるのではないだろうか。しかし、それからわずかひと月余りのちに、信長と弥助は運命の本能寺の変を迎えるのである。












